「前期全ての授業の読み物の中で、一番よかった!
 」
」 と何名かの生徒に絶賛された、
とっても好評なリーディング (授業の前に読む読み物) があった。
それは、経済学の授業で使われた
『Kicking Away the Ladder (はしごを外せ)』
という本の中の第6章(約20ページ)。
※残念ながら、ダウンロードできるサイトは見つからず
私が参考にしたサイト(英語)はこちら http://www.paecon.net/PAEtexts/Chang1.htm
今の先進国の途上国に対するやり方を痛烈に批判する内容で、
先進国が 『よい政策』 として、
途上国に今勧めているものは本当に途上国にとっていいのか?
という疑問を投げかけている。
内容の1部をかいつまむと・・・
先進国は自分達がやってきた、という理由で
 自由市場 (フリーマーケット:政府や権力で取引を行わない)
自由市場 (フリーマーケット:政府や権力で取引を行わない) 自由貿易 (フリートレード:輸出入に制限や保護を加えない)
自由貿易 (フリートレード:輸出入に制限や保護を加えない)といった政策を途上国に勧めている。
けれど実際、今の裕福な国のほとんどは関税をかけたり、
補助金を出して自分の国の産業を守ってきたという事実があり、
そのことはほとんど知られていない。
特に、経済面でトップに立つイギリスとアメリカは、
過去に関税と補助金を積極的に使っていたことがある

先進国は自分達の利益を短期的に優先してしまっているけれど、
状況を変えるには、歴史の真実がもっと広められないといけないし、
途上国がもっと関税や補助金を使えるようにして、
より自分の国にあった政策を選べるようにしないといけない。
・・・・・・・・・・・・・・
題名の 「はしごを外す」 というのがすごくしっくりきて、
先進国が自分達が登ってきたはしごを、
後から途上国が登ろうとしてるのに、蹴り飛ばしてる、という意味なのだ。
自由市場・自由貿易がいかにもいい、みたいな風潮は確かにある気がする。
だからこそ、「へ~、知らなかった!
 」 って驚きだったし、
」 って驚きだったし、こういう新しい視点を持つと世界がまた違ったように見えてくる。
この本はもっともっと世間に広まってもいい気がする

同じ作者でほぼ同じ題名のレポート・本を見つけたので、
もっと詳しく知りたい人は、これら
 を読むといいかも
を読むといいかも
ダウンロード: Kicking Away the Ladder: The "Real" History of Free Trade
※経済学の授業で特にオススメされた本。こっちも評判が高いのでオススメ^^
英語版
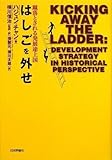



 にお呼ばれしたのだった。
にお呼ばれしたのだった。








 を作っていた。
を作っていた。 )
)



 十分なお金が貯金できるまでものすご~く長い道のり
十分なお金が貯金できるまでものすご~く長い道のり なので、
なので、 銀行が預かるようにすれば、
銀行が預かるようにすれば、 や酒への課税もまた、ムダ使いを止める効果が出てくるかも。。という提案。
や酒への課税もまた、ムダ使いを止める効果が出てくるかも。。という提案。
 じゃ、どうするか。
じゃ、どうするか。 より効果があるの?」 など。
より効果があるの?」 など。


 」 と思わせないようにする。
」 と思わせないようにする。







 の木を見つけた。
の木を見つけた。








