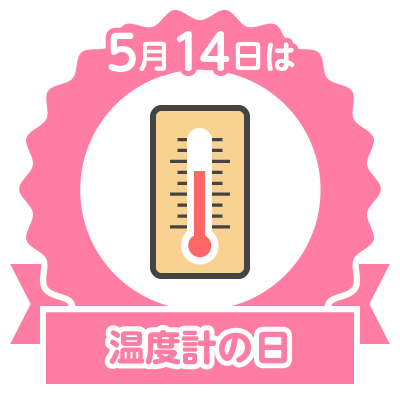温度の表記は「℃」と書きますが、この中には「C」という頭文字が入っています。
これは、この定義のもとを考案したアンデルス・セルシウス博士の名に由来します。
この「℃」という単位は水の温度をもとにして考えられました。
すなわち、水が凍る温度を「0℃」、沸騰する温度を「100℃」として、
その間を100分割したのが、この単位のもとになっています。
一方で『華氏451度』に見られる「゜F」という表記もあります。
これはガブリエル・ファーレンハイト博士の名に由来します。
5月14日が「温度計の日」というのも、この博士の誕生日だから、だそうです。
説明が難しいのですが、水が凍る温度を「32 ゜F」、沸騰する温度を「212 ゜F」として、
その間を180分割します。
この単位の便利な点は、冬の気温がマイナスを使わずに表現できる、体温が「100 ゜F」になると熱っぽい、など、生活実感に根差しているところ。
まぁ、我々にはなじみがないので、生活実感とはかけ離れていますが…。
海外で初めて聞くと、とんでもない気温(例えば「30℃」は「86゜F」なので)を天気ニュースが言っていたりして驚くことがあります。
( ※ 華氏・摂氏併用の温度計)
ちなみに、紙が燃える温度として題名に採られた「華氏451度」(451゜F)は「233℃」です。
さらには、熱力学温度を表す定義として、「K」(ケルビン)という単位もあります。
これには「 °」はつけません。
由来となったのは、ケルビン卿ウィリアム・トムソン博士。
これを使うと「絶対零度」(原子も動かなくなる極低温状態)は「0 K」となります。
さて、一口に「温度」と言っても、様々な単位があることが分かりました。
これを変換するための計算式もありますし、そういったものも含めてまとめてみると、立派な自由研究になると思いますよ。
今日の気温、何度かわかる?
▼本日限定!ブログスタンプ

![華氏451度〔新訳版〕 (ハヤカワ文庫) [ レイ・ブラッドベリ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9553/9784150119553.jpg?_ex=128x128)