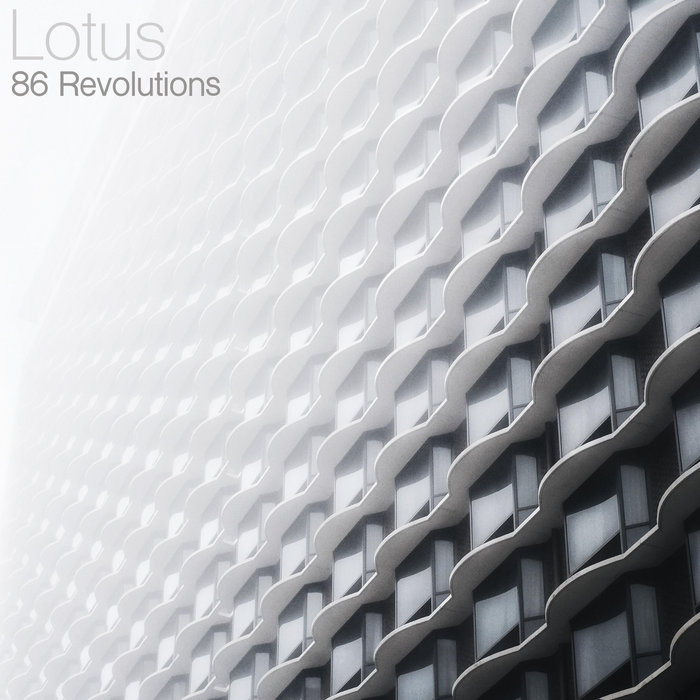今日の一曲!Lotus「Bjorn Gets a Haircut」―新作と過去のライブ盤の発掘―
今回の「今日の一曲!」は、Lotusの「Bjorn Gets a Haircut」(2020)です。今年8月にリリースされたばかりのスタジオアルバム『Free Swim』収録曲。
エレクトロニックジャムバンド・ロータスについて詳しくは過去の特集記事をご覧くださいと丸投げして、前置きなしで本筋のレビューに入ります。『Free Swim』から特にお気に入りの4曲に言及した後に、Bandcampで購入出来る複数のライブ盤からおすすめのジャム音源を紹介する二部構成です。
06. Bjorn Gets a Haircut
教科書の例文の如き曲名に何処かミーマチックな魅力のある本曲が、新作に於いて個人的にいちばんのフェイバリットでした。近年のナンバーにしては上掲MVの再生数が多いため、僕のみならず多くのロータスファンに刺さったキラーチューンであると推測します。ボーカル曲とインスト曲を折衷したようなつくりが特徴的で、バンドが得意とする「ボーカルトラックを楽器的に扱うセンス」が冴え渡っている名曲です。
心地好いディスコサウンドをバックに、シンセに'choir'系統の名称で収められていそうなプリセット感のあるクワイアがボーカルを務めているのは、音声合成技術の発展が目覚ましい昨今ではかなりオールドスクールに聴こえますが、大抵の楽曲では文字通りコーラス的もしくはパット的な言わば脇役での使用が多いイメージの中で、本曲の堂々と主役を張らせるクワイア使いはその実新しいアプローチなのではと感心しました。僕が目下思い付かないだけでおそらくこのような実例は過去にも存在するでしょうが、どうしてもチープになってしまうからか忌避されがちな手法だと認識しています。
とはいえ本曲のそれは絶妙に人間(肉声)らしさも機械(合成)らしさも漂わせていて不思議だと感じたのできちんと調べたところ、上掲記事にメンバーのLuke Millerによる解説が載っていました。それによると本曲のボーカルはメロトロンで生成されたもののようです。ソースにはもう少し具体的な手法が書いてあるのですが誤訳が怖いため確認は各自でと逃げまして、メロトロンによるものとわかるとテープに録音された人声("'Oh' patch")が同楽器の鍵盤演奏を通して独特のピッチの揺らぎを獲得しているのだなと得心がいきます。メロトロンはサンプラーのご先祖様みたいなものなのでサンプリング元次第で幅広い音色の生成が可能ですが、声ネタが効果的に使われていたとなると思い当たるのは70年代のプログレ全盛期です。Wikipediaにも例示されている通り、Rick Wakemanのシンフォニックなコーラス使いには圧倒されますよね。
そのような往年の使用法が'choir'の原義に近い聖歌隊的なものだとしたら、本曲の'Oh'は厳かさからは程遠い仕上がりです。どちらかと言えば受ける印象はコミカルで、きちんと主旋律たりうるメロディ性と区分性が備わっています。ゆえに敢えてJ-POP的な楽想で説明することすら可能で、【Aメロ(0:35~) → Bメロ(1:08~) → AB繰り返し(1:25~2:13) → サビ(2:14~)】と理解すれば、インストナンバーが苦手な方でも幾分聴き易いのではないでしょうか。サビメロのお気楽な感じから、曲名のビョルンの人物像を妄想するのも一興です。2:47~の間奏はジャム用パートらしい高いポテンシャルが秘められていて、ライブならここで7分ぐらい即興に割きそうな気がします。
03. Free Swim
表題曲もアルバムの顔に相応しい良質なナンバーで、「Free Swim」を象徴する自在なグルーヴと物語性に酔い痴れました。リズム隊が身体にBPMを刻む時間をくれる冒頭の24秒を経て、跳ね感の気持ち好いピアノリフがインしてくる0:25~で既に覚えた綺麗めな名曲の予感が、0:57~でキメの格好良い展開を見せる意外性によって鮮やかに裏切られ、満を持して登場する1:30~のギターが陽光を思わせるメロディを奏で出した時点で、「…やられた!」と脱帽です。競泳の自由形が実質的にクロールであっても5泳法目の開発を否定しない名称であるように、かつてない理想のグルーヴを追求せんとする試みがここまでのメリハリで表現されていると解釈しました。
3:15~のジャムセクションは一転してスペイシーなシンセで幕を開け、リスナーに別の不穏な側面を提示してきます。3:46~の灼熱感漂うサイケデリックなギターが後半の主役で、まだ秩序のある環境で泳いでいたと想定される前半とは異なり、大海原に投げ出されたかのような過酷さが窺えるサウンドスケープです。'freestyle'ではなくここからが本当の「Free Swim」だと言わんばかりの、ジャケットに独りぽつんと描かれているスイマーの持つフロンティアスピリットに胸が熱くなります。ギターのサウンドは次第に煌めきを増していきいつの間にかネガティブな質感が払拭され、4:53~のタメパートを経由して再度ポジティブなラインに戻っていくので、本曲の主人公は試練の果てに希望を見出したのでしょう。
08. Earl of Grey
アールグレイではなく間に'of'が入る少しひねった曲名なのは紅茶でも伯爵位でもなく一般名詞を強調したいからだろうかと疑問に思う本曲は、下掲のインタビューをソースとするにルークのフェイバリットナンバー(のひとつ)だそうです。曰く'it has a chill vibe with a timeless-type sound'には納得で、本曲のゆったりとしたリズム感と可愛らしい音遣いには上質の癒しがあります。作曲者自らが「時間を超越したサウンド」と形容しているため特定のジャンル名を出しにくいですが、レトロファンクなリズム隊とイージーリスニングなベル系シンセサウンドとメロディアスなギターが織り成すキャッチーな音像には、インストナンバーをただのBGMで終わらせないロータス節が顕です。
'a timeless-type sound'という表現は書き手のKillian O'Neilもお気に召したようでまとめの文章にも引用されており、多様なルーツを窺わせて一言ではジャンルを規定しにくい彼らの音楽は、制作者の側から見てもクロスオーバーの複雑性ゆえに定義が困難なのだと改めて認識しました。冒頭にリンクした特集記事では便宜上「エレクトロニックジャムバンド」をジャンル名としていましたが、これは言わばスタイル名なので文脈が少し異なります。そもそもスタジオ音源に対してジャムを持ち出して語るのもずれた話で、その点はライブ(音源)で原曲との聴き比べを行ってこそ味わえる魅力ですよね。というわけで、アフターコロナを意識させられるドライブイン形式ライブの模様を以下に埋め込んでおきます。オリジナルより多弁なギターとキーボードを堪能してください。
02. Turtlehead
「アルバムの中で最も驚きがあった楽曲は?」と問われれば本曲を推します。スロウテンポでファンキーな最後まで落ち着きのあるタイプのナンバーかなと予想しながら聴いていたら、1:51~のシンセベースで毛色が変わったと思ったのも束の間、2:03~のウワモノで一気にエレクトロニックに傾く二面性に痺れました。上掲動画の演奏をご覧いただければわかる通り、MPK249のパッド(MPC)を叩いて出音をコントロールする姿は、曲前半の段階では思い至らない画ではないでしょうか。3:29~は手数が増えて一層の激しさを帯び、バンドサウンドであることを一瞬忘れてしまいそうになるほどの電子音楽優位なつくりは、ロータスお得意の「機械ともジャムをしている感じ」のマシンライブな産物です。
―
新作への言及は以上で、ここからは過去のライブ盤をディグるセクションになります。以前の特集記事で紹介したライブ盤ないしライブアルバム(この違いの意味合いも当該記事を参照のこと)はiTunes Storeから購入可能なものに偏っていたので、本記事ではBandcamp編としてジャム音源の魅力をお伝え出来ればなと思います。実は更新予定記事でネタバレしちゃっているのですが、基本的にはそこに挙げたナンバーにふれていくつもりです。
■ 『86 Revolutions』 (2017)
ロータスのライブ盤のタイトルは公演名や時期をそのまま冠したものが殆どの中、Jesse Millerが選曲とミックスに時間を掛けた点(ソースはリリース時のNEWS)でコンセプチュアルだからか本作には珍しくきちんとした題名が付いています。公式サイトのディスコグラフィーにもラインナップされており、是非とも聴いて欲しいライブ盤なのだろうとの理解です。内容は2017年W/S期のツアーからセレクションされた全14曲で、当時の最新作『Eat the Light』(2016)のナンバーは勿論のこと、過去曲から未スタジオ音源化楽曲、Talking HeadsとLindstrømのカバーまで収められたバランスの好い作品に仕上がっています。
同盤から最もおすすめなのは03.「Livingston Storm」です(スタジオ音源は『Nomad』(2004)に収録)。本作のバージョンは本当に素晴らしくて、個人的には「これぞロータスのベストジャム!」と喧伝したいほどに過去最高レベルで神格化しています。オリジナルは少し気怠い雨の日に聴きたくなるようなメランコリックでお洒落なナンバーとの認識で、平均以上には好きなレベルだけれども7分あるわりには展開に乏しくやや単調だなとの評価でした。ところが本作では5:10から11:37まで続くジャムセクションが神懸かり的な発展性を有しているおかげで、何度繰り返し聴いても飽きない変化の妙に圧倒されっぱなしです。
8:52あたりまでは鍵盤が優勢というか幻想的なパッドをバックにピチカート系統のはじく音が前面に来る構成なので(特に8:24~8:39のポップなフレージングが好み)、ともすると『Nomad (Remastered)』(2014)付属のライブ盤『Nomad Live 6.8.2013』収録の同曲のようにシンフォニックなシンセワークスで突き抜けるアレンジかと思いきや、その後はまた別の新しいフェーズが顔を覗かせてきます。8:54~で楽曲の雰囲気が一段とダークに傾き始め、9:23~の妖しいリードに煽られながら徐々に主張を強めてくるギターが、10:22~で愈々主役に躍り出て抒情的なソロを奏で始めるのです。10:52~はまさに泣きのギターで、そのメロディの雄弁さたるや至極甚深、ジャム明けの11:38で聞こえる歓声にも大いに納得出来ます。
次点のおすすめは07.「Neon Tubes Part I >」~08.「Slow Cookin' >」~09.「Neon Tubes Part Ⅱ」のリプリーズ(反復・再開)シークエンスです。「Neon~」はスタジオアルバム『Build』(2013)の、「Slow~」はライブアルバム『Escaping Sargasso Sea』(2007)の収録曲で、連作である「Neon~ Pt.1/2」のジャムパートに「Slow~」をぶち込む意表を突いた構成に曲目の段階からわくわくさせられます。「Neon~」のスタジオ音源版は過去の特集記事でレビュー済みで、「古いアクションゲームもしくはレースゲームのBGMにありそうな、懐かしさと疾走感の畳み掛けが印象深い」と評していただけに、「Slow~」を挟んだのは言葉遊び的な面もあるのかなと感じました。
スタジオ音源に於ける「Pt.1」は続く「Pt.2」のために存在する前奏部といった趣でしたが、緩急が誇張されてジャムが追加された本作の場合は「Pt.Ⅰ」単体でも深い味わいがあり、前半のメロディアスなベースラインとファンキーなギターによる陶酔性は当然の聴きどころとして、後半の映画等で幽霊もしくは地球外生命体が発していそうなSE(或いはそれらの探知機が出している音)的な浮遊感に満ちたシンセの音色もユニークです。5:47あたりからギターのなぞるラインにバックトラックとミスマッチな明るさが出てきた時点で既に「Slow~」への布石が打たれているとはいえ、セットリストを知らない会場のオーディエンスは0:00のボイス'Slow'にさぞ驚いたことでしょう。
「Slow~」にはスタジオ音源版が存在しないので基本となる楽曲像はそも不明ですが、『ESS』の場合は次曲に繋がらず一度きちんと演奏が終わるため、後に「Pt.Ⅱ」が控える本作とはジャムの性質(パーカス/ドラムスソロ後の展開)にも差があります。緊張感のあるシンセリフで波状的に攻めてくるセクションがあるのは同じでもフレーズが全く違いますし、5:18~のダンサブルなクラップとボコーダーの登場は僕が今までに知らなかった「Slow~」でした(『Lotus Live at Schubas 06/15/2004』(2004)のともまた別という意味で)。クライマックスの「Pt.Ⅱ」は楽想こそオリジナルを踏襲しているものの、原曲よりハネたノリがライブ向けにチューンされていると感じます。
■ Spring 2012 Selections (2012)
本作は無料ダウンロード作品なので同じく無料の『Post-Rock Set』(2010)と併せて、ファンは勿論ロータスの音楽延いてはジャムバンドに興味を持ち始めたばかりのビギナーにもお誂え向きです。内容は2012年春季ライブからの全12曲で、紛らわしいですがジャケットに印字されている9月のライブ情報は単なるお知らせ(本作のリリースは8/30)ゆえ、つまり宣伝を兼ねたバラマキでもあったのでしょう。とはいえそのクオリティは決して低くなく、このレベルのパフォーマンスをタダで配布してしまうところは実にジャムバンドらしいと言えます。
本作随一のフェイバリットは07.「Invincibility of Youth」です(スタジオ音源は『Hammerstrike』(2008)に収録)。オリジナルは正直「One Last Hurrah」を導くための前座に過ぎない小品だと捉えていて、だからこそ曲長も短く2:44なのだろうと納得していました。それが本作では6:29まで拡張される大変化を見せており、「ロータス史上最高にロック」とのキャプションを副えたいほどにボルテージが上がりっぱなしの荒々しいジャムパートは、蓋し「無敵の若さ」(自然な日本語を意識した訳)のサウンドスケープです。あれこれと解説をするよりも、聴けば良さはわかるであろうと期して言及はこれだけに止めます。
ライブ毎に多彩な展開を見せる10.「Wax」は本作でもやはり素晴らしいです。総合的には『ESS』収録のものがいちばんツボではありますが、それはどちらかと言えば前半の定型(非ジャム)パートの絶妙な力の抜け具合に魅せられているからで、後半部についてのみ言えば本作のジャムに軍配を上げたいと考えています。別けても好きなのは6:04~のギラギラとしたシンセで、漫然と聴いただけではシンプルなフレーズを繰り返しているような印象を受けるものの、その実微妙な変化の連続で再現性に乏しい(誉め言葉)ところにライブ感が宿っていて素敵です。これだけ新鮮なアレンジでも、特集記事に書いた大まかな流れ「序盤にはゆるさと断続的なアッパーサウンド、中盤にはキーボードが主張を強めるパート、終盤にはギターが雄弁に語り出すバンド全開のセクション」は変わっておらず、軸がぶれていないからこそ後半も「Wax」と理解出来るんですよね。
■ 『Unoriginals - Live 2015』 (2015)
本作は直球の「アンオリジナルズ」と題されたカバー曲集で、無料ダウンロードと銘打たれてはいませんが最低価格設定がないのでタダでも入手可能です。内容は2015年冬季ツアーからの全8曲で、当たり前ながらロータスの持ち歌は含まれていません。バンド畑からは『86~』の項でも名前を出したTalking HeadsとVulfpeckのナンバーが取り立てられてファンキーに、電子音楽界隈からはDeadmau5にTodd TerjeにMord Fustangと著名DJによるトラックでダンサブルに、更にはHerbie HancockでジャズにShuggie Otisでソウルにと、「Earl~」のところに書いた「多様なルーツ」をまさに窺わせるラインナップに得心がいきます。
同盤からの個人的なヒットは01.「Inspector Norse」です(Todd Terjeが2012年に発表したトラックのカバー)。オリジナルは上に埋め込んだ通りの底抜けのポップさで、果たしてこれを嫌う人間がいるのだろうかと思うほどには万人受けするメロディが耳に残ります。トッドはおそらくロータスというかルークのお気に入りで、最初に紹介した「Bjorn~」もその影響を受けているとの本人談があるほどです(同項にリンクした記事のことなので戻って確認してください)。『86~』で名前を出したLindstrømも併記されているところから、彼のノルウェー贔屓な一面が窺えます。
ロータスによる同曲のカバー最大の特徴は主旋律をシンセではなくギターに委ねている点で、そのことにより原曲の持つフロア志向な性質が薄れた代わりにアウトドア用途に適うナチュラルな風味が芽生えており、野外フェスで風を感じながら堪能したい一曲に敷衍されていると高評価です。後半にはしっかりジャムパートもあって、そこまで進むともはやオリジナルに聴こえます。
■ 『Space Disco (Live)』 (2016)
本作もカバー曲を中心に構成された音源で、『Unoriginals~』よりも有名どころが多いせいか(…どうか定ではないものの)有料です。内容は2016年10月29日に行われたライブからの全10曲で、説明にはスペシャルハロウィンセットと記されています。Todd TerjeとLindstrømのトラックが当たり前のように披露されているのは最早持ちネタの域として、他の楽曲はDavid BowieにMadonnaにNew OrderにDaft Punkの豪華っぷりで、広く一般にも受けるセトリにしているなとの印象です。
ここで特筆したいのは10.「Get Lucky」です。ご存知Daft Punkがグラミー賞を獲得するに至った名盤『Random Access Memories』(2013)からの代表曲で、本記事をご覧になるような方には尚の事説明不要でしょう。実際問題今ここで掘り下げたいポイントは、「ロータスがダフトパンクをカバーするなんて俺得だなぁ」といった部分ではないのです。そろそろ「あれ?貼る動画間違えてない?」とツッコミが聞こえてきそうですが、言わんとしている枢機はまさにそこにあります。
僕は本曲の3:07~を聴いてびっくりしました、『なんで「Fortune Favors」が聴こえるんだ!?』と。同曲はスタジオアルバム『Frames Per Second』(2018)の収録曲で、本作のリリースはその2年前です。『Frames~』よりも前に『Space~』を聴いていなかったがために生じたこの驚きは、上掲記事でこの小ネタにふれ損ていることと共通の「やっちまった…」案件と自戒します。というわけでこの場を借りてフォローをしますと、「Fortune~」の2:45~のエキゾチックなシンセソロは、本曲のジャムパートが元になっていたと2年越し(2018 → 2020)で気付いた次第です。よく聴くと当該ソロ前のシーケンスフレーズも共通していて、何なら「Fortune~」自体原曲の「Get~」とマッシュアップ出来そうだと感じました。
これを機にしっかりと調べたらこの情報は上掲記事にもちゃんと記載されていたので、自分の調査不足をただ嘆くほかありませんね。「Fortune~」のかなり詳しいセルフレビューもあり、僕の書いたテクスト論的な理解と照らし合わせながらお楽しみいただければ幸いとして、アイデンティティを保ちたいと思います。笑
■ 『Live Selections Winter 2016』 (2016)
変則的とはいえカバーへの言及が続いたので最後はオリジナルにふれて〆るとしましょう。悪い意味ではなく本作は何処か雑多な内容で、後年にスタジオ音源化されたナンバーに未だそうなっていないライブだけのナンバーもあれば、過去曲は当時の最新作からも旧作からもアルバム未収録曲からも選ばれていて、カバーはTame ImpalaにRatatatとサイケなチョイスです。この選曲は2016年冬季ツアーからとなっています。
語りたいというか語らなきゃならないと思っているのは02.「Eats the Light」です(スタジオ音源は『Eat the Light』に収録)。同盤についてはそのノーマルな作風のせいで特集記事の中でディスり気味だったのがずっと引っ掛かっていて、大改訂に際して文章をマイルドにした結果消えてしまった過去のレビュー文には、「でもライブで化けるんじゃないかなぁとは思います」との一節を認めていました。その部分は今では「バックトラックに耳を凝らすと、どの曲も中々にクールなプレイで魅せているとわかるので、ボーカルラインも楽器のひとつと見做して均してしまえば、そこまで悪くない一枚かもしれません」と、ライブから遠ざける書き方に変化させていたのです。
しかし、本作に於ける同曲はまさに当初想定していた「ライブで化けた」例でして(シングルで一足先にリリースされていたことを考慮した時系列です)、スタジオ音源版までの演奏が終了した後に長尺のジャムパートが控えているおかげで、単なるポップスの域を超えた完成度を誇っている点を買っています。具体的には5:35~のエレクトロニックな音作りがとにかく格好良く、前半の定型パートの要所要所で存在感を露にしていたバウンシーなシンセを拡大解釈したかのような、バンドサウンドに傾かないアレンジが新鮮でした。
―
以上、2020年の最新作『Free Swim』から過去のライブ盤5作品にふれた、特集記事レベルの「今日の一曲!」でした。新作は相変わらずのハイクオリティで満足でしたし、ライブ盤の発掘も一向に終わりが見えないので嬉しい反面蒐集の大変さは折紙付ですね。Bandcampには他にもまだまだ多くのライブ盤が販売されており、僕もまだその全てに手を出したわけではありません。作品あたりの価格は安く設定されているため金銭的なネックはさしてないものの、聴いて深く理解するにはそれなりの時間を要するがゆえに、ちまちま買い揃えていくのがベストだと信じて気長に集めています。
iTunes StoreとBandcampに関してはこの戦法で構いませんが、公式サイトの「LIVE DOWNLOADS」からジャンプ出来るNugs.net(下掲リンク参照)では、ページを開いた先の「Showing 1 - 12 of 711 Results」(2020.10.16時点)の表示を見ただけでその途方の無さに面食らうレベルなので、こちらは流石にサブスク頼りが現実的ですね。特に気に入ったテイクがあったりセトリが好みだったりしたら購入すればいいかなと考えています。
インストナンバーは歌詞がないだけに、こちらが言葉を尽くせば尽くすほど或いは背景情報を深く知れば知るほど、自身の内にある愛着が具現化されていくのを強く実感出来るため、大変ですが書き甲斐も大きく楽しいものです。ロータスの音楽が素晴らしいということは、その良さについてこれだけ文字に起こした人間がいる事実でもって補強されるであろうと自画自賛した上で、このプロセスを同じくロータスが好きなあなたにも共感していただけたなら恐悦至極に存じます。
最後に編集後記的な情報というか裏話を載せますと、以前の特集記事が常に検索上位なのは有難いことですが、同記事は最初の自分語りパートが長いせいで読者を遠ざけている気がするので、即レビューに移行している本記事が上位に来たほうがいいのでは正直思っています。というより来てもいいやとの思惑で、敢えて内容を充実させた向きもあるくらいです。母語での言及が少ないミュージシャンのファンになると、「なら自分が発信するか」との使命感に駆られる僕はその典型かもしれません。