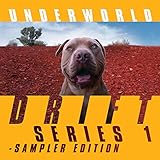DRIFT SERIES 1 - SAMPLER EDITION / Underworld
Underworldの10thアルバム『DRIFT SERIES 1 - SAMPLER EDITION』(2019)のレビュー・感想です。本記事では日本限定発売の2枚組盤を扱います。
【追記:2020.3.7】
間が空いてしまいましたが、後に『DRIFT SERIES 1』のBOX SETのレビューを改めて行いました。本記事とリンク先とでは言及の対象とした楽曲が異なっているため、どちらもあわせてお楽しみいただければ幸いです。
【追記ここまで】
記事タイトルにアルバム名を掲げておきながら全曲レビューに至らない理由は本盤の特殊性にあるため、まずは作品背景の解説から始めます。作品題に「SAMPLER EDITION」とあるように、本作は『DRIFT』という長期プロジェクト下でリリースされた多くの楽曲群の中から、文字通りサンプラーとして抜粋された数曲が収められているディスクです。佐久間英夫さんによる解説文では「ベスト盤的な内容」とされており、確かに同プロジェクトのエッセンスを抽出した一枚であることには相違ないと思いますが、Underworld側の説明文では'neither a difinitive record nor a curated "best-of" type album'とされており、あくまで'a sampler'だと強調されています。続けて意訳をしますと、「完全版はデジタルかボックスセットで用意してあるから、本盤を気に入ったならそちらもどうぞ」と、堂々たる案内が書いてあるほどです。
ということで、仮にこのサンプラー版を隅々まで紹介したとしても、それは全体(完全版はBD含む8枚組+80頁ブックレットで構成)のごく一部を切り取っただけのものにしかならないため、ならば開き直ってレビューもサンプリング形式でお届けしようと思い至りました。僕は後にボックスを購入する予定というか予約済みゆえ、改めて作品への全体評を書きたくなったとしたら、また新たに記事を立ち上げようと考えています。8枚組総レビューはさすがに骨が折れるので、書き方は依然抜粋的になる公算が大きいですけどね。
お次は『DRIFT』の説明に入ります。上掲の動画がプロジェクトのローンチを宣言するものですが、これは2018年の11月1日から2019年同日にかけての52週間で、週にひとつは作品(音源だけでなく映像やエッセイも含む)を発表し続けるという、リアルタイム且つリミテッドな制約下での創作活動のことです。未だ"ongoing experiment"だそうで、本作に「1」と冠されているところからも察せる通り、いずれ「2」以降の展開もあるのではと窺えます。
このコンセプトが発表された当時の感想を述べますと、正直「がっかりした…」でした。なぜなら、僕はUnderworldが時間を掛けて練り上げたトラックが大好きで、細部の作り込みに酔い痴れる高度なリスニング体験と、享楽的なダンスミュージックのシンプルさを同時に味わえるところに、最大の価値を見出しているからです(参考記事)。従って、旧来のスタジオアルバムよりも制作期間が短かった9th『Barbara Barbara, We Face a Shining Future』(2016)の路線を、更に推し進めるかのような方向性に対して、結果的に9thをあまり好きになれなかった自分としては、いの一番に出てくるリアクションは「ノー!」でした。その証拠に、僕は『DRIFT SERIES 1』の発表期間にあたる一年間、その動向を一切追っていなかったことを白状します。
しかし、結論から先に申し上げますと、この選択は失敗でした。敢えて距離を置いていたのが功を奏した面もあると推測可能ながら、サンプラー版とはいえ初めて作品の形でふれた『DRIFT SERIES 1』の音源は、どれも僕にとって好ましいUnderworldのブランニューサウンドに満ちていたからです。先に否定した「9thの路線」とはリンク先にも記してあるように、即ち「シンプル過ぎる」点をネガティブに捉えた言でした。『DRIFT』は週に一作品という時間的な制約があったため、アウトプットも当然単純なものになるのだろうと予想し、この認識が前出の「更に推し進めるかのような方向性」に繋がっています。ただ、このこと自体はある意味予想通りで、10thの収録曲はいずれも過去作と比べたらシンプルなつくりであるのは事実なので、ともすれば9thと同じく気に入らない可能性もあったはずです。
ところが、現実にはそうはならなかった。この理由を考察してみるに、同じ「シンプル」でも9thは「冗長」と感じてしまったのに対して、10thは「ワンアイデア」の手法が強化されていると感じられ、さながら「アイデア集」の如き受け取り方が出来たのが良かったのではと思います。喩えるならビュッフェの美学で、多種多様なUnderworldらしさを味わえるところが、本作延いてはサンプラー版ならではの愉しみではないでしょうか。完全版を鑑賞したらまた違った感想が出てくるかもしれませんが、ともかく現時点で言えることは、シンプルさの隙間に鏤められたスパイスがしっかりと効いてくるような、そう表現したい楽曲が揃い踏みしているということです。
ということで、ここからは『DRIFT SERIES 1 - SAMPLER EDITION』(DISC 1)および日本限定のボーナスディスク(DISC 2)に収めれられている全18曲の中から、とりわけ気に入っているトラックを順不同で簡単に紹介していきます。YouTube上に公開されている作品も多く、埋め込み過多によって重いかもしれませんがご了承ください。なお、以降で表示する曲番号はサンプラー版に準じたものですが(1-01.ならDISC 1の1曲目といった具合)、そもそも『DRIFT SERIES 1』は5つのエピソードに大別されており、完全版はそれに則った収録順となっているので、その情報も曲番号の後に併記しておきます。
1-06. SCHIPHOL TEST(Ep.4 [Space] Pt.2)
「JAL to Tokyo」(2005)を彷彿させる暫定的な曲名だと思ったら案の定、佐久間さんの解説文によるとスキポール空港での飛行機待ちの間にiPadで制作された楽曲のようです。シンプルでバウンシーなリズムトラックの上を、カールの浮遊感のあるボーカルが漂う、実にUnderworldらしいサウンドメイキングが印象的な良曲。歌詞内容も単純だからこそ素晴らしく、幾度も繰り返される"Push"や"Moving on"や"One"に潜む洗脳的な心地好さには、まさに"Connected to the source"の心持ちを覚えます。
本曲をトップバッターに持ってきた理由は、先述の「アイデア集」的なファクターが顕著に窺えるからで、具体的には2:57以降の技巧性な変化の付け方を絶賛したいからです。"For someone"を合図に、続く歌詞頭の"The rhythm"の[rí]が吃音じみたリピートに陥り、同時に墜落していくイメージの縒れたストリングスが場を支配し、3:27から独特のリズムを刻み出す展開に、初聴時は思わず唸ってしまいました。鍵盤か弦楽器か判然としませんが、同時に鳴り出す切なくて仄暗い音の残響もひたすらに素晴らしいです。
サンプラー版に収められているのは4:42までで、"One, One, One, One"で消え行くクロージングも刹那的で格好良くはあるけれども、完全版および上掲動画の8分超えのバージョンと比べると物足りなさを拭えません。後者では次第に歌詞が複雑になっていく対比が見られ、"Whose words are these?"から始まる苦悩の吐露パートを経て、"Tell me I'm not crazy"で悲しく結ばれるのは、非常にドラマチックだと言えます。7:08から残響に混ざり出すチープな音も地味に好みです。
1-02. THIS MUST BE DRUM STREET(Ep.3 [Heart] Pt.3)
初聴時にはそこまで耳に残らなかったものの、その魅力が後からじわじわと主張を強めてきて、今ではサンプラー版の中で最も好きなトラックにまで昇格しました。佐久間さんも解説の中で本曲を絶賛しており、大いに同意したいと思います。ベースラインの素敵さはご指摘の通りで、終始楽曲を力強く牽引していてダンサブルです。2:40からの単純なシンセによる畳み掛けもグルーヴィーで、一段と踊れる仕上がりになっています。
とても個人的な所感を付け足しますと、本曲を聴いたらなぜかSFCのゲームソフト『スーパードンキーコング』シリーズのBGMが脳内に浮かんできました。全体的にトライバルなところもその根拠となりますが、とりわけ0:47から鳴り出すロングトーンの音は、近しいものをゲームの中で聴いたことがあるような気がしたくらいです。雄大で険しい自然を予感させる、暗示的なサウンドスケープとでも言いましょうかね。上に埋め込んだ「(Film Edit)」ではこの音を確認出来ないため、音源化に際したナイスアレンジだと評しておきます。ビートがガチャガチャし出す1:06からの忙しなさも好みで、小さなバネを弾いた際のビヨビヨした成分を含んだ音(電子機器から乾電池を抜いた時に聴こえるようなもの)が、左右に小刻みにパンして作るリズムがユニークです。これも上の「FE」だと聴き取りにくい気がしますね。
本曲が更に面白いのは、これだけクールなバックトラックを下敷きにしておきながら、ボーカルがなぞるリリックが"Do you want to buy my car?"と、文脈が謎のフレーズである点です。何処か神聖性を覚えるクリアなエフェクトまで施されており、"僕の車を買わない?"(歌詞対訳:伴野由里子さん)といった普通の一節が、あたかも啓示らしく響いてきます。
2-05. DUNE(Ep.3 [Heart] Pt.1)
本作を初めて通して聴いた時に、最も感銘を受けたのは本曲でした。動画のコメント欄でも最多の支持を集めている通り、「Sola Sistim」(2002)が過るダウンテンポ志向の長尺トラックで、同曲が大好きな僕には気に入らない道理がありません。ただ、「SS」がダウナーで破滅的な世界観に根差しているとしたら、「DUNE」では反対に明るい展望が描かれていると感じられ、より癒される楽曲の軍配は本曲にあげたいと思います。モチーフが「デューン」である以上、癒しと言ってもそれは儚い希望に過ぎない気はしますけどね。
カールの歌唱もしくはポエトリーリーディングとしてもいいかもしれませんが、その落ち着いた声音の魅力が遺憾なく発揮されており、徐々にではあるけれども確実に変化していくチルなバックトラックの美しさと相俟って、延々と流していても全く苦痛になりません。一音一音に最適な塩梅のパラメータ(ADSRやベロシティなどの値のこと)が付加されているのは勿論、リズム隊には加えて絶妙な空間干渉力(リバーブやディレイなどの空間系エフェクトによる影響)が備えられていると聴き取れ、この匙加減はさすがベテランの面目躍如です。
1-08. S T A R (Rebel Tech Version)(Ep.5 [Game] Pt.6)
厳密にはEp.5のPt.6にあたるのは無印の「S T A R」で(上掲動画もこのバージョン)、「(Rebel Tech Version)」はサンプラー版のみの収録です。両者のサウンドは結構に趣を異にしていて、前者はブレイクビーツの強調が著しいのに対し、後者は「Tech」を冠しているだけはある電子的なアプローチが光っています。
ちなみにですが、動画のコメ欄でも指摘されているように、前者は過去曲「Lenny Panne」をベースにしており、ビートメイキングに既聴感を覚えた方は耳聡いです。同曲はスタジオ音源としては公式サイト限定販売のデジタル盤『Lovely Broken Thing』(2005)に、ライブ音源としては受注生産の『Live in TOKYO 25th November 2005』(2005)に、変化球としてはアプリ『iDrum Underworld Edition』(2009)にと、いずれも収録先がレアなので、熱心なファンでない限りは馴染みのないトラックかもしれませんね。ダウンロード購入が今でも可能かは定かでありませんが、上記のライブ盤は割とディスクユニオンで見かける機会も多いので、足繁く通っていればいつかは入手出来るでしょう。
話を戻して、どちらのバージョンにせよ本曲を決定付けるのは聴けば瞭然のヒップホップ要素で、この手のスタイルもまたUnderworldの得意とするところではありますが、本曲の特筆性は歌詞のカオティックさにあります。例示するのが面倒なほどに多くの著名人や有名キャラクターの名前がオンパレードする内容で、曲名に違わぬスター性にくらくらすること請け合いです。ただ適当に列挙しているわけでもなくて、音韻上ぴったりと嵌る名前が適切にチョイスされているため、イヤガズムを覚えますし更には口遊みたくなります。
1-04. BORDER COUNTRY(Ep.4 [Space] Pt.6)
Ø [Phase]をフィーチャーしたトラック。解説の佐久間さん曰く、アングラミニマルテクノDJ界隈での支持が厚いレーベル・Tokenの看板アーティストだそうなので(勉強不足の自身を恥じるばかり)、その触込みに偽りのない本曲の見事なミニマルさにはただただ感服致しました。このダークな疾走感はUnderworldの真骨頂と言っても過言ではないトラックメイキングであるため、この傑作がコラボによって生まれたこと自体が凄いと絶賛します。フェイズというかアシュレー・バーチェットの才能引き出し力、ヤバくね?と。
常に緊張の連続を強いられるヒリヒリとした音遣いが特徴的で、不安や焦燥を抱えたまま深淵に落ち込んでいくようなビジョンが浮かびます。しかし、ただ座して死を待つイメージではなくて、たとえ敵わずとも何とか足掻こうとする必死さが;そのためなら他の一切を犠牲にしても構わないといった攻撃性が、細かな音の積み重ねで次第に顕になっていると表現したいです。観念的な歌詞も意味深長で読み解き甲斐があり、出だしの"What's that noise?/Hit your head/But it don't hurt"が謳う正体不明の恐怖や、"Some are cold/Some are hot/Blah blah blah"に見られる曖昧さ加減に、何とも言えない気持ちになります。後者は訳詞も巧くて、"冷たいものもあれば/熱いものもある/とかなんとかね"は、戯けた結びが愛おしい名訳です。
以上、全18曲から抜粋してフェイバリットトラックを5曲紹介しました。サンプラー版から更に一部をレビューするというクローズドな言及ではありますが、本記事で取り立てた5曲だけを聴き比べてみても、収録曲の多彩さは推し測れると期待します。
ここまでにも度々ふれているように、曲名に特記がなくともサンプラー版に収められている楽曲はショートバージョンになっているものが多いので、全体像を掴みたければやはり完全版に手を出すしかありませんね。届くのが楽しみです。
【追記:2020.3.7】
間が空いてしまいましたが、後に『DRIFT SERIES 1』のBOX SETのレビューを改めて行いました。本記事とリンク先とでは言及の対象とした楽曲が異なっているため、どちらもあわせてお楽しみいただければ幸いです。
【追記ここまで】
記事タイトルにアルバム名を掲げておきながら全曲レビューに至らない理由は本盤の特殊性にあるため、まずは作品背景の解説から始めます。作品題に「SAMPLER EDITION」とあるように、本作は『DRIFT』という長期プロジェクト下でリリースされた多くの楽曲群の中から、文字通りサンプラーとして抜粋された数曲が収められているディスクです。佐久間英夫さんによる解説文では「ベスト盤的な内容」とされており、確かに同プロジェクトのエッセンスを抽出した一枚であることには相違ないと思いますが、Underworld側の説明文では'neither a difinitive record nor a curated "best-of" type album'とされており、あくまで'a sampler'だと強調されています。続けて意訳をしますと、「完全版はデジタルかボックスセットで用意してあるから、本盤を気に入ったならそちらもどうぞ」と、堂々たる案内が書いてあるほどです。
ということで、仮にこのサンプラー版を隅々まで紹介したとしても、それは全体(完全版はBD含む8枚組+80頁ブックレットで構成)のごく一部を切り取っただけのものにしかならないため、ならば開き直ってレビューもサンプリング形式でお届けしようと思い至りました。僕は後にボックスを購入する予定というか予約済みゆえ、改めて作品への全体評を書きたくなったとしたら、また新たに記事を立ち上げようと考えています。8枚組総レビューはさすがに骨が折れるので、書き方は依然抜粋的になる公算が大きいですけどね。
お次は『DRIFT』の説明に入ります。上掲の動画がプロジェクトのローンチを宣言するものですが、これは2018年の11月1日から2019年同日にかけての52週間で、週にひとつは作品(音源だけでなく映像やエッセイも含む)を発表し続けるという、リアルタイム且つリミテッドな制約下での創作活動のことです。未だ"ongoing experiment"だそうで、本作に「1」と冠されているところからも察せる通り、いずれ「2」以降の展開もあるのではと窺えます。
このコンセプトが発表された当時の感想を述べますと、正直「がっかりした…」でした。なぜなら、僕はUnderworldが時間を掛けて練り上げたトラックが大好きで、細部の作り込みに酔い痴れる高度なリスニング体験と、享楽的なダンスミュージックのシンプルさを同時に味わえるところに、最大の価値を見出しているからです(参考記事)。従って、旧来のスタジオアルバムよりも制作期間が短かった9th『Barbara Barbara, We Face a Shining Future』(2016)の路線を、更に推し進めるかのような方向性に対して、結果的に9thをあまり好きになれなかった自分としては、いの一番に出てくるリアクションは「ノー!」でした。その証拠に、僕は『DRIFT SERIES 1』の発表期間にあたる一年間、その動向を一切追っていなかったことを白状します。
しかし、結論から先に申し上げますと、この選択は失敗でした。敢えて距離を置いていたのが功を奏した面もあると推測可能ながら、サンプラー版とはいえ初めて作品の形でふれた『DRIFT SERIES 1』の音源は、どれも僕にとって好ましいUnderworldのブランニューサウンドに満ちていたからです。先に否定した「9thの路線」とはリンク先にも記してあるように、即ち「シンプル過ぎる」点をネガティブに捉えた言でした。『DRIFT』は週に一作品という時間的な制約があったため、アウトプットも当然単純なものになるのだろうと予想し、この認識が前出の「更に推し進めるかのような方向性」に繋がっています。ただ、このこと自体はある意味予想通りで、10thの収録曲はいずれも過去作と比べたらシンプルなつくりであるのは事実なので、ともすれば9thと同じく気に入らない可能性もあったはずです。
ところが、現実にはそうはならなかった。この理由を考察してみるに、同じ「シンプル」でも9thは「冗長」と感じてしまったのに対して、10thは「ワンアイデア」の手法が強化されていると感じられ、さながら「アイデア集」の如き受け取り方が出来たのが良かったのではと思います。喩えるならビュッフェの美学で、多種多様なUnderworldらしさを味わえるところが、本作延いてはサンプラー版ならではの愉しみではないでしょうか。完全版を鑑賞したらまた違った感想が出てくるかもしれませんが、ともかく現時点で言えることは、シンプルさの隙間に鏤められたスパイスがしっかりと効いてくるような、そう表現したい楽曲が揃い踏みしているということです。
ということで、ここからは『DRIFT SERIES 1 - SAMPLER EDITION』(DISC 1)および日本限定のボーナスディスク(DISC 2)に収めれられている全18曲の中から、とりわけ気に入っているトラックを順不同で簡単に紹介していきます。YouTube上に公開されている作品も多く、埋め込み過多によって重いかもしれませんがご了承ください。なお、以降で表示する曲番号はサンプラー版に準じたものですが(1-01.ならDISC 1の1曲目といった具合)、そもそも『DRIFT SERIES 1』は5つのエピソードに大別されており、完全版はそれに則った収録順となっているので、その情報も曲番号の後に併記しておきます。
1-06. SCHIPHOL TEST(Ep.4 [Space] Pt.2)
「JAL to Tokyo」(2005)を彷彿させる暫定的な曲名だと思ったら案の定、佐久間さんの解説文によるとスキポール空港での飛行機待ちの間にiPadで制作された楽曲のようです。シンプルでバウンシーなリズムトラックの上を、カールの浮遊感のあるボーカルが漂う、実にUnderworldらしいサウンドメイキングが印象的な良曲。歌詞内容も単純だからこそ素晴らしく、幾度も繰り返される"Push"や"Moving on"や"One"に潜む洗脳的な心地好さには、まさに"Connected to the source"の心持ちを覚えます。
本曲をトップバッターに持ってきた理由は、先述の「アイデア集」的なファクターが顕著に窺えるからで、具体的には2:57以降の技巧性な変化の付け方を絶賛したいからです。"For someone"を合図に、続く歌詞頭の"The rhythm"の[rí]が吃音じみたリピートに陥り、同時に墜落していくイメージの縒れたストリングスが場を支配し、3:27から独特のリズムを刻み出す展開に、初聴時は思わず唸ってしまいました。鍵盤か弦楽器か判然としませんが、同時に鳴り出す切なくて仄暗い音の残響もひたすらに素晴らしいです。
サンプラー版に収められているのは4:42までで、"One, One, One, One"で消え行くクロージングも刹那的で格好良くはあるけれども、完全版および上掲動画の8分超えのバージョンと比べると物足りなさを拭えません。後者では次第に歌詞が複雑になっていく対比が見られ、"Whose words are these?"から始まる苦悩の吐露パートを経て、"Tell me I'm not crazy"で悲しく結ばれるのは、非常にドラマチックだと言えます。7:08から残響に混ざり出すチープな音も地味に好みです。
1-02. THIS MUST BE DRUM STREET(Ep.3 [Heart] Pt.3)
初聴時にはそこまで耳に残らなかったものの、その魅力が後からじわじわと主張を強めてきて、今ではサンプラー版の中で最も好きなトラックにまで昇格しました。佐久間さんも解説の中で本曲を絶賛しており、大いに同意したいと思います。ベースラインの素敵さはご指摘の通りで、終始楽曲を力強く牽引していてダンサブルです。2:40からの単純なシンセによる畳み掛けもグルーヴィーで、一段と踊れる仕上がりになっています。
とても個人的な所感を付け足しますと、本曲を聴いたらなぜかSFCのゲームソフト『スーパードンキーコング』シリーズのBGMが脳内に浮かんできました。全体的にトライバルなところもその根拠となりますが、とりわけ0:47から鳴り出すロングトーンの音は、近しいものをゲームの中で聴いたことがあるような気がしたくらいです。雄大で険しい自然を予感させる、暗示的なサウンドスケープとでも言いましょうかね。上に埋め込んだ「(Film Edit)」ではこの音を確認出来ないため、音源化に際したナイスアレンジだと評しておきます。ビートがガチャガチャし出す1:06からの忙しなさも好みで、小さなバネを弾いた際のビヨビヨした成分を含んだ音(電子機器から乾電池を抜いた時に聴こえるようなもの)が、左右に小刻みにパンして作るリズムがユニークです。これも上の「FE」だと聴き取りにくい気がしますね。
本曲が更に面白いのは、これだけクールなバックトラックを下敷きにしておきながら、ボーカルがなぞるリリックが"Do you want to buy my car?"と、文脈が謎のフレーズである点です。何処か神聖性を覚えるクリアなエフェクトまで施されており、"僕の車を買わない?"(歌詞対訳:伴野由里子さん)といった普通の一節が、あたかも啓示らしく響いてきます。
2-05. DUNE(Ep.3 [Heart] Pt.1)
本作を初めて通して聴いた時に、最も感銘を受けたのは本曲でした。動画のコメント欄でも最多の支持を集めている通り、「Sola Sistim」(2002)が過るダウンテンポ志向の長尺トラックで、同曲が大好きな僕には気に入らない道理がありません。ただ、「SS」がダウナーで破滅的な世界観に根差しているとしたら、「DUNE」では反対に明るい展望が描かれていると感じられ、より癒される楽曲の軍配は本曲にあげたいと思います。モチーフが「デューン」である以上、癒しと言ってもそれは儚い希望に過ぎない気はしますけどね。
カールの歌唱もしくはポエトリーリーディングとしてもいいかもしれませんが、その落ち着いた声音の魅力が遺憾なく発揮されており、徐々にではあるけれども確実に変化していくチルなバックトラックの美しさと相俟って、延々と流していても全く苦痛になりません。一音一音に最適な塩梅のパラメータ(ADSRやベロシティなどの値のこと)が付加されているのは勿論、リズム隊には加えて絶妙な空間干渉力(リバーブやディレイなどの空間系エフェクトによる影響)が備えられていると聴き取れ、この匙加減はさすがベテランの面目躍如です。
1-08. S T A R (Rebel Tech Version)(Ep.5 [Game] Pt.6)
厳密にはEp.5のPt.6にあたるのは無印の「S T A R」で(上掲動画もこのバージョン)、「(Rebel Tech Version)」はサンプラー版のみの収録です。両者のサウンドは結構に趣を異にしていて、前者はブレイクビーツの強調が著しいのに対し、後者は「Tech」を冠しているだけはある電子的なアプローチが光っています。
ちなみにですが、動画のコメ欄でも指摘されているように、前者は過去曲「Lenny Panne」をベースにしており、ビートメイキングに既聴感を覚えた方は耳聡いです。同曲はスタジオ音源としては公式サイト限定販売のデジタル盤『Lovely Broken Thing』(2005)に、ライブ音源としては受注生産の『Live in TOKYO 25th November 2005』(2005)に、変化球としてはアプリ『iDrum Underworld Edition』(2009)にと、いずれも収録先がレアなので、熱心なファンでない限りは馴染みのないトラックかもしれませんね。ダウンロード購入が今でも可能かは定かでありませんが、上記のライブ盤は割とディスクユニオンで見かける機会も多いので、足繁く通っていればいつかは入手出来るでしょう。
話を戻して、どちらのバージョンにせよ本曲を決定付けるのは聴けば瞭然のヒップホップ要素で、この手のスタイルもまたUnderworldの得意とするところではありますが、本曲の特筆性は歌詞のカオティックさにあります。例示するのが面倒なほどに多くの著名人や有名キャラクターの名前がオンパレードする内容で、曲名に違わぬスター性にくらくらすること請け合いです。ただ適当に列挙しているわけでもなくて、音韻上ぴったりと嵌る名前が適切にチョイスされているため、イヤガズムを覚えますし更には口遊みたくなります。
1-04. BORDER COUNTRY(Ep.4 [Space] Pt.6)
Ø [Phase]をフィーチャーしたトラック。解説の佐久間さん曰く、アングラミニマルテクノDJ界隈での支持が厚いレーベル・Tokenの看板アーティストだそうなので(勉強不足の自身を恥じるばかり)、その触込みに偽りのない本曲の見事なミニマルさにはただただ感服致しました。このダークな疾走感はUnderworldの真骨頂と言っても過言ではないトラックメイキングであるため、この傑作がコラボによって生まれたこと自体が凄いと絶賛します。フェイズというかアシュレー・バーチェットの才能引き出し力、ヤバくね?と。
常に緊張の連続を強いられるヒリヒリとした音遣いが特徴的で、不安や焦燥を抱えたまま深淵に落ち込んでいくようなビジョンが浮かびます。しかし、ただ座して死を待つイメージではなくて、たとえ敵わずとも何とか足掻こうとする必死さが;そのためなら他の一切を犠牲にしても構わないといった攻撃性が、細かな音の積み重ねで次第に顕になっていると表現したいです。観念的な歌詞も意味深長で読み解き甲斐があり、出だしの"What's that noise?/Hit your head/But it don't hurt"が謳う正体不明の恐怖や、"Some are cold/Some are hot/Blah blah blah"に見られる曖昧さ加減に、何とも言えない気持ちになります。後者は訳詞も巧くて、"冷たいものもあれば/熱いものもある/とかなんとかね"は、戯けた結びが愛おしい名訳です。
以上、全18曲から抜粋してフェイバリットトラックを5曲紹介しました。サンプラー版から更に一部をレビューするというクローズドな言及ではありますが、本記事で取り立てた5曲だけを聴き比べてみても、収録曲の多彩さは推し測れると期待します。
ここまでにも度々ふれているように、曲名に特記がなくともサンプラー版に収められている楽曲はショートバージョンになっているものが多いので、全体像を掴みたければやはり完全版に手を出すしかありませんね。届くのが楽しみです。
■ 同じブログテーマの最新記事