今日の一曲!björk「Play Dead」【平成5年の楽曲】
【追記:2021.1.5】 本記事は「今日の一曲!」【テーマ:平成の楽曲を振り返る】の第五弾です。【追記ここまで】
平成5年分の「今日の一曲!」はbjörkの「Play Dead」(1993)です。初出は映画『The Young Americans』(邦題は曲名と同じ『プレイデッド』)のサウンドトラックで、同年の内にシングルとしてもリリースされました。
スタジオアルバムに於いては時期的に『debut』(1993)に収録されていいはずのナンバーですが、これは初期のエディションでは見送られています。理由はサントラのリリース日と近過ぎたからだと推測しますが、年を跨がずに出たリイシュー盤にはボーナストラックとして収められているため、後年からビョークを聴き始めた方にとっては、元より同盤の収録曲だという理解が優勢なのではないでしょうか。斯く言う僕も、残念ながら映画は観たことがないのでこのクチでした。
さて、当ブログでビョークの楽曲を扱うのはこれが初めてではなく、一昨年には現状の最新作である『utopia』(2017)のレビューをアップしています。それほど長きに亘って好んで聴き続けているわけですが、その音楽性を既存のジャンルで説明出来ると考えたことは個人的にあまりなく、一要素として電子音楽オリエンテッドなアレンジが魅力だとは言えるものの、「ジャンル名:ビョーク」と表現するのがいちばん据りが良いような、唯一無二のセンスが光るアーティスト性を備えた存在であるとの認識です。
アルバムも出す度に複雑性を増した仕上がりとなっていて、ひとつのジャンルでは形容不可能なクロスオーバーが披露されていると感じますが、遡って初期の作品に意識を向けると、比較的シンプルな楽曲も目立ちます。『debut』の収録曲では、例えば「Big Time Sensuality」や「Violently Happy」は、単純性を際立たせた反復の美学でもって、ダンスミュージック的なアプローチが特徴のトラックだと評せるでしょう。それはプロデューサーおよびライターとして、Nellee Hooperを共同制作者に招いていることと無関係ではないはずです。
その一方で、後の込み入った楽曲制作の片鱗を窺わせるようなナンバーもあり、とりわけハープが印象的な「Like Someone In Love」は、元々はジャズのスタンダードだという歴史のある楽曲ながら、そのサウンドから2017年の作品である『utopia』に入っていてもおかしくない奥深いアウトプットとなっており、今から振り返れば伏線的でもあるなと思いました。
そんな中で今回紹介する「Play Dead」に目を向けると、前述した収録経緯の特殊性も含めて、リリース年的には同時期となる他の『debut』収録曲とは、音楽性からして色々と趣を異にしていることが見えてきます。
冒頭に記した通り、映画の挿入歌ゆえに別次元の世界観とストーリー性を背景に抱えていることが一点目。ビョークはその後も『ダンサー・イン・ザ・ダーク』や『拘束のドローイング9』などで劇伴を手掛けるのみならず、自身が俳優として出演することでも活動の場を広げていきますが、これに「Play Dead」の成功は少なからず影響しているでしょう。尤も、女優業としては『プレイデッド』の公開年より前にも出演作品がありますし、彼女が嘗て所属していたバンド・The Sugarcubes時代のキャリアにまで遡れば、『ソドマ(・レイキャビク)』(英題:『Remote Control』)という映画にも音楽の提供はあるみたいです。
二点目は単純に、作編曲にもプロデュースにもネリー・フーパーがタッチしていないことによる差異です。ライターにはビョークの他にJah WobbleとDavid Arnoldがクレジットされており、ウォブルはイギリスのバンド・Public Image Ltdのベーシストして既に名が通っていた、アーノルドは後に『インデペンデンス・デイ』や『ジェームズ・ボンド (007) シリーズ』の劇伴を担った作曲家として有名になる存在で、この情報だけでもわかる人には堪らないポテンシャルの高さが窺えますよね。また、プロデュースにはアーノルドの他に『プレイデッド』の監督であるDanny Cannonもタッチしているので、映画のために抜かりの無いサウンドディレクションが行われたことがわかります。
バックグラウンドの紹介にかなりの文章を割いてしまい恐縮ですが、要するに'for film'の特性が存分に活かされたドラマチックな楽想が、『debut』の中で殊更に強大な存在感を放っていると言いたいのでした。これを踏まえた上で、ここからはもう少し具体的に「Play Dead」の内容に迫っていくとしましょう。
なお、情報が散漫になるのを防ぐ目的で先程は割愛しましたが、Additional productionおよびremixの担当者として印字されているTim Simenonまで含めると、都合5名がトラックメイキングに深く関わっていることになるため、以降の文章に於いて「誰がどの領分を担ったか」については、誤解や憶測も多分にあるかもしれないと断りを入れておきます。
スペイシーなパッドに足音のようなドラムスが重なり、怪しい雰囲気が醸されているイントロ。それを緊張感のあるストリングスが破り、俄にハードなビジョンが浮かんでくるという立ち上がりには、劇伴作家としてのアーノルドのスタイルが色濃く反映されているように感じます。歌始まりまでのブラスのインサートも、聴き手の期待感を煽る技巧的なものであると高評価。
イントロは同時にファンキーなベースラインの格好良さを心地好く味わえるセクションでもあり、これにはベーシストとしてのウォブルの手腕が振るわれているのだろうと思っています。その後も曲全体を通してベースは只管にクールですが、鮮やかなプレイが冴え渡る類のものというよりは、シンプルな繰り返しによる陶酔感の拡大に重きが置かれているようなスタイルであるので、そこに電子音楽的な良さが宿っているとも言えそうです。
英語版のWikipediaでは'trip hop-influenced track'と形容されていますが、トラックだけを取り立てたら確かにその向きもあるかなという気はします。アーノルドとウォブルと勿論ビョークのそれぞれの得意な分野が放り込まれた本曲を表すならば、複数のジャンルに跨るカテゴライズになることは自然でしょうから。加えて、後にリリースされる『POST』(1995)と『homogenic』(1997)を語る際にも、トリップ・ホップはキーのひとつとして挙げられる音楽性であるため、「Play Dead」は後続作への布石となる曲だったのかもしれませんね。
補足:ここの文章に曖昧なところがあるのは、僕自身が実はあまりトリップ・ホップというジャンルをよく理解していなからです。この類の音楽がよりメジャーとなった後年から電子音楽畑に踏み入ったからでしょうが、わざわざ特定のジャンル名を用いる必要性がわからず、ヒップ・ホップ的なビート感で構成されているテクノ或いはエレクトロニカは、そのままこう表現されるだけの基本的なトラックメイキング方法のひとつであるとのイメージでしかありません。当時は斬新だったがゆえに特別な呼称が付いたのでしょうが、今はその時に流行したミュージシャンの新譜でもない限りは、わざわざ使用しない言葉ではないでしょうか。ただ、よりビートレスになって近接ジャンルとされているダウンテンポまでいくと、以前に上げたThe Sushi Clubの記事に書いたように、好みのアプローチになりますし特筆性もあると考えています。そもそもビョークに関しては先に記したように「ジャンル名:ビョーク」の認識なので、詳細にタグ付けしていくこと自体に懐疑的ですけどね。
トラックの方向性はどうあれ、ビョークの歌声が入ると一気に彼女の楽曲として成立します。10年代のナンバーに比べると格段にわかりやすくはあるものの、アレンジの素直さに対するメロディラインの複雑性もしくは譜割りの独特さは、この頃から芽生えていたのだと分析可能です。小節に囚われない音符の乗せ方に妙味があるとも言い換えられますが、その結果として纏わり付くような歌い方になっても気持ち好さを維持したままでいられるのは、真に歌が上手く声質にも魅力のあるシンガーだからこそ為せる業であると絶賛します。
自傷的な歌詞内容も実にビョークらしく、"darling"の呼び掛けに続くのが甘いフレーズではなく"stop confusing me/with your wishful thinking/hopeful embraces"といった拒絶である点や、自身を取り巻く環境を"no-one cares and no-one loves/no light no air to live in/a place called hate"と無慈悲の畳み掛けで描いているところ、長いので中略表記にしますが"it's sometimes"から"every ache"までに語られる苦痛の浄化プロセスの丁寧さ、それらをまとめて表題の"i play dead"に結ぶ説得性の大きさなどは、彼女ならではの表現力が遺憾無く発揮された結果でしょう。
平成5年分の「今日の一曲!」はbjörkの「Play Dead」(1993)です。初出は映画『The Young Americans』(邦題は曲名と同じ『プレイデッド』)のサウンドトラックで、同年の内にシングルとしてもリリースされました。
 | Young Americans 1,695円 Amazon |
スタジオアルバムに於いては時期的に『debut』(1993)に収録されていいはずのナンバーですが、これは初期のエディションでは見送られています。理由はサントラのリリース日と近過ぎたからだと推測しますが、年を跨がずに出たリイシュー盤にはボーナストラックとして収められているため、後年からビョークを聴き始めた方にとっては、元より同盤の収録曲だという理解が優勢なのではないでしょうか。斯く言う僕も、残念ながら映画は観たことがないのでこのクチでした。
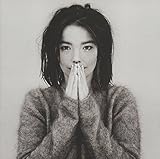 | Debut 1,453円 Amazon |
さて、当ブログでビョークの楽曲を扱うのはこれが初めてではなく、一昨年には現状の最新作である『utopia』(2017)のレビューをアップしています。それほど長きに亘って好んで聴き続けているわけですが、その音楽性を既存のジャンルで説明出来ると考えたことは個人的にあまりなく、一要素として電子音楽オリエンテッドなアレンジが魅力だとは言えるものの、「ジャンル名:ビョーク」と表現するのがいちばん据りが良いような、唯一無二のセンスが光るアーティスト性を備えた存在であるとの認識です。
アルバムも出す度に複雑性を増した仕上がりとなっていて、ひとつのジャンルでは形容不可能なクロスオーバーが披露されていると感じますが、遡って初期の作品に意識を向けると、比較的シンプルな楽曲も目立ちます。『debut』の収録曲では、例えば「Big Time Sensuality」や「Violently Happy」は、単純性を際立たせた反復の美学でもって、ダンスミュージック的なアプローチが特徴のトラックだと評せるでしょう。それはプロデューサーおよびライターとして、Nellee Hooperを共同制作者に招いていることと無関係ではないはずです。
その一方で、後の込み入った楽曲制作の片鱗を窺わせるようなナンバーもあり、とりわけハープが印象的な「Like Someone In Love」は、元々はジャズのスタンダードだという歴史のある楽曲ながら、そのサウンドから2017年の作品である『utopia』に入っていてもおかしくない奥深いアウトプットとなっており、今から振り返れば伏線的でもあるなと思いました。
そんな中で今回紹介する「Play Dead」に目を向けると、前述した収録経緯の特殊性も含めて、リリース年的には同時期となる他の『debut』収録曲とは、音楽性からして色々と趣を異にしていることが見えてきます。
冒頭に記した通り、映画の挿入歌ゆえに別次元の世界観とストーリー性を背景に抱えていることが一点目。ビョークはその後も『ダンサー・イン・ザ・ダーク』や『拘束のドローイング9』などで劇伴を手掛けるのみならず、自身が俳優として出演することでも活動の場を広げていきますが、これに「Play Dead」の成功は少なからず影響しているでしょう。尤も、女優業としては『プレイデッド』の公開年より前にも出演作品がありますし、彼女が嘗て所属していたバンド・The Sugarcubes時代のキャリアにまで遡れば、『ソドマ(・レイキャビク)』(英題:『Remote Control』)という映画にも音楽の提供はあるみたいです。
二点目は単純に、作編曲にもプロデュースにもネリー・フーパーがタッチしていないことによる差異です。ライターにはビョークの他にJah WobbleとDavid Arnoldがクレジットされており、ウォブルはイギリスのバンド・Public Image Ltdのベーシストして既に名が通っていた、アーノルドは後に『インデペンデンス・デイ』や『ジェームズ・ボンド (007) シリーズ』の劇伴を担った作曲家として有名になる存在で、この情報だけでもわかる人には堪らないポテンシャルの高さが窺えますよね。また、プロデュースにはアーノルドの他に『プレイデッド』の監督であるDanny Cannonもタッチしているので、映画のために抜かりの無いサウンドディレクションが行われたことがわかります。
バックグラウンドの紹介にかなりの文章を割いてしまい恐縮ですが、要するに'for film'の特性が存分に活かされたドラマチックな楽想が、『debut』の中で殊更に強大な存在感を放っていると言いたいのでした。これを踏まえた上で、ここからはもう少し具体的に「Play Dead」の内容に迫っていくとしましょう。
なお、情報が散漫になるのを防ぐ目的で先程は割愛しましたが、Additional productionおよびremixの担当者として印字されているTim Simenonまで含めると、都合5名がトラックメイキングに深く関わっていることになるため、以降の文章に於いて「誰がどの領分を担ったか」については、誤解や憶測も多分にあるかもしれないと断りを入れておきます。
スペイシーなパッドに足音のようなドラムスが重なり、怪しい雰囲気が醸されているイントロ。それを緊張感のあるストリングスが破り、俄にハードなビジョンが浮かんでくるという立ち上がりには、劇伴作家としてのアーノルドのスタイルが色濃く反映されているように感じます。歌始まりまでのブラスのインサートも、聴き手の期待感を煽る技巧的なものであると高評価。
イントロは同時にファンキーなベースラインの格好良さを心地好く味わえるセクションでもあり、これにはベーシストとしてのウォブルの手腕が振るわれているのだろうと思っています。その後も曲全体を通してベースは只管にクールですが、鮮やかなプレイが冴え渡る類のものというよりは、シンプルな繰り返しによる陶酔感の拡大に重きが置かれているようなスタイルであるので、そこに電子音楽的な良さが宿っているとも言えそうです。
英語版のWikipediaでは'trip hop-influenced track'と形容されていますが、トラックだけを取り立てたら確かにその向きもあるかなという気はします。アーノルドとウォブルと勿論ビョークのそれぞれの得意な分野が放り込まれた本曲を表すならば、複数のジャンルに跨るカテゴライズになることは自然でしょうから。加えて、後にリリースされる『POST』(1995)と『homogenic』(1997)を語る際にも、トリップ・ホップはキーのひとつとして挙げられる音楽性であるため、「Play Dead」は後続作への布石となる曲だったのかもしれませんね。
補足:ここの文章に曖昧なところがあるのは、僕自身が実はあまりトリップ・ホップというジャンルをよく理解していなからです。この類の音楽がよりメジャーとなった後年から電子音楽畑に踏み入ったからでしょうが、わざわざ特定のジャンル名を用いる必要性がわからず、ヒップ・ホップ的なビート感で構成されているテクノ或いはエレクトロニカは、そのままこう表現されるだけの基本的なトラックメイキング方法のひとつであるとのイメージでしかありません。当時は斬新だったがゆえに特別な呼称が付いたのでしょうが、今はその時に流行したミュージシャンの新譜でもない限りは、わざわざ使用しない言葉ではないでしょうか。ただ、よりビートレスになって近接ジャンルとされているダウンテンポまでいくと、以前に上げたThe Sushi Clubの記事に書いたように、好みのアプローチになりますし特筆性もあると考えています。そもそもビョークに関しては先に記したように「ジャンル名:ビョーク」の認識なので、詳細にタグ付けしていくこと自体に懐疑的ですけどね。
トラックの方向性はどうあれ、ビョークの歌声が入ると一気に彼女の楽曲として成立します。10年代のナンバーに比べると格段にわかりやすくはあるものの、アレンジの素直さに対するメロディラインの複雑性もしくは譜割りの独特さは、この頃から芽生えていたのだと分析可能です。小節に囚われない音符の乗せ方に妙味があるとも言い換えられますが、その結果として纏わり付くような歌い方になっても気持ち好さを維持したままでいられるのは、真に歌が上手く声質にも魅力のあるシンガーだからこそ為せる業であると絶賛します。
自傷的な歌詞内容も実にビョークらしく、"darling"の呼び掛けに続くのが甘いフレーズではなく"stop confusing me/with your wishful thinking/hopeful embraces"といった拒絶である点や、自身を取り巻く環境を"no-one cares and no-one loves/no light no air to live in/a place called hate"と無慈悲の畳み掛けで描いているところ、長いので中略表記にしますが"it's sometimes"から"every ache"までに語られる苦痛の浄化プロセスの丁寧さ、それらをまとめて表題の"i play dead"に結ぶ説得性の大きさなどは、彼女ならではの表現力が遺憾無く発揮された結果でしょう。