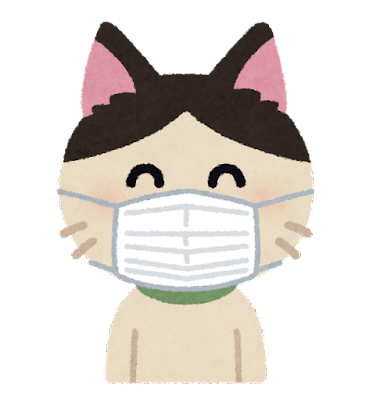暑い季節になると増えてくるのが「虫刺され」です。
蚊、ブユ、アブ、毛虫、ノミ、ダニなど多彩ですが、
とくに気をつけなくてはいけないのがハチです。
【種類・時期】
ヒトを刺すハチは、主にミツバチ、スズメバチ、アシナガバチの3種類で、
危険な時期は、スズメバチとアシナガバチは7~9月、ミツバチは1年中です。
【症状】
刺されると、強い痛みとともに皮膚が赤く腫れ、水疱になることもあります。
【応急処置】
傷口を水でよく洗い流し、毒を手で絞り出す。針が残っていたら抜く。
傷口を冷やす。抗ヒスタミン剤やステロイドの軟膏を塗る。
こうした症状は自然に良くなることがほとんどで、初めて刺された場合は
それほど心配することはありませんが、2度目に刺された場合は要注意です。
【ハチアレルギー】
1度刺されて体内に抗体ができると、2度目以降に刺された時に
アレルギー反応が現れることがあります。
刺されてから15分以内に、全身にかゆみや発疹、顔の火照り、むくみ、嘔気
などが現れ、さらに動悸、呼吸困難、意識障害を来す場合は「アナフィラキシ
ー・ショック」を起こした可能性があります。
非常に危険ですので、すぐに救急車を呼びましょう。
とくにスズメバチ、アシナガバチに刺された場合は注意が必要です。
【予防】
ハチが多い場所で作業する際は、
顔面を保護する「防蜂網」や「防護手袋」を使用しましょう。
ハチは、ヘアスプレーや香水などの匂いに反応して攻撃する習性があります。
またスズメバチは、黒い物(黒髪、黒い服、黒い靴など)に激しく反応し攻撃
する習性もあるので要注意です。
私のような白髪頭の人は安心ですね。
皆さんも「泣きっ面に蜂」にならないよう、この夏も笑顔で過ごしましょう。
【大久保忠俊(おおくぼ ただとし)医学博士・大久保外科/消化器科院長】
大久保外科/消化器科 浜松市中区菅原町16−15(県居小学校そば)
TEL:053-453-4598 FAX:053-453-4975
 ホームページは
ホームページは