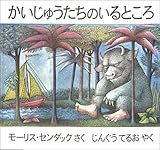- かいじゅうたちの、にんげんどらま
- かいじゅうたちのいるところ/モーリス・センダック
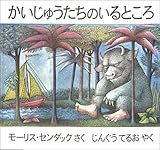
- ¥1,470
- Amazon.co.jp
誰でも知ってる、とまでは行かないかもだけど、何処かで見たことがあるというくらい有名な絵本を原作とした映画。なんだけれども、監督が
スパイク・ジョ-ンズ(俺はあんまり観てないけどね)だから一筋縄じゃあ行かない作品に仕上がっている。
原作のあらすじ。
ふざけてお母さんに叱られた子供・マックスが部屋に閉じこめられる。
すると部屋が森のように変化して、マックスはそこからボートに乗って一年と一日航海して「かいじゅうたちのいるところ」へ到着する。
かいじゅうに脅かされるも対抗するマックスはかいじゅうたちから一目置かれ、王様になって踊ったり騒いだり。
しかし何処からかいい匂いがしてきたのでホームシックになり帰ろうとする。
かいじゅうたちは「食べちゃいたいくらいお前が好きなんだ、食べてあげるから行かないで」と言うが、「いやだよ」と断り一年と一日航海して部屋に戻ってくると、まだ温かい夕食がテーブルの上に置いてあった。
というお話。
正直これを1時間半から2時間にするという事自体が難しい。
アニメでそのままやれば、15~30分くらいで終われるレベルの話だからだ。
映画にするとしても、せいぜい騒いでるシーンを増加させるくらいだろう。
しかしひねくれ者のスパイク・ジョーンズは、この作品を解体&再構築して、
同じ筋であるにも関わらずかなり毛色の異なる作品に仕立て上げてしまった。
流石、というべきか。
原作者センダックも気に入っていると言うことだし、原作の行間を埋めるみたいな話でもあったようだが、結果的には
受ける印象がかなり違う。お陰で
映画公開自体が危ぶまれたという話だが、その作品性を評価されて無事公開に漕ぎ着けた由。
何が一番異なっているか。
マックスとかいじゅうたちとの関係性だろう。
原作ではマックスは母親に叱られるも、部屋の中から異世界に飛び出して「かいじゅうたちのいるところ」を征服し、恋しくなったから帰る。短い筋だからと言うのもあるが、そこには子供らしい
万能感・全能感という物が見え隠れしている。かいじゅうたちは恐ろしい部分も無いではないがユーモラスで、全体を通して
マックスに従属する存在だ。
最初はマックスの威嚇に驚いて王様に仕立て上げ、最後は「食べてあげるから」と懇願するもにべもなく断られる。だからマックスの部屋が森に変貌するという状況も加わって
ある種の子供の理想郷、空想の世界を思わせる(但し、空想なのか現実なのかを困惑させる仕掛けもある)
一方映画では
マックスは孤独な存在として描かれる。
父親の居ない家庭。
マックスは一人でイグルーを創って遊び、姉に見せようとするも相手にされない。
姉の友達に雪合戦を仕掛けて束の間楽しむも、巫山戯た彼らにイグルーを壊されて泣きわめき、姉の部屋を荒らす。母親はある程度の理解を示すが、マックスが自室に秘密基地を創っても見に来てくれない。
若い男性と仲良くお酒を飲んでいる。
マックスはこれに怒り、母親と喧嘩をして外に飛び出し、外の川からボートで航海をする。
単なるイタズラ、喧嘩ではなく、孤独感が埋められない為の逃避であることが示されている。
「かいじゅうたちのいるところ」の性質も、かなり異なっている。
かいじゅうたちにはそれぞれの性格付けがなされており、
彼らには彼らの関係性を持っている。
マックスはその中の一人、
キャロルの持つ不満ややるせなさに自分を重ね合わせて共に暴れる。
キャロルはKWというかいじゅうと仲違いをしており、その怒りをぶつけてかいじゅうたちの家を破壊する。
マックスも協力するが、他のかいじゅうに詰め寄られる。
そこで
苦肉の策として自らが力ある者、王様であることを語るのだ。
絵本ではマックスは自らの威嚇によってかいじゅうたちを驚かせて(力を示して)王様に推戴される。
映画でもキャロルに望まれる部分こそあれ、
危機を脱する為の方便として自らの力を誇張する。
この時点で、既に
マックスの立場の危うさが示されている。
王様の冠と杖も、
「前の王様」らしき骨の中から取り出される。
キャロルは骨について「最初からあった」と語るが、これが嘘であり
前にも何人か王様が居て、みんな食べられてしまったことが終盤で分かる。
そしてマックスは
孤独を埋めることをかいじゅうたちに懇願され、請け負う。
かいじゅう踊りを踊り、みんなで重なって寝て、キャロルの理想とする世界の模型を見せて貰い、みんなで一つの家を造ろうと提案する。KWもなし崩し的にコミュニティへ帰還し、一応の平和が築かれる。
しかしマックスの子供らしい提案は、
根本的に問題を解決出来ずに、再びかいじゅうたちに亀裂が入り始める。
最終手段の泥団子合戦は姉の友達との雪合戦同様、楽しいと思った矢先に
問題が暴発してしまう。
KWはキャロルの元から去り、
キャロルは王様に対する苛立ちと不信感をあらわにする。
そしてマックスがただの子供であることをしって怒り狂って追いかけ始める。
KWにかくまって貰って難を逃れたが、そこでマックスは家に帰ることを考えるのだ。
ここに示されるのは
万能感とはほど遠い。
マックスがぶち当たる
現実の壁であり、無力感だ。
実際マックスは
かなり利己的に描かれており、特にデイヴィスはマックスに皮肉やからかいの言葉を投げかけ、アレクサンダーはかいじゅうたちの中でも軽んじられていて、マックスにも無下に扱われる(しかし単に嫌な奴、どうでもいい奴じゃないところがこの作品の面白いところだったりする)
マックスは
家族というコミュニティの断裂に不満を感じて逃避し、同じように
不満を抱いていたキャロルへ共感を覚えるのだが、今度はキャロルを中心としたコミュニティの断裂に耐えきれず、元の世界に戻ろうとする。
これもまた逃避であり、「かいじゅうたちのいるところ」も理想郷と見えたのは僅かの間だった。
理想郷など存在しない。
ある意味、
子供には過酷すぎる事実を容赦なく叩き付けてくるのがこの作品だ。
映画会社のお偉方が渋面を作ったのも理解出来る。
しかしこれはスパイク・ジョーンズが
子供をナメていない証拠だ。
かいじゅうたちの複雑さも、問題の提起も、
親が見せたい子供の映画では取り払われる類のものだ。
けれど
『ジャッカス』というガキみたいな大人の企画をやってきた彼にとっては、子供はあやす者ではなく、包み隠さず対等に話し合い語り合う者なのだろう。
理想郷は存在しないし、問題の無いコミュニティも無い。
それは隠してはいけない、必要なことだからこそ示すのだ。
もちろん、問題だけを言いっぱなしという訳でもない。
希望も提示する。
別れのシーンがそれであり、家に帰ってきたシーンも同様だ。
生きている限り問題は起きるかもしれない、でも、
許し合うことだって、仲直りすることだって出来る。
大好きという気持ちさえあれば。