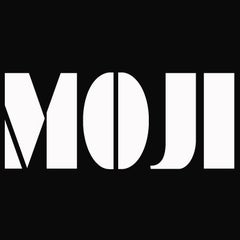The Witches(2020 アメリカ)
監督:ロバート・ゼメキス
脚本:ギレルモ・デル・トロ、ロバート・ゼメキス、ケニヤ・バリス
原作:ロアルド・ダール
製作:ジャック・ラプケ、ギレルモ・デル・トロ、アルフォンソ・キュアロン、ルーク・ケリー
撮影:ドン・バージェス
編集:ジェレマイア・オドリスコル
音楽:アラン・シルヴェストリ
出演:アン・ハサウェイ、オクタヴィア・スペンサー、スタンリー・トゥッチ、クリス・ロック
①クセが強い「奇妙な味」
「チャーリーとチョコレート工場」のロアルド・ダール原作、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のロバート・ゼメキス監督。
アメリカでも2020年公開予定でしたが、配信のみに切り替えられてしまったようです。
日本を含む海外では、予定通り公開。日本もギリギリで先はわからない感はありますが、まずはよかった。
脚本にギレルモ・デル・トロが参加してます。アルフォンソ・キュアロンと共に製作も兼ねてる。
欧米では熱心なファンが多いんですね、ロアルド・ダール。
映画化も多い。「チャーリーとチョコレート工場」はティム・バートンだし、「ファンタスティックMr.FOX」はウェス・アンダーソン。「BFG:ビッグ・フレンドリー・ジャイアント」はスピルバーグ。
思い入れの強いクリエイターも多いようです。子供の頃に本を読んでるんでしょうね。
児童文学ながら、非常にブラックで「奇妙な味」がある、ロアルド・ダールの童話。
上記した映画もそうだけど、結構「クセが強い」のですよね。非常に毒が強くて、時にびっくりするぐらい残酷。
日本では宮崎駿がファンだと発言してますが。割と、優しい作品を好む日本人には評価が分かれるかもしれない。
藤子不二雄Aがブラック短編を描くにあたって、ロアルド・ダールの味を狙った…というのを読んで、なるほどと思った記憶があります。
藤子不二雄Aの漫画の味わいが、とても近い気がします。意地の悪いブラックな笑いと、オモチャっぽいガチャガチャした賑やかさ。
そういうロアルド・ダールの持ち味が、存分に発揮された映画だと思います。
「奇妙な味」が嫌いでなければ、きっと楽しい時間を過ごせるんじゃないでしょうか。
②怖い魔女と弱者の戦い
不幸な少年(ジャジール・ブルーノ)は交通事故で両親を失い、おばあちゃん(オクタヴィア・スペンサー)に引き取られます。
おばあちゃんのおかげで悲しみも癒え、楽しく過ごす少年ですが、ある日不気味な女に出会います。おばあちゃんはそれは邪悪な魔女だと言い、子供の頃に友達がニワトリに変えられた話をして、危険から逃れるために海岸のホテルへ出かけます。
しかしそこには、強大な力を持つ大魔女(アン・ハサウェイ)が大勢の魔女を引き連れて来ていたのです…。
魔女が怖い!です。
魔女は完全に邪悪な存在で、何よりも子供というものを憎んでおり、子供をいじめることに喜びを見出している。
魔女はお菓子をくれるけど、貰ったが最後、魔法で動物に変えられて、叩き潰されてしまう。
問答無用。言い訳なし。最初は怖く見えるけど、だんだん人間味が見えて優しくなる…とか、湯婆婆みたいなことは一切なし。
最初から最後まで、ひたすら邪悪で怖い。
そして、中身だけじゃなく見た目も怖いですからね。
魔女は口が耳まで裂けていて、手には鉤爪の指が3本、足には1本しかなくて、髪の毛はカツラで脱いでしまうとつるっぱげ。
美人のアン・ハサウェイがゲラゲラ笑いながら、この正体を晒すシーンはまさに悪夢です。夢でうなされそう。
そんな魔女に対抗するのは、幼い少年と年老いたおばあちゃん。
当然魔法の力もなく、財力も後ろ盾も何もない。子供と老婆だから、普通の大人に比べても弱い。
そんな弱者代表みたいな二人が、怖くて強力な怪物である魔女たちに対抗していくわけです。
映画では二人が黒人に設定されてて、60年代アメリカという背景からも、社会的な弱者であることがより強調されているようです。
子供たちは常に弱い立場に置かれるものだから、主人公たちにどっぷり感情移入して、ドキドキ、ハラハラしていくことになる。
弱者が知恵や勇気で強者を打ち負かすのは、だからカタルシスがあるし、児童文学の教科書みたいな展開ですね。
ただ、そこはロアルド・ダールだから。過程もシビアで容赦がない。
主人公の少年はあっさり大魔女に捕まって、ネズミに変えられてしまいます。ここ、子供たちはびっくりして、絶望感を感じるでしょうね。
子供とおばあちゃんというだけでもかなりハンデのある弱者だったのに、更に弱々しいネズミとおばあちゃんにされてしまう。
ちっぽけなネズミにされて、床を走り回るはめになって、それでもめげない。少年は前向きに、同じくネズミにされた仲間も得て、勇敢に魔女に立ち向かっていきます。
この展開、絶体絶命の危機は子供をやきもきさせるはずだし、魔女が怖ければ怖いほど、逆境でもめげない勇気も伝わるはずですね。
さすが、一見ガチャガチャして見えるけど、実は非常に教育的だし、きちんと子供に向けた作品になってると思います。
③容赦のない怖さはジュブナイルの原点!
本作の容赦のない怖さは、今だったらもっとマイルドに改変されちゃいそうなところだけど、日和らずに真っ向描いてるのは偉いなと思います。
そこはやっぱり、作り手が子供の頃に読んで、ショックを受けて記憶に刻まれて、その強烈な印象をきちんと再現したいと思ってるからなんでしょうね。
考えてみれば、子供に向けた物語というのはもともと、そういう容赦のない怖さを伴うものだったんですよね。
民話が元々は非常に残酷だったり。狼に食われちゃう赤ずきんとか、狼のお腹に石詰めて沈めるとか、婆さん殺して爺さんに食わせるかちかち山とか。
外国でも日本でも、昔から子供はドギツイ残酷な話をドキドキしながら楽しんで、その中でしてはいけないことを学んできたわけです。
本作で言えば、知らない人にお菓子もらっちゃダメ、という教訓とかですね。
その教訓が教訓として子供の心に残るためには、悪者はとことん悪くて、怖くなくちゃならない。
悪者だと思ったけど結構いい人で、反省して改心して味方になった…という話では、結局何も心に残らないんですよね。
だから…脱線しますけど…「鬼滅の刃」なんて、すごく理想的な「少年漫画」だし、これはまさに子供に見せるべき作品だと思うんですよね。
悪の残酷さ、取り返しのつかない死の怖さが存分に描かれているからこそ、悪を憎む心が育ち、悪に屈しない尊さが伝わるわけだから。
鬼滅って、死は取り返しがつかない。戦いの終わりは戦闘不能とかでごまかさず、常にどちらかの死で終わる。
殺すことも取り返しがつかない。一人でも人を殺したら、許されることは絶対にない。だから、よくある敵が味方になるみたいな展開もないんですよね。
このシビアさは、単なる刺激を求めた残酷趣味ではなく、子供に向けた表現としてむしろ基本に立ち返ってるんじゃないかと思えます。それが大ブームになってるというのが、面白いですね。
④過酷な運命に立ち向かう!
閑話休題!
「魔女がいっぱい」の真のシビアさは、最後に発揮されます。以下ネタバレ。
魔女をやっつけても、主人公はネズミから人間に戻らない!
仲間も、みんな戻らない! ネズミのまま!
これからの人生はネズミとして生きていくけど、仲間もいるし、慣れたらそれなりに楽しいし、ネズミでも愛してくれるおばあちゃんと一緒だから大丈夫。
いや、敵をやっつけたら呪いは解けて元に戻れる…という展開を見過ぎているので、これはかなり意外な展開。
すんなりと、ハッピーエンドとして受け入れ難いものがありました。
キツいのは、ネズミだから寿命が短いということが示唆されるんですよね。
実際にエピローグでも、おばあちゃんはそれほど変わらないのにネズミは老いていく。
おばあちゃんと一緒に生きて、一緒に死ねる! 良かった!と本人は言うのだけど。
それをハッピーエンドと思うには、まだまだ修行が足りない感じです。
これは原作に忠実であるようで、原作でも大きな衝撃として受け取られるところみたいです。
そしてやっぱり、この意外性があるからこそ、本作は人々の記憶に刻まれるのでしょうね。もし子供の頃に読んでたら、良くも悪くも強烈に記憶に残ったと思います。
この世界は、常に勧善懲悪になるとは限らない。
何の落ち度もない子供がひどい目にあって、そのままどうにもならないなんていう理不尽も起こり得る。
ちょうど、クリスマスの日に両親を一気に失うなんてことが起こり得るように。世界はそんな不条理に満ちている。
そんな世界観は、子供が受け取るにはなかなかハードだと思うけど。
でも、たぶん子供の頃に読んでいたら、そんな不条理の中でもとことん前向きに生きようとする主人公の姿が、強い印象になっていたのではないかと思います。
世界が時に残酷なのは、嘘じゃないしね。オブラートに包まれた、甘やかされた優しい世界より、ずっと真実味を持って感じられる。
そして、そんな世界でも前向きに生きられるということも、決して嘘ではないわけで。
正しい人が報われるとは限らない、理不尽なこともいっぱいある世界。
手放しのハッピーエンドに終わらない、どこか苦いものが残るからこそ、その中で生きることが切実に感じられる。
そう言えば鬼滅も…って、ネタバレ厳禁ですね。
⑤伝統的はちゃめちゃナンセンスの魅力
と、いろいろシビアなストーリーだけど、それ以上にはちゃめちゃなドタバタ劇である本作です。
魔女たちにネズミになる薬を飲ませたら、みんなロケットみたいに飛び上がっって空中でネズミに変身して、大騒ぎになっていく…。
「BFG」でもオナラでロケットになってましたね。そういう男子小学生的な身もふたもないナンセンスも、ロアルド・ダールの味だったりします。
たぶんマザーグースやアリスから、ハリポタのハナクソ味までずっと続く、イギリス的ナンセンスの系譜。
モンティパイソンとか、ジョン・レノンとかにも通じるような。ここは日本では、好みの分かれるところでしょうね。
映画では舞台はアメリカになってて、ソウルミュージックが鳴り響くのですが。この雰囲気も、良かったですね。
コンプライアンス的なことを言うと、本作は魔女の「3本指」の表現に関して、障害者団体から抗議を受けて謝罪したそうです。
指の欠損を悪人の印にしちゃうのは、これは確かにマズかったですね…。原作にはない特徴であるようなのでなおさら。
そこは確かに抗議されてもしょうがない…と思ったのですが、ただ、何かとコンプライアンスにうるさくて、「誰かを傷つけるかもしれない表現」にうるさい風潮の中で、本作のブラックに徹した作りは僕は好ましいと感じました。
やっぱり、黒いものや毒のあるものを「なかったことにする」のは何か違うと思うから。だって、現実世界にはそういうものは現にあるんだから。
それだけに、突っ込まれどころがない形にしているとより良かったのかな…。
ロバート・ゼメキス監督の前作。これもクセの強い映画だったなあ…。
ロアルド・ダールの原作本。
ロアルド・ダール原作シリーズ。