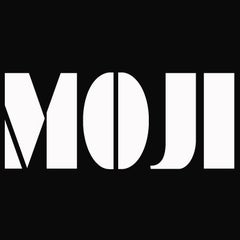The Favourite(2018 アイルランド、アメリカ、イギリス)
監督:ヨルゴス・ランティモス
脚本:デボラ・デイヴィス、トニー・マクナマラ
製作:セシ・デンプシー、エド・ギニー、リー・マジデイ、ヨルゴス・ランティモス
撮影:ロビー・ライアン
衣装:サンディ・パウエル
美術:フィオナ・クロムビー
編集:ヨルゴス・モヴロフサリディス
出演:オリヴィア・コールマン、エマ・ストーン、レイチェル・ワイズ、ニコラス・ホルト、ジョー・アルウィン、ジェームズ・スミス、マーク・ゲイティス、ジェニー・レインスフォード
①コメディ寄りだけど毒も健在の、野心作
ヨルゴス・ランティモス監督といえば、昨年の「聖なる鹿殺し」が強烈に印象に残っています。
ギリシャ神話の悲劇を現代に持ち込んだような、残酷な不条理劇だったんだけど、実にブラックな、コールタールのようにドス黒い、まさに暗黒のような映画でした。
ホラー的に怖いというわけではないんだけど、とにかく気が悪い。底意地が悪い。
まるで人間を虫ケラのごとく見下ろす冷笑的な視点が、強烈で。いまだに脳裏に焼きつけられてます。
こうして映画の印象を書いていくと、まるで貶しているみたいになるんだけど。
でも、この底意地の悪さがね。なんというか、逆に気持ちよくなってくるんですよね。
突き抜けたブラックさの面白さ。いつの間にか癖になる、危険な麻薬のような映画作家だと思いました。
その監督が、今度はコスチュームもの? 実在の女王や貴族を題材に、中世イングランドの王宮劇。
でも、普通の史劇じゃない。女王の寵愛を巡って、女同士が熾烈な騙し合い、謀り合い、蹴り落とし合いを演じる。これは…かなりの底意地の悪さが期待できそうです。
トラウマ級のダークさに突き落としてくれることを期待して、観に行ってきました。
で、その辺に関しての感想を先に言うと、今回「聖なる鹿殺し」ほどの邪悪さはありませんでした。ブラックコメディですが、どちらかというとコメディの方に重心の振れた作りです。
普通に、笑えます。毒は効いてますがでも引いてしまうほどではなくて、ちゃんとコメディになってます。
女3人のぶつかり合いはまさに格闘技。本当にエンタメとして面白い。今回、娯楽映画としてばっちり成立してると思いました。
あ、あくまでも当社比ですが。「聖なる鹿殺し」と比べればだいぶマイルド、というだけで。
毒はしっかりとあります。普通の王宮歴史絵巻を期待して観にくると、のけぞると思います。
「Fuck!」とか連発されるしね。歴史的な正確さも、ほとんど重視されていません。
いい人と悪い人がいる世界観じゃなくて、出てくる奴はみんなおかしい。腹黒くて、身勝手で、行動をどんどんエスカレートさせていく。
そんな有り様を、例の高みから見下ろす視点で、嘲笑するように撮っていきます。
ランティモス監督の持ち味をしっかりとキープしつつ、前作よりはだいぶ観やすくなっている。間口を広げつつも作家性を失っていない、野心作と言えるのではないでしょうか。
②グングンのし上がるアビゲイルの痛快さ
18世紀初頭のイングランド。アン女王(オリヴィア・コールマン)は女王として絶大な権力を持ちながら、持病の痛風に悩み、政治に関しても無知でした。政治の実権を握っていたのは、幼馴染で女王の信頼厚いレディ・サラ(レイチェル・ワイズ)。進行中のフランスとの戦争で、サラは戦争を避けて講和を進めようとする野党のハーリー(ニコラス・ホルト)を退け、アンを主戦論に導いていました。
そんな中、サラの従妹と名乗るアビゲイル(エマ・ストーン)が王宮にやってきます。彼女は元貴族でしたが、父親が賭けにはまって財産を失い、没落していました。王宮の女中になったアビゲイルは、女王の痛風に効く薬草を献上したことから気に入られ、サラの侍女に抜擢されます。アビゲイルは更に、さまざまな手段で貴族へののし上がりを画策していきます…。
まずはアビゲイルですね。彼女の強さ、たくましさ。
貴族の娘から、糞の匂いのする泥を浴びる境遇におちぶれ、女中部屋の中でも女中頭にいじめられ、悲惨な状況を余儀無くされる。
それでも、全然めげないんですね。常に強気な目を崩さず、チャンスを虎視眈々と狙っている。
昔の少女漫画みたいな設定なんだけど、いじめられてかわいそう…というふうには決してならない。
罰を受ける時とかはわざと悲鳴をあげたりして、めいっぱい同情を引く。
女王が通りかかるところで、「ゴホゴホ…」と咳をしてみせたりね。どうしたのか聞かれると、「薬草を探しに行って、風邪をひいてしまって…」と弱々しく説明して。
彼女が偉い人の信用を得ていくと、情報を得ようとして、いろんな人たちが近づいてくる。そんな相手にも、「ご主人様の信頼は裏切れません…」なんてしおらしい態度を見せながら、その実それもうまいこと利用していく。
アビゲイルが目立ち出すと、男も寄ってくる。彼女に言い寄ろうと迫るマシャムを、良いようにあしらうアビゲイルの様が痛快です。あしらうというか、もうほとんど殴る蹴る。貴族の男相手でもまったく物怖じせずに、甘噛みかと思えば本気のダメージを与えたりして、いつの間にか相手を屈服させてしまう、天性のご主人様ぶり。
侍女の身ながら女王に直訴してマシャム大佐との結婚を認めさせ、いよいよ貴族の一員たる立場を手に入れると、もう用済みとばかりに夫のことなど顧みず、次のターゲットへと狙いを絞ります。初夜の様子は爆笑ものです。
そしていよいよ、最大の難敵レディ・サラとのガチンコ対決へ…。
小分けのチャプター構成になっていて、アビゲイルがどんどん出世していく様が小気味好く、非常にテンポよく楽しむことができます。
エマ・ストーンの気の強そうな表情が、実にはまり役だと思います。
でも、なんていうか…どこか「望んでやっちゃいない感」があるというか。
そもそも時代も状況も風習も何もかもが「ちょっと…いや、まるっきりおかしい」んですよね。そんな中に放り込まれて、生きていくためにはこうするしかない、どこかやり切れない感じがある。
それはアビゲイルだけじゃなく、サラにも、女王にも同じなんですけどね。
③貴族も庶民も嘲笑う、絶望的な世界を見下ろす視点
中世という時代の、貴族たちの生活風俗のヘンテコさ。
これを、ランティモス監督は得意の「嘲笑う視点」で、とことん滑稽に、醜悪に描き出していきます。
ものすごいゴテゴテした服を着ていて、男たちも化粧していて、おっさんたちもフサフサのかつらかぶってて、ものすごいゴテゴテした広大な屋敷に暮らしている。
女王がサラに「何その化粧。アナグマみたい」とか言われるんだけど、他の全員も似たり寄ったり。生活がそのまま、やりすぎの舞台芸術みたいになっています。
そんな贅沢を尽くした宮殿で、アヒルを競争させたり、ロブスターを競争させたりして遊んでる。
あるいは、おっさんを裸にしてトマトを投げつけたりね。いったい何が面白いんだ…。
宴会をしては、そこらの高そうな壺にゲロゲロと吐く。
醜悪の極み。倦怠の美もへったくれもない、ただただどうしようもないまでの傲慢で幼稚な暮らしぶり。
そんなはちゃめちゃな暮らしをしている連中が国を牛耳っていて、戦争するかしないか、税金上げるかどうか、なんてことを全部決めている。
どう見てもその資格のない人たちが、国民の生殺与奪を握っている。その空恐ろしさ。
そういう意味では、定番の金持ち批判、指導者層への風刺、傲慢な上流階級への批評という側面もあるんだけれども。
でも、それだけに終わっていない。ただの王室批判にはとどまらない、もっと人間全般を見下した、冷徹な視点というものがあるんですね、この監督には。
描かれていくのは英国王室の無様さなんだけど、でもただ英国王室だけをバカにしているわけではない。
もっと大きく、人間の在りようそれ自体をバカにしている。
視点は王室の中に固定され、その外の世界というのはほぼ描写されません。一般庶民の生活というのは、ほとんど描写されないんだけれども。
しかし、この無能でめちゃくちゃな指導者層に支配され、導かれている世界なんて、どうせろくなもんじゃなかろうと思えてしまう。
バカな女王にバカな貴族、それに支配されてる一般庶民もみんなバカ。
風刺の度合いが突き抜けていて、もうあらゆる対象を見下してしまっています。そんな視点。
一般庶民の様子は、ちょっとだけ出てきます。アビゲイルが王宮に着く前、乗合馬車の描写。それから、サラが落馬してけがをして、担ぎ込まれた売春宿の描写。
前者では男がいきなり自慰を始めてアビゲイルに見せつけるし、後者では庶民も貴族も薄汚い小屋みたいなところで売春に勤しんでる。サラを売り物にしようとするけれど、いとも簡単に後ろ盾を呼ばれて脱出されちゃう売春宿の主人も形無しで。
庶民だから貴族よりつつましいとか、賢明であるとかってわけでもないんですよね。みんな愚かであって、どっちもどっちの世界でしかない。
でね、そこまで「見下した視点」が徹底されると、これはもはや一周回って、喜劇というより悲劇に見えてきちゃうんですよね。
本当にもう、どうしようもない人間の世界。それでもその中でじたばたあがいて、生き抜いていかなければならない人間の悲劇。
醜悪なおばちゃんのご機嫌とって、ウサギのご機嫌もとって、あんなとこ揉んだり、あんなとこ舐めたりして……
痛風抱えてケーキを貪り食い、召使いに怒鳴り散らし、いちばん信頼していた友人も信じられなくなる女王も同じだし、権力を保ち続けるために立ち回って、あげくに寵愛を失って放逐されるサラも同じ。
みんな、絶望的な世界の中に生きている。キーワードは「絶望」ですね。
この世界は絶望的。「聖なる鹿殺し」と同じ。
中世英国の王室だけじゃない。現代の、我々の世界だって同じ。
この世は絶望的で、我々はみんなその中で鼻をヒクヒクさせて生きるウサギ。それが、ヨルゴス・ランティモス監督の世界観ですね。
④そして終盤は女王の悲劇へ
映画は後半になるにつけ、喜劇から悲劇へと見え方を変えていきます。
同時に、アビゲイルの成り上がりストーリーとして、アビゲイルを中心に据えていた視点から、少しずつサラやアン女王の内面へと移行していくことになります。
観客も、序盤はアビゲイルに感情移入していたのが、彼女がやり過ぎになってきて悪役にシフトしていくとともに、サラやアン女王に興味が移っていく。
劇中での心変わり、「お気に入り」の変遷を、観客も実感していくことができる。そういう仕掛けになっていますね。
サラは、最初のうちほとんど女王を傀儡のようにして操る影のボスとして、絶大なパワーを見せます。
アビゲイルの台頭でその立場を脅かされかけると、そのしたたかな面を見せつけてアビゲイルを圧倒するのですが、そこでアビゲイルが実力行使に打って出る。ここが運命の分かれ目ですね。
それでもなお、サラは気力を失わないんだけど、落馬事故によって顔に傷を負ったのが致命傷でした。それによってサラは、アン女王の寵愛を失うことになってしまいます。
最後にサラの運命を決めるのは、アビゲイルではなくアン女王でした。ここから、アン女王が大きな存在感を見せつけていくことになります。本作の主役はアビゲイルでもサラでもなく、アン女王であることがはっきりするんですね。
痛風に苦しみ、肥満した体を支えられず、精神的にも不安定で、しょっちゅう怒鳴り散らしているアン女王。17回も流産や死産で子供を失い、17匹のウサギを飼っている。
彼女の「お気に入り」になろうとして、サラとアビゲイルが争う。彼女たちだけでなく、大臣や政治家たちも…要は女王以外の皆が、女王の「お気に入り」になろうとしています。
この状況、アン女王の側から見てみれば、取り巻く人々はみんなウサギと一緒ですね。
かわいがってやるか、冷たく接するか、それはアン女王が決められる。人々はただすり寄ってくるだけ。どうするか決めるのはアン女王だけ。
こうなっては、そりゃあ国にも政治にも民衆にも、興味なんて持てないですね。自分以外の人は、みんなウサギでしかないのだから。
女王にすべての権力が集中する国のシステムが、問題なんですけどね。みんなわかってるんだろうけど、どうにもできない。女王本人も含めて。
わけのわからない「決まり」の中で、ウダウダとやっていくしかない。これまた、絶望ですね。
終盤、アン女王とサラの間の関係は、純愛めいた感じにも見えてきます。
ただ一人、アン女王を叱りつけることのできたサラ。
本音で接してくれるサラを必要としていたアン女王。
でも、アビゲイルの存在で、二人のバランスは崩れてしまって。互いに必要だった相手を失って、特にアン女王は、いよいよどうしようもない孤独の中に沈んでしまうことになります。
サラだけは、ウサギではなかったかもしれないんですけどね。サラが消えて、王宮に残ったのは取り囲むウサギだけ…。
喜劇の主人公であり、見ようによっては悲劇の主人公であるアン女王を、オリヴィア・コールマンが魅力的に演じています。
オリヴィア・コールマン、サラを演じたレイチェル・ワイズよりも年下なんですね。そうは見えない…と思ったけれど、実際のサラとアン女王の関係も、サラの方が年上だったようです。だから、これも史実通りなんですね。驚くべきことに。
⑤史実はというと…?
はちゃめちゃな物語なんですが、登場するのはすべて実在の人物。史実を背景にしています。
…ということ自体、驚いてしまうんですが。
アン女王は1665年生まれ。最後のイングランド王国・スコットランド王国君主にして、最初のグレートブリテン王国君主として知られています。
1683年にデンマーク王子ジョージと結婚。それから毎年のように妊娠しましたが、6回の流産、6回の死産を経験し、無事に生まれた子も幼くして死亡しました。その数17回。
サラ・チャーチルは1660年生まれ。1673年にヨーク公の夫人付きの女官に取り立てられ、1675年頃からヨーク公の次女アンと親友になります。
1677年にヨーク公配下の軍人ジョン・チャーチルと結婚。1683年にアンが結婚すると、アンの寝室付き女官に任命されました。
1685年にヨーク公がジェームズ2世としてイングランド王に即位。1688年には、王に反発するウィレム3世がオランダ軍を引き入れ、アンとサラはホワイトホール宮殿に軟禁されました。この時、自分を勇気付けてくれたサラにアンは感謝を抱き、以降、より厚遇するようになっていきます。
ジェームズ2世は亡命し、ウィレム3世は妻メアリー(ジェームズ2世の長女、アンの姉)とともに1689年にイングランド王に即位します。
この頃から、サラはアンの側近として影響力が知られるようになっていきました。メアリーは不快感を示し、アンにサラを解雇するよう迫りますが、アンは拒絶。姉妹関係は悪化します。
メアリーに嫌われ、アンとサラ、チャーチルは冷遇されることになります。しかし、1694年にメアリーが天然痘で急死。さらに1702年にはウィレム3世が急死し、アンが女王として即位します。
女王になったアンはジョン・チャーチルをマールバラ公として授爵。サラは「ミストレス・オブ・ザ・ローブス/王室女官の最高位」に任命されました。
アン女王はまた、サラにオックスフォードシャーの広大な荘園を与え、サラは宮殿の建設を始めました。この件は、映画の冒頭で語られています。
アンが即位した頃から、スペイン継承戦争が本格化しています。これはスペイン王位の継承者を巡って行われた戦争で、1701年から1714年にかけて続きました。イングランドはオランダ、ポルトガルなどとともに、フランス王国、スペイン帝国などと戦うことになります。
アン女王はジョン・チャーチルをイングランド軍総司令官に任命、その友人のシドニー・ゴドルフィンを大蔵卿に任命して、戦争を遂行させていきます。
戦争中の1707年には、イングランドとスコットランドが統合されてグレートブリテン王国となり、アンはその最初の君主となりました。
サラは女王の側近として権力を振るいましたが、やがてアン女王は和平推進派に傾き始め、サラを疎むようになっていきます。
サラやゴドルフィンがひいきにし、戦争推進派の立場をとるホイッグ党を、アンは嫌うようになっていきました。かわりに、サラの従妹アビゲイル・メイシャムを重用し、和平を推進するトーリー党に近づいていきます。
アビゲイル・メイシャムは1670年生まれ。父はロンドン商人、母はサラの叔母に当たります。生活が窮乏していたため奉公に出されていましたが、サラに引き取られ、1702年にアンが即位してからは、サラの斡旋で寝室付女官として宮廷に入りました。
1704年頃からサラが宮廷を休みがちになり、アンとサラの関係が冷え込むようになると、アンに重用されるようになっていきます。
トーリー党の指導者ロバート・ハーレーがそんなアビゲイルに目をつけ、彼女を通してアンと通じるようになります。
1707年にサミュエル・メイシャムと結婚した時、アンからは持参金を提供される一方で、サラは招待されなかったばかりか、しばらくその事実を知らされることもありませんでした。
アンとサラは多くの書簡を交換していましたが、アンが多くの手紙を書いてもサラからの返事はまれでした。また、サラが宮廷を長く離れ、自身の宮殿にばかりいるのにも、アンは苛立っていました。アンはトーリー党への支持をあらわにするようになっていましたが、サラは夫のためにホイッグ党を支援するようアンに求め続けました。
1708年、アンの夫ジョージが死亡します。サラは悲嘆に暮れる女王に別の宮殿に移るように言いましたが、アンは断り、アビゲイルを呼ぶように命じました。
アビゲイルの影響力に気づいたサラは、夫の死に嘆き悲しむアンを叱りつけました。しかしこれは、アンの気持ちを著しく害することになりました。
サラはアビゲイルに苛立ち、アンに同性愛傾向があると暴露したりしましたが、女王との仲は修復不能でした。
1710年、サラは宮廷から追放され、ゴドルフィンも更迭。総選挙でトーリー党が大勝して、ハーレーが大蔵卿に就任。マールバラ公も司令官を罷免され、夫妻は1712年にイングランドを離れます。
アン女王は、晩年には歩くこともできないほど肥満していました。1714年に崩御した際、棺桶は正方形に近いものだったと言います。
アビゲイルはサラにかわって権力を手にしましたが、1714年にハーレーが大蔵省を罷免され、アンが死去すると辞任して宮廷から離れることになります。1734年に亡くなりました。
サラはアン女王が崩御した1714年にイングランドに戻りました。アン女王に次に即位したジョージ1世に協力したのはホイッグ党で、マールバラ公も勢力を回復。サラは1744年まで生き、84歳という長寿を全うしました。その家系からはウィンストン・チャーチル、ダイアナ妃などが出ているということです。
…というのが、史実です。映画とあんまり変わらないことに驚いてしまいます。あんなこと、本当にやってたんですね…。
たぶん日本の時代劇とかも、こういうシニカルな視点で撮ったらブラックコメディになるんだろうなと思います。古今東西、人間のやってきたことって、バカでヘンテコなんでしょうね…。