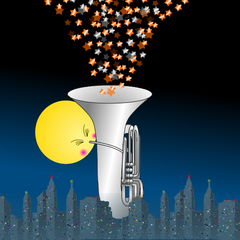Claude Maulyのオムニトニックに関する記事の考察、連載11は、John Callcottのホルンです。
今回は、あまり追加説明する必要もないので、Mauryの記事を、そのまま引用します。
特許取得済みの楽器に加えて、ジョン・コールコットの「ラディウス・フレンチ・ホーン」(1801〜1882年)は、それを再発見したフィリップ・ベイトのおかげで、オムニトニック・ホーンのファミリーで最も関連文書を残した楽器の1つです 1947〜48年頃、その後1950年にそれを取得したレジナルド・モーリー・ペッジ、そして最後に1980年代後半にベイト大学歴史楽器コレクションのためにそれを修復したピーターバートンオックスフォード。 3人全員が、それぞれ1949年、1950年、1990年にThe Galpin Society Journalに掲載された記事に証言を残しました。さらに、Morley-Peggeは、彼の著書The French Horn(1960)のオムニトニック・ホーンに関する章でそれらを分析します。
フィリップ・ベイトによってダブリンで見つかった楽器には、次の碑文があります。
「J. CallcottのRadiusフレンチホルン。優勝」。
ホーン自体は、長い円筒形のパイプで構成されます。このパイプには、それぞれ半音に対応する毎に、可動伸縮可能なパイプと接続できるピストンを備えたノッチがあります。
各ノッチは、押されると、そこから空気を逃すピストンを備え、適切な場所に挿入された伸縮可能な管が、ピストンを押すと空気は、その可動管に導かれます。
単一の連続パイプで構成され、半音ごとに単純に穴が開けられたこの楽器は、この効率的な方法で、ハイBからローBまでのすべてのトーンを提供しますが、ピーターバートンのように、フィリップ・ベイトも「特に高音域では、気柱の円筒形状があまりにも大きいため、音質に問題あり」と言及しています。
この問題は、楽器のデザインそのものが原因で、タバード楽器の問題と似ています。
ベイトがそれを見つけた状態では、楽器には2つのペリネットピストンが装備されており、1つ目は空気の柱を1音伸ばし、2つ目は半音だけ伸ばすようになっていますが、これらのピストンはオリジナルではありません。
Morley-Peggeがそれを取得したとき、機器はすでに元の状態に戻されていました。つまり、バートンの復元のずっと前に、ピストンはありませんでした。
ColdstreamGuardsオーケストラの非常に若いメンバーであるCallcottは、長年にわたってロンドンオペラの3rdホルンでした。 Morley-Peggeによると、彼のホーン「Radius」は、1851年のロンドンでの展覧会の直前にトーマスキー(バートンは疑う)によって作られたようです。
「新しく発明されたホーン。 その応用可能な新機能は、一般的に使用される移調が統合されています:音色を変更するには、連続パイプを13の部分に分けます。各部分は半音で区切られ、そこに開口部があり、そこに小さなパイプが挿入され、 ホーンを中心に向け、そこを任意の方向に回転させて、ホーンを通過するときに空気を受け取り、外部パイプに向けて空気を導きます。」
特許庁の「仮出願」の中で、Morley-Peggeは「Exhibition1851.Class10.No.547.J.Callcott’sRadiusFrenchHorn andCornet-à-Piston」というタイトルの文書を発見しました。これは、機器のかなり詳細な図面、およびその原理と有用性の説明を示すシンプルなシートです。残念なことに、このテキストは実際には現実に対応しておらず、公式特許も取得していないようです。 リーフレットには、当時の有名なホルン奏者の証言、特にPuzziの証言も含まれています
ようは、中心から同心円状に伸縮する管が、穴に見えるが実は中にバルブが仕組まれている部分にはめ込まれて、コイル状の管のその場所までの長さのホルンとなるといことです。
つづく