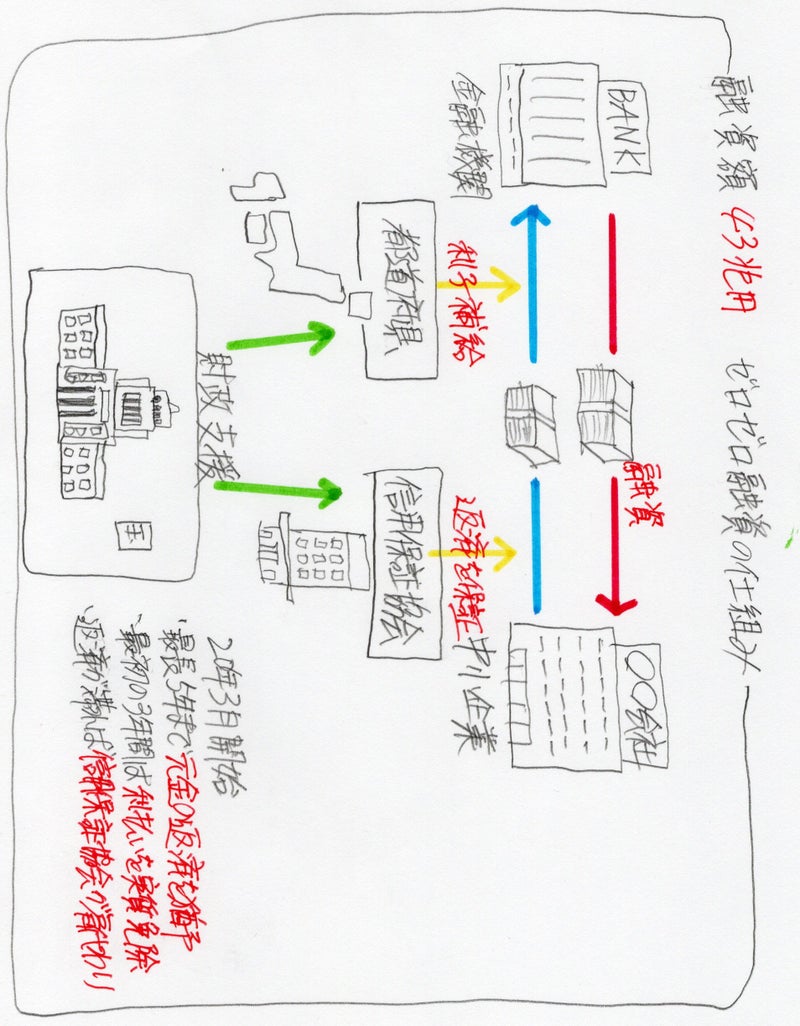1999年(平成11年)10月2日に県内地銀四行の一角・新潟中央銀行が経営破綻し、県内金融地図が大きく塗り替えられようとした年。
本県は全国有数のオーバーバンキング(銀行過剰)地域とされ、その数は地銀四行、信用金庫、信用組合十四組合。
大手銀行がこぞって支店を構え、金融激戦区を形作っていった。
ペイオフ(破綻銀行の預金の払い戻し限度額を一千万とする措置)解禁。
信用組合に対する激しい不良債権分類基準の導入。
環境変化に対応しようと各金融機関は生き残り策を模索する。
県内では1998年長岡信用組合、朝銀新潟信用組合が破綻。
証券業界に転じれば、地場の越後証券、日新証券が姿を消し、県経済の象徴といえる新潟証券取引所が明治以来の歴史に幕を下ろす。
地域金融が次々と倒れ行くさまは、新時代へ。
2000年代の始まりとなる県内金融再編時代への序章ととらえ、県内金融会の歴史を振り返る。
過去を振り返ると,本県を含め国内の金融機関は合従連衝(がっしょうれんこう)や自由化への対応など繰り返す歴史を歩んできた。
明治維新後、政府が近代化に向け取り組んだのが経済の整備だった。
富国強兵を最重要課題として揚げ、殖産興業を目指し国立銀行条例を制定する。
本県でも、第四国立銀行(旧第四銀行)や第六十九国立銀行(旧北越銀行)などが相次いで産声を上げた。
新潟証券の取引所の前身となる米の取引所が発足したのも明治初期だった。
明治、大正初期は各地で金融機関が乱立時期でもあった。
ピーク時には九十二行がひしめき合った。
これほどの数の金融機関が存在し得たのは、県内の有力経済人が相次いで銀行業に参入したためだ。
勃興(ぼっこう)した石油産業の隆盛も銀行設立ラッシュに拍車をかけたが、大正以降、幹部らの不正経理や昭和恐慌が経営を直撃、次第にその姿を減らしていき、戦時下はさらに集約が進んだ。
戦後、日本経済は連合国軍総司令官(GHQ)の指令下に入り、財閥銀行は解体、金融機関の名称変更が相次ぐ、本県でも六十九銀行が北越銀行に改称した。
1949年には新潟証券取引所が開所する。
当時の地場業者は二十五にのぼったが、売買が東証へ集中していく中で減少し、五社となった。
金融機関の合従連衝が本格化するのは60年代ころからで、68年に三井銀行と東都銀行が合併する。
72年には第一銀行と日本勧業銀行が合併し、国内トップバンクとなる第一勧業銀行が誕生した。
本県金融界に変化が現れたのは79年のこと。
大光相互銀行の幹部らによる不正融資が発覚、総額百四十億円にのぼる不正融資事件は現社長らの逮捕に発展した。
信金、信組の合併も相次いだ。
80年に長岡信金と栃尾信金が合併。
86年に糸魚川信組と能生信組が、88年に新栄信組と新潟産業信組が、89年には新潟大栄信組と相川信組がそれぞれ合併した。
金融の自由化も徐々に進んだ。
譲渡性預金(CD)の販売が79年から始まり、85年には市場金利連動型預金(MMC)の取り扱いがスタート。
銀行と証券業務の垣根(ファイアウオール)の撤廃、信託業務への参入、相互銀の普銀転換の方針も打ち出された。
バブル崩壊後護送船団方式に守られた金融界にも国際競争の荒波が押し寄せる。
国際決済銀行(BIS)による自己資本比率の達成や不良債権の処理などが急務となり、生き残りをかけた合併、提携が進んだ。
その一方で、競争に敗れる金融機関も続出、山一証券や北海道拓殖銀行、日本債券信用銀行、日本長期信用銀行の経営が相次いで行き詰まった。
県内でも新潟中央銀行以前に、長岡信組が破綻し、北越銀行に営業譲渡、新潟証券も自主廃業に追い込まれた。
金融年表
1946年(昭和21年)県商工経済会を解散、新潟商工会議所設立
1948年 長岡六十九銀行、北越銀行と改称
1949年 新潟証券取引所開所。1ドル=360円の単一為替レート設定
1965年 山一証券の経営悪化表面化。日銀が特別金融措置を決定
1968年 三井銀行と東都銀行が合併
1969年 新潟東港が開港
1971年 ニクソン・ショック。米国が金とドルの交換停止など新経済政策発表。円切り上げ、1ドル=308円に。第一銀行と日本勧業銀行が合併、国内トップバンクに
1973年 第一次オイルショック。円、変動相場制に移行。神戸銀行と太陽銀行が合併、太陽神戸銀行誕生
1975年 繊維不況、栃尾や五泉などの産地に影響
1979年 大光相互銀行で乱脈融資事件。不正融資総額は約142億円。第二次オイルショック。都銀などが譲渡性預金(CD)の販売を決定
1980年 長岡信用金庫と栃尾信用金庫が合併、長岡信金に
1985年 金融機関が市場金利連動型預金(MMC)の取り扱い開始。プラザ合意、円高進行
1986年 糸魚川信組と能生信組が合併し、糸魚川信組に。住友銀行が平和相互銀行を吸収合併
1987年 ブラックマンデー、株式相場が暴落。国際決済銀行(BIS)、銀行の自己資本比率の国際統一基準案を発表、最終目標を8%に達成に
1988年 新栄信組と新潟産業信組が合併、新栄信組に
1989年(平成元年)消費税スタート。相互銀行52行が普銀転換、新潟相互銀が新潟中央銀に、大光相互銀行が大光銀に改称。新潟大栄信組と相川信組が合併、新潟大栄信組に
1990年 株価暴落。大蔵省、不動産業向け融資に対し総量規制の方針を通達。太陽神戸銀行と三井銀行が合併
1991年 地価高騰、新潟、長岡の最高路線価格が前年比30%以上アップ。協和銀行と埼玉銀行が合併。証券会社による損失補てん発覚。富士銀、東海銀、協和銀で巨額不正融資事件。日銀、窓口指導を廃止
1992年 証券取引等監視委員会が発足
1993年 共同債権買収機構が発足。銀行の証券子会社、証券会社の信託子会社が相次ぎ営業開始。民間金融機関、変動金利預金と中長期預金の取り扱い開始
1994年 三菱銀行、日本信託銀を子会社に
1995年 木津信用組合など金融機関の破綻続出
1996年 三菱銀行と東京銀行が合併。住専問題表面化、処理に税金投入
1997年 越後証券が自主廃業決定。北海道拓殖銀行、山一證券が破綻。證券・金融不祥事が発覚、幹部ら相次ぎ逮捕。改正預金保険法が成立。金融機関の破綻処理手法を拡充
1998年 長岡信用組合が自主再建断念、北越銀行に営業譲渡。大蔵省、日本銀行汚職事件。金融安定2法が成立。預金者保護と金融システム安定目指し総額30兆円の公的資金投入可能に。改正外為法と日銀法が施行、日本版ビックバン(金融制度改革)がスタート。大蔵省から金融検査、監督部門を分離した金融監督庁が独立。金融再生委員会が発足。金融再生法が成立、施行。日本債券信用銀行、日本長期信用銀行が破綻
1999年 新潟中央銀行が破綻。国民、幸福、なみはや、東京相和の第二地銀各行も破綻。朝銀新潟信組が破綻し、朝銀関東信組に事業譲渡へ。第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が業務提携発表。都銀や信託銀などの合併・提携発表相次ぐ