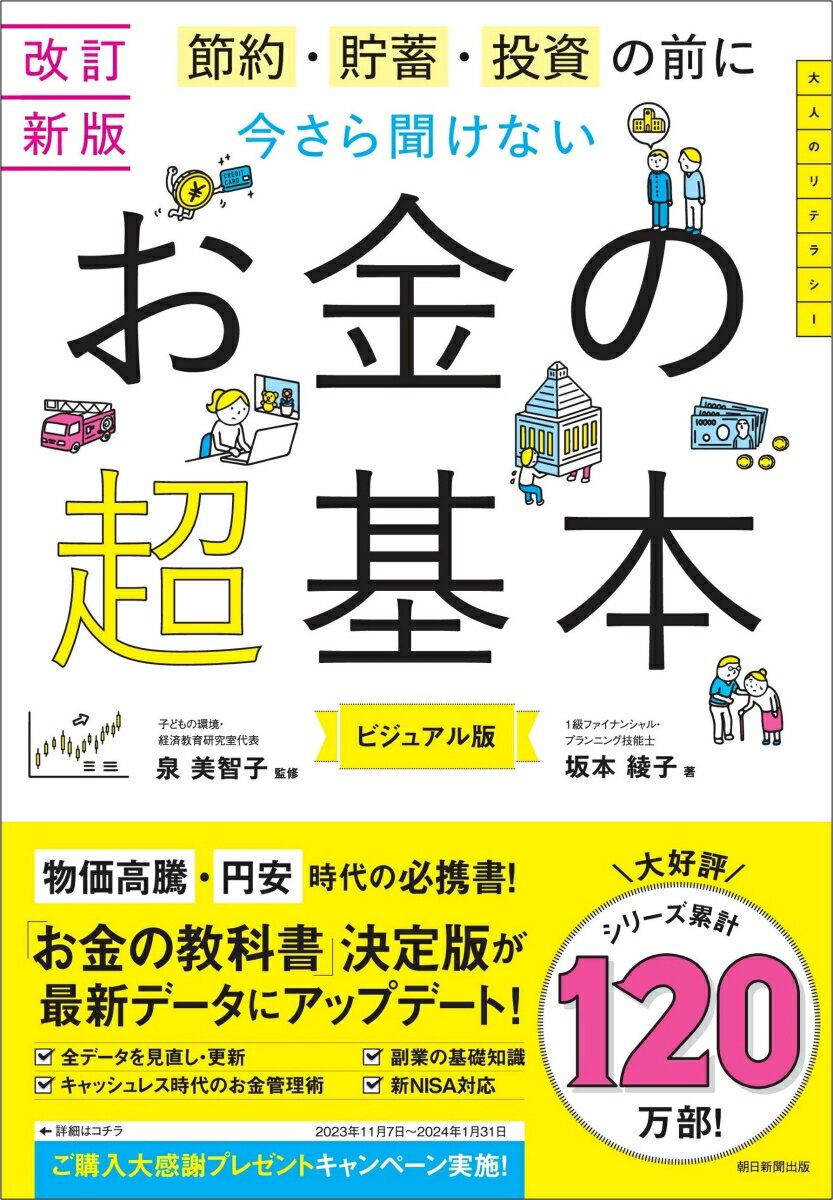お金が持っている6つの機能とは。
お金という言葉を耳にした時にどんなイメージをお持ちでしょうか?
お金のことを口にするのが下品であるとかそういった、お金に対するマイナスイメージを持っていないでしょうか?
このマイナスイメージを捨てることが極めて重要だということです。
当たり前ですがお金というのは生きていくために絶対に必要なものであります。
お金があるに越したことがないというのは同意するところでしょう。
上手な使い方をすればお金は私たちにとてつもなく大きなパワーを授けてくれるんです。
ですがお金に対するマイナスイメージがあると、どうしてもお金を稼ぐことに消極的だったり、お金を遠ざける行動を自然にとってしまうのでマイナスイメージは捨てましょう。
近年お金を取り巻く状況が急速に変わりつつあります。
クレジットカードやオンライン決済の普及で現金が手元になくても生活できるようになってきました。
さらにインターネット上で使える、未来のお金である仮想通貨も話題です。
この仮想通貨を活用すれば、海外送金が瞬時に安くできることから注目され、需要が高まり価値が高まってきました。
今後、仮想通貨で支払いができるお店がどれくらい増えるかによって、仮想通貨がどれぐらい普及するのかは変わってきますが、大きな可能性が秘められております。
またお金の変化に加えて、私たちの寿命は伸び続け、人生100年時代を迎え、生き方や働き方を見直す必要性も高まっております。
さらに、これからの日本経済はどうなってしまうのか。
10年先、私の給料一体どうなるのかといった、不安に苛まれるようになる。
こうした疑問なり不安なりに答えようとすればお金を抜きにして、経済に関わる話は実のところ、お金の一語につきます。
お金は今や日本そして世界の経済と社会を考えるにあたって、絶対に欠かせないキーワードとなっている。
自分、そして家族の人生を正しく賢く舵取りするには、まずはお金の動きと働きを正しく理解することが絶対に必要です。
お金に関する知識や勉強は難しいというイメージを持っている人もいるでしょう。
知らない、分からないと初めから逃げ腰になってしまっている人も、お金に関する知識を基本から身につけていただきたいと思います。
このような大きな状況の変化についていけない人、あるいはお金のことを習わないままに大人になってしまった人たちなどは、お金についてしっかり向き合って学び直す必要があります。
私たちにとってお金とはどういうものでしょうか。
お金とは生きていくために欠かせない「暮らしの道具」と考えると分かりやすいです。
衣・食・住はもちろん、自分の楽しみのために使いたい。
病気やけがの時も困らないようにしたい。
老後も充実した人生を送りたい。
私たちの願いを叶えるための道具こそがお金です。
しかし、道具である以上、その機能と扱い方を知らないまま闇雲に使ってもうまくいかないと思います。
道具をしっかりと使いこなすには、機能と扱い方をしっかりと抑えて、上手に使うことが重要です。
お金を上手に使うことができれば、自分らしい人生の実現に大きく近づくことができます。
では、具体的にお金という道具にはどんな機能があるのか。
お金には次の6つの機能があります。
1 稼ぐ
2 納める
3 貯める
4 使う
5 備える
6 増やす
まず、お金にはこの6つの機能があるんだということを頭に叩き込んでおきましょう。
そしてお金という道具をうまく活用するためには、この6つの知識を身につける必要があります。
お金の勉強をするというのは言い換えれば、この6つのお金の機能の知識をしっかり抑えるということです。
まず1つ目の機能である「稼ぐ」ためには、自分の能力を生かして働いてお金を稼ぐ必要があります。
お金を稼ぐ方法や働き方と収入の関係についての身につける必要があります。
会社から給与をもらうという人は、思いつかない人もいるかもしれませんが稼ぐ方法はほかにもあります。
そして2つ目の機能である「納める」ですが、稼いだお金から社会を維持するための費用として私たちは税金を納めていますが、税金の仕組みを知って税金を賢く納めることができればお金を節約することができます。
そして3つ目の機能である「貯める」、お金は銀行口座などに財産として貯めることができます。効率的な貯め方を実践するとともに貯めるための家計の工夫も大切になります。
そして、4つ目の機能である「使う」、生活必需品の確保のためでなく、私たちが幸せな人生を送るためには、趣味や楽しみのために使うお金だって必要です。 また、将来どれぐらいの金額が必要になるのかといった計算も必要です。なかなか、世の中に正しくお金を使えている人はいないというのがおそらく現状です。
そして 5つ目の機能である「備える」、社会全体で備えるのが社会保険であります。 仕組みを理解し社会保険だけでなく、自分で備える方法も是非勉強しましょう。
そして6つ目の機能である「増やす」、 お金は運用によって、100万円が105万円になるなど増やすことができます。
様々な投資方法のメリットとデメリットをしっかり勉強することができれば、自分のためたお金からお金を生み出すことも可能となる。