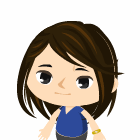『光る君へ』第19回は、ふたつの〈これって史実なの???〉案件以外にもいろいろありました。〈一条朝の四納言〉がついに始動! まだ誰も納言になってないけど。まずは源俊賢兄ちゃんが、陣定でコロンとひっくり返されてスネてしまった伊周&隆家を説得しに行きました。
源俊賢は道隆政権下で蔵人頭に補せられたので、中関白家に恩義を感じているはず。「伊周のほうが先の見込みがある」という説得は、なかば本心だったかもしれません。定子が皇子を生めば、流れは一気に変わるわけだし。伊周&隆家本人がその見込みをブチ壊しにするんだが。
蔵人頭を卒業した俊賢の後任が、F4 最年少の藤原行成。彼は物心つく前に祖父と父を亡くし、従兄弟である花山天皇退位のあおりを食らったこともあって無官のまま放置されていたのですが、やっと日の目を見ることができました。行成は後任に推挙してくれた俊賢に感謝し、俊賢の上座に座るのを遠慮していたそうです。
スパイというよりゴシップ記者のような行成くんの勧めで、道長は日記を書き始めました。倫子さんがのぞき込んでいたのは、
「直廬(高官が内裏に設ける執務室)に御料牧場から分配された馬が届いた。使者への心づけとして2反分の絹を与えた」
という部分。倫子さん、浮気の証拠が見つかるとでも思ってました? 子孫の頼長と違って、デート記録は書かないよ!
道長の日記には、のちに子孫が『御堂関白記』という名称をつけますが、道長は関白になったことがないんです。
「天皇の補佐役である関白にならず、あくまで公卿の筆頭として政治を行いたい」
と一条天皇にも申し上げましたし。関白は陣定に出られない慣例なので、陣定を伊周に引っかきまわされたくなかったんだろうねぇ。ちなみに〈御堂〉は道長の通称。土御門殿の東に九体の阿弥陀仏を祀るお堂を建てたことからの名です。
四納言の残り二人、公任は文化人として頑張れ。そして斉信は……来週、重要な役割がありそうですね。
そして、ダメ時……もとい、為時パパ、叙爵(従五位下に昇進すること)おめでとう! 正六位上と従五位下は一階級差ですが、天と地ほどの差があります。言ってみれば、アルバイトと正社員の差です。
70弱ある国は、生産力によって大国・上国・中国・下国の4等級に分類されます。下国である淡路国ならバイトでも国守になれるんですが、越前国は大国なので従五位上が必要なはず。でも、まひろが言うとおり、大胆不敵な望みでも口に出していってみれば、誰かが叶えてくれるかもしれません。まひろも「宮中に行ってみたい」という望みを清少納言に聞きいれてもらい、大殿籠り待ちという貴重な経験をしたわけですから。
今週のまひろが書き写していたのは新楽府(しんがふ)。もともと前漢の時代に楽府という役所があり、各地の民謡を採集していました。中国では〈民の声は天の声〉と考えられています。民が、
「旦那がサビ残で帰ってこないんですけど!」
「となりの姉ちゃん、ええケツしとるのぉ」
などといった、日常的なネタで歌っているぶんには問題ない。しかし、〈死〉だの〈滅〉だのという不吉な言葉を折りこんだ意味不明な歌を歌っている場合は、天が君主に警告を与えていると考えるのです。
楽府で採集された民謡を元に替え歌を作ることが流行し、それらの替え歌もまた楽府と呼ばれました。唐代の新楽府は漢代の楽府の様式を復興したもので、すでに歌うことはなかったそうです。
中国では、詩によって世を正すのが詩人の役割と考えられており、新楽府は民の声を反映して政治批判を含むことがあります。でも、調子こいて批判しすぎると、どっかの白楽天さんみたいに左遷され、
「香炉峰サイコー。都なんかクソだ」
と強がったり、
「詩文の才も琵琶の腕前も、都以外で披露したって無意味だわ」
とボヤいたりする羽目になるよ!