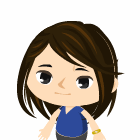いやー、ありましたね。ぼくらの実資さんの恋愛イベント! 相手がまひろとは予想外でしたが。なのに、「(赤痢で)半分死にかけておる」という宣孝おじちゃんの暴言で破談になってしまいました。実資さんはあと60年生きますよ……。
実資さんのほうでも「鼻クソのような縁談」という認識だったので、どのみち成立はしなかったでしょうが。しかし、宣孝おじちゃんからの手紙に「秘蔵の書を献ず」とあったことに興味を持ち、宣孝が手土産に持ってきた『捜神記(そうじんき)』を開いてみると、そこにはフルカラーの挿絵が……。
『捜神記』は中国 六朝時代の志怪小説。〈志〉は「記す」の意で、中国版『世にも奇妙な物語』ってところです。『捜神記』のなかには日本の羽衣伝説と同様な話があります。天女が羽衣を奪われて、人間の男性に嫁ぐはめになるってお話。挿絵は、スケスケの衣をまとった天女でしょうか。史実の実資さんは、美女なら女王でも下女でもいいという人だったので、正しい贈り物ですね。
後半で描かれたのは庚申待(こうしんまち)の夜。中国から伝わった道教の風習で、親戚や友人同士で食べ物や遊び道具を持ち寄り、60日に一度の庚申の夜を励ましあいながら明かしました。眠ってしまうと、体内に住む三尸(さんし)という3匹の虫が天に昇り、天帝に悪事を告げ口するからです。
紀行のコーナーで紹介された京都 八坂庚申堂でぶら下げられていた色とりどりの丸いものは〈くくり猿〉という縁起物。小さい座布団の四隅を集めて縫いつけ、丸い頭をつけて猿を模してあります。猿は三尸の天敵なのだとか。下の写真は奈良市 奈良町の庚申堂のもので、身代わり猿と呼んでいるそうです。でけーな。
5匹連ねて〈五猿(御縁)〉、9匹で〈苦が去る〉と言います。また、手足を束ねて動けなくしてあることから、〈(客が)去らない〉の意味のおまじないとして遊郭でつるしたそうです。江戸時代以降の流行なので、『光る君へ』とは関係ない話ですが。
しかし、兼家パパの家では庚申待をしません。982年、兼家パパの長女 超子(春宮 居貞親王の生母)が、庚申待のさなかに急死したからです。集まって賑やかに過ごす気分になれないよね。
そんなわけで、道長にとってはフリーに動ける夜でもあるわけです。例の廃屋にまひろを呼び出し、
「妾でもいいと言ってくれ」
と念を送りました。しかし、道長の婿入り先が土御門の倫子さまだと知って、まひろは「妾でもいい」とは言い出せなくなってしまいました。ぜんぜん知らん嫡妻なら、
「妾のわたしのほうが愛されてるもんね!」
と思えるだろうけど、仲良しのお友達が嫡妻ではねぇ。
まひろにフラれた道長は土御門殿へ。文をやりとりするという手順を踏まなかった道長ですが、穆子ママは倫子さんの部屋に入れてやることにしました。ほんとはダメなんですよ。倫子さんが軽く見られてしまうから。でも、泣くほど道長が好きなら仕方ないわね。正しい手順は当ブログの過去記事をご覧ください。