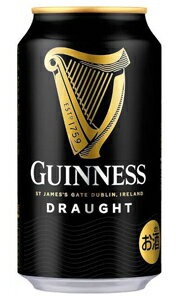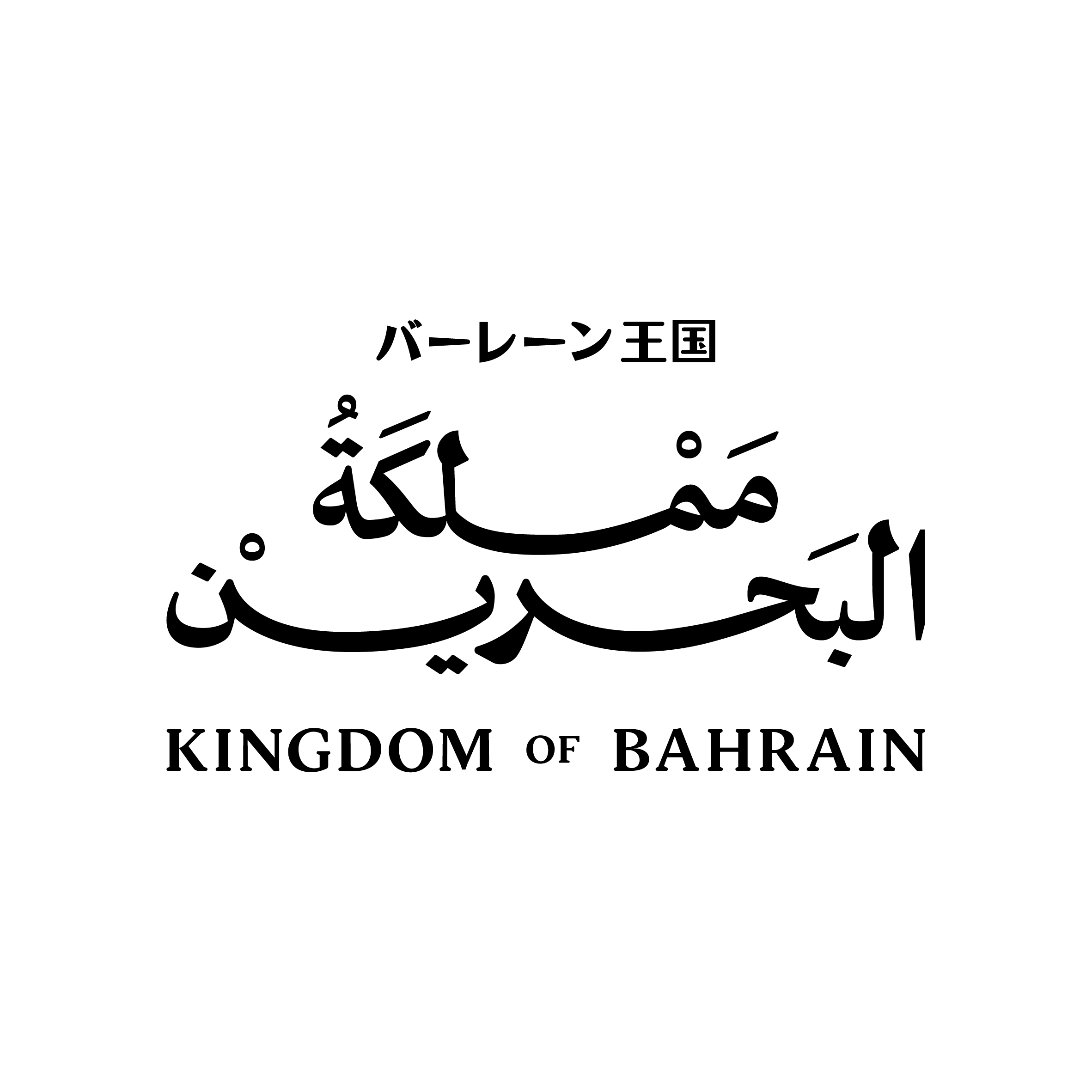万博に何度か通っている私も、「ここはハードル高いな」と思っているパビリオンの一つがアイルランドパビリオンです。今回は、整理券を手に入れて入館できたので、その様子をお伝えします。
整理券が必要な時間帯に注意!体験内容をチェック
アイルランドパビリオンは、自由入場や事前予約ではなく一部整理券制を採用しています。
体験内容は時間帯によって異なり、以下のように分かれているようです(6月上旬確認):
-
9:00~10:00/19:30~20:45:展示+映像体験(整理券不要)
-
10:00~18:00:展示+生演奏体験(午前4回・午後4回のガイドツアー、各回35人、整理券が必要)
-
18:00~18:45:展示+生演奏(先着順、整理券不要)
私が訪れたのは日曜日。「生演奏」が目的だったため、13時20分配布の整理券を狙って12時ごろから並び始めました。その時点で既に列は長く、先頭の方は何時から並んでいたのか気になるほど。椅子を持ってきている人はいくぶん快適そうに、そうでない人は地面に座るなどして静かに順番を待っていました。
整理券は並んでいる人本人の分しか発券されず、代表での取得は不可。さらに、予定数に達すると整理券配布列に並ぶこと自体ができなくなります。この仕組みは、万博でも屈指の“難関”といえるかもしれません。
館内体験:五感で味わうアイルランド
指定時間の5分前に再集合。入館してまず印象的だったのは、なんとなくいい香りが漂っていたこと。アイルランドに多く見られる「ボグ(bog)」=湿原の再現展示が最初に現れます。しっとりとした空気感で、心が落ち着く感覚でした。
次の部屋では、アイルランドの手工業に関する展示。こちらの丸いのは、シンプルなのに、なぜか惹かれる不思議な形でした。
そして、アイルランドのシンボルであるハープも展示されており、実際に触れることができました。ギネスビールのマークにハープが使われているのも、アイルランドの象徴であることが理由だそうです。
展示には英語と日本語の解説がしっかりついていて、質問にもスタッフが丁寧に対応してくれました。アイルランドパビリオンでは、ただ多くの人に見せるのではなく、一人ひとりの来場者に向き合い、じっくりと体験してもらうことを大切にしている印象を受けました。
最後は生演奏
展示の最後の部屋では、生演奏のセッション。
静かに耳を傾ける部分と、観覧者も一緒に踊ったりできる構成で、背景にはアイルランドの荒野の風景。風の音も再現されていて、とおい国に思いをはせる時間になります。ほんの数十分の体験とは思えないほど、心に残るひとときでした。
静かな感動と出会うまで
確かに、並ぶのはたいへんです。でも、6月初旬の現在なら、タイミングよく並べば2時間以内で整理券を入手できるのではないかと思います。その先に広がっているのは、静かで丁寧で、どこか懐かしさを感じるアイルランドの世界。体験の密度は高く、興味のある方にはぜひおすすめしたいパビリオンでした。
※ 最新の整理券配布状況は、当日の現地掲示や公式SNSでご確認ください。