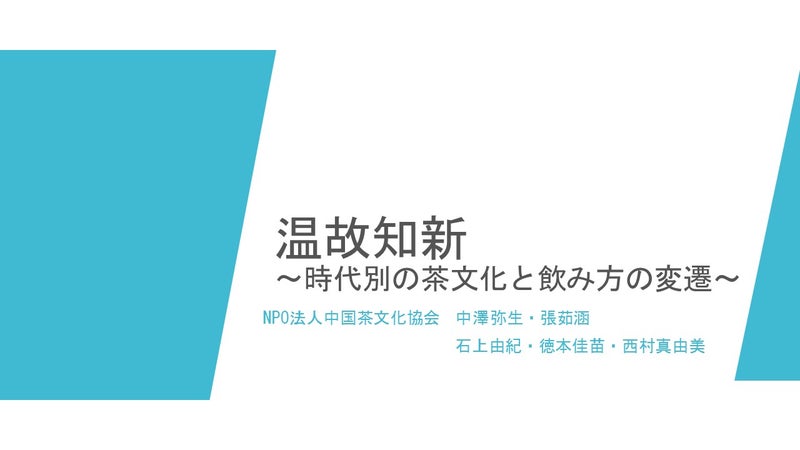ふとしたご縁で、9月に台湾から戻った直後、NPO法人中国茶文化協会の理事に就任しました。
中国茶文化協会は、全国各地で開催されるイベント・セミナーや中国茶教室などを通じて、中国茶の楽しみ方をお伝えするとともに、中国茶の魅力をお伝えするための人材を育成することを目指している団体です。理事のメンバーは華泰茶荘のインストラクター協会とシンガポールの留香茶芸と提携しています。
早速に先月末の中国茶研究会「温故知新~時代別の茶文化と飲み方の変遷」を担当させていただきました。唐代・宋代・明代・清代を一通り解説して、潮州式茶芸と台湾茶芸で締め括るという壮大なプロジェクトを1ヶ月で企画を練り上げました。講師の中澤さん、留香茶芸の皆さんと事前に数回の打ち合わせを重ねた上で、講義の資料・原稿・パワーポイントを作成し、当日に臨みました。お蔭様で大盛況を迎えることができて、感無量です。
貴重な機会をくださった林聖泰理事長と役員の皆さん、お越しいただいた参加者の皆さんに感謝しております。
当日は3時間という盛りだくさんの講座でした。まずはトップバターの中澤さんが唐代・宋代について解説してくださいました。
『封氏聞見記』と『茶経』の接点を探る資料がとても面白かったです!
つづいて私がバトンタッチして、明代・清代の解説をしました。
明代ではやはり自分の研究対象となる文人喫茶の話しを中心にして、清代では工夫茶というネーミングの由来、多穆壺、乾隆帝とお茶の関係をそれぞれかいつまんでご紹介しました。
3時間目は留香茶芸にお3方にバトンを渡して、ひたすら優雅な茶芸を眺めていました。
茶席に創意工夫を凝らした趣向が伺えたし、工夫茶(ゴンフーチャ)のことに儀式性を加えたシンガポール発祥の留香茶芸が凛としていて、見た側として、存分楽しめました。
そして、3時間にバックヤードの茶車からどんどんお茶も淹れていただきました。今回お出しした4種類の茶葉の集合写真です。
「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」は、自分の「師になる」と続くと私は読み解いています。それが最終的にぶれない自分というところまでたどり着ければ、歴史という昔の文化にふれてみる甲斐があるのではないかと思います。
NPO法人中国茶文化協会で皆さんの力を合わせた結果に、新しい役員として、感銘を受けていました。
自分はしばらく協会で頑張っていくつもりで、記事をご覧になられた皆さんも是非、協会のことをごひいきくださいませ☆どこかでお目にかかれれば嬉しいです。
次回は来年の2/11(火・祝)にイベントを予定しています。乞うご期待!
*NPO法人中国茶文化協会HP→https://cha-tea.org/
FB→☆
IG→☆
TL→☆