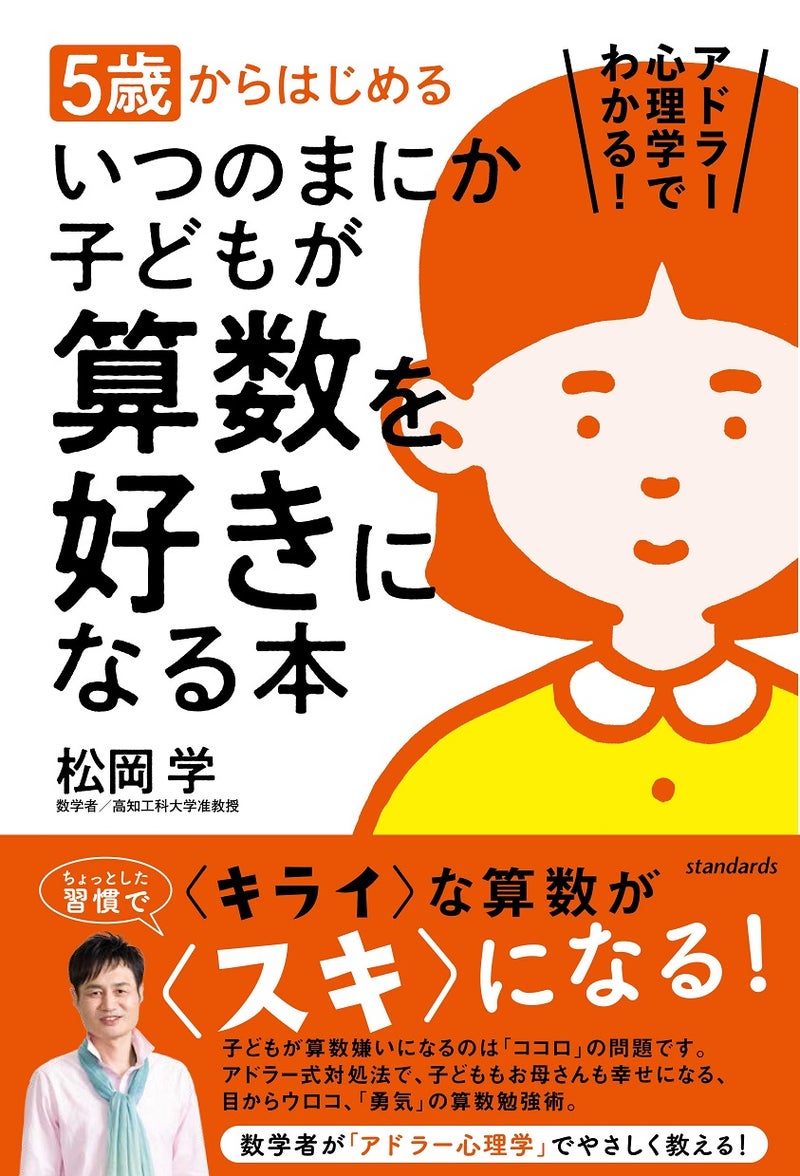不思議の国のアリスというとファンタジーなイメージがありますが、
実は、作者のルイス・キャロルはイギリスの数学者です。
本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドジソンで、
作家としてのペンネームがルイス・キャロルなのです。
絵本や映画だけでは伝わりにくいかもしれませんが、
原作を読むと、数学的なエッセンスがいたるところに散らばっていて、
数学的な雰囲気を感じる物語です。
そんなことから、ここでは、
ルイス・キャロルの 『不思議の国のアリス』 と 『鏡の国のアリス』 から、
数学的な部分をいくつか紹介したいと思います。
不思議の国のアリスには、チェシャ猫という不思議な猫が出てきます。
チェシャ猫は自分が狂っていることを、アリスに次のように説明します。
「犬は狂っていない」 ということを確認したうえで、次のように言いました。
「犬は、怒ったときにうなり、うれしいときにしっぽをふ振る。
だが私は、うれしいときにうなり、怒ったときにしっぽを振る。
だから、私は狂っている。」
なんだかもっともですね。
それもそのはず、この文章は論理的に組み立てられているからです。
そんなことを次の記事で解説しました。
アリスは鏡の国で、ハンプティ・ダンプティと出会います。
ハンプティ・ダンプティはイギリスの古い民謡に出てくる卵の形のキャラクターです。
ハンプティ・ダンプティは王さまと女王さまから贈られた
素敵なネックレス(チョーカー)をしていました。
ハンプティ・ダンプティはそのネックレスを、
「非誕生日プレゼントとして賜った」
と言います。
なんだか不思議な表現ですね。
そのことについて、次の記事で解説しました。
不思議の国のアリスでは、時間や時計にまつわる出来事が出てきます。
たとえば、
「1日に2回正しい時間を指す時計と2年に1回正しい時間を指す時計では、
どちらが正確でしょうか?」
という問題をどう思いますか?
このことについて、次の記事で解説しました。
不思議の国のアリスと算数・数学の関係を
いくつか紹介してきましたが、いかがでしたか?
作者が数学者だけあって、とても不思議な数学ワールドが広がっています。
ぜひあなたも、『不思議の国のアリス』 や 『鏡の国のアリス』 の原作を読んでみてください。
絵本や映画だけでは伝わらなかった、きっと何かを感じると思います。
☆ 子どもの算数力アップを願う、お母さんのための本
子どもの算数力を育てる接し方を、
アドラー心理学にもとづいて書かれています。
実践しやすいように具体的に書かれています。
☆ 恋愛・結婚生活の本
大切なパートナーと幸せになれるような、
アドラー心理学のエッセンスを詰め込んだ本となります。
(出版社:CLAP)
【コラムの執筆者】
松岡 学
高知工科大学 准教授、博士 (学術)
数学者、数学教育学者
大学で研究や教育に携わる傍ら、
一般向けの講座を行っている。
アドラー心理学の造詣も深く、
数学の教育や一般向け講座に取り入れている。
音楽 (J-POP) を聴くのが趣味。
ファッションを意識し、自然な生活を心がけている。
出版物:『数の世界』ブルーバックスシリーズ、講談社。
『5歳からはじめる いつのまにか子どもが算数を好きになる本』スタンダーズ社。
< お問合せ先 >
※ 企業様などから、松岡へのお仕事のご依頼の窓口はこちらから
※ ただし、出版社様からの執筆(出版)のご依頼は、
こちらから直接ご相談ください。
< コラム・エッセイ >
◆ お母さんが読むだけで、子どもの算数や数学の成績が上がるコラム