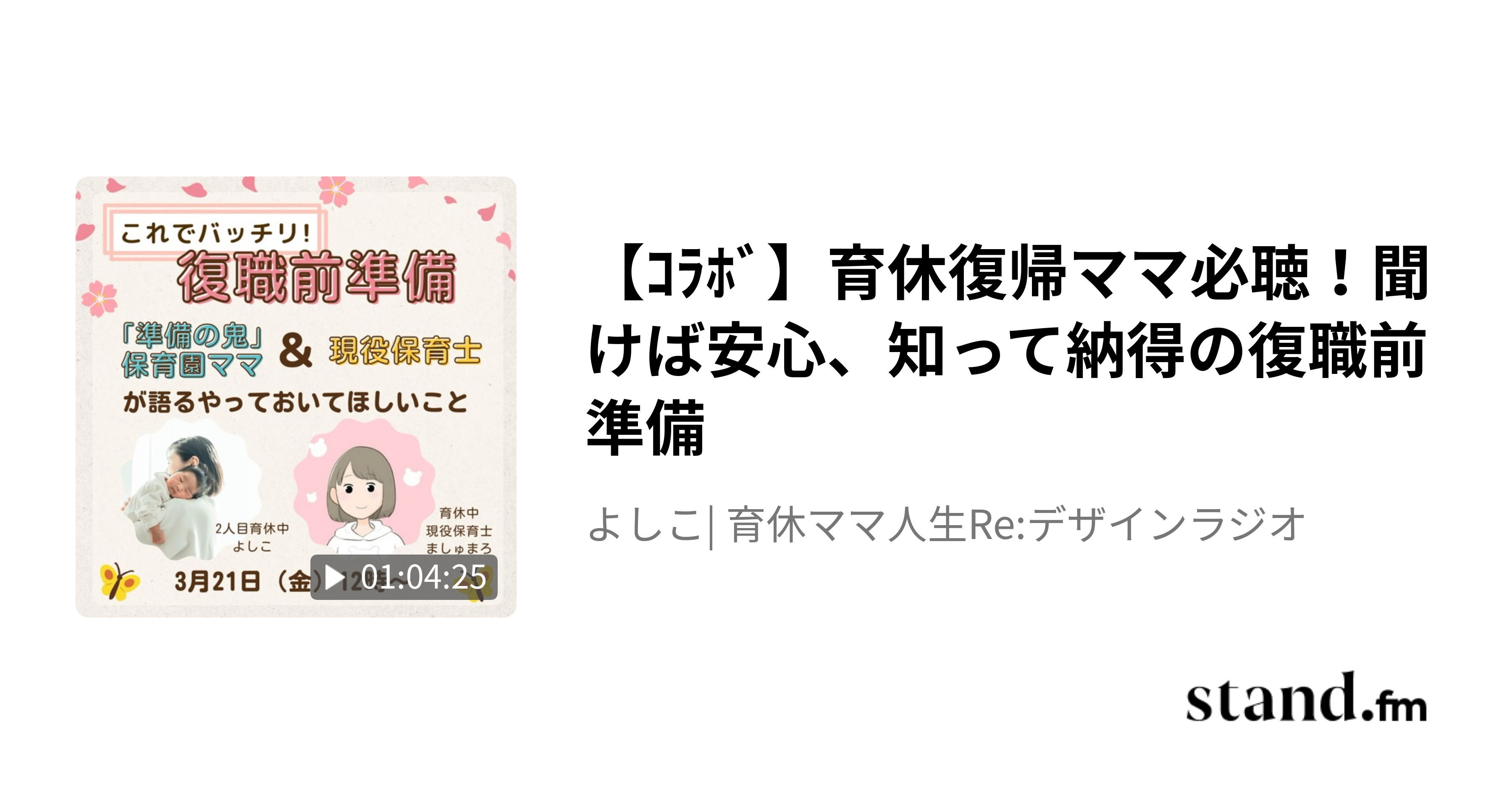4月から新しい環境での
スタートを迎える方が
多いと思います![]()
ドキドキしますよね〜![]()
慣らし保育では
子どもたちが少しずつ
園生活に慣れていく時期![]()
実は保育士もこの期間は
特に慎重に子どもたちと関わっています![]()
初めての集団生活にドキドキしている子![]()
ママやパパと離れることが寂しくて
涙が止まらない子![]()
興味津々であちこち探検する子![]()
子どもによって様子は
本当にさまざまです![]()
![]()
でも、どんな子にとっても
「安心して過ごせること」
が何より大切なんです。
安心できるかによって
慣らし保育のペースも変わると思います![]()
そこで今回は、
保育士が慣らし保育の期間に特に気をつけていること
についてお伝えします!
これから慣らし保育が始まる方も、
すでに経験した方も、
「そんなふうに関わってくれるんだ!」
「こうやって配慮してくれてたんだ!」と
少しでも安心してもらえたら嬉しいです![]()
1. 環境の整備
慣らし保育では、子どもが
「ここは安心できる場所だな」
と思えるように
過ごしやすい空間をつくることを
心がけています![]()
初めての場所って、
大人でも緊張しますよね![]()
あとあまりにも刺激が多いと、
落ち着かなくなることがあるので、
シンプルな空間を意識しています。
だからこそ、
おもちゃや遊具は必要な分だけにして、
スッキリとした環境にします![]()
安全対策もしっかりとしています。
新しい場所では、
いつもと違う動きをすることもあるので、
転びやすいところがないか、
誤飲しそうなものはないか、
細かくチェックしています。
おもちゃもこまめに点検をして
危険がないかチェックしながら
消毒をしたりしています。
あとは生活の流れをわかりやすくすることです。
保育園のリズムはおうちと違うので、
いきなり全部に合わせるのではなく、
少しずつ慣れていけるようにしています![]()
例えば、食事やお昼寝の時間を調整したり、
「次は〇〇するよ」と声をかけたりして、
見通しが持てるように工夫しています![]()
(私はどの年齢でも声掛けをするようにしています)
2. 受け入れ時の対応
まず、大切なのは笑顔で迎えること![]()
パパ、ママと離れるのが寂しくても、
温かく迎えられると
お子さんも安心できると思います![]()
名前を呼んで「おはよう!」と声をかけることで、
保育士の存在を身近に感じてもらうようにもしています![]()
あとは保護者の方との別れ際は、
できるだけスムーズにを心がけています![]()
長引くとお子さんの不安が強くなることがあるので、
「いってらっしゃい!」と声をかけて
送り出してもらうことをお願いすることもあります![]()
(ここは保護者の方の頑張りどころ!)
その後は、気持ちの切り替えができるように
好きなおもちゃを用意したり、
膝の上でゆっくり安心できる時間を作ったりします![]()
それでも泣いている子には
無理に泣き止ませようとせず、
気持ちを受け止めることが大事で
「ママと離れて寂しいね」
「泣いても大丈夫だよ」
と声をかけながら、
少しずつ園の雰囲気に慣れていけるように
寄り添っています![]()
3. 一人ひとりのペースを大切にする
保育園に慣れるまでは
一人一人のペースを大切にしています。
初めての環境にドキドキしている子もいれば、
すぐに遊び始める子もいます。
おうちの人と離れるのが寂しくて泣いてしまう子、
じっと様子をうかがって慎重に動く子、
保育士のそばから離れない子、
本当にさまざまです![]()
![]()
「早く慣れてほしい」
と思うのは大人の気持ちですが、
子どもにとっては大きな環境の変化。
無理に慣れさせようとするのではなく、
その子が安心できる関わりを大切にします![]()
好きな遊びを一緒に楽しんだり、
安心できる場所で見守ったり、
必要に応じて抱っこや手をつなぐこともあります。
「先生がそばにいる!」
「ここにいても大丈夫!」
と感じられることが何より大事です![]()
また、同じ子でも日によって
気持ちが変わることもあります![]()
(そりゃ人間だもの![]() )
)
昨日は楽しく遊んでいたのに、
今日は涙が出てしまうことも![]()
それもとても自然なことです!
少しずつ笑顔が増え、
保育士やお友だちとの関わりが広がり、
安心して過ごせるようになるまで、
その子のペースを大切にしながら見守っていきます![]()
4. 保護者との連携
慣らし保育の期間は、
保護者にとっても
新しい環境に慣れる大切な時間です![]()
そこで保育士として大事にしているのは
保護者との連携です。
子どもは環境の変化に敏感で、
不安になりやすいです。
だからこそ!
保護者の方としっかりコミュニケーションをとることで、
お子さんの安心につなげていきます![]()
もちろん保護者の方の安心にもつなげます!
朝のお預かりのときには
お家での様子を保護者の方から
話を聞くようにしています。
夜泣きをしていなかったか、
ごはんを食べたか、
体調は良さそうかなど、
家での様子が分かると、
子どもの気持ちに寄り添いやすくなります![]()
でも実際、朝の受け入れ時はバタバタするので
おたより帳などを活用することをおすすめします!
お迎えのときは、
その日の子どもの様子をできるだけ詳しく伝えます。
泣いていた時間が長かったのか、
どんな遊びをしていたのか、
ごはんはどれくらい食べたのか等を
お伝えしています。
何か少しでも分からないことや
困っていること、
保育園ではどうしているのか気になることがある場合は
ぜひ遠慮なく相談してくださいね![]()
保護者の方が安心できると、
その気持ちは子どもにも伝わります![]()
不安が少しでも減るように、
一緒にお子さんの成長を見守っていきたいと思っています![]()
5.SIDS(乳幼児突然死症候群)を防ぐ
慣らし保育中で特に注意していることは
SIDS(乳幼児突然死症候群)です。
SIDS(乳幼児突然死症候群)は、
元気だった赤ちゃんが
突然亡くなってしまう原因不明の病気。
保育園でも細心の注意を払って見守っています。
まず、赤ちゃんのお昼寝中は
必ず仰向け寝 にします。
うつぶせ寝はリスクが高くなるため、
寝返りをしてしまってもすぐに戻します。
最近ではうつ伏せになるとアラームが鳴る
センサーが導入されている園もあります。
また、 寝ている間もこまめに呼吸や体勢をチェックします 。
数分おきに見回りをして、
しっかり呼吸しているか、
顔色が悪くないかを確認しています。
私が勤めている保育園では
入園から3ヶ月間は0〜3歳の子は
5分おきに呼吸・顔色・姿勢の確認をします。
特に、熱があったり体調が優れない子は
いつも以上に注意して見守ります。
(熱性痙攣の可能性もあるので特に注意しています)
あと顔色や呼吸をしているかのチェックが
しっかりできるように
部屋は暗くはせず、
明るい環境の中でお昼寝をします。
お子さんがこの環境に慣れるまでが
少し時間がかかるかもしれません![]()
室温や服装の調整も大切 。
暑すぎる環境はリスクを高めるので、
適温を保ちつつ、
布団の掛けすぎにも気をつけます。
汗をかいていないか、
手足が冷たすぎないかなど、
こまめにチェックして調整しています。
大切な命を守るために、
日々気をつけながら見守っています。
どの保育園でとても慎重に
お子さんの睡眠時の様子をみているので
安心してくださいね!
最後に
慣らし保育は、
子どもにとっても
保護者にとっても
新しい環境への第一歩![]()
最初は泣いたり、
不安そうな表情を見せたりすることもありますが、
一人ひとりのペースで少しずつ慣れていき、
やがて「園が楽しい!」と感じられる日が増えていきます。
そのために、
私たち保育士は安心できる関わりを大切にしながら、
子どもたちの気持ちに寄り添い、
無理なく園生活に慣れていけるようサポートしています![]()
そして保護者の皆さんにも、
「子どもが泣いてしまっても大丈夫」
「焦らなくても大丈夫」
と、少しでも安心してもらえたら嬉しいです![]()
慣らし保育は、
親子にとって大きな変化の時期ですが、
乗り越えた先には子どもたちの成長が待っています。
慣れない子はいません!
私たち保育士も、一緒に見守りながら、
お子さんが「ここでなら安心して過ごせる!」と
思えるような環境を作っていきますので、
何か不安なことがあればいつでも相談してくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました![]()
育休アドバイザーのよしこさんと復帰前準備についてお話をしています📻![]()
知識として知っていると知っていないでは大違い❗️
この配信を聞くと安心できる部分も多いと思いますのでぜひお聞きください![]()
https://stand.fm/episodes/67dce5adfafe3d0fb2dddd9c
慣らし保育中のあるあるについてもぜひチェックしてください![]()
保育士のある特技についても書いています〜![]()
![]()
おすすめグッズ掲載中
ラジオでもお話し中 Stand.fm 📻
Stand.fm 📻