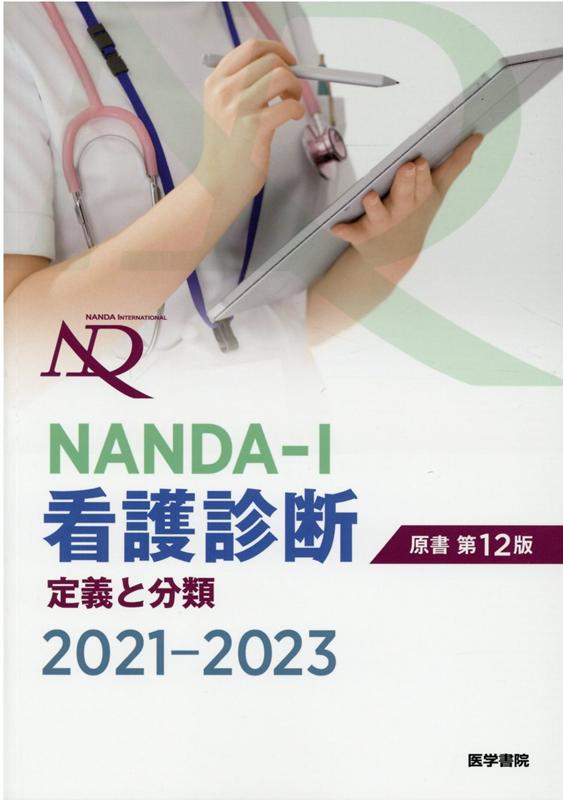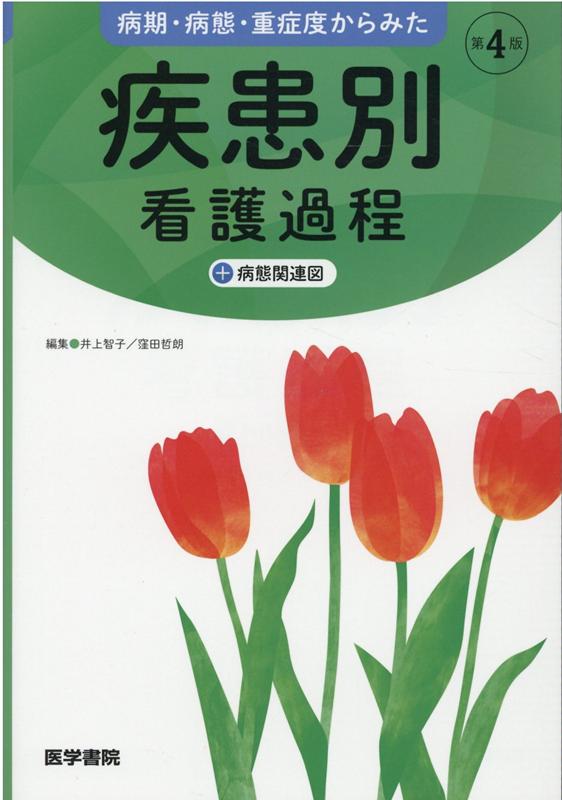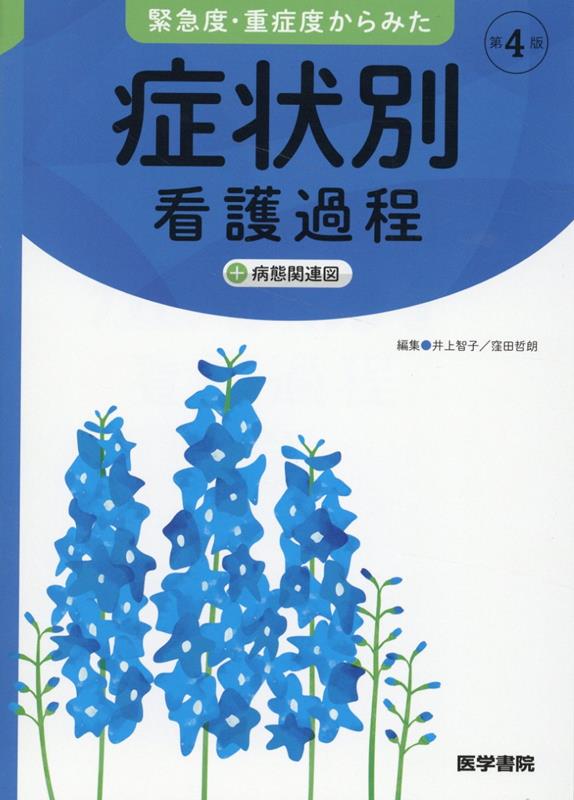実習の辛さは過去にも記事にしました。
実習期間は、家に帰っても地獄が続きます。
膨大な記録![]()
それも手書きで![]()
今はタブレットやパソコンでの記録OKの学校も多いでしょう。
実習で来る学生さん達も、ほとんどがタブレット。
羨ましい〜
手書きって本当に時間がかかる。
パソコンなら思いついたワードをぱぱぱーっと打ち込んで、文章を組み立ていけます。
日本語がおかしいかなーと思ったらすぐに修正できる。
そして何より手書きよりも見やすい![]()
私の通っていた看護学校の記録用紙は、A4もしくはA3サイズ。
その用紙を5ミリほどの大きさの字で埋めていきます。
結果
すでに30代後半だった私には
「あなたももうすぐ読めなくなるわよ」
と仰っていました笑
そんなにビッシリ書かなくてもいいんです。
要点を押さえて書いていけば。
でも、疲れて頭が働かない時には、とりあえずダラダラした文章で埋めていました。
何故なら
内容がそこそこでもスルーされるから![]()
こすい手口ですが、なかなか有効。
ちゃんとやってる風に見せるのが大事。
読むのを諦めさせるほどに書き込む作戦!
当日の目標や学びは、見学や実施した援助をシラバスと結びつけて書いときゃOK。
シラバスに沿って実習は行われているので、必ず繋がる。
あとは実習の指導者や教員によって内容は変わる。
ゆるい先生と記録を読まない実習先は大当たり。
スッカスカの記録で臨みます![]()
眠れる実習は貴重。
しっかり3週間休みました。
しかし、丁寧に記録を見られる場合は手抜きできない。
かと言って全ての記録を全力でやると、睡眠時間がなくなる。
指導者が見るのは、当日の行動計画のスケジュールが組めているかと援助の手順。
スケジュールは実習初日か翌日に把握しておかないと後が大変。
患者さん、指導者、リハビリなどに、さっさと予定を聞いて、1週目に見学を入れていきます。
援助の手順は、ベースは参考書に書いてある基本の手順を。
そこに麻痺などの疾患による注意点を必ず付け加える。
どんなことに気をつけて、そのために自分はどこに立ち、どう援助するのか。
そこを押さえておかないと
個別性は![]()
![]()
と、あるあるの指導が入ります。
スムーズに記録を書くために、参考書は高くても購入していました。
必須だったのは
看護診断
患者さんの状態に合わせて、看護問題から援助を調べられます。
働き出しても、とにかく使える。
私の場合は、学校で購入する教科書に含まれていました。
実習で一番助かったのは
疾患別看護過程
この本、めちゃくちゃ使いました。
実習であたるような疾患は載っているので、プランをそのまま書き写せば良いだけ。
カルテを読んでよくわからない疾患の治療も、これと照らし合わせて調べられます。
問題は、この本が分厚くて重くて、持ち歩きに不向きなところ![]()
そこで、
必要なページを切り取って持ち歩いていました。
その受け持ち患者の疾患のページだけ持っておくと、実習先でかなり記録が進みます![]()
あまりに便利すぎて
症状別看護も購入。
その名の通り、症状ごとに看護が書かれているので、臨床に出てからも使えます。
症状は流石に索引から調べたいので、切り取らずに使いました![]()
上の3冊は、他にも似たような内容でカラフルでイラストが書いてある読みやすい本もあるんです。
が、内容の充実度を優先。
ネットでも調べられる時代ですが、真偽がわからない情報も多いので![]()
結局は専門書の方が詳しいですし、根拠もきちんと書いてある。
金額は高くても、元を取ったと言えるくらいには使い込みました。
![]() クリックしていただけると嬉しいです
クリックしていただけると嬉しいです![]()
シングルマザーランキング