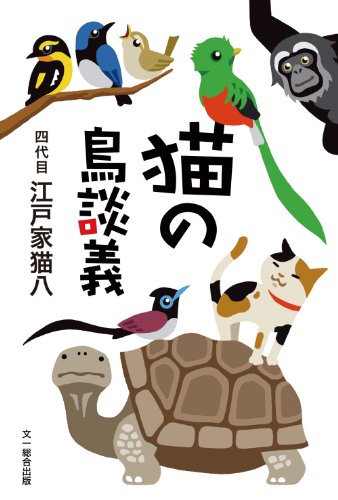正月は大阪の実家に帰省した。
例によって、親父とオカンの動向をレポートさせていただきたい。
その日の夜、親父とオカンはコタツに入りながら、テレビで「相棒」を観ていた。
僕は同じコタツで、昨年末に取材した音源をイヤホンで聞きながら、書き起こし作業にいそしんでいた。
すると親父が、何やら僕に話しかけてくる。作業の手を止めたくないので、イヤホンを片耳だけ外して聞く。どうやら、親父なりの推理を聞かせたいらしい。
もちろん僕にとってはどうでもいい話なので、適当に相づちを打ちながら作業をすすめる。
しかし人間というものは、2つの作業を同時に進めることができないようになっているらしい。
気がつくと、パソコンのテキストファイルに、
「右京さんがな、あそこでおかしいなっていう顔しとったやろ。あれはな……」
という文字が入力されている。
いつの間にか、親父のどうでもいい推理を書き起こしてしまっていたのだ。
「あかん、俺は何をやってるんや……!!」
すぐにその文章を消して作業に戻ったが、次第にテレビの方が気になり始め、ついには事件解決まで見届けてしまった。
翌日は、親父の運転する車に乗って、オカンと3人で出かけることになった。
その道中、信号のない横断歩道で、お年寄りが車の流れが途切れるのを待っていた。
すると親父は一時停止し、そのお年寄りを先に渡らせてあげようとした。
「おお、さすがに70歳にもなると、ちょっとは丸くなるもんやなあ……」
僕は助手席で目を細めていたが、次の瞬間、そんな自分の甘さを思い知らされることになった。
「はよ渡れぇ〜〜〜!!!!!」
親父の怒鳴り声が車中に響き渡った。
おかげで僕も「現実」に帰ってくることができた。危うく「ありえない妄想の世界」に引き込まれてしまうところだった。
その後、ある家電量販店に到着し、エスカレーターに乗った。
ご存知のとおり、大阪のエスカレーターではみんな右側に並び、急ぐ人のために左側を空けるのが慣習になっている。
しかしそこで、親父はわざわざ左側に立つのである。
「親父、右側に立っとかんと、急いでる人が通られへんやん!」
そう指摘すると、親父は当然のように反論してきた。
「何言ってんねん。いま放送で、エスカレーターは2列で並んでくださいって言ってたやないか」
「いや、真面目な人が言うんならわかるけど、ふだん社会のルールを守らへん親父が、なんでそこだけ守ろうとするねん!」
親父も「確かに」と思ったのかどうか知らないが、次のエスカレーターからは右側に並ぶようになった。
用事を終えた帰り道、僕は実家の最寄り駅のあたりで、ちょっとパソコン作業をしてから帰ることにした。しかしここは田舎。駅周辺とはいえ、ゆっくりできる喫茶店がほとんどないのだ。
「どっかお茶しながら作業できる店ないかなぁ」
僕がつぶやくと、オカンが「そうやなぁ……」と考えながら言った。
「この駅の近くやと、マクドかマックか……」
「どっちも一緒やん!!」
しかもここでオカンが言おうとしていたのは、ロッテリアのことである。
「めちゃくちゃやな!」
オカンにかかれば全てのテレビゲームは「ファミコン」に一元化されてしまうが、それと同じ原理なのだろう。
僕はあきれながらもロッテリアに入ってコーヒーを注文し、ノートパソコンを広げた。親父とオカンは、先に車で帰っていった。
さて、気を取り直して作業を始めるか……と思ったところに、親父から電話がかかってきた。
「どうしたん?」
「いや、お母さんがな、『ロッテリアは今日休みや』って言ってるで」
「そのロッテリアでいまコーヒー飲んでるよ!」
一体どこから仕入れた情報なのか。僕には知るよしもないし、知りたくもなかった。
結局そこでの作業は断念し、疲弊した精神と肉体の回復に専念することにした。
……以上、ご報告でした。
ちなみに親父とオカンの過去の横暴ぶりは、下記の電子書籍にまとめています。人生が深刻なものに思えてきたら、ぜひこれを読んでみてください。「ああ、本当はどうでもよかったんだ!」ということを、きっと思い出せると思います。
本年もよろしくお願いいたします。


『読むだけで神経が図太くなる!「伝説の親父」の奇行録〜時々オカン〜』