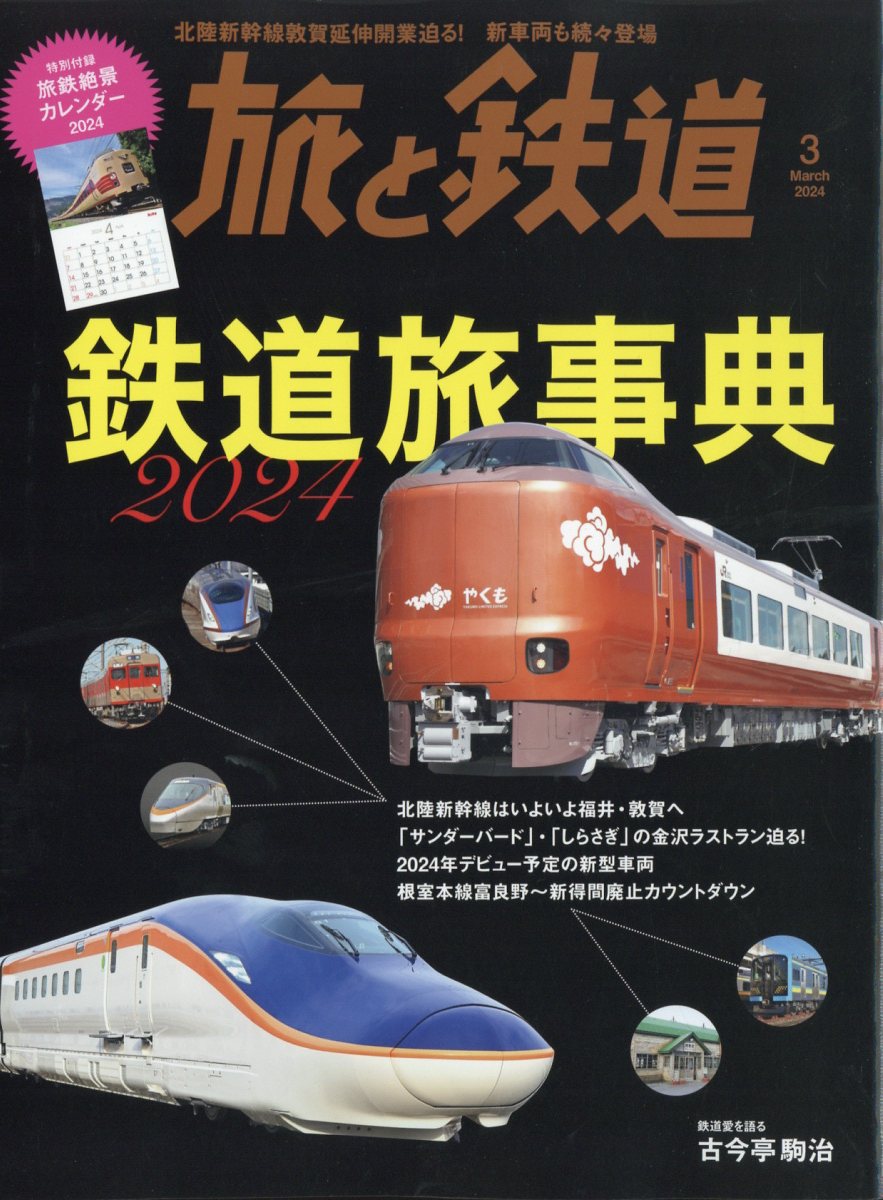承天寺から博多駅方面に戻ると若八幡宮の石鳥居が見える。明治37年建立の石鳥居だ。
別名「厄八幡」と呼ばれる神社で、厄除・災難除の神様として全国的に知られている。
新社格制度の下では、村社に列せられているが、創建等は不明だ。
貝原益軒の「筑前國続風土記」に「鎮座の始詳ならず。箱崎の摂社なりしといふ。むかしは藪八幡と称せし毎年十一月初夘日櫛田宮の巫女御倘を供へ奉る。いつの比よりか御社を東向に造建せるならん。」と記されている。
筥崎宮、櫛田神社と関係がある神社だ。
明治42年(1909)博多区店屋町にあった楊池神社が福博電気軌道開業のため合祀された。
令和3年に社殿が増築された。
二の鳥居は平成12年の建立だ。
祭神は、大鷦鷯命(おおさぎのみこと:仁徳天皇)、大己貴命(おおなむちのみこと:大国主神)、少彦名命(すくなひこなのみこと)で、大己貴命、少彦名命は合祀される前の楊池神社の祭神だった。
境内社として、白髭神社が鎮座している。道祖神の猿田彦大神が祀られている。大己貴命の御子・事代主大神と保食神(うけもちのかみ)も祀られている。
白髭神社横に置かれている力石(重さ180.2kg)は、福岡市指定有形民俗文化財だ。記録上でしか知られない江戸の力持ち木村興五郎が持ち上げた現在確認できる唯一の力石だ。木村與五郎は、文政8年(1825)3月大坂難波新地で行われた「江戸力持」興行引き札にも見える江戸の力持ちである。
銘文に「奉納 東都本所木村與五郎力石 持之西町上世話人中文政十三年 寅 正月」と刻まれている。文政13年(1830)に奉納されたものだ。元々は楊池神社にあったが、合祀の際に遷された。
力石の由来は神霊の依坐である石を持ち上げることで豊凶・天候・武運等の神意を伺う石占の信仰に遡るものだった。時代を経て、本来の意味を失い、港町の神社によく見られるように、力自慢の道具と見られるようになっていった。