それでは、ここで与謝野晶子の登場である。![]()
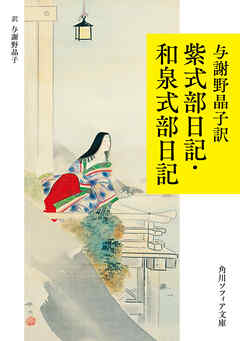
![]() 与謝野晶子訳「紫式部・和泉式部日記」(角川ソフィア文庫 2023)
与謝野晶子訳「紫式部・和泉式部日記」(角川ソフィア文庫 2023)
巻末の田村隆による「解説」から、引用しておこう。
![]() ・・・ちなみに、為尊親王の弟で、親王の死後に和泉式部と恋仲になる敦道親王は、「帥の宮」、「宮」と記される。・・・(p.292)
・・・ちなみに、為尊親王の弟で、親王の死後に和泉式部と恋仲になる敦道親王は、「帥の宮」、「宮」と記される。・・・(p.292)
![]() ・・・『和泉式部日記』については、自序の中で、
・・・『和泉式部日記』については、自序の中で、
源氏物語の大作と比較することはできませんが、ともに我国の写実小説の祖であり、ことに和泉式部日記が遠く明治の小説に先だって、自己の経験を書く小説の最初の作であることは文学史上の光栄だと信じます。(七頁)と高い評価を与えており、『紫式部日記』を史料として捉える見方に対し、『和泉式部日記』は『源氏物語』と比較するなど、「小説」として把握していることが見て取れる。和歌は『紫式部日記』と同様に訳されていないが、『和泉式部日記』については与謝野夫妻による評釈『和泉式部歌集』(大正四年)の共著がある。・・・(p.293-4)

![]() では、和泉式部についてはいかがですか?
では、和泉式部についてはいかがですか?
和泉式部の人生を眺めると、まさに自分のために世の中はあると考え、あらゆるものを利用して自分のしたいことをした女性だったと感じます。和泉式部は、母が冷泉天皇の后の昌子内親王の乳母を務めていたため、後宮で育ちました。後宮というのは愛欲にまみれた場所ですから、和泉式部はかなり早熟で、優れた容姿とも相まって、多くの男性と浮名を流しました。そのため、紫式部からは「人の道から外れている」などと評されています。
しかし、和泉式部自身は、「外れている」ことに対して悔いがありませんでした。保守的な人からどう思われようと気にしない。よくも悪くも欲望に忠実で、恋愛と、歌人としての感覚や技能を磨くことしか頭にないような人でした。それだけに、今回採り上げている3人の中では、もっとも感性が鋭く、情報感度も高い。歌の技法的には、漢学に通じている紫式部のほうが上だったかもしれません。しかし、歌というのは理屈ではありません。歌そのものから感じられる情熱や情緒は、和泉式部のほうが勝っていたように思います。実際、紫式部ですら、人間としてはともかく、歌人としては和泉式部を高く評価していました。
そのように3人を見比べると、情報の重要性を等しく認識して活用した一方で、情報を求める方向性とアウトプットの仕方といった戦略は、三者三様だったことがわかります。
こんな評価もあるわ(^^)![]()
まさに、これは「日記」という名が冠せられているけど、和泉式部が三人称で描いた「小説・物語」であろう。紫式部の向こうを張った意気込みさえ感じられるけどなあ。。。![]()

和泉式部については、ここらで幕引きに。。。![]()