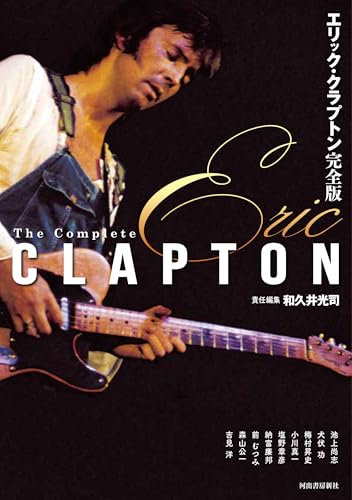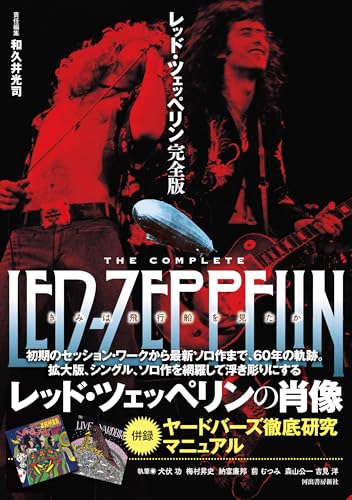和久井光司という音楽家・音楽評論家・編集者をご存知だろうか。昨2024年3月、自らのFBに“ ゴールド・レーベルのモノラル盤で持っていないヤツに、ビートルズを語る資格なんかないよ。”と書き、その言葉が炎上して、一躍、時の人となった。その騒動(!?)は各自、検索していただくことにして、彼がその資格があり、音楽評論や音楽制作において、言動一致を貫き、彼の作る“完全版”シリーズは確実に売り上げ、そのバンドのライブには人が駆け付ける。ついこの間、先週、8月27日(水)にも新刊の刊行に際してトークとライブのスペシャルショーがあったが、ソールドアウトになっている。同時に客席には音楽業界のお歴々と音楽界を牽引する方もいらしていた。
そのイベントとは、8月27日(水)に原宿クロコダイルで行われた和久井光司責任編集の『ビートルズ以後のモダン・ポップ完全版』(河出書房新社)の発売記念SPECIAL SHOW(TALK SESSION+LIVE)だ。
TALK SESSION、登壇者は同書を作った和久井光司とビートルズ研究家・藤本国彦、そして井上陽水に「少年時代」、松田聖子に「瑠璃色の地球」を提供し、大滝詠一や杉真理、竹内まりやなどとの仕事で知られる日本のジョージ・マーティン・川原伸司、司会進行は同書に関わった納富廉邦。そのテーマは「それは『ラバー・ソウル』から始まった」。
そしてLIVEは和久井光司+宮崎裕二(元SCREEN)with川原伸司+伴慶充(急遽出演)による“Plays SCREEN”。SCREENは和久井が1981年に結成した、日本のパンク、ニューウェイヴ以降のシーンを牽引した伝説のモダン・ポップ・バンドだ。これだけの音楽のマエストロ、博覧強記の梁山泊の住人達が揃う。これは行かないわけにはいかないだろう。和久井光司のこの“完全版シリーズ”は音楽ファンならどれも必読。新しい視点を与えてくれ、その楽しさを何倍ものものにしてくれるのだ。
改めて同書の説明をしておくと、1965年以降のレコーディング技術革新によって生まれた“モダン・ポップ”を網羅した世界初のディスク・ガイド。表紙には“from RUBBER SOUL to SKYLARKING”とある。中にはホリーズやゾンビーズ、プロコル・ハルム、ELO、スタクリッジ、10cc、セイラー、パイロット、スティーヴ・ハーリー&コックニー・レベル、ビバップ・デラックス、ルパート・ハイン、デフ・スクール、シティ・ボーイ、バグルズ、トニー・マンスフィールド、トーマス・ドルビー、XTC、そしてトッド・ラングレン、スパークス……などがてんこ盛り。かつて今野雄二の“NOK(ノックノック・ニューおもしろ倶楽部)“や葡萄畑の青木和義の“3Sの法則”、鈴木慶一がかつて“カフェ・ジャックス”を推薦していたことを少しでも覚えている方にはたまらないはず。類書はあったものの、これは完全版にして決定版だろう。
▲TALK SESSIONの登壇者(写真左から)川原伸司、和久井光司、藤本国彦、
そして司会進行の納富廉邦
▲稀月真皓
▲小堀裕之(二丁拳銃)
まずはトークセッションの前に和久井の陣頭指揮の下、会場に来ていた詩人の稀月真皓のその場でお題を貰い、それを詩にするという即興ポエトリーリーディングが始まり、続いてビートルズっぽいPVでかつてルーフトップセッションの時のジョージの扮装をしたことがある二丁拳銃の小堀裕之の前説がある。そんな無茶ぶりと人材の豊富さが和久井らしい。
オフレコ噺が多いので、トークセッションは詳述できないが、川原が同書を3日で読み終え、ディスコグラフィーを参考にサブスクやYoutubeなどで聞き込んだと語った。それだけ、同書の内容が濃く、刺激的であることの証明だろう。『ジョージ・マーティンになりたくて〜プロデューサー川原伸司、素顔の仕事録〜』(シンコーミュージック)の構成を手がけた藤本国彦も感心していた。ビートルズ研究家の藤本はビートルズが川原とともに“ライブはやらない。レコーディングだけにする”宣言後の重要な場所になるアビー・ロード・スタジオや同所のエンジニアなどを紹介。レコーディングマジックを語る。モダン・ポップ誕生の背景にイギリスがレコードありきでレコード芸術を極めようとしたのに対して、アメリカがライブありきでショービズを極めようとしたという文化的な相違の指摘も興味深かった。司会・進行の納富は同書を作っている時、『船を編む~私、辞書をつくります~』の池田エライザ演じる新米・辞書編集者の岸辺みどりに感情移入したそうだ(笑)。和久井は書籍にしたことはすべてやり終えたことなので、詳しくは語らないが、この『ビートルズ以後のモダン・ポップ完全版』は、この10月のオアシスの来日前には出るという『オアシスとブリット・ポップ完全版』に繋がることを教えてくれた。歴史は積み重なるということか。『ビートルズ以後のモダン・ポップ完全版』が出たばかりだが、早くも次が読みたくなるというもの。
この『ビートルズ以後のモダン・ポップ完全版』は当然の如く、読みどころ、見所は数多あるが、和久井が書いた巻頭の「長嶋茂雄はポップだった」は飛ばさず、必ず、読んで欲しい。その覚悟と決意の言葉にぐっとなる。某騒動で反感を抱いていた方もきっと好きになるはず(笑)。

▲LIVE SHOW(写真左から)川原伸司(キーボード)、伴慶充(ドラムス)、和久井光司
(ヴォーカル、ギター)宮崎裕二(ギター)
▲(写真左から)伴慶充、宮崎裕二、和久井光司、川原伸司、藤本国彦、納富廉邦
1時間30分、実際は2時間近いトークショーの後はライブショーになる。モダン・ポップを語るイヴェントなので、ライブも日本のモダン・ポップの先駆け、スクリーンのナンバーも演奏しようということになったらしい。当初はドラムレスだったが、無理を言ってスースー&バンチョーズや桃電などで和久井と活動をともにする伴慶充に来てもらい、ベースはいないものの、川原のキーボード、宮崎のギター、和久井のギター、伴のドラムで、無事にバンドセットでの演奏が可能になる。同ライブでは、和久井は“「瑠璃色の地球」はモダンポップの頂点にある1曲”と言っていたが、同曲も演奏された。実は「瑠璃色の地球」は1986年6月にリリースされた松田聖子のアルバム『SUPREME』に収録され、初公開されている。スクリーンのこの日、披露した「ライフ・ゴーズ・オン」は1983年5月に3曲入りのEPがオリジナル・シングルとしてリリースされているが、同曲は和久井をして“モダン・ポップの極み”という、1986年11月にリリースされたスクリーンのサードアルバム『Camp Humours』にも収録されている。同アルバムには同じく、この日に披露した「陽のあたる場所」や「僕のファクトリー」も収録されている。同じ80年代、それもほぼ同時期に生まれているのだ。モダン・ポップの流れに乗り、ここで再び、出会うというのは偶然かもしれないが、何か、必然にも感じる。当然、スクリーン自体もに再注目だろう。再結成もあるかもしれない。
和久井は“完全版シリーズは100号まで作りたい”と言っている。毎回、ワクワクさせてくれる同シリーズの継続は嬉しい限り。この日、新たな企画なども披露された。勿論、公開はしないが、気になるテーマだった。お初の方には次もいいが、まずは『ビートルズ以後のモダン・ポップ完全版』を読んで欲しい。和久井はプロフィール欄で、モダン・ポップに改めて想うことという問いに“人類史上最も粋で知的、かつ文化的な音楽”と答えている。江戸っ子なら買うべき。必読だ。
大事なことなので、繰り返すが、和久井は言動一致、言ったことはやる音楽家でもある。批評の落とし前をちゃんと自らの音楽でもつけてくれる。彼のバンドを何度か、見ているが、納得のパフォーマンス。彼のバンド、東京暮色やスースー&バンチョーズ、桃電には窪田晴男や伴慶充、小泉信彦、菊池琢己、阿部桃子、鈴木亜紀……など、精鋭が参加している。彼が一門の音楽家であることの証明だろう。今回のライブで久しぶりにスクリーンの音楽に再会したが、改めて新生スクリーンもしっかり見たくなる。きっと、その場にいた方もスクリーン流のモダン・ポップの2025年ヴァージョンも聞いてみたくなったと思う。
「著者が直販しているサイン本の“デラックス・エディション”」は、まだ、あるそうだ。SNSなどで彼と直接、やりとりしながら買うのも楽しいだろう。ちなみにすぐ売り切れる“スーパー・デラックス・エディション”もお勧め。機会があれば是非、お求めいただきたい。