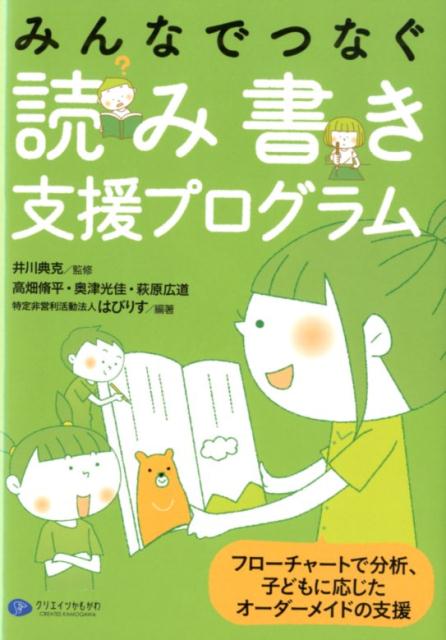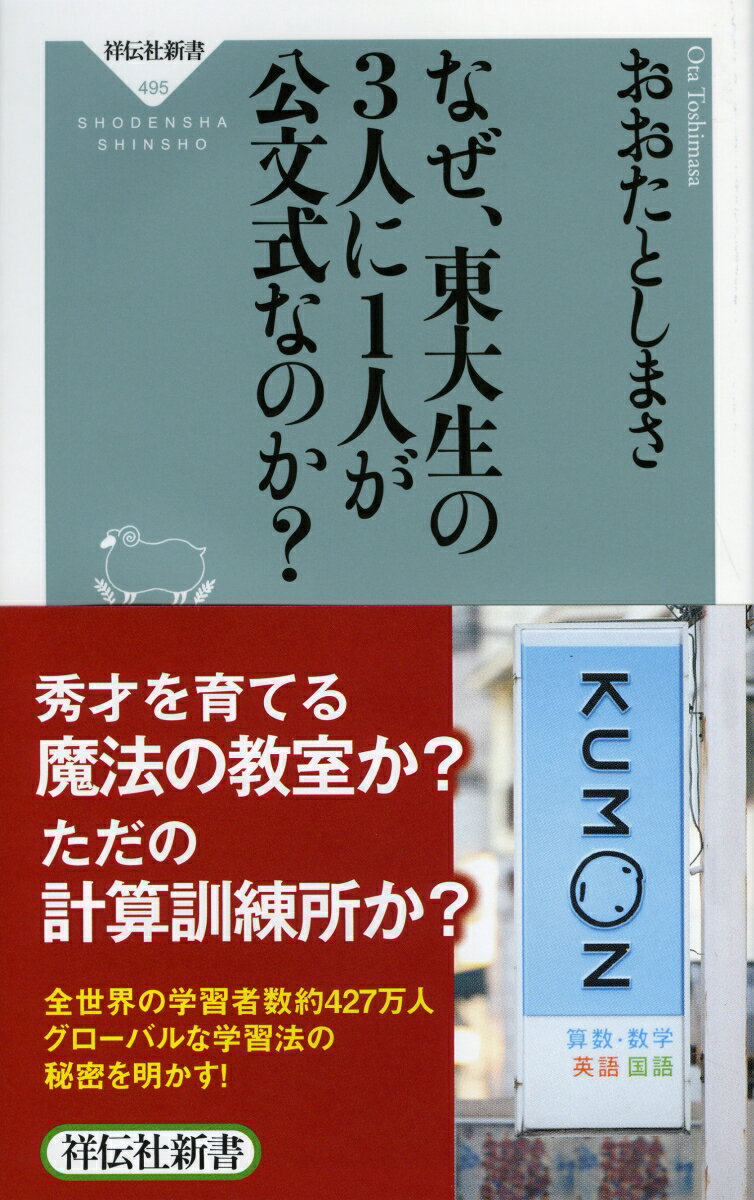長男は、3歳から5歳までピグマリオンの家庭教材を学習のメインに使っていました。その後、公文式へ移行。ピグマリオンから公文式へ移行した経緯、最近、試している「たぶお式」の反応など。
少し長くなりますが、長男の今について記録してみます。
ピグマリオンと幼児教育
ピグマリオンは、幼児教材としてすばらしいと今でも感じます。
我が家は家庭教材で学びましたが、ピグマリオンの家庭教材では、「指先・図形・空間・数・言語」の6分野が軸となっています。特に幼い子どもにとって「指先の調整能力」というのは、とても大切だと感じました。
また、それぞれのグレードごとにカリキュラムが決まっていて、1回のレッスンで何をどのくらいやるのかわかりやすく説明されています。子供への指導法も伊藤先生のDVD付で、具体的にどのような声掛けが必要かといった部分まで説明があります。
それでもわからない場合は、ピグマリオンへお電話をするとスタッフの方が親切丁寧に教えてくれます。
ピグマリオンと特別支援教育
私は、仕事で特別支援教育に携わっていますが、ピグマリオンメソッドは、特別支援教育にも共通する部分が多くあります。
例えば、ピグマリオンの教具にある、魚つり。
特別支援教育の読み書き支援の書籍でも魚つりを使った教材が出てきました。
ピグマリオンでは、点描写を毎日やるように指導されていますが、点描写も特別支援教育では効果的だとされています。
特別支援教育や療育にも重なる点が多いピクリオンメソッド。
私は、色板トントンという教具がとてもお気に入りでした。
娘も使っていた色板トントン。
ピグマリオンの教具はとても考え抜かれたものが多く、幼児期に導入することで、英才教育としてでなく、子どもが成長とともに必要とする能力の育成に役立つ教材だと感じます。
長男が年長で公文式に移行した理由
長男は、3歳から2年間、ピグマリオンに取り組みました。
「指先・図形・空間・数・言語」この6つの分野を満遍なく日々取り組むことで、マイペースな長男でも5歳の頃には成長をとても感じることができました。
特に図形については、その効果を一番感じました。色板トントンも天地パズルもペリカンパズルも大好きだった長男。点描写も難易度の高いレベルまで挑戦するまでになりました。
ただ、なかなか計算スピードが早くならないことが悩みでした。小学校に入学前に、もっと計算問題に取り組むことの必要性を感じ始めました。
公文式に通ってみて感じたこと
当時、長男が仲良かったお友達が公文の算数を習っていて、そのお友達から長男は算数の良い影響を受けていました。
そこで、長男に合う合わないは別として、ひとまずやってみようと思い、公文式のお教室に入会しました。
公文のお教室に通い始めて感じたことは、
・小学校入学前に一人で教室に入り、準備→学習→片付けまで行うことで自主性が育つ
・同じ作業を繰り返すことで作業スピードがあがる
・淡々と取り組む学習の習慣が身に着く
ということです。
これまでピグマリオンの家庭学習で学んできた我が家は、「親と一緒に学ぶ」ことがあたり前だったので、長男にすべてを任せる学び方をしたことがありませんでした。
とてもマイペースな長男。
器用なタイプでもなく、一人でお教室で学習できているのか(もちろん先生は見守ってくれていますが)最初は心配でした。けれど、通い始めて数週間ですぐに慣れたようでした。
公文式で一番効果を感じたのは勉強ではなく作業スピード
今思えば、年長から公文式に通ったことは、小学校に入学するための「作業スピードの訓練」にとても役立ったと感じます。勉強の準備のためにカバンからプリントを出す、筆箱をセットする、鉛筆を持って作業を始める、消しゴムで素早く消す、片付けをして帰宅準備をする、など。長男のタイプを考えると、小学校での集団行動が始まる前に、公文式のお教室に通って正解でした。
もちろん、計算スピードは驚くほど速くなったのですが、それ以上に効果があったと感じるのは、マイペースな長男が「ちょっと色々な作業が速くなった」こと。
ゆっくりのんびり、よくぼーっとしている長男なので、長男にとっては公文のお教室は「小学校入学前のトレーニングのお教室」のような存在だったと感じます。
慣れてきた公文プリントとの付き合い方
今は、お教室には通わずに公文のプリントを自宅で行っている我が家。
長男は、公文式が完全に習慣化され、「計算の特訓」ととらえています。
つまづくこともたくさんあって、そのたびに「今、一番つらい時なんだよね」なんて口にしますが、「ここを乗り越えると楽なんだけどなー」と、その先にあるものも見据えられるように。
それもこれも、公文がひたすら同じことの繰り返しだから。
「苦手→少しできるようになる→簡単」を繰り返して次の単元に進んでいく。
子供にとって、とてもわかりやすいです。
とはいえ、苦手=辛い時期にどうサポートするか、そこはちょっと気を使います。
枚数も減らしますし、本人の希望をできるだけ聞くように心がけています。
公文式から「たぶお式」への移行も検討
一つの教材を長く続けることを好む長男。
何かをやり始めると、その教材に思い入れが強くなるようです。
少し前に娘がスタートした「たぶお式」。
長男にも取り入れたいと考えていますが、まずは娘がやっている姿を見せて興味を持ってもらうようにしています。娘がわからないときは、長男に先生をお願いしてみたり![]()
長男の反応を見ながら、ゲーム感覚で答えを聞いてみたりもしています。正直、「たぶお式」と、相性良さそうだなと私は感じました。
自分のペースで進めて行くのが好きな長男。たぶお式をスタートしてもオンライン学習会などに参加したがることはなさそうですが、本人の意見を尊重しつつ、たぶお式を楽しめる準備を今進めています。
ちなみに、教材の呼び方を自分で決める長男。
たぶお式は、「たぶお君」と呼んでいます![]()