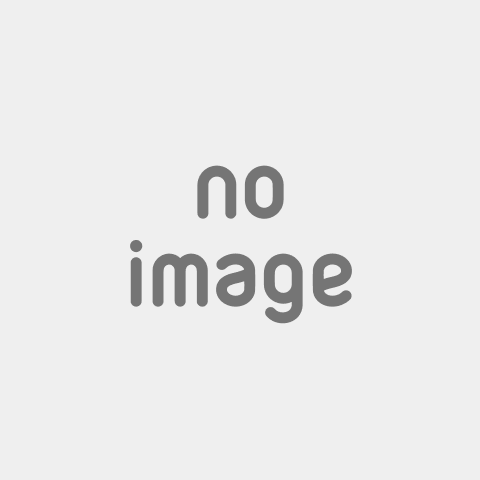[ お話は 前回 から引き続いて ]
ジョージ・ガーシュインの親友にしてアーノルド・シェーンベルクの直弟子なんて20世紀の音楽史を(勿論音楽家として)生き抜くには申し分のない経歴でしょう、そんなひとも羨むピアニストがいま私の目の前をフレッド・アステア、ジャック・ブキャナン、ナネット・ファブレーといった名うての芸達者に挟まれて景気よく踊り猛っております、ヴィンセント・ミネリ監督『バンド・ワゴン』(アメリカ 1953年)です。アステアはかつては名を轟かせたブロードウェイの寵児でしたのに吹き荒ぶ風は彼を過去に追いやって(顔でこそ余裕綽々ですが)実のところ崖っぷち、その彼をふたたびロングラン札止めの第一線へ返り咲かせようと目論むのがファブレーとそう、オスカー・レヴァントです。ミュージカル映画というのは劇場の絢爛さに学びつつ映像表現としての可能性を思う存分切り開いてまさに華と吹き綻んだのは30年代から40年代半ば、しかるに映画会社の経営がだんだんと左前になるに従って湯水のように製作費を注ぎ込むミュージカル映画は嫌がられて... 50年代以降作られるミュージカル映画というのは言えば歌って踊る歌謡映画ですものね。そういう激しい引き潮に自ら波の只中に立ってミュージカル映画の王道を示さんと格闘していたのが本作のプロデューサーであるアーサー・フリードで彼の膝下で脚本から劇中歌の作詞まで二人三脚の健筆を奮っていたアドルフ・グリーンとベティ・コムデンをそっくり引き写してレヴァントとファブレーの本作での奮闘ぶりです。彼らを夫婦という設定にしたのは物語に収めやすいからか(夫婦以上に長きに渡ったふたりの共同作業をからかった)洒落なのか、ともあれミュージカル製作の裏側から(失敗と挫折に一度は重く閉じ込められながらやがて高まる人気にそれを喰い破って)檜舞台の喝采へと昇っていきます。そもそもオケと共演できるようなピアニストですからレヴァントの役は自ずと音楽家が多くなります。『ユーモレスク』(ジーン・ネグレスコ監督 1946年)では素朴な境遇のなかでヴァイオリンへの熱情に目覚めていく主人公に寄り添う巷のピアノの先生ですし、『巴里のアメリカ人』(ヴィセント・ミネリ監督 1951年)でもジーン・ケリーを見守る作曲家です。かの作では畏友ガーシュインのピアノ協奏曲をフルオーケストラを従えて演奏して(ただ... 作中ではこれは彼が気怠く吐き出す紫煙の彼方に見る夢でして)まさにレヴァントの本分たる姿にこちらが畏まるのも束の間見れば指揮棒を振るのも彼、やがて五重奏のヴァイオリン奏者が五人とも彼で、木琴も彼(ここでも見事なマレット捌きを披露して)、ティンパニーも彼、挙句に喝采にひと際声高に立ち上がる聴衆までが彼なんですから澄ました顔でそんなアチャラカをやっております。
さてオスカー・レヴァントに分け入る前に折角ですから彼の先生から語り始めてみましょう、そうです長いヨーロッパの調性音楽をひっくり返して和音を構成する中心的な音階を解放したあのいかめしい十二音技法のシェーンベルクとわれらがハリウッドとの関わりです(オットー・フリードリック『ハリウッド帝国の興亡』文藝春秋 1994.04)。当時MGMにはまだ<ラスト・タイクーン>のアーヴィン・タルバーグが存命中でこの辣腕の映画製作者はアメリカに亡命していたシェーンベルクを映画音楽に引き入れることを思い立ちます。(まあ同じく亡命したジャン・ルノワールに<とりあえず西部劇でも撮らせよう>と考えるハリウッドの面々ですから、その名を知られたヨーロッパの作曲家にミュージカルナンバーのひとつでも作らせようとひらめいたからと言って何ら不思議はありません。)<二時に撮影所に来られたし>、ビジネスレターのこの簡素な言い廻しを見てシェーンベルクの無調的精神が沸騰します、<ウィーンにあれば皇帝フランツ・ヨーゼフでさえも私には<貴殿のご来駕を賜りたく>であるぞ!>。こういうことについては(無調どころか)まったく19世紀的な気位のなかにあるシェーンベルクにアメリカでは外交文書でしか使わないような最上級の敬語に書き直して撮影所への御越しを乞います。当日も粗相のないように早くからお待ちしておるタルバーグですが約束の時間を過ぎても待てど暮らせど閣下がやって参りません。痺れを切らして方々に連絡を入れると何とシェーンベルクは時間通りに撮影所に辿り着きながら門のところに集合していたスタジオ見学ツアーの一行に紛れ込んでしまっていることが判明。しかるに閣下に置かせられましては自分が撮影所に参るや多数のお付きの者たちで出迎えて(どうもこの辺り国王や王妃が離宮などを散策するのに道化や侍女があまたさぶらうのを思い描いたらしく)撮影所の隅々まで案内しようというMGMの心尽くしに甚だ感じ入りご満悦で見学ツアーを続けたとか。そのシェーンベルクの許でピアノ協奏曲を書き上げたオスカー・レヴァントです。融通の利かない堅物の師匠ですが弟子のことになると優しい気遣いを綻ばせて如何にしてこの曲を世に出してやるか一計を案じます。ちょうどロサンジェルス交響楽団の指揮者に就任していたオットー・クレンペラーに聞かせることを思い立ちパーティでクレンペラーが同席した折さりげなくレヴァントをピアノへ誘います、<どうだろう、お聞かせしては?>。この師匠の計らいに重々感謝しその目論見を重々理解しながら、ピアノについたレヴァントは自分の曲を弾く代わりに(何故こんなことをしているのか自分にもわからないまま)<アイルランドの瞳が微笑む時>という流行歌をクレンペラーにたっぷり弾き語ってしまって... 挙句に20世紀にその名を刻むこの偉大な指揮者に<ベートーベンは... お好きですか>と質問していま思い返しても自分で自分に戸惑うこの夜の振る舞いです。最高の結果が目の前にぶら下がるや(あとはそれをそっともぎ取るだけでいいのに)ドン・キホーテ的な突進に身を委ねずにはおけないとは何と愛らしいこと。
さて私の愛するレヴァントの一本となりますとハワード・ホークス監督「赤い酋長の身代金」でしょうか。ジョン・スタインベックを導き手にO・ヘンリーのよく知られた短編をそれぞれ監督と俳優を組み合わせて織り成した『人生模様』(1953年)の一編でしてフレッド・アレンを相棒に株の不正転売によっていまでは全国に指名手配を受けるふたり組がオスカー・レヴァントです。都会育ちで身なりこそ紳士ですがこんな片田舎に参りましたのもここいらで目鼻の立つ金を手に入れようと子供の誘拐を思い立ったからでしてアレンは2回、レヴァントに及んでは6回も刑務所に出入りしながら一向に懲りない男たちです。しかしそれ以上に世の中には上には上がいることをまだ知らないとんだ世間知らずでこれから一昼夜かけてそのことを嫌と言うほど思い知らされるわけです。子供と言いましても手の掛かるほど幼すぎては困りますし成長しすぎていては捕らえておくのに骨が折れます、手頃な幼さの上に田舎にあっても親はそれなりの金満家でなければ身代金の額が見合いませんからさて慎重に見極めてこれぞというひとりを後ろから袋詰めにして連れ去ります。その一部始終をたまたま窓から母親が見掛けていますが別段驚く様子もなく(まるで何度も読んだ雑誌を捲るように結末までの気怠いなりゆきにあくびさえ出す始末で)この辺りから彼らふたりの運命は自分たちではどうしようもできない傾斜に追いやられてあとは必死でその坂にしがみついておくしか... 被せた袋を引っ剥がすと泣くでも喚くでもなくいやに落ち着き払った子供がこちらを見据えていて(というよりこの袋を剥いだ瞬間にひとつの悪夢が子供の形で生まれ落ちたという感じで)彼こそ題名の<赤い酋長>そのひとでして身代金を受け取るまでと呪文のように(やがてふたりして独り言のように)繰り返しながら酋長に乗っ取られた夜に呑み込まれていきます。しかも結末にはこの酋長すら出し抜き更に一枚上手にお尻の毛まで脱毛です。フレッド・アレンもレビューに身を置く古株の芸達者ですが彼と手に手を携えてオスカー・レヴァントのまさに芸は身を助く男一代でございます。
こちらをポチっとよろしくお願いいたします♪
関連記事
1年前の記事
前記事 >>>
■ フォローよろしくお願いします ■
『 こけさんの、なま煮えなま焼けなま齧り 』 五十女こけ