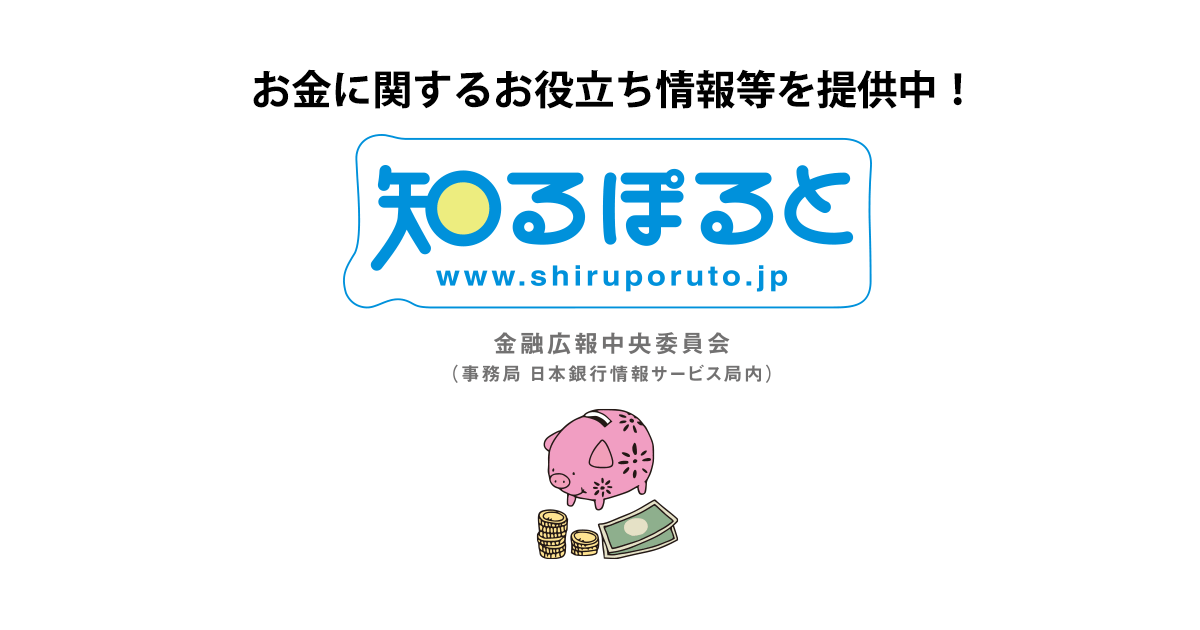今年度もはや半分が過ぎそうです!
そんな今年は、
やはり4月から高校の家庭科の授業で、
社会ではなく家庭科で学ぶところがポイント。
将来の生活のために学ぶべき一つとして、
また、先日8月29日の日経新聞の記事では、金融庁が金融教育を
ついに、全世代でお金の教育が当たり前に!
お金の話は下品という時代から、大人もこどもお金のことをしっかり学んで、![]()
では、その最近よく聞くようになった「金融リテラシー」
金融庁が示している「最低限身に付けるべき金融リテラシー」で、何歳ごろに、どんな内容を理解しているべきか一覧にした”金融リテラシーマップ”というものがあり
「最低限身に付けるべき金融リテラシー」の内容は
①家計管理
②生活設計
③金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択
④外部の知見の適切な活用
の4分野に分かれます。
年齢層は小学生低学年、中学年、高学年、中学生、高校生、
例えば、①家計管理の部門
「小学校中学年」では、
- 買い物に当たって、必要なもの(ニーズ) と欲しいもの(ウォンツ)を区別すること ができる など
「一般社会人」では、
- 収入(手取り額)、支出の特性(
一時的か定常的か等) を的確に把握し、先行きの収支見通しを立てることがで きる - ○○収支の改善に努め、黒字を確保し、貯蓄や投資を通じて 将来に向けた資産形成を行っている
- 必要に応じ、負債(住宅ローン等)も計画的かつ有効に 利用することができる などなど
このあたりはなんとなく想像がつきますね。
ではこちらはいかがでしょう。
③の金融分野共通の項目では
「大学生」から
- リボ払い
- ドルコスト平均法
- 72の法則
という言葉が出てきます。
ドルコスト平均法:定期的に定額で購入する方法
72の法則: 複利計算により、
例えば、年利3%
いかがですか?このあたり、![]()
恐らく年齢に関係なく、金融商品を学ぶ時点で最初から抑えるべきポイント、ということだと思います。
成人年齢が18歳になりましたし、大学生から金融商品を検討する機会はもちろんありますよね。
ではこの機会に、軽い金融リテラシークイズにチャレンジしてみましょう!
① 家計簿などで、収支を管理する
② 本当に必要か、収入はあるかなどを考えたうえで、支出をするかど
③ 収入のうち、一定額を天引きにするなどの方法により、貯蓄を行う
④ 支払いを遅らせるため、クレジットカードの分割払いを多用する
⑤ わからない
答え:④
① 一生涯の生活費、子の教育費、医療費
② 子の教育費、住宅購入費、老後の生活費
③ 住宅購入費、医療費、親の介護費
④ わからない
答え:②
① 運用は固定金利、借入れは固定金利にする
② 運用は固定金利、借入れは変動金利にする
③ 運用は変動金利、借入れは固定金利にする
④ 運用は変動金利、借入れは変動金利にする
答え:③
① 2年未満
② 2年以上5年未満
③ 5年以上10年未満
④ 10年以上
⑤ わからない
答え:②
① 消費生活センター
② 金融ADR制度
③ 格付会社
④ 弁護士
答え:③
以上5問。
さて、直前にお伝えした72の法則は思い出して頂けましたでしょうか?![]()
こちらのミニテストの点数、
全国平均 50.6 点(一問20点)
性別平均 女性49.4 点
年齢層別平均 (ちなみに30代は44.1 点)
正答率は、
1問目51.8 %
2問目46.2 %
3問目43.4 %
4問目40.8 %
5問目70.8 % です。
都道府県別の平均点も調べられます。
ぜひ満点を目指したいですね![]()
そういえば実はこのブログは、すべての方にFP3級レベルの知識をお届けすべく始まったものなんですよね![]()
日本FP協会のデータによりますと、
金融業界で働いている方だけが持っている資格ではないことがわか
またお子さんにとっては、学校で教えてくれるようになっても、一番身近な存在であるお父さん、お母さんの協力は必須です。
金融商品の知識はどこでお勉強できても、根底にあるお金の大切さを教えられるのは、
一番身近な単位である家計についても、![]()
ご紹介した金融マップとクイズのページはこちらです。詳細や解説など、ぜひご参考ください。
また、キッズマネーステーションでは、金融庁の金融リテラシーマップに沿った講座をたくさん開催しております。親子でお金のことを楽しく学べる内容となっております。こちらもぜひご参考くださいね😊