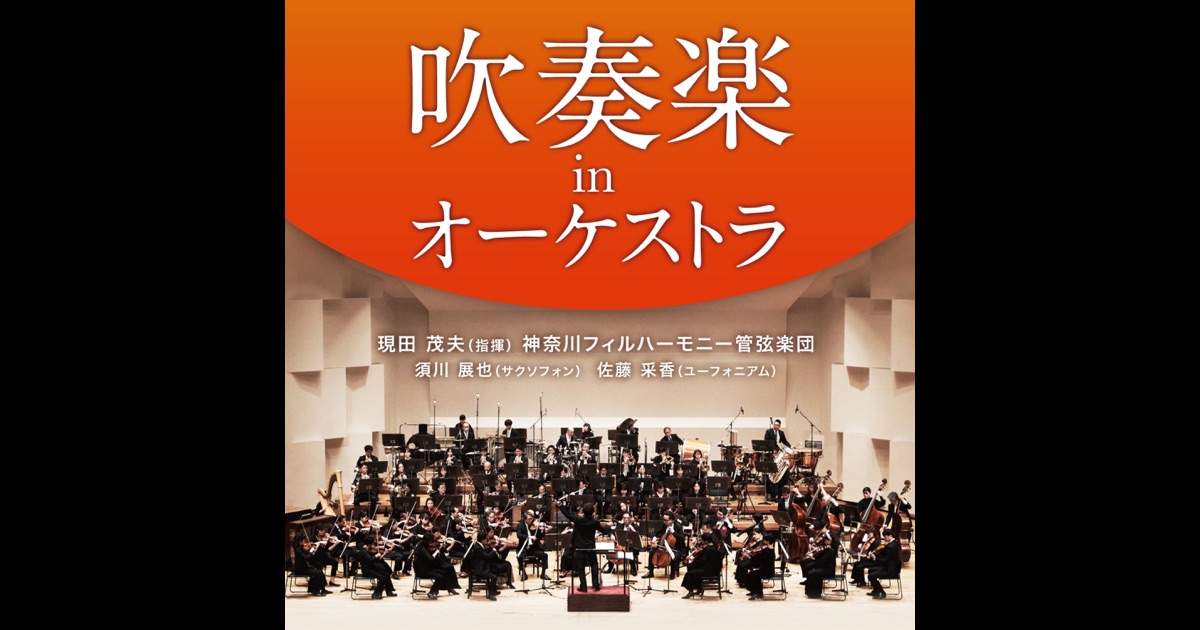管弦楽作品が編曲されて吹奏楽で演奏されることは珍しいことではなく、例をあげるとレスピーギの「ローマの祭」やラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲、ドビュッシーの交響詩「海」、バルトークのバレエ組曲「中国の不思議な役人」など多くの名曲たちが吹奏楽編曲されている。逆に吹奏楽曲が管弦楽版となることは少なく、パッと考えてもヴォーン・ウィリアムズの「イギリス民謡組曲」(ジェイコブ編曲版)やフサの「プラハ1968年のための音楽」くらいしか思い浮かばない。私が忘れているだけかもしれないので、他にあればぜひコメント欄に投稿をお願いします。
さて、吹奏楽曲をオーケストラで演奏するという今回のコンセプトだが、今から6年前にあたる2018年に21世紀オーケストラが特別演奏会「吹奏楽曲をオーケストラで!vol.1」で杉並公会堂にて同様の企画を行なっていた。この演奏会は私も聴きに行ったが、プログラムをなくしてしまったのが残念なところ。吹奏楽コンクール課題曲から人気投票を行い、上位3曲を管弦楽版での演奏やC.T.スミスの代表作である「華麗なる舞曲」と今回のCDにも収録されているバーンズの「アルヴァマー序曲」がオーケストラで演奏された。この時の編曲に関してはホームページにも記載がないので不明となっている。プログラムが見つかり次第追記したいと思う。
・バーンズ:アルヴァマー序曲(大橋晃一編曲)
録音:2023年11月4日(ライヴ)
大橋さんによる編曲版として初演になっている管弦楽版の「アルヴァマー」、演奏されるテンポによって聴こえ方が大分変わる曲である。今回は速さにものを言わせている感覚は基本的にない。オーケストラ全体におけるバランスとしても充分になっており、細かいオーケストレーションが違うこともあって普段聴き慣れた吹奏楽版とは違い弦楽器のスケールが土台として完成されている。それにより分厚いスケールと伸びやかなサウンドを聴くことができるようになった。弦楽器の音色に関しても管楽器群に押し負けることのない分厚いサウンドのもと演奏されているため基本として全く違和感を感じることなく、元々は管弦楽のための曲であったかのようなバランス感である。若干金管楽器の音色が吹奏楽寄りに作られている印象も受けなくはない。
・保科洋:管弦楽のための「風紋」(原典版)
録音:2023年11月4日(ライヴ)
1987年全日本吹奏楽コンクール課題曲として作曲された「風紋」。なお課題曲はカット版であり、後に原典版が発表されている。今回の管弦楽版はその原典版を基に作曲者自身によって管弦楽版に編曲されている。管弦楽版は2009年に初演された。作曲者自身による編曲ということもあってオーケストレーションは見事なものとなっており、重厚的で分厚いスケールを奏でる弦楽器群の濃厚な音色がオーケストラ全体を包み込んでいる。それもあって金管楽器や木管楽器の音色にもキツさを感じることなく演奏されており、奥深さを重視しているような感覚をたっぷりと味わえながら往年の時代における吹奏楽の課題曲をオーケストラで味わえるようになっている。
・スパーク:パントマイム(大橋晃一編曲)
録音:2023年11月4日(ライヴ)
ユーフォニアム独奏と吹奏楽またはピアノによって演奏されるこの曲。オーケストラをバックに今回は佐藤采香さんがユーフォニアムを演奏している。まさに超絶技巧の連続とも言える名曲で、数多くの金管バンド作品や吹奏楽曲を作曲しているスパークの遊び心ある「パントマイム」を演奏している。テンポの緩急ある三部構成となっているのもそうだが、非常にまろやかで伸びやかなユーフォニアムの音色と響きは神奈川フィルが奏でるサウンドともぴたりと相性が合っているという感覚である。「緩→急」へと変化した際のスピーディな推進力からなるエネルギーも良いが、緩やかなテンポによって奏でられる演奏時も非常に聴きごたえがある演奏となっている。
・リード:アルメニアン・ダンス・パート1(大橋晃一編曲)
録音:2023年11月4日(ライヴ)
吹奏楽による定番曲である「アルメニアン・ダンス」。今回はpart2は演奏されず、part1のみとなっている。こちらも大橋さんによる編曲版での管弦楽版としては初演にあたる。冒頭のトランペットの特徴的な音色によって若干驚かされてしまうかもしれないが、普段通りのテンポ設定によって演奏されているため違和感はそこまで感じられない。また、メドレーとなっているためそれぞれの曲の際にソロがあるのだが、一部弦楽器による演奏が割り当てられて演奏が行われている。全体を通しても非常に安定感のある演奏となっており、各楽器が演奏する音色からはキャラクターがわかりやすく作り込まれていることもあって最初から最後まで聴き入ってしまった。
・狭間美帆:サクソフォン・ソナタ第1番「秘色の王国」(管弦楽版)
録音:2023年11月4日(ライヴ)
日本におけるサクソフォーン奏者である須川展也さんに委嘱されたサクソフォーンとピアノのための曲である。今回は作曲者自身の手によって管弦楽に編曲されて演奏されている。全3楽章からなるソナタで、どちらかといえば現代的なジャズという曲ともいえる。それをオーケストラで演奏しているため、より新鮮味は感じられるだろうか。今回の演奏はもちろん須川さんによる演奏となっており、安定感のあるオーケストラとのバランスの良さが明確となった演奏で、各楽章ごとに個性的な世界観が展開されている。濃密で魅力的なサクソフォーンの甘い音色と響きが功を奏する形となっているのは間違いなく唐突に終わってしまうものの、昔の映画の幕切れのような感覚であるためこれも良いとは思える。
・ラヴェル:ボレロ
録音:2023年11月4日(ライヴ)
「ここまで吹奏楽曲だったのになぜここで「ボレロ」が?」と考えてしまうかもしれない。冷静になってみると、同じ旋律を繰り返す中で数多くの管楽器よるソロが登場するから選曲されているのだろう。そして、よく聴いてみるとユーフォニアムも演奏をしている。少しずつ楽器が増えていき、その密度は増していく。最終的にオーケストラ全体のテンションは非常に高いものとなり、ボルテージが最高潮に達した瞬間は、まさに度肝を抜かされる演奏である。
・東海林修:管弦楽のための「ディスコ・キッド」
録音:2023年11月4日(ライヴ)
1977年全日本吹奏楽コンクール課題曲作品であり、現在でも盛んに演奏される名曲である。楽譜には書いていない「ディスコ!」という掛け声は当時から入れられており、全国大会でも何団体か掛け声を入れている。今回は作曲者自身による管弦楽編曲となっており、課題曲版ではなくそれ以降の年代の楽譜が基とされている。オーケストラでポップスをやること自体それほどないためか、若干控えめに聴こえなくもなかったがクラリネットソロや弦楽器を加えたことによるオーケストレーションの変化などが、普段聴き慣れた「ディスコ・キッド」とは違う品も加わっているのでぜひ聴いてみてもらえたい演奏となっている。
この類いの企画は中々長続きしないため、今回こうしてCD化されたのは今後としても非常に大きな効果をもたらしてくれるのではないか?と個人的に考えていたりもする。賛否両論あるかもしれないが、今のところそこまで荒れていないので好印象として捉えられていることに間違いはないだろう。ぜひ第2弾の企画が出れば演奏会に行ってみたいところ。