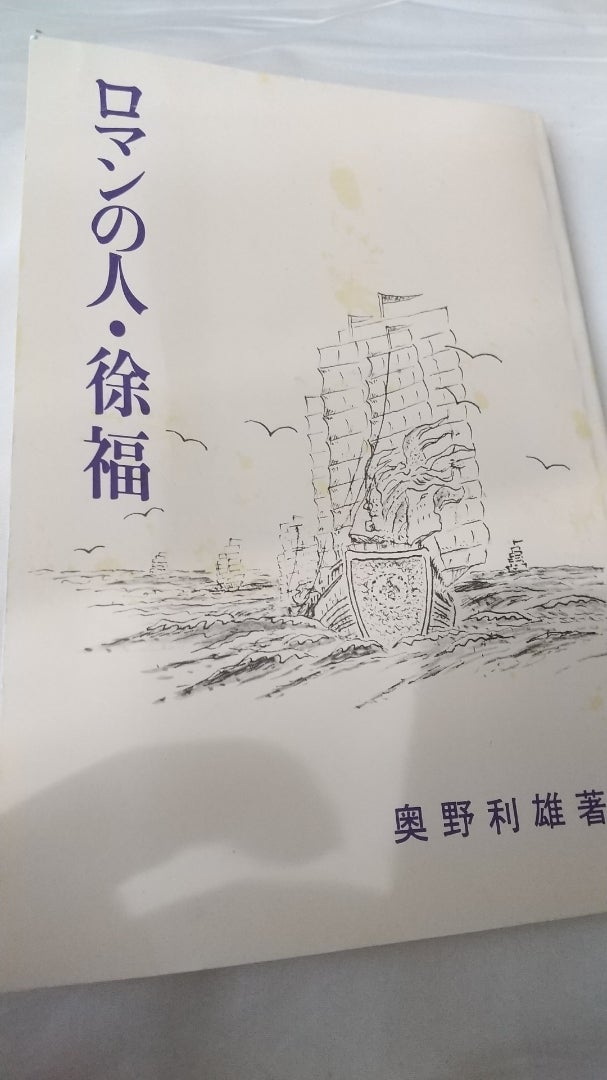(徐福の宮の境内に立つ墓碑)
◆ 徐福 (方士が見た理想郷) ~7
(熊野市波田須編)
海無し県民の海への憧れというのは
かなりのものでして…
海を見るだけで気分が高揚。
時には黄昏れ…
ここに徐福の伝承地があるから、というだけでなくここから見る海辺の美しさを求めて、気づけば4回も訪れてます。
アクセスが大変やのに。
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
■過去記事
* ~ 1 … 始皇帝を欺く!
* ~ 2 … 神薬を求め出航!
* ~ 3 … 九州の徐福伝承
* ~ 4 … 四国の徐福伝説
* ~ 5 … 新宮市 前編
* ~ 6 … 新宮市 後編
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
◎漂着か
新宮市からおよそ北へ20km余り。すり鉢状に抉られた小さな海辺の村「波田須(はだす)」という地があります。
自然が織り成す風光明媚な海岸の景色は訪れる者を魅了するものの、ここで住むにはちょっと…というような地。
町のほとんどが急峻な斜面。川も無く棚田をするにも斜面がきつく困難。漁をするにも船を寄せられる港を作りようも無し。家が10軒ほど建てられそうな僅かな台地があるのみ、そこに徐福の宮が建てられています。
およそ難破し命からがら漂着…そんな様子を想像させられます。
人口は95世帯152人(2019年尾鷲市データ)。生活を営むのに困難なこの地に、まるで徐福の伝承地を守りぬくために住んでいるかの如く。
◎「波田須」は「秦栖」「秦住」
「熊野市観光公社」サイトを引用したWiki掲載の徐福伝説は以下の通り。
━━徐福の一行は数十艘で出航したが、途中で台風に遭い、徐福を乗せた船だけが波田須に流れ着いた。当時の波田須には3軒しか家がなかったが、この3軒は徐福らの世話を行った。当地に上陸した徐福は中国への帰国を諦め、「秦」に由来する「ハタ」と読む姓(波田、羽田、畑など)を名乗り、窯を作り焼き物の作り方を村人に教えた。さらに土木事業、農耕、捕鯨、医薬品、製鉄など、この地域になかった文明を次々と伝授した。このため住民は、徐福を神として崇めた━━
捕鯨はいささか問題あるも、多くの伝承や証拠品が残されています。
当地は新井白石の「国文通考」などにも記されるように「秦住」、または「秦栖」と表記されていたようです。
上陸時にあったという3軒は、「東家」「仲家」「西家」として現在も続いているとのこと。
◎徐福が伝えたもの
徐福の宮を守り続けているという中本氏所有の「秦徐福宝物由来」(大正八年記)には以下の内容が示されているようです。
━━波多須神社(波田須神社のこと)合祀ノ神ニ座ス秦徐福ノ御遺物、剱、古文書、鉢ノ三品ハ往昔、矢賀里ノ東・仲・西ノ三家ニテ輪番ニ保存ナシツツアリテ、仲家ノ番ノ時天火ノタメ古文書ヲ焼失シ、剱ハ東家の番ノ或ル夏、字矢口ニ子供ヲ連レテ草刈リニ行キタルニ、子供ハ海辺ニテ遊ビ居タルガ、不幸ニモ鮫ノ為二喰ワレケレバ無念ノ余リ、仇ヲ討ツベク剱ヲ携エテ海辺二行キタルニ、鮫ハ再ビ姿ヲ表ワセシニゾ、鮫ヲ目掛ケテ突キ刺シタルママ紛失シタリ。
鉢ハ如何ニシテ失イシカ不明ノ所、測ラズモ今回伊勢四日市市中町、川村又助氏方二秘蔵サレテイルヲ、前南牟婁郡長平賀正文氏ヨリ聞イテ知リ、区長中本鉄五郎が津市二平賀氏ヲ訪ネ、同氏ト共二四日市市二致リ、川村家二其ノ奉還ヲ請イタレド、是ヨリ先平賀氏ハ予メ交渉シ置キタル故、直チニ承諾セラレタリ (中略)。
同時二往昔鮫ヲ刺シ失ヒタリト云ウ剱ハ東牟婁郡太地町ノ地引網二掛リ拾得シタレバ、受取リ来ルベシト云イ越セシ事ノアリシト云ウ。昔ノ言伝エヲ頼リテ氏子総代久保長左ヱ門ヲ遣シ、種々聞キ合シタレドモ容易二判明セズ、同町ノ或ル有志者二捜索方ヲ依頼シ置キテ帰リケリ。伝エ聞クニ其ノ剱ニハ秦ト云ウ文字ヲ切リ付ケテアル由、当時少林寺什器打鐘二秦栖村ト記シアリ、其ノ昔現今ノ波多須ヲ秦住村ト称セシト言ウモ事実ナカランカ、茲二宝物御体ノ由来ノ大略ヲ記ス━━
この他、上述の中本家には秦代の通過や半両銭が保管されているとのこと。徐福の宮付近からは弥生式土器片が出土しています。そして徐福が求めたという「天台烏薬(テンダイウヤク)」「アシタバ」が自生しています。
また徐福が開拓したという「釜所」「釜屋敷」という地名があり、製鉄を始めたと言い伝えられる伝承があるようです。ちなみに付近から砂鉄が出ているとされます。
さらに同市内の産田神社には、徐福が伝えたという赤米が出ているとのこと。
新井白石は「国文通考」において、徐福が当地に漂着後、新宮へ移住したとしています。
*誤字・脱字・誤記等無きよう努めますが、もし発見されました際はご指摘頂けますとさいわいです。