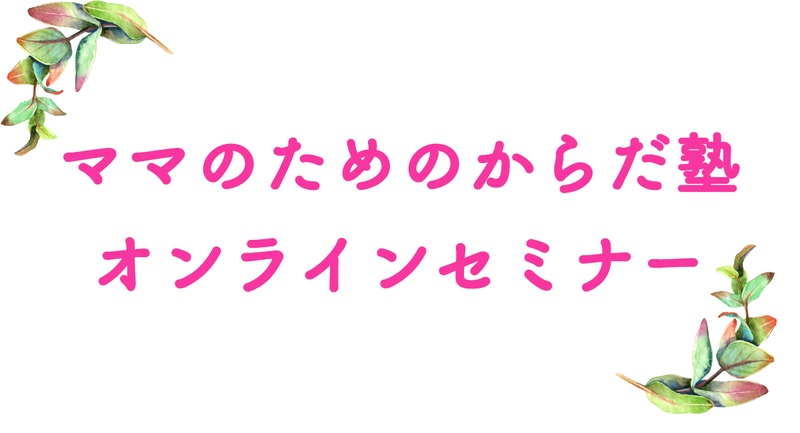桜の膨らみにドキドキしている、こつばんママです。
昨日、娘が学校から泣きながら帰ってきたので、
一緒に「アウェアネス・好きなことノート」を作りました。
これは、そもそも「ストレスコーピングノート」のことです。
8歳に「ストレスコーピング」って言っても意味不明なので、
「学校で嫌なことがあったり、我慢しなくちゃいけない時があったら、
帰ってきて、このノートに"好きなこと"を埋め尽くして楽しもう」
そんなコンセプトで昨日お買い物に行きました。
私も表紙作りからやろうと思って、まだ手付かず。
私は昔から、このストレスコーピングという名前を知らない頃、もう20年前から、
ノートに「好きなことを埋め尽くす」をやっていました。
のちに、これが「ストレスコーピングリスト」と名前があることを知り、
結構嬉しかった記憶(笑
去年、ひろみっちのPOF理論のWSに参加した時も、同じような課題が出ていました。
POFをもとに、閃いたことを記録する、というものでした。
年々、心の中で呟いてきたことを、
こうやってアウトプットするようになってきました。
追い風は去年のPOFWSだったな、と思ってます。
そして、
アウトプット=排出力=副交感神経
という事を体現する出来事が増えています。
娘は笑顔で登校できたし(学校行きたくない、とは言っていたけれど、戻る「軸」をきちんと受け止めてくれていました。)
何より、私自身がそれを何度も経験しているからです。
アウトプットは、なんでもいいんです。
女性は喋る生き物なので、
女子会、おしゃべりでもOK
でも、条件があります。
この女子会、おしゃべりは「安心、安全な相手とだけ行うもの」
へんな気遣いや、腹の下の探り合い、難しい会話になるママ友
これは避けてください!
書き出すアウトプット
ノート、手紙、メール、ブログなど・・・
日記もそうですね。
なんでもいいんです。
でも、今回お伝えしたいのは、
"自律神経を整える"アウェアネス・好きな事ノート
「おねしょ」
この相談をこの8年間、一番多く頂いたんじゃないかと思います。
ブログにも、「おねしょ」テーマに記事を何度もアップしてきましたが、
ハッシュタグで1位になったのは、初めてです。
正直、とっても嬉しいです。
読んでくださった方、ありがとうございます♬
届けたいところに、少しずつ届く「線路」ができたようなイメージ。
都度、いろいろなテーマで「おねしょ」を書いているのですが、
そもそも、なんで「おねしょ」気になるんでしょうね。
だいたい、自律神経の切り替えができるようになってくるのが、
4歳前後です。
この頃から、夜のおしっこに個人差が出てくるんじゃないかな。
この8年間の足裏診断、親子面談などから見えてきているのは、
慢性のおねしょと突発的なおねしょの境目があるようです。
慢性のおねしょは、膀胱の病気が関連することもあるので、
これは、医療にお任せします。
慢性だけど、精神的な部分からくるおねしょ
これは、家庭環境と個人の性格によるものが大きく、
現象をどう捉えているのか?がかかってきます。
突発的なおねしょについては、きっとママさんたちも「しょうがない」って思うかもしれませんが、時々怒ってしまう方からもお話を聞きます。
「もう、●歳なんだから!おねしょなんて恥ずかしいでしょ!」
この言葉が、引き金になって、慢性化することも・・・
まず、「おねしょ」は怒らないでください。
だって、自律神経は自分でコントール不可能なんですから。
「突発のおねしょ」は、イベント事の前後に起こりやすいです。
運動会やお遊戯会的な「発表の場」の前後。
緊張状態が継続することが原因です。
対処法は、マッサージや抱っこ、アロマスプレーなどを利用して、
気持ちを切り替えることです。
睡眠の導入を「すでにリラックスしている」状態に導くことをオススメしています。
一般的には、おねしょをはじめとする成長期の「自律神経」の問題は、
生活習慣、早寝、早起き、食事と快便、快眠
なんて言われていますが、これを教科書通りにしっかりやっても、
おねしょが起こることがあります。
何故なのか?
自律神経の根っこは、「どう感じるのか?」から引き起こされるからです。
同じ現象を体験しても、感じ方が違うと、リラックスするか、防衛本能が働くか?違ってくるんです。
例としてよくあるのが・・・・
幼稚園などでマッサージを教えることが多いのですが、
おねしょにも有効ですよ、とお伝えすると、
ご自宅で「おねしょにはマッサージだから!」と意気込んでマッサージをやろうとすると、お子さんが逃げる、というパターンです。
子どもは、大人が思っている以上に大人の反応を観察しています。
「このマッサージでおねしょをなおしてやるぞ!」
という責め体制で、マッサージをしたり、
規則正しい生活を!と、時計とにらめっこして、ママがイライラしたり、
おねしょを治すために!
とママ自身がイケイケの責め体制でケアをしようとすると、
子どもは防衛本能が働きます。
ママに責められることを防衛する、という図式です。
そうなると、、、子どもは、「怒らせないために、おねしょで心配させないために」という防衛本能にスイッチが入り、さらに交感神経にスイッチが入り続けるようになります。
「ママを喜ばせたい!」
それも、案外カラダに無駄な力が入り、交感神経が優位になることも。
リラックスの神経に切り替えるレッスンを、親子でやって欲しいな、と思うんです。
そして、「トイレ」がリラックスできる環境に。
トイレが楽しい、おしっこが出て気持ちいい!
そんなトイレ作りをしてみませんか?
誰のためでもない。
自分のために。
1年生以上であれば、今回私が娘とやった「アウェアネス・好きなことノート」は一緒に作れると思います。
これも、対処法のひとつ。
誰のためでもない、自分のために「好きなこと」で埋め尽くす。
過去記事でも、こんなチェックリスト作ってます。
より、抜粋します。
【身体知性を高めるー自律神経編⑤】
誰と、どこで、どんな食事が心地良いですか?
□ 毎朝気持ちよくご飯を食べることができる
□ 毎日全ての食事が楽しくできている
□ 毎日全ての食事が美味しいと感じている
毎日全ての食事が自分にとって満足できている
不調和な食事は攻撃要素の交感神経に繋がる
【身体知性を高めるー自律神経編⑥】
どんな寝具で、誰と、どう寝たら気持ち良い?
□ 毎日の睡眠時間に満足がいっている
□ 毎朝気持ちよく起きることができる
□ 毎晩、スムーズに入眠できている
□ 毎朝、疲れが取れている、と感じられる
思考を休め、生理機能をスムーズにするのが睡眠
【身体知性を高めるー自律神経編⑦】
思考を真っ白にできる遊びの心地よさを知っている。
□ 毎日一つでも「楽しい!」と思う行動をしている。
□ これさえやっていれば、楽しくなる!という事がある。
□ 頭が真っ白になるくらいになれる遊びを知ってる。
思考パターンを外すキッカケを作る。
【身体知性を高めるー自律神経編⑧】
出せてないと入らない
食事と連動する
□ 常に排尿が気持ちよくできている
□ 常に排便が気持ちよくできている
□ 排便が1日1回は必ずある
排尿は我慢せずにすぐにできる
骨盤底筋群は心地良さのバロメーター
月経とも関わる。
「おねしょ」に悩むママたちへ
まずは、ママから「アウェアネス・好きなことノート」を作ってみませんか?
食 の好き
寝 の好き
遊 の好き
排泄 の好き
この4つの問いかけから書き出してみよう。
そして、このノートは、自分が戻る場所。
この場所に戻れば、安心する、ほっとする。
その「軸」作り。
◆ 家族と喋りながら食べるご飯
◆ 誰かが作ってくれるご飯(笑
◆ サラっとしたシーツにふわふわの毛布にくるまって寝る
◆ 脚の間に手を挟むか、娘の足を挟んで寝る
◆ 粉物をひたすらこねる、焼く、誰かに食べてもらう
こんな風に、ご自身の中で、
クウネルアソブダス
この4つのテーマから始めると良いと思います。
そして、このとき選ぶノートも大事。
自分でデコレーションしても良し、
高価なノートにするも良し、
安くても描きやすさを選ぶも良し、
つまり、このノート選びから始まってます
「アウェアネス・好きなことノート」(ストレスコーピングリストのこと)
幼児のお子さんであれば、お母さんが文字を書いてあげて、
写真を貼ったりするのは良いかもしれません。
きっと、我が娘であれば「プリンセス」とかプリントして、
貼ったに違いありません。
この表紙も、きっと、どんどん書き込まれていくのだと思います。
「おねしょ」テーマに限らず、
便秘も、根っこは同じ。
第1子より、第2子、第3子に便秘が多いかもしれません。
第2子以降は、自分のペースより、上のお子さんのペースが強くなりがち。
お母さんは、お子さんの数だけ、意識が分散しますから、
独占できないモヤモヤも、お子さんの自律神経が乱れる鍵。
昨日もちょっと書いてますが、
育児というのは、自分を一瞬無くすような感覚に陥ることがあると思います。
この「アウェアネス・好きなことノート」で自分に戻る。
書き出しは、「食う寝る遊ぶ出す」から始めてみよう。
次回のママのためのからだ塾は、4/11開講です♬
お申し込み時に「おねしょ」と書いてくだされば、そんなお話交えていきますね。
「ママのためのからだ塾」で、お会いしましょう♩
4月11日(木)10:30-11:30を予定中です!
Zoomにて開講します!
![]() 詳細はクリック!
詳細はクリック!
完全版はYoutubeの概要欄に記載しています。
同時に、noteにも記事をアップしています。
定期開催の3/14骨盤・股関節大掃除へ
オンライン参加も募集中です。
【参加者特典】
◆ 非公開動画を配信
◆ 参加者には、繰り返し復習できるまとめ動画のURL公開
◆ 2回続けてリピート参加される方は、メールコンサルを無料で提供