改善指標
金属部品加工工場のお客様で実施した,QCC活動の実践研修の事例をご紹介しよう.
11サークルのメンバーに,課題設定から発表までを,実際に活動する形で指導した.
活動のQCステップごとに講義・演習をし,次の回までに各サークルの実テーマをそのステップまで完了し,サークルごとに発表をしてもらっている.
ひとつのサークルは「ロット不良の低減」をテーマに取り組んでいる.彼らの原因分析ステップの発表を聞いても,全く理解できない.こういう場合は,研修室を出てすぐ現場に行くことにしている.
4月にロット不良が44件もあった.これを8件までに減らす目標を立てている.
しかしその原因解析が,要領を得ない.
現場で分かったコトは,このサークルは製造部門のサークルではなく,IPQC(工程内品質管理)部門のサークルである.彼らが発見するロット不良を,減らしたいと言うテーマだ.
製造部ならばロット不良を減らすことが目標となるのは分かるが,IPQCがなぜロット不良低減を目標としているのか理解が出来ない.
IPQCはたくさん不良ロットを見つけるのが成果だ.ロット不良を減らすのは目標にならない.
理解不能の原因はこの工場のロット不良の定義にあった.
この工場では,自動生産設備が生産している部品を,2時間に一回10個抜き取り検査を行い,不良が見つかるとロットアウトとして廃棄処分をする.
しかし彼らはそれをロット不良としてカウントしない.2時間以内に見つけられなかった場合をロット不良として定義している.
IPQC検査員は12台の設備を巡回しながら,抜き取り検査をしている.従って一回の検査を10分以内に完了しないと,12台の設備の抜き取り検査に2時間以上かかってしまう.この時不良を見つけると,ロット不良となる.
考え方としては,IPQCが不良を適時に発見した場合はロット不良としない(製品は廃棄)ということだ.製造部や,設備メンテナンスの部門にとって明らかにロット不良であるが,IPQCがその損失を最小限に抑えたのだから,大目に見るということだろう.
これで全てが見えた.
彼らの活動は,ロット不良を減らす,という品質改善のテーマでは無い.
2時間以内に12台の設備の抜き取り検査を終わるようにする,という作業改善のテーマなのだ.
改善指標は(正しい意味の)ロット不良の低減ではなく,抜き取り検査時間の短縮,なのだ.
ならば話が早い.
現場でIPQC検査員の作業を観察すると,二次元投影測定器の操作に個人差があるのが分かる.これを改善すれば良いのだ.特定のIPQC検査員が出来ていないだけなので,この改善で2時間以内は全員が達成できるだろう.
しかし2時間に一回抜き取り検査というのは,自分たちの都合で決めた決まりだ.もし1時間に1回抜き取り検査をすれば,不良損失は半分になる.
本来不良をなくすのが改善だが,IPQCのメンバーにとっては検査時間を半分にするのが改善のはずだ.
こういう話を現場のリーダにすると即座に「不可能!」と答えが返って来た.
それは今の方法でやっているから,不可能なだけだ.方法を変えれば,可能となる.
その方法を教えたいのは山々だが,ぐっとこらえる(笑)
まず2時間以内をIPQC検査員全員が実現することで,達成感を持ってもらう.
その次の課題として「検査時間半分=損失半減」と言う改善に取り組んでもらうことが出来ればと考えている.
ところでこの事例のように,製造部とIPQCで正反対の目標(つまり,一方はたくさん良品を造る.他方はたくさん不良を見つける)を持っている場合,適切にその指標を決めてやらなければならない.
正しい意味でロット不良を減らすことは製造部にとっては,努力しなければならない目標だが,IPQCが同じ目標を達成しようとすれば,検査をしなければ良いのだ.一方IPQCが不良を見逃せば,製造部は何の努力も無く改善できた様に見える.
今回の事例では,IPQCの指標を「不良適時発見による損失コストの削減」とし,廃棄しなければならなくなった製品が何時間分(少ない方が良い)とするのが良かろう.
こうすれば製造部は品質を改善してロット不良を減らす.
IPQCは作業改善をして,短時間で抜き取り検査を完了することにより,不良を造り続ける時間を減らす.当面は利害が一致するはずだ.
「当面は」と書いたのは,本来は設備を改善して不良を作らなくする,生産中に良品・不良品の判定機能を付加し,不良が発生したら停止する(人偏のある自働化)というのが本質的改善だからだ.
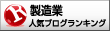
11サークルのメンバーに,課題設定から発表までを,実際に活動する形で指導した.
活動のQCステップごとに講義・演習をし,次の回までに各サークルの実テーマをそのステップまで完了し,サークルごとに発表をしてもらっている.
ひとつのサークルは「ロット不良の低減」をテーマに取り組んでいる.彼らの原因分析ステップの発表を聞いても,全く理解できない.こういう場合は,研修室を出てすぐ現場に行くことにしている.
4月にロット不良が44件もあった.これを8件までに減らす目標を立てている.
しかしその原因解析が,要領を得ない.
現場で分かったコトは,このサークルは製造部門のサークルではなく,IPQC(工程内品質管理)部門のサークルである.彼らが発見するロット不良を,減らしたいと言うテーマだ.
製造部ならばロット不良を減らすことが目標となるのは分かるが,IPQCがなぜロット不良低減を目標としているのか理解が出来ない.
IPQCはたくさん不良ロットを見つけるのが成果だ.ロット不良を減らすのは目標にならない.
理解不能の原因はこの工場のロット不良の定義にあった.
この工場では,自動生産設備が生産している部品を,2時間に一回10個抜き取り検査を行い,不良が見つかるとロットアウトとして廃棄処分をする.
しかし彼らはそれをロット不良としてカウントしない.2時間以内に見つけられなかった場合をロット不良として定義している.
IPQC検査員は12台の設備を巡回しながら,抜き取り検査をしている.従って一回の検査を10分以内に完了しないと,12台の設備の抜き取り検査に2時間以上かかってしまう.この時不良を見つけると,ロット不良となる.
考え方としては,IPQCが不良を適時に発見した場合はロット不良としない(製品は廃棄)ということだ.製造部や,設備メンテナンスの部門にとって明らかにロット不良であるが,IPQCがその損失を最小限に抑えたのだから,大目に見るということだろう.
これで全てが見えた.
彼らの活動は,ロット不良を減らす,という品質改善のテーマでは無い.
2時間以内に12台の設備の抜き取り検査を終わるようにする,という作業改善のテーマなのだ.
改善指標は(正しい意味の)ロット不良の低減ではなく,抜き取り検査時間の短縮,なのだ.
ならば話が早い.
現場でIPQC検査員の作業を観察すると,二次元投影測定器の操作に個人差があるのが分かる.これを改善すれば良いのだ.特定のIPQC検査員が出来ていないだけなので,この改善で2時間以内は全員が達成できるだろう.
しかし2時間に一回抜き取り検査というのは,自分たちの都合で決めた決まりだ.もし1時間に1回抜き取り検査をすれば,不良損失は半分になる.
本来不良をなくすのが改善だが,IPQCのメンバーにとっては検査時間を半分にするのが改善のはずだ.
こういう話を現場のリーダにすると即座に「不可能!」と答えが返って来た.
それは今の方法でやっているから,不可能なだけだ.方法を変えれば,可能となる.
その方法を教えたいのは山々だが,ぐっとこらえる(笑)
まず2時間以内をIPQC検査員全員が実現することで,達成感を持ってもらう.
その次の課題として「検査時間半分=損失半減」と言う改善に取り組んでもらうことが出来ればと考えている.
ところでこの事例のように,製造部とIPQCで正反対の目標(つまり,一方はたくさん良品を造る.他方はたくさん不良を見つける)を持っている場合,適切にその指標を決めてやらなければならない.
正しい意味でロット不良を減らすことは製造部にとっては,努力しなければならない目標だが,IPQCが同じ目標を達成しようとすれば,検査をしなければ良いのだ.一方IPQCが不良を見逃せば,製造部は何の努力も無く改善できた様に見える.
今回の事例では,IPQCの指標を「不良適時発見による損失コストの削減」とし,廃棄しなければならなくなった製品が何時間分(少ない方が良い)とするのが良かろう.
こうすれば製造部は品質を改善してロット不良を減らす.
IPQCは作業改善をして,短時間で抜き取り検査を完了することにより,不良を造り続ける時間を減らす.当面は利害が一致するはずだ.
「当面は」と書いたのは,本来は設備を改善して不良を作らなくする,生産中に良品・不良品の判定機能を付加し,不良が発生したら停止する(人偏のある自働化)というのが本質的改善だからだ.
2011年中国的QCC事情
4月15日に,広東省質量協会,広東省科学諮詢服務中心主催のQCC成果発表大会「2011科技創新与QC小組成果発表大会」に招待され参加してきた.
1日半で50ほどのテーマ発表をするという,超過密スケジュールだった.
私は,家電メーカ・美的集団,エアコンメーカ・格力,志高,Welling,洗剤メーカ・立白,通信関連・Skywordなど16のテーマ発表を聞いた.
全て中国企業のサークルだ.
昔,日本のQCCが活発だった頃を思わせる活気があり,発表者は皆活き活きと発表していた.彼らはまったく原稿を見ずに15分の発表をする.よほど練習をしたのであろう.十分熱意が伝わる発表であった.
発表内容は,ほとんどが不良低減など「問題解決型」のテーマであった.
しかも全てが製造部門を中心とした発表であり,間接部門の発表はなかった.
このあたりも,日本でQCCが活発だった頃と状況は似ている.
取り組んだ内容を見ると,設計問題としか思えない不良がいくつもあった.
本来生産前に解消しておくべき問題点が,先送りされ工程内不良として認識され,対策を打っている,という状況にあるようだ.
初歩的な設計ちょんぼが散見され,まだまだ私が貢献できそうな領域が残っていると確信した(笑)
そんな中に1件だけ「課題達成型」といえる発表があった.
問題を解決するのではなく,「生産効率を2倍にする」の様な課題を設定して,それに取り組む活動を「課題達成型」と呼んでいる.
したがって原因分析よりは「あるべき姿」を明確にし,現状とあるべき姿のギャップをいかにして埋めるのか,という活動になる.
問題を解消するのではなく,「現状打破」「新規業務」に対する取り組みには,課題達成型の活動が適している.
特に間接部門の取り組みは,問題解決型のQCストーリィに違和感があり,課題達成型のQCストーリィで取り組むとうまく行く事例が多い.
今回の発表でも,課題達成型で取り組んだほうがうまく行きそうなテーマが他にも2件ほどあった.
問題解決型で取り組んでいるため,あるべき姿を明確にせずに,原因分析をして,「非要因」「要因」と振り分けてしまっている.「非要因」の中にあるチャンスを捨てることになる.
実は以前勤務していた会社では1990年代に,間接部門の取り組みや,更に大きな成果を目指した取り組みを活発にするために,「課題達成型」「顧客指向型」というQCストーリィを追加し,「問題解決型」QCストーリィと合わせ新しいQCストーリィを再構成した.
中国企業のQCCへの取り組みは,我々の1990年代の取り組みに一歩近づいたといえるだろう.発表会の熱気や,活動メンバーたちの熱意を考えると,日本をキャッチアップするのはそう遠い時期ではないと感じた.
50数テーマの発表の中に日系企業の発表は1テーマしか確認できなかった.
うかうかしていられない.日系企業も,中国企業のQCC活動と交流し,刺激を受けた方がよい.
QCC活動の適切な指導をし,成果とともに,人材の育成を図らなければ,日本企業の優位点はあっという間に埋められてしまうという危機感を持った.
「課題達成型」「顧客指向型」の新しいQCC活動詳細については,
こちら書籍をご参照いただきたい.
「続QCサークルのためのQCストーリー入門」
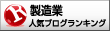
1日半で50ほどのテーマ発表をするという,超過密スケジュールだった.
私は,家電メーカ・美的集団,エアコンメーカ・格力,志高,Welling,洗剤メーカ・立白,通信関連・Skywordなど16のテーマ発表を聞いた.
全て中国企業のサークルだ.
昔,日本のQCCが活発だった頃を思わせる活気があり,発表者は皆活き活きと発表していた.彼らはまったく原稿を見ずに15分の発表をする.よほど練習をしたのであろう.十分熱意が伝わる発表であった.
発表内容は,ほとんどが不良低減など「問題解決型」のテーマであった.
しかも全てが製造部門を中心とした発表であり,間接部門の発表はなかった.
このあたりも,日本でQCCが活発だった頃と状況は似ている.
取り組んだ内容を見ると,設計問題としか思えない不良がいくつもあった.
本来生産前に解消しておくべき問題点が,先送りされ工程内不良として認識され,対策を打っている,という状況にあるようだ.
初歩的な設計ちょんぼが散見され,まだまだ私が貢献できそうな領域が残っていると確信した(笑)
そんな中に1件だけ「課題達成型」といえる発表があった.
問題を解決するのではなく,「生産効率を2倍にする」の様な課題を設定して,それに取り組む活動を「課題達成型」と呼んでいる.
したがって原因分析よりは「あるべき姿」を明確にし,現状とあるべき姿のギャップをいかにして埋めるのか,という活動になる.
問題を解消するのではなく,「現状打破」「新規業務」に対する取り組みには,課題達成型の活動が適している.
特に間接部門の取り組みは,問題解決型のQCストーリィに違和感があり,課題達成型のQCストーリィで取り組むとうまく行く事例が多い.
今回の発表でも,課題達成型で取り組んだほうがうまく行きそうなテーマが他にも2件ほどあった.
問題解決型で取り組んでいるため,あるべき姿を明確にせずに,原因分析をして,「非要因」「要因」と振り分けてしまっている.「非要因」の中にあるチャンスを捨てることになる.
実は以前勤務していた会社では1990年代に,間接部門の取り組みや,更に大きな成果を目指した取り組みを活発にするために,「課題達成型」「顧客指向型」というQCストーリィを追加し,「問題解決型」QCストーリィと合わせ新しいQCストーリィを再構成した.
中国企業のQCCへの取り組みは,我々の1990年代の取り組みに一歩近づいたといえるだろう.発表会の熱気や,活動メンバーたちの熱意を考えると,日本をキャッチアップするのはそう遠い時期ではないと感じた.
50数テーマの発表の中に日系企業の発表は1テーマしか確認できなかった.
うかうかしていられない.日系企業も,中国企業のQCC活動と交流し,刺激を受けた方がよい.
QCC活動の適切な指導をし,成果とともに,人材の育成を図らなければ,日本企業の優位点はあっという間に埋められてしまうという危機感を持った.
「課題達成型」「顧客指向型」の新しいQCC活動詳細については,
こちら書籍をご参照いただきたい.
「続QCサークルのためのQCストーリー入門」
広東省2011年最低賃金調整
先週広東省の最低賃金調整の発表があった.
それによると,2011年3月1日から,最低賃金は以下のように改定となる.
昨年の最低賃金上昇率は,
広州:19.8%アップ
珠海,彿山,東莞,中山:19.5%アップ
汕頭,恵州,江門:20.9%アップ
韶関、河源、梅州など20都市:22.4%アップ
その他四類都市:24.5%アップ
となっており,最低賃金の安い地区ほど上昇率が高かった.
地域格差を少なくしようと言う,意図が感じられた.
しかし2011年の改訂には,そのような意図が感じられない.
いずれにせよ,ここ数年は20%前後の上昇率で最低賃金は上がり続けるだろう.最低賃金は4年で2倍,6年で3倍になる.
労務費が2倍3倍になると考えると,大変なピンチのように思えるが,労働生産性を1年間で20%上げるだけで良いのだ.これでも大変だと言うのならば,毎月労働生産性を2%上げると考えてはどうだろう.たった月2%で年間26.8%の改善となる.
外的要因で経営がうまく行かないと嘆いても始まらない.それは同業者全て同じ条件のはずだ.
ならばそれをチャンスと捉え,改善すれば良いだけだ.たった月2%の改善でも,最低賃金の上昇をカバーしお釣りが来る.
現実には最低賃金が20%上昇しても,労務費は20%上昇しない.
ただ数字の大きさにたじろぐことなく,改善を継続すれば良いだけだ.
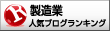
それによると,2011年3月1日から,最低賃金は以下のように改定となる.
| 広州 | 1300元 | 28.2%アップ | |
| 珠海,彿山,東莞,中山 | 1100元 | 19.6%アップ | |
| 汕頭,恵州,江門 | 950元 | 17.3%アップ | |
| 韶関、河源、梅州など20都市 | 850元 | 19.7%アップ |
昨年の最低賃金上昇率は,
広州:19.8%アップ
珠海,彿山,東莞,中山:19.5%アップ
汕頭,恵州,江門:20.9%アップ
韶関、河源、梅州など20都市:22.4%アップ
その他四類都市:24.5%アップ
となっており,最低賃金の安い地区ほど上昇率が高かった.
地域格差を少なくしようと言う,意図が感じられた.
しかし2011年の改訂には,そのような意図が感じられない.
いずれにせよ,ここ数年は20%前後の上昇率で最低賃金は上がり続けるだろう.最低賃金は4年で2倍,6年で3倍になる.
労務費が2倍3倍になると考えると,大変なピンチのように思えるが,労働生産性を1年間で20%上げるだけで良いのだ.これでも大変だと言うのならば,毎月労働生産性を2%上げると考えてはどうだろう.たった月2%で年間26.8%の改善となる.
外的要因で経営がうまく行かないと嘆いても始まらない.それは同業者全て同じ条件のはずだ.
ならばそれをチャンスと捉え,改善すれば良いだけだ.たった月2%の改善でも,最低賃金の上昇をカバーしお釣りが来る.
現実には最低賃金が20%上昇しても,労務費は20%上昇しない.
ただ数字の大きさにたじろぐことなく,改善を継続すれば良いだけだ.
広東省2010年優秀QCサークル成果発表会
4月20日から22日まで,広州市で『広東省2010年科技創新与優秀QC小組成果発表大会』というQCサークル成果発表会が開かれている.
初日にゲストとして参加させていただき,11サークルの発表を聞いてきた.
このQCC発表会は,広東省科学技術協会,広東省質量協会,広東省科学技術諮詢服務中心が主催しており,すでに10年の歴史がある.中国でQCC活動が開始されてからすでに30年経っている.
改革開放により,深センに進出してきた第一期の日系企業が始めたものと思われる.
今回の発表会には180人前後が参加しており,3日間で70サークルほどが発表をするという.
日系ではない企業も多く参加しており,中国華南地区でのQCC活動に対する熱意を感じた.
11サークルの発表は全て「問題解決型」活動の発表であった.
日本のQCC発表会に参加しても遜色がない内容のものも2,3あった.
今後「問題解決型」だけではなく「課題達成型」「顧客指向型」の活動に発展してゆけば更に大きな成果が期待できる.

クリックすると大きくなります.
「課題達成型」「顧客指向型」の応用は,製造部門以外や,非製造業での取り組みにもうまく適用できる.今回発表を聞いた11サークルは全て製造業であったが,すでに非製造業中国企業でもQCC活動に取り組んでいる企業があると聞いている.
こういう発表会により,互いに競争・切磋琢磨の交流をもっと盛んにして行きたいと感じている.
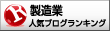
初日にゲストとして参加させていただき,11サークルの発表を聞いてきた.
このQCC発表会は,広東省科学技術協会,広東省質量協会,広東省科学技術諮詢服務中心が主催しており,すでに10年の歴史がある.中国でQCC活動が開始されてからすでに30年経っている.
改革開放により,深センに進出してきた第一期の日系企業が始めたものと思われる.
今回の発表会には180人前後が参加しており,3日間で70サークルほどが発表をするという.
日系ではない企業も多く参加しており,中国華南地区でのQCC活動に対する熱意を感じた.
11サークルの発表は全て「問題解決型」活動の発表であった.
日本のQCC発表会に参加しても遜色がない内容のものも2,3あった.
今後「問題解決型」だけではなく「課題達成型」「顧客指向型」の活動に発展してゆけば更に大きな成果が期待できる.

クリックすると大きくなります.
「課題達成型」「顧客指向型」の応用は,製造部門以外や,非製造業での取り組みにもうまく適用できる.今回発表を聞いた11サークルは全て製造業であったが,すでに非製造業中国企業でもQCC活動に取り組んでいる企業があると聞いている.
こういう発表会により,互いに競争・切磋琢磨の交流をもっと盛んにして行きたいと感じている.
非常識なパフォーマンス
以前広東省珠海にあるアルミダイキャスト工場を訪問したことが有る.
工程を見せていただくと,工程内不良率が2,30%はありそうだった.そのため通常は,原材料としてアルミインゴットを投入するが,この工場は不良品を鋳潰したアルミの塊が原材料として置いてあった.
しかしこの工場の経営者は,工程内不良の高さをほとんど気にしていなかった.彼は原材料の歩留まり率がそこそこ良い値なので満足をしているようだった.
歩留まり率とは,原材料が製品になる率であり,何度不良になっても手直しをして最終的に製品として完成すれば,よしとする考えかただ.
一方電子部品や電子応用製品を生産している工場では,歩留まり率よりは直行率を指標として考えているところが多い.
直行率とは生産投入品が手直し・修理なしで良品として完成する率である.
通常この電子部品・電子応用製品の業界では,前述のアルミダイキャスト工場より一桁,二桁以上低い工程内不良率を達成している.
私が以前指導していたスイッチング電源ユニットを生産していた工場は,工程内不良率100ppm以下を達成していた.つまり99.99%以上の直行率である.
このくらいの直行率を達成すると,かなり安心してしまう.
ところが,自動車関係の部品を生産している人たちに言わせると,不良率を議論することそのものが間違っているということになってしまう.つまり人の生命・安全に影響のある部品であるから,不良はゼロであるのが当然だという考えかただ.
この様に業界によっては,数10%の工程内不良率でも歩留まり率さえ良ければ満足してしまう.別の業界では数%以下の工程内不良率でなければ満足できない.また不良率を語ること自体が忌避される業界も存在する.
同じ業界内だけでパフォーマンスを比較していたら,業界の常識しか分からない.同じ業界内でも,一桁二桁上の実績を持っているところもある.
同業者との競争だけをしていたのでは,非常識なパフォーマンスは得られないであろう.
前述のアルミダイキャスト工場が,歩留まり率を捨てて直行率を管理指標とし,電子部品業界並みの直行率を目指す.
電子部品工場が自動車部品業界並みに不良ゼロを目指す.
この様な業界を超えた,ベンチマーキングとベストプラクティスが,常識を超えたパフォーマンスを手に入れる第一歩だろう.
例えば異業種の工場が,毎月巡回で一日改善をする.
こういうことをすれば,業界・業種を超えたベンチマーキングをすることが出来,それぞれの工夫をベストプラクティスで取り入れることが出来るはずだ.
「生産革新研究会」
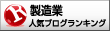
工程を見せていただくと,工程内不良率が2,30%はありそうだった.そのため通常は,原材料としてアルミインゴットを投入するが,この工場は不良品を鋳潰したアルミの塊が原材料として置いてあった.
しかしこの工場の経営者は,工程内不良の高さをほとんど気にしていなかった.彼は原材料の歩留まり率がそこそこ良い値なので満足をしているようだった.
歩留まり率とは,原材料が製品になる率であり,何度不良になっても手直しをして最終的に製品として完成すれば,よしとする考えかただ.
一方電子部品や電子応用製品を生産している工場では,歩留まり率よりは直行率を指標として考えているところが多い.
直行率とは生産投入品が手直し・修理なしで良品として完成する率である.
通常この電子部品・電子応用製品の業界では,前述のアルミダイキャスト工場より一桁,二桁以上低い工程内不良率を達成している.
私が以前指導していたスイッチング電源ユニットを生産していた工場は,工程内不良率100ppm以下を達成していた.つまり99.99%以上の直行率である.
このくらいの直行率を達成すると,かなり安心してしまう.
ところが,自動車関係の部品を生産している人たちに言わせると,不良率を議論することそのものが間違っているということになってしまう.つまり人の生命・安全に影響のある部品であるから,不良はゼロであるのが当然だという考えかただ.
この様に業界によっては,数10%の工程内不良率でも歩留まり率さえ良ければ満足してしまう.別の業界では数%以下の工程内不良率でなければ満足できない.また不良率を語ること自体が忌避される業界も存在する.
同じ業界内だけでパフォーマンスを比較していたら,業界の常識しか分からない.同じ業界内でも,一桁二桁上の実績を持っているところもある.
同業者との競争だけをしていたのでは,非常識なパフォーマンスは得られないであろう.
前述のアルミダイキャスト工場が,歩留まり率を捨てて直行率を管理指標とし,電子部品業界並みの直行率を目指す.
電子部品工場が自動車部品業界並みに不良ゼロを目指す.
この様な業界を超えた,ベンチマーキングとベストプラクティスが,常識を超えたパフォーマンスを手に入れる第一歩だろう.
例えば異業種の工場が,毎月巡回で一日改善をする.
こういうことをすれば,業界・業種を超えたベンチマーキングをすることが出来,それぞれの工夫をベストプラクティスで取り入れることが出来るはずだ.
「生産革新研究会」