生産ラインが困る仕組み
生産性の改善を上からの指導でドンとやると何とか改善できるが,現場の創意工夫で日々改善がなかなか出来ない.日本の工場では作業現場による改善が普通に行われていても中国の工場では夢のような話ではないだろうか?
ちょっとした工夫で日々改善の習慣付けができる.
今回はそんなお話をする.これをお読みになっているあなたの工場で応用していただければ,大変光栄だ.
結論から言うとタイトルに示したように「生産ラインが困る仕組み」を作ればよいのだ.これだけでは何の意味か解らないので例で説明しよう.
不良が発生するとラインが止まるようにしておく
問題点がリアルタイムに見えるようにしておく
この二つの事例で「生産ラインが困る仕掛け」をご理解いただけただろうか?
このように問題点の発生が即改善を要求する仕掛けを作っておき,班長さんたちの現場力を鍛え,日々改善の習慣をつける.
これも一種のOJT(現場教育)だと思う.
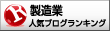
ちょっとした工夫で日々改善の習慣付けができる.
今回はそんなお話をする.これをお読みになっているあなたの工場で応用していただければ,大変光栄だ.
結論から言うとタイトルに示したように「生産ラインが困る仕組み」を作ればよいのだ.これだけでは何の意味か解らないので例で説明しよう.
現場の班長さんが,一番怖れているのはラインストップだ.生産計画が時間内に達成できなければ,生産管理,営業からいっせいにクレームが来る.したがって生産量の確保が任務だと思っている班長さんは結構いる.
こういう人たちにはラインストップは大きなプレッシャーになる.
不良が発生したらすばやく解決する.そして次に同じ不良が発生しないように工夫させる.これを習慣付けておけば,一気に生産性改善はできないにしても,日々少しずつ改善ができる.
小さな改善でも複利で効いてくるので,継続すれば大きな改善効果になる.
中国で先端的な組み立てラインを実現されている船井電機さんもこの手法を取られている.作業中に何か問題点があれば,作業者がライン停止のボタンを押す様になっている.ライン停止が発生するとすぐさま班長さんが問題解決をしラインを再稼動する.
ラインが止まっている間に工程内の大きな時計が停止時間を累積カウントしていく様になっている.一日の停止目標時間が決まっているので,班長さんのすばやい行動と再発防止の工夫が必要になってくる.
こういう人たちにはラインストップは大きなプレッシャーになる.
不良が発生したらすばやく解決する.そして次に同じ不良が発生しないように工夫させる.これを習慣付けておけば,一気に生産性改善はできないにしても,日々少しずつ改善ができる.
小さな改善でも複利で効いてくるので,継続すれば大きな改善効果になる.
中国で先端的な組み立てラインを実現されている船井電機さんもこの手法を取られている.作業中に何か問題点があれば,作業者がライン停止のボタンを押す様になっている.ライン停止が発生するとすぐさま班長さんが問題解決をしラインを再稼動する.
ラインが止まっている間に工程内の大きな時計が停止時間を累積カウントしていく様になっている.一日の停止目標時間が決まっているので,班長さんのすばやい行動と再発防止の工夫が必要になってくる.
不良の発生でラインを停止するのも問題点の可視化になるが,その手前で問題点を見えるようにする.
生産管理板などにより,2時間おきに生産出来高を記入して管理している工場が多い.これでも生産性を阻害する問題が発生していることを可視化できるが,リアルタイムには見えていない.過去2時間の間に何らかの問題が発生した,
という事がわかるだけである.結果だけを見ていてはなかなか改善ができない.
これをリアルタイムに見えるようにしておく.今現在完成していなければならない数量と,実際に完成している数量がリアルタイムに見えていれば,すぐに手が打てる.
さすがにホワイトボードに記入する方式ではこういうことはできない.リアルタイムに計画生産高を計算表示し,現在出来高との差異がマイナスになっていれば赤行灯が点灯する電子生産管理板が既製品で簡単に手に入る.
こういうツールを応用して,班長さんに赤行灯が点灯したらすぐに生産性を阻害している原因を除去するように指導をしておく.
もちろんボトルネックが発生している工程を手助けするのではなく,ボトルネックが発生する原因を解決するように動機付けておく必要がある.
生産管理板などにより,2時間おきに生産出来高を記入して管理している工場が多い.これでも生産性を阻害する問題が発生していることを可視化できるが,リアルタイムには見えていない.過去2時間の間に何らかの問題が発生した,
という事がわかるだけである.結果だけを見ていてはなかなか改善ができない.
これをリアルタイムに見えるようにしておく.今現在完成していなければならない数量と,実際に完成している数量がリアルタイムに見えていれば,すぐに手が打てる.
さすがにホワイトボードに記入する方式ではこういうことはできない.リアルタイムに計画生産高を計算表示し,現在出来高との差異がマイナスになっていれば赤行灯が点灯する電子生産管理板が既製品で簡単に手に入る.
こういうツールを応用して,班長さんに赤行灯が点灯したらすぐに生産性を阻害している原因を除去するように指導をしておく.
もちろんボトルネックが発生している工程を手助けするのではなく,ボトルネックが発生する原因を解決するように動機付けておく必要がある.
この二つの事例で「生産ラインが困る仕掛け」をご理解いただけただろうか?
このように問題点の発生が即改善を要求する仕掛けを作っておき,班長さんたちの現場力を鍛え,日々改善の習慣をつける.
これも一種のOJT(現場教育)だと思う.
改善のフットワーク
以前改善のお手伝いをしている工場で,作業の無駄をなくすためにレイアウトを変えようということになった.
考え方と方向性を示して,次回訪問時までに自分たちで考えてレイアウトを変更しておくように指示をした.
一ヶ月後の訪問で,どのような変化があるか楽しみにしていた.
しかし何も変化はない.一ヶ月もかかって何もやってないとは何事かと叱ると,コンピュータで作画したレイアウト変更計画図面を見せてくれた.
絵だけを描いて一ヶ月待っていたのだ.
そうではないすぐにやろうといって,その場で作業台の並べ替えを始めようとした.ところが又まずレイアウト図面を作ろうという.
絵だけを描いても何も改善できない.まずやってみて問題があれば,又改善する.これを繰り返しているうちに,「現場の改善力」がついてくる.
頭で考えない.手で考える.体で考える.
現場の人たちが体を動かして考えることが肝要である.私が一方的に指示をしてレイアウトを変更して見せても『現場の改善力』は向上しない.
小さなことでもすぐやってみる.そして又次の問題が見つかればそれを改善する.これをフットワークよくやる.山登りと同じである.小さな峰に到達すると次の峰が見えるものだ.
あなたの工場の改善のフットワークはいかがだろうか.軽~いフットワークで改善のサイクルを軽快にまわしたい.
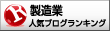
考え方と方向性を示して,次回訪問時までに自分たちで考えてレイアウトを変更しておくように指示をした.
一ヶ月後の訪問で,どのような変化があるか楽しみにしていた.
しかし何も変化はない.一ヶ月もかかって何もやってないとは何事かと叱ると,コンピュータで作画したレイアウト変更計画図面を見せてくれた.
絵だけを描いて一ヶ月待っていたのだ.
そうではないすぐにやろうといって,その場で作業台の並べ替えを始めようとした.ところが又まずレイアウト図面を作ろうという.
絵だけを描いても何も改善できない.まずやってみて問題があれば,又改善する.これを繰り返しているうちに,「現場の改善力」がついてくる.
頭で考えない.手で考える.体で考える.
現場の人たちが体を動かして考えることが肝要である.私が一方的に指示をしてレイアウトを変更して見せても『現場の改善力』は向上しない.
小さなことでもすぐやってみる.そして又次の問題が見つかればそれを改善する.これをフットワークよくやる.山登りと同じである.小さな峰に到達すると次の峰が見えるものだ.
あなたの工場の改善のフットワークはいかがだろうか.軽~いフットワークで改善のサイクルを軽快にまわしたい.
マルチカラーの時代
 山根一眞さんの「メタルカラーの時代」をもじって「マルチカラーの時代」というテーマを考えてみた.
山根一眞さんの「メタルカラーの時代」をもじって「マルチカラーの時代」というテーマを考えてみた.中国にも「ホワイトカラー」「ブルーカラー」という言葉はある.
それぞれ《白領族》《藍領族》という.
中国の工場では作業者《藍領族》と文員・技術者《白領族》がしっかりと分かれているところが多い.
作業者から文員への登用の道を用意している会社もあるが,文員になると作業現場には入らなくなってしまう.
又大卒の人間に作業現場研修をさせようとすると辞めてしまう.工場勤務なので作業服を支給すると着るのを嫌がる.ということもあるようだ.《白領族》としての間違った誇りがそうさせるのだろう.
管理者と作業者,頭脳労働者と肉体労働者の間には,我々日本人が考えているより根深い階級意識があるようだ.
中国では毎年最低賃金が上昇しいる.2009年は最低賃金の調整が見送られたが,2010年はかなりの額が上がると予想される.
そのため,特に沿岸地区では安価な労務費を期待したローコスト生産は難しくなってきている.実際には,工場作業員を募集しても集まらない状況となっている.
これからは作業者一人一人の能力を高め,高品質・高付加価値の生産活動に移行してゆかなければ中国では生き残れないだろう.
この様な考える力を持った従業員に「マルチカラー」という名前をつけてみた.
中国語に訳すならば《彩領族》とでも言えばよいだろうか.
単純に多能工を意味する言葉ではない.
《白領族》が《藍領族》を管理するという構図ではなく,作業者も作業改善を考える.技術者も作業者と一緒になって作業する中で作業改善,工程改善を考える.この様な人たちを《彩領族》と呼びたい.
日本の製造業が力を持っていたのは,工場労働者が「マルチカラー」だったからだと考えている.
 「痛くない注射針」を作れる町工場,砲丸投げの玉を世界中に輸出している町工場,こういう今でも力のある中小企業は経営者,従業員が全て「マルチカラー」なのだと思う.
「痛くない注射針」を作れる町工場,砲丸投げの玉を世界中に輸出している町工場,こういう今でも力のある中小企業は経営者,従業員が全て「マルチカラー」なのだと思う.中国の工場でも《彩領族》を次々と育て上げる仕組みと仕掛けを作り上げることが,競争優位に立つことになると考えている.
者に語らせるな,モノに語らせよ
中国で仕事をしていると,部下の報告を鵜呑みにして痛い目に合うことがしばしばある.
例えば生産日報を見ると毎日1000台とか1200台のようにキリのいい数字が並んでいる.これはおかしい.その日によって不良の数も違っているはずだし,まだ仕掛で完成していないものもあるはずだ.
現場に行って確認してみると,投入台数が生産台数として報告されていることがわかったりする.
生産管理が,部品が欠品しており別の部品を代替に使用して生産を開始しても良いかと相談してくる.そんなはずはない,昨日入荷したコンテナに入っていたはずである.
倉庫に行ってみると,違う場所に該当の部品が置いてあったりする.
何事も担当者の思い違い,理解不足,思惑という色眼鏡を通して報告が上がってくるものだ.
これを部下の出来が悪いと嘆いてはいけない.上司の指導が足りないのである.
上記の例では,担当者が生産現場の班長に聞いた数字を報告しているだけ.
きちんと完成品在庫の数字を確認すれば間違いはなかったはずである.
生産管理の人間は,倉庫の担当者から部品の欠品を報告されるとそのまま上司に報告する.きちんと受け入れ記録を調べればIQC(受け入れ検査課)の検査完了データが見つかるはずである.
人に聞いた話をそのまま報告するのではなく,現場・現物を確認して報告をする.
これが本日のテーマ「者に語らせるな,モノに語らせろ」の意味である.
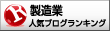
例えば生産日報を見ると毎日1000台とか1200台のようにキリのいい数字が並んでいる.これはおかしい.その日によって不良の数も違っているはずだし,まだ仕掛で完成していないものもあるはずだ.
現場に行って確認してみると,投入台数が生産台数として報告されていることがわかったりする.
生産管理が,部品が欠品しており別の部品を代替に使用して生産を開始しても良いかと相談してくる.そんなはずはない,昨日入荷したコンテナに入っていたはずである.
倉庫に行ってみると,違う場所に該当の部品が置いてあったりする.
何事も担当者の思い違い,理解不足,思惑という色眼鏡を通して報告が上がってくるものだ.
これを部下の出来が悪いと嘆いてはいけない.上司の指導が足りないのである.
上記の例では,担当者が生産現場の班長に聞いた数字を報告しているだけ.
きちんと完成品在庫の数字を確認すれば間違いはなかったはずである.
生産管理の人間は,倉庫の担当者から部品の欠品を報告されるとそのまま上司に報告する.きちんと受け入れ記録を調べればIQC(受け入れ検査課)の検査完了データが見つかるはずである.
人に聞いた話をそのまま報告するのではなく,現場・現物を確認して報告をする.
これが本日のテーマ「者に語らせるな,モノに語らせろ」の意味である.
答えは現場にある
以前指導していた台湾資本の中国工場でこんなことが有った.
ここの工場ではQE(品質エンジニア)がお客様からの不良返却品に対し,再発防止などの対策書を作成することになっていた.
しかし彼らは現場はおろか返却された不具合品もあまり見ることがない.
返却不具合品は専門の解析チームがあり,彼らが原因解析をする.その原因解析のメモを見ながら,対策はQEが机の上で作文をする.報告書に必要な写真があれば,解析チームに依頼する.
報告書の作成に手間取っていると,不具合品はすでに廃棄されていたり,修理されていることすらある.
これでは永久に不具合は減らないだろう.
しかもまともなレポートをお客様に提出することも出来ない.
再発防止対策はいつも「作業者に注意を喚起した」「作業者に作業教育を再実施した」という内容だ.これでは再発防止になっていないし,何も改善できない.
私は彼らに「問題は現場で発生している.答えも現場にある」としょっちゅう発破をかけ,机に座っているQEを現場に追い出していた.
毎朝,前日発生した工程内不良の会議にもQEを参加させて,現場で不具合発生や対策の効果を確認させた.
彼らをオフィスから追い出し,現場に有る解析チームの横に机を持っていった.
こうすることにより,彼ら自身の改善がスタートしたといって良いだろう.
現物・現場から離れたところの発想では何も生まれない.まさに「問題は現場で発生している.答えも現場にある」
改善・問題解決のための答えはいつも現場に有る.
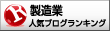
ここの工場ではQE(品質エンジニア)がお客様からの不良返却品に対し,再発防止などの対策書を作成することになっていた.
しかし彼らは現場はおろか返却された不具合品もあまり見ることがない.
返却不具合品は専門の解析チームがあり,彼らが原因解析をする.その原因解析のメモを見ながら,対策はQEが机の上で作文をする.報告書に必要な写真があれば,解析チームに依頼する.
報告書の作成に手間取っていると,不具合品はすでに廃棄されていたり,修理されていることすらある.
これでは永久に不具合は減らないだろう.
しかもまともなレポートをお客様に提出することも出来ない.
再発防止対策はいつも「作業者に注意を喚起した」「作業者に作業教育を再実施した」という内容だ.これでは再発防止になっていないし,何も改善できない.
私は彼らに「問題は現場で発生している.答えも現場にある」としょっちゅう発破をかけ,机に座っているQEを現場に追い出していた.
毎朝,前日発生した工程内不良の会議にもQEを参加させて,現場で不具合発生や対策の効果を確認させた.
彼らをオフィスから追い出し,現場に有る解析チームの横に机を持っていった.
こうすることにより,彼ら自身の改善がスタートしたといって良いだろう.
現物・現場から離れたところの発想では何も生まれない.まさに「問題は現場で発生している.答えも現場にある」
改善・問題解決のための答えはいつも現場に有る.