改善OJT
改善リーダを育てるためにはOJTが欠かせないと考えている.
OJTというのは(On Job Training)の略称で,現場教育とか実践教育という意味である.
それに対応する言葉としてOff-JT(Off Job Training)が有る.いわゆる座学であり,セミナーや研修などの,現場を離れて知識を習得するための教育だ.
知識(形式智)だけを,頭に詰め込んでも能力(暗黙智)にはならない.いわゆる頭でっかちとなり,行動が取れない状態となる.得た知識(形式智)を能力(暗黙智)に変換して,初めて行動が起こせる.形式智を暗黙智に変換するためには「経験」が必要だ.その経験を養うのがOJT(実践教育)である.
しかしOJT(実践教育)だけしていれば良いという訳ではない.Off-JTで,きちんと理論的な裏付けを教え込んでおかなければ,応用が利かなくなる.
またOJTをきちんと理解しておかないと,効果は出ない.
現場に放り込んでおけば自動的に人材が育つわけではない.これではOJTとは言えない.OJTは育成計画に沿って,計画的に行わなければならない.
現場で発生する機会を捉えてOJTをしても,偶然に左右され「計画的なOJT」など不可能だとお考えではないだろうか?
「計画的にOJT」をするためには,QCCなどのチーム改善活動を応用するのが良いと考えている.
実際の改善活動の中で,問題発見能力,問題解決能力,プレゼンテーション能力を磨くのである.
問題発見能力,問題解決能力,プレゼンテーション能力の原理・原則,方法論を教え,それを実践の中で「稽古」をこなす.言ってみれば「改善道場」である.
日本ではQCC活動が下火になってしまったが,中国の意欲的な若者の改善力を磨くのに,もう一度QCCに注目したいと考えている.
 もう随分昔の書籍であるが,右の「国際競争力の再生」の著者吉田耕作氏は,米国でQCCを応用して,企業や政府機関の改善をしてきた人だ.
もう随分昔の書籍であるが,右の「国際競争力の再生」の著者吉田耕作氏は,米国でQCCを応用して,企業や政府機関の改善をしてきた人だ.
中国でも同じことが出来るはずだ.むしろ高い成長意欲を持つ中国の若者達には,更に効果は大きいだろう.
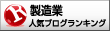
OJTというのは(On Job Training)の略称で,現場教育とか実践教育という意味である.
それに対応する言葉としてOff-JT(Off Job Training)が有る.いわゆる座学であり,セミナーや研修などの,現場を離れて知識を習得するための教育だ.
知識(形式智)だけを,頭に詰め込んでも能力(暗黙智)にはならない.いわゆる頭でっかちとなり,行動が取れない状態となる.得た知識(形式智)を能力(暗黙智)に変換して,初めて行動が起こせる.形式智を暗黙智に変換するためには「経験」が必要だ.その経験を養うのがOJT(実践教育)である.
しかしOJT(実践教育)だけしていれば良いという訳ではない.Off-JTで,きちんと理論的な裏付けを教え込んでおかなければ,応用が利かなくなる.
またOJTをきちんと理解しておかないと,効果は出ない.
現場に放り込んでおけば自動的に人材が育つわけではない.これではOJTとは言えない.OJTは育成計画に沿って,計画的に行わなければならない.
現場で発生する機会を捉えてOJTをしても,偶然に左右され「計画的なOJT」など不可能だとお考えではないだろうか?
「計画的にOJT」をするためには,QCCなどのチーム改善活動を応用するのが良いと考えている.
実際の改善活動の中で,問題発見能力,問題解決能力,プレゼンテーション能力を磨くのである.
問題発見能力,問題解決能力,プレゼンテーション能力の原理・原則,方法論を教え,それを実践の中で「稽古」をこなす.言ってみれば「改善道場」である.
日本ではQCC活動が下火になってしまったが,中国の意欲的な若者の改善力を磨くのに,もう一度QCCに注目したいと考えている.
 もう随分昔の書籍であるが,右の「国際競争力の再生」の著者吉田耕作氏は,米国でQCCを応用して,企業や政府機関の改善をしてきた人だ.
もう随分昔の書籍であるが,右の「国際競争力の再生」の著者吉田耕作氏は,米国でQCCを応用して,企業や政府機関の改善をしてきた人だ.中国でも同じことが出来るはずだ.むしろ高い成長意欲を持つ中国の若者達には,更に効果は大きいだろう.
変革リーダを探せ
中国の工場で生産の方法を変えたり,組織を変えたりするのがなかなかうまく行かないことがある.リーダ層や作業員の抵抗にあう.
日本の工場でも同様だが,多くの人は「今までのやり方」を変えることに抵抗がある.これは人類共通の特性ではなかろうか.いやひょっとすると生物共通の特性かもしれない.
ぬるま湯に浸かった蛙は徐々に水温が上がっているのに気がつかずついには,熱湯で死んでしまう.
早く温度の変化に気がついて,危機感を持つリーダがいないことには組織もぬるま湯に浸かったまま,熱湯で死んでしまうだろう.
経営者が危機感を持っていても現場がなかなか変革についてこない.抵抗勢力になってしまう.しばしばこういう局面に出会う.
現場で変革を推進なければならないリーダが抵抗勢力側に入ってしまう.
無理もない.現場のリーダは「現在のオペレーション」をきちんと推進できる能力を評価されリーダの役割を担っているはずだ.
往々にして現状に満足しない人たちは,職場での評価が低く,埋もれていることがある.しかしこういう現状に満足しない人が「変革リーダ」としての役割を果たすことがある.
工場の中で改善活動をしていると,「現状リーダ」と「変革リーダ」の違いがよく見えてくる.
「現状リーダ」をすぐに「変革リーダ」に変えることはかなり難しい.
「現状リーダ」に変革マインドを埋め込む.変革マインドを持った人にリーダマインドを埋め込む.
いずれにせよ「変革リーダ」を見つけ養成するのは現場の活動を通してでなくては達成できないと考えている.
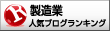
日本の工場でも同様だが,多くの人は「今までのやり方」を変えることに抵抗がある.これは人類共通の特性ではなかろうか.いやひょっとすると生物共通の特性かもしれない.
ぬるま湯に浸かった蛙は徐々に水温が上がっているのに気がつかずついには,熱湯で死んでしまう.
早く温度の変化に気がついて,危機感を持つリーダがいないことには組織もぬるま湯に浸かったまま,熱湯で死んでしまうだろう.
経営者が危機感を持っていても現場がなかなか変革についてこない.抵抗勢力になってしまう.しばしばこういう局面に出会う.
現場で変革を推進なければならないリーダが抵抗勢力側に入ってしまう.
無理もない.現場のリーダは「現在のオペレーション」をきちんと推進できる能力を評価されリーダの役割を担っているはずだ.
往々にして現状に満足しない人たちは,職場での評価が低く,埋もれていることがある.しかしこういう現状に満足しない人が「変革リーダ」としての役割を果たすことがある.
工場の中で改善活動をしていると,「現状リーダ」と「変革リーダ」の違いがよく見えてくる.
「現状リーダ」をすぐに「変革リーダ」に変えることはかなり難しい.
「現状リーダ」に変革マインドを埋め込む.変革マインドを持った人にリーダマインドを埋め込む.
いずれにせよ「変革リーダ」を見つけ養成するのは現場の活動を通してでなくては達成できないと考えている.
設計不良
あるメーカの中国工場を指導していて驚いた事がある.
半完成品の最初の通電検査で不良が大量に発生しているのである.数%というオーダーではなく数十%も不良になっている.
訳を聞いて更に驚いた.
回路に使用しているICのばらつきによって,このようなことはしばしば起きる.
その場合検査外れ品は回路中の抵抗を交換してやれば検査は合格し良品となる.
従って工程内に山ほどラインアウトされた半完成品は,後ほど作業者が抵抗を交換してラインに再投入するのである.
私に言わせれば,これは設計不良である.
このような製品はすぐにラインを止めて,設計を変更すべきである.
しかしこの製品は量産開始以来ずっと工場の努力で生産し続けてきたのである.
今更差し戻されても,というのが本社設計部門のいいわけである.
ここは100歩譲って,先にICの特性を測っておきランク別にしておく.出庫するICのランクにあわせて抵抗を変更して生産する.このように部品表と製造基準を変えてもらった.
これで不良は1%未満となり通常の生産が可能となった.
更にこの工場には,試作審査と量産移行審査の制度を導入させた.
試作時の生産性の問題を整理し,これがきちんと解決していなければ量産には移らない.これをこの2回の審査できちんと確認をしてゆくわけである.
審査を通らなければ,本社の設計部門に差し戻しである.
この制度を導入して一番喜んだのが,工場サイドのエンジニアだった.彼らは毎回本社設計部門の言われるがままに生産するしかなかった.それが自分たちで審査をしてだめなら「設計を受け取らない」「作らない」という選択があることを知り,モチベーションがすごく上がった.
もちろん「作らない」という負の対応ばかりではなく,今まで押し付けられていた生産を,自分たちで改善するという意欲が出てきた.
このように製造現場が変わると,本社設計部門も必然的に変わらなければならなくなる.現場の改革が,連鎖して全社を改革してゆくのである.
こちらの記事もどうぞ
源流改善
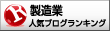
半完成品の最初の通電検査で不良が大量に発生しているのである.数%というオーダーではなく数十%も不良になっている.
訳を聞いて更に驚いた.
回路に使用しているICのばらつきによって,このようなことはしばしば起きる.
その場合検査外れ品は回路中の抵抗を交換してやれば検査は合格し良品となる.
従って工程内に山ほどラインアウトされた半完成品は,後ほど作業者が抵抗を交換してラインに再投入するのである.
私に言わせれば,これは設計不良である.
このような製品はすぐにラインを止めて,設計を変更すべきである.
しかしこの製品は量産開始以来ずっと工場の努力で生産し続けてきたのである.
今更差し戻されても,というのが本社設計部門のいいわけである.
ここは100歩譲って,先にICの特性を測っておきランク別にしておく.出庫するICのランクにあわせて抵抗を変更して生産する.このように部品表と製造基準を変えてもらった.
これで不良は1%未満となり通常の生産が可能となった.
更にこの工場には,試作審査と量産移行審査の制度を導入させた.
試作時の生産性の問題を整理し,これがきちんと解決していなければ量産には移らない.これをこの2回の審査できちんと確認をしてゆくわけである.
審査を通らなければ,本社の設計部門に差し戻しである.
この制度を導入して一番喜んだのが,工場サイドのエンジニアだった.彼らは毎回本社設計部門の言われるがままに生産するしかなかった.それが自分たちで審査をしてだめなら「設計を受け取らない」「作らない」という選択があることを知り,モチベーションがすごく上がった.
もちろん「作らない」という負の対応ばかりではなく,今まで押し付けられていた生産を,自分たちで改善するという意欲が出てきた.
このように製造現場が変わると,本社設計部門も必然的に変わらなければならなくなる.現場の改革が,連鎖して全社を改革してゆくのである.
こちらの記事もどうぞ
源流改善
現場の工夫を引き出す
モノ造りにおいて,与えられた道具をそのまま使わない,何らかの工夫を入れて道具を使うという姿勢が重要だ.匠と呼ばれる職人さんたちの道具には全て工夫がある.工夫を道具に与えて初めて道具を使いこなしているといえるのではないだろうか.
中華系工場の生産現場を見ていて感じるのは,設備・道具をきちんと使いこなせているところが少ない.与えられた設備・道具の本来の機能を維持することすら難しい.
いい加減な日常点検やメンテナンスでは高価な日本製の設備を導入してもすぐに使えなくなってしまう.
日系の工場に行くと,旧式の設備をきちんとメンテナンスをして使いこなしているところが多い.中には設備の年式の古さを自慢げに大きく表示している工場もあった.
同じ中国人が作業をしていても,きちんとした指導で設備の可動率は全然変わってしまう.
この日常点検・メンテナンスで設備・道具の機能をきちんと維持するのは基本だ.更に設備・道具に現場の工夫を入れてゆかねばならない.
中国人のメンタリティでは,設備を保守する人,設備を工夫・改善する人,設備を使って作業する人は全然別の人種であり,相互に干渉しないことが「善」と考えているフシがある.
これを打開するために,こんな工夫をしている.
難しいことはあまり期待できないが,治具を使って生産する方法を思いついたり,治具の改善を思いついたりしたらすぐ褒めることにしている.
そしてそれをすぐに実行に移す.その治具には「○○式治具」など考えた人間の名前をつける.「○○式治具」のすばらしさを他のラインなど全社に吹聴する.
こんなちょっと幼稚とも思える方法で現場の人間が自分も工夫してみようという気になる.
こういう仕事上の工夫は製造現場だけではない.
以前日本で仕事をしていた時も同じ事をやっていた.
品証部の部下が面白い評価方法を考え付くと,「○○メソッド」とか「○○式マトリックス評価法」などと考えた人間の名前入りで名称をつけてやる.
この名称をことあるごとに使うわけだ.
これで考えた本人もその気になるし,他の人間も工夫をしだす.
私はこんな一見幼稚な方法でもある程度成果が出せた.
皆さんは現場の工夫を引き出すためにどんな工夫をしておられるだろうか?
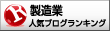
中華系工場の生産現場を見ていて感じるのは,設備・道具をきちんと使いこなせているところが少ない.与えられた設備・道具の本来の機能を維持することすら難しい.
いい加減な日常点検やメンテナンスでは高価な日本製の設備を導入してもすぐに使えなくなってしまう.
日系の工場に行くと,旧式の設備をきちんとメンテナンスをして使いこなしているところが多い.中には設備の年式の古さを自慢げに大きく表示している工場もあった.
同じ中国人が作業をしていても,きちんとした指導で設備の可動率は全然変わってしまう.
この日常点検・メンテナンスで設備・道具の機能をきちんと維持するのは基本だ.更に設備・道具に現場の工夫を入れてゆかねばならない.
中国人のメンタリティでは,設備を保守する人,設備を工夫・改善する人,設備を使って作業する人は全然別の人種であり,相互に干渉しないことが「善」と考えているフシがある.
これを打開するために,こんな工夫をしている.
難しいことはあまり期待できないが,治具を使って生産する方法を思いついたり,治具の改善を思いついたりしたらすぐ褒めることにしている.
そしてそれをすぐに実行に移す.その治具には「○○式治具」など考えた人間の名前をつける.「○○式治具」のすばらしさを他のラインなど全社に吹聴する.
こんなちょっと幼稚とも思える方法で現場の人間が自分も工夫してみようという気になる.
こういう仕事上の工夫は製造現場だけではない.
以前日本で仕事をしていた時も同じ事をやっていた.
品証部の部下が面白い評価方法を考え付くと,「○○メソッド」とか「○○式マトリックス評価法」などと考えた人間の名前入りで名称をつけてやる.
この名称をことあるごとに使うわけだ.
これで考えた本人もその気になるし,他の人間も工夫をしだす.
私はこんな一見幼稚な方法でもある程度成果が出せた.
皆さんは現場の工夫を引き出すためにどんな工夫をしておられるだろうか?
ダラリ
ダラリというのは「ムダ」「ムラ」「ムリ」のおしまいの3文字を取って「ダラリ」だ.
作業のムダ・ムラ・ムリをなくして作業をやりやすくすれば,改善できる,という意味で使う.
この話を中国人にする時はちょっと苦労する.
通訳に「ムラ」を『斑点』と訳されたことがある.これは「色むら」の「ムラ」だ.
これでは全然話が通じない.
そこで自分なりに中国語を考え,こんな言い方をしている.
ムダ:『無益』
ムラ:『無均』
ムリ:『無理』
この三つを『三無』ということにしている.
ムラを『無均』というのはちょっと無理があるが,『斑点』と訳されるよりはましだと思っている.
仕事の出来高に「ムラ」がある.
品質に「ムラ」がある.
の「ムラ」に良い中国語訳ができないものかと悩んでいる.
もちろん「ダラリ」のように語呂がよくなければならない.
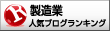
作業のムダ・ムラ・ムリをなくして作業をやりやすくすれば,改善できる,という意味で使う.
この話を中国人にする時はちょっと苦労する.
通訳に「ムラ」を『斑点』と訳されたことがある.これは「色むら」の「ムラ」だ.
これでは全然話が通じない.
そこで自分なりに中国語を考え,こんな言い方をしている.
ムダ:『無益』
ムラ:『無均』
ムリ:『無理』
この三つを『三無』ということにしている.
ムラを『無均』というのはちょっと無理があるが,『斑点』と訳されるよりはましだと思っている.
仕事の出来高に「ムラ」がある.
品質に「ムラ」がある.
の「ムラ」に良い中国語訳ができないものかと悩んでいる.
もちろん「ダラリ」のように語呂がよくなければならない.
