稼働率と可動率
稼動率と可動率の違いについて説明したい.
稼動率は,生産量(販売量)の増減によって変動する.残業・休日出勤など操業時間を越えて生産をすれば,稼動率は100%を越える.
したがって稼働率をコントロールしているのは,工場ではなく,マーケットの需要・受注量である.稼働率を無理に上げようとすると,売れるあてのない製品を生産することになる.
可動率は,生産設備のスイッチがONになっている時間のうちどれだけ正味生産をしたかという指標である.暖機運転,メンテナンス・点検,段取り換え,チョコ停,故障などにかかる時間が正味生産に寄与していない時間となる.したがって100%を超えることはない.
可動率は工場の責任である.工場は可動率を上げるために日々改善をしなければならない.
こちらの記事もご参考に
最適ロットサイズ
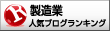
稼動率:
生産のために工場・設備が稼動した時間と操業時間の比率を百分率であらわしたものである.
可動率:
設備が生産のために稼動した正味時間と設備を動かした時間の比率を百分率であらわしたものである.
稼動率は,生産量(販売量)の増減によって変動する.残業・休日出勤など操業時間を越えて生産をすれば,稼動率は100%を越える.
したがって稼働率をコントロールしているのは,工場ではなく,マーケットの需要・受注量である.稼働率を無理に上げようとすると,売れるあてのない製品を生産することになる.
可動率は,生産設備のスイッチがONになっている時間のうちどれだけ正味生産をしたかという指標である.暖機運転,メンテナンス・点検,段取り換え,チョコ停,故障などにかかる時間が正味生産に寄与していない時間となる.したがって100%を超えることはない.
可動率は工場の責任である.工場は可動率を上げるために日々改善をしなければならない.
こちらの記事もご参考に
最適ロットサイズ
最適ロットサイズ
生産ロットのサイズをどうするかという問題について考察してみたい.
下の図は,よくオペレーションリサーチ理論(OR理論)の教科書に出ている図だ.「サドル点」が最適ポイントだという説明である.
在庫にかかる費用と段取り換えにかかる費用の総和が一番低い点が,理想的な点である.
こういう議論の信憑性について疑問を持っている.
まず在庫にかかる費用が,製品単価の10~20%であるという仮定が疑わしい.
完成品倉庫にある製品が売れ残ってしまう場合もありうる.この場合の損失は,固定係数(20~30%)であるはずがない.現実はこんなに単純ではない.在庫費用はマーケットの需要動向と,売れ残り(在庫量)の関数になるはずだ.
仮に全て売れると仮定しても,在庫費用は在庫期間の関数であるはずだ.
また在庫になる製品を作っている間の機会損失も考えなければならない.
こういう理論の前提は,工場の稼動率,生産設備の稼働率を少しでも上げたいという要求から発生している.
しかし工場の稼働率や生産設備の稼働率を決定するのは,工場ではない.マーケットだ.
工場が決められるのは,可動率(「べきどうりつ」と読み「稼働率」と区別する)
工場ができることは,可動率を上げることだ.
段取り換えにかかる時間と費用を極限まで下げ,注文の数量だけ生産できるようにすることである.
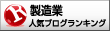
下の図は,よくオペレーションリサーチ理論(OR理論)の教科書に出ている図だ.「サドル点」が最適ポイントだという説明である.
在庫にかかる費用と段取り換えにかかる費用の総和が一番低い点が,理想的な点である.
こういう議論の信憑性について疑問を持っている.
まず在庫にかかる費用が,製品単価の10~20%であるという仮定が疑わしい.
完成品倉庫にある製品が売れ残ってしまう場合もありうる.この場合の損失は,固定係数(20~30%)であるはずがない.現実はこんなに単純ではない.在庫費用はマーケットの需要動向と,売れ残り(在庫量)の関数になるはずだ.
仮に全て売れると仮定しても,在庫費用は在庫期間の関数であるはずだ.
また在庫になる製品を作っている間の機会損失も考えなければならない.
こういう理論の前提は,工場の稼動率,生産設備の稼働率を少しでも上げたいという要求から発生している.
しかし工場の稼働率や生産設備の稼働率を決定するのは,工場ではない.マーケットだ.
工場が決められるのは,可動率(「べきどうりつ」と読み「稼働率」と区別する)
工場ができることは,可動率を上げることだ.
段取り換えにかかる時間と費用を極限まで下げ,注文の数量だけ生産できるようにすることである.
ナガラ化
1950年代末から1960年代あたりの若者を示す「ナガラ族」という言葉がある.当時はラジオの深夜放送を聴きながら勉強したものだ.○○しながら□□するので「ナガラ族」というわけだ.
そのナガラが「ナガラ化」の語源である.
一つの作業をしている間の「手待ち時間」を有効に活用するのが「ナガラ化改善」である.
例えば,製品組立て後,機能検査をして製品ラベルを貼る工程を考えてみよう.
機能検査は自動検査装置で行っているが,検査時間が長い.このため検査工程のスループットを上げるため,検査員は検査だけに専念して,次工程の作業員がラベルを貼る.
作業時間は図1の様になる.
検査時間の間検査員は「手待ち状態」となっている.
この手待ち時間のムダを改善するために,ナガラ化治具を作る.
検査装置に検査中の製品の他にもう一台製品をつなぎ,スイッチで切り替えるようにする(図2)
この治具を使うことにより,検査員の手待ちはなくなり,更に後工程のラベル貼りまでできるようになる(図3)
検査工程のサイクルタイムも短くなっているのが,お分かりいただけるだろうか.
スループットを上げて,作業員を一人省人化できる.
改善に投資したのは,検査装置につなぐスイッチボックス一つだけ.
これが「ナガラ化」の威力だ.
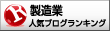
そのナガラが「ナガラ化」の語源である.
一つの作業をしている間の「手待ち時間」を有効に活用するのが「ナガラ化改善」である.
例えば,製品組立て後,機能検査をして製品ラベルを貼る工程を考えてみよう.
機能検査は自動検査装置で行っているが,検査時間が長い.このため検査工程のスループットを上げるため,検査員は検査だけに専念して,次工程の作業員がラベルを貼る.
作業時間は図1の様になる.
検査時間の間検査員は「手待ち状態」となっている.
この手待ち時間のムダを改善するために,ナガラ化治具を作る.
検査装置に検査中の製品の他にもう一台製品をつなぎ,スイッチで切り替えるようにする(図2)
この治具を使うことにより,検査員の手待ちはなくなり,更に後工程のラベル貼りまでできるようになる(図3)
検査工程のサイクルタイムも短くなっているのが,お分かりいただけるだろうか.
スループットを上げて,作業員を一人省人化できる.
改善に投資したのは,検査装置につなぐスイッチボックス一つだけ.
これが「ナガラ化」の威力だ.
ムダ取り
筆者は中国の生産現場で,中国人リーダに改善を教えている.
ムダ取りによる作業改善などは,少し教えてあげれば彼らにも簡単にできる.
作業現場で実際の作業を見ながら教える.
動作のムダ
指導現場で「改善前」「改善後」の写真を撮っておけば,その現場のための改善教科書ができる.
そんなことをしているが,日本でよい教科書を見つけた.
「カンタン!ムダとりポケットブック」
この本の良いところは,文章がほとんどないところだ.
少し日本語が出来る人材がいれば,簡単に読める.
何社かクライアントのリーダたちに読ませてみたが,好評だ.
この教科書を使って,中国人リーダが部下に教えることができるようになれば,現場の改善力が上がるだろう.
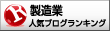
ムダ取りによる作業改善などは,少し教えてあげれば彼らにも簡単にできる.
作業現場で実際の作業を見ながら教える.
動作のムダ
持ち替えのムダ
取り置きのムダ
探すムダ
両手を使わないムダ
振り向きのムダ
歩行のムダ
…etc.
取り置きのムダ
探すムダ
両手を使わないムダ
振り向きのムダ
歩行のムダ
…etc.
指導現場で「改善前」「改善後」の写真を撮っておけば,その現場のための改善教科書ができる.
そんなことをしているが,日本でよい教科書を見つけた.
「カンタン!ムダとりポケットブック」
日刊工業新聞社
監修:山田日登志
著者:三浦聡彦
監修:山田日登志
著者:三浦聡彦
この本の良いところは,文章がほとんどないところだ.
少し日本語が出来る人材がいれば,簡単に読める.
何社かクライアントのリーダたちに読ませてみたが,好評だ.
この教科書を使って,中国人リーダが部下に教えることができるようになれば,現場の改善力が上がるだろう.
ラインを止めろ!
「停線!(ting2 xian4)」
以前指導していた電気製品の組立工場で,しょっちゅう大声でこういっていた.日本語で言えば「ラインを止めろ!」という意味だ.
ベルトコンベアの流れ作業で,何か小さな問題が発生してもなかなかラインを止めない.現場の班長さんたちは,ラインを止めないで何とか修復しようと必死になっている.
彼らには「生産量のプレッシャー」があるのでなかなかラインを止めたがらない.ラインを止めるのは「悪」だと思っていたりする.
例えば,半田槽を出てきたプリント基板アッセンブリィの半田手直し工程で,作業が追いつかず手直し待ちの半製品があふれてしまっている.
こんな状況で,現場の班長さんは作業者の後ろで一生懸命作業者をせかしている.または自分で手直し作業を手伝って何とかしようとしている.黙って見ている班長さんなどは論外だ.
こんな時に「停線!」と大きな声を出すわけだ.
こういう状況で作業者をせかして仕事をさせれば,後工程の半田目視検査やICT検査(インサーキットテスト)で不良が増加する.そしてその不良品は修理されてまた半田手直し工程に再投入されるからますます物は滞留する.悪循環だ.
こういう状況ではまずラインを止めて作業が追いつかない原因を除去しなければならない.
半田槽の調整が悪く半田不良が多発しているので,手直しが増えている.
部品が浮いてしまったり,傾いてしまうために,手直しが増えている.
等,原因が必ずあるはずである.
この原因を除去した上でコンベアを再稼動する.
ラインを止めずに生産を継続する方が生産のロスは大きいはずだ.
ラインを止めるのが早ければ早いほど,生産のロスは減る.何よりも品質不良のリスクを少なくする事が出来る.
班長さんたちにはラインを止める勇気を持てというのだが,なかなか出来ない.
ラインを止めることにより,問題点をその場で改善するという習慣を身につけるべきだ.
特に設備で物を作っている場合など,多少の不出来は後で手直しすればよいと考え,そのまま作ってしまうことはないだろうか.
先日見せていただいたアルミダイキャストの工場は,原材料にアルミのインゴットを投入することはまれであった.殆ど不良品を鋳潰した再生材料で足りてしまっている.
実はこういう工場のほうが好きである.簡単に改善して差し上げられる(笑)
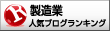
以前指導していた電気製品の組立工場で,しょっちゅう大声でこういっていた.日本語で言えば「ラインを止めろ!」という意味だ.
ベルトコンベアの流れ作業で,何か小さな問題が発生してもなかなかラインを止めない.現場の班長さんたちは,ラインを止めないで何とか修復しようと必死になっている.
彼らには「生産量のプレッシャー」があるのでなかなかラインを止めたがらない.ラインを止めるのは「悪」だと思っていたりする.
例えば,半田槽を出てきたプリント基板アッセンブリィの半田手直し工程で,作業が追いつかず手直し待ちの半製品があふれてしまっている.
こんな状況で,現場の班長さんは作業者の後ろで一生懸命作業者をせかしている.または自分で手直し作業を手伝って何とかしようとしている.黙って見ている班長さんなどは論外だ.
こんな時に「停線!」と大きな声を出すわけだ.
こういう状況で作業者をせかして仕事をさせれば,後工程の半田目視検査やICT検査(インサーキットテスト)で不良が増加する.そしてその不良品は修理されてまた半田手直し工程に再投入されるからますます物は滞留する.悪循環だ.
こういう状況ではまずラインを止めて作業が追いつかない原因を除去しなければならない.
半田槽の調整が悪く半田不良が多発しているので,手直しが増えている.
部品が浮いてしまったり,傾いてしまうために,手直しが増えている.
等,原因が必ずあるはずである.
この原因を除去した上でコンベアを再稼動する.
ラインを止めずに生産を継続する方が生産のロスは大きいはずだ.
ラインを止めるのが早ければ早いほど,生産のロスは減る.何よりも品質不良のリスクを少なくする事が出来る.
班長さんたちにはラインを止める勇気を持てというのだが,なかなか出来ない.
ラインを止めることにより,問題点をその場で改善するという習慣を身につけるべきだ.
特に設備で物を作っている場合など,多少の不出来は後で手直しすればよいと考え,そのまま作ってしまうことはないだろうか.
先日見せていただいたアルミダイキャストの工場は,原材料にアルミのインゴットを投入することはまれであった.殆ど不良品を鋳潰した再生材料で足りてしまっている.
実はこういう工場のほうが好きである.簡単に改善して差し上げられる(笑)



