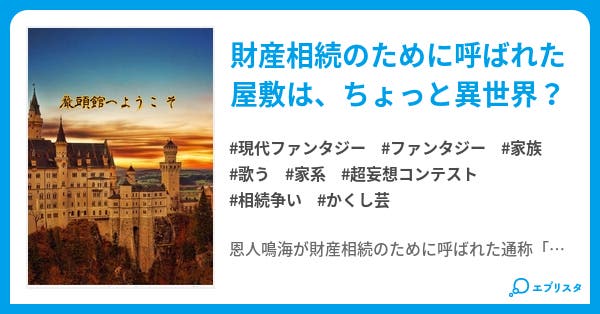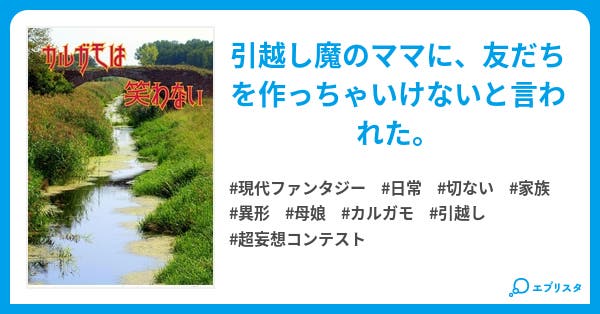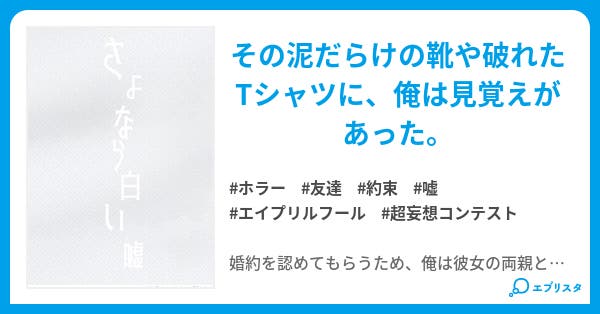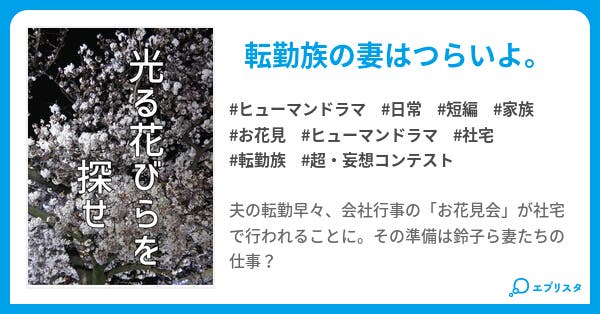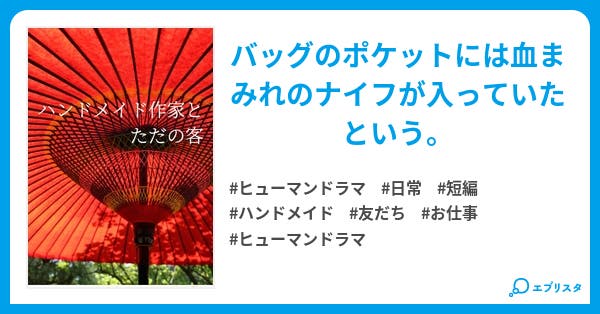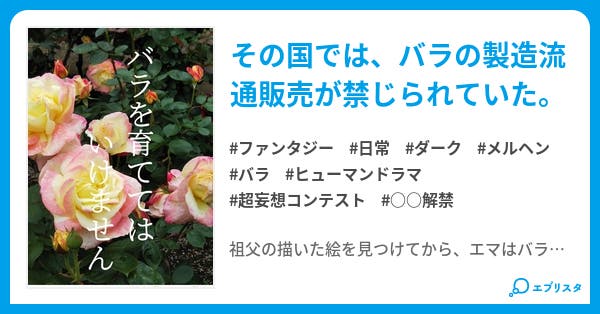どんな話を書くにしても、
読み手がコンクールの審査員であれ、小説サイトのフォロワーさんであれ、何年後かの自分であれ、とにかく最後まで面白く読み終えてほしい。
基本的にはその気持ちだけなのだけれど。
そのためには、シナリオ学校やら小説サイトやら、様々な物書き基本マニュアルやら。
これまで読んだり教わったり聞いたりした話の中で、できることをやっている。
そのノウハウの全部が全部自分に合っているわけではないと思ったし、すべてをやろうとすると疲れてしまって書けなくなったりするので、自分仕様の自分ルール。
まずはとにかく「つかみ」。
出だし。冒頭。
自分が読者だったり視聴者側だった時、こう来たら「え、何、何?」と食いつきたくなるような導入にしたい。
よく言われるのは、クライマックスを最初に持ってこい、と。
私が初めてシナリオを書いた頃よりも最近は更に読み手は飽きっぽい。だからいきなり最高潮で突っ走れ、となる。
私の場合は、会話で始まることも多い。何の話してるの、そのセリフ、どういう意味? みたいな、興味をそそる確率が高いと思っているから。
次に、キャラクターの表し方。
「この子はドジなのである」と一言書いても、読み手も書き手もすぐ忘れてしまう。
例えば、乗り換え電車を間違えてしまうとか、止まっている車にぶつかってケガするとか、その行動っぷりから「ドジ」を表す。
「ドジである」という文言は使わずにそれをわからせることができればいいと思っている。
それから、キーとなる小道具、セリフ。
これが、前半と後半でまったく別の意味で使えたら本当に面白いし、印象的だと思う。
そして、もう自分の使命じゃないかな、と思っていることがある。
昭和の目撃者。
といっても、前半はほとんど知らない。
でも、高度成長期やバブル期、バブル崩壊、男女雇用機会均等法、IT革命、働き方改革、ダイバーシティなど。
昭和後半から現在まで、その怒涛の急激な変化を実際目で見て肌で感じてきた世代。
この時代を背景にした物語をリアルに書けることは強みで、それを残すことが自分にできる一つの大仕事なのではないかと思っている。
もっと古く、江戸時代などの「時代もの」も書いてみたいと思いつつ、日本史の成績が壊滅的だった自分の頭では大河ドラマを楽しむくらいが精いっぱいで。
実体験を反映したエンタメの方が少しでも書きやすいし、書けるものからどんどんアウトプットしておくべきかと。
懐かしく読んでくれる人はもちろん、
最近は「フロッピーって何ですか?」と言い切る若手社員に出会うくらいなので、物珍しく読んでくれる人もいるかもしれない。
(了)
「歌う」がお題の新作短編です。14分で読めます。(現代ファンタジー)
↓
「引越し」がお題の短編です。11分で読めます。(現代ファンタジー)
↓
「エイプリルフール」がお題の短編。11分で読めます。(ホラーのつもり)
↓
「お花見」がお題の短編です。14分で読めます。(ヒューマンドラマ)
↓
********
☆彡読み切り連載始めました⚾
「キッコのベンチ裏レポート」(ただいま第8話まで公開中)
第213回コンテストで佳作に選んでいただいた「ポケットの中」がお題の短編はこちら↓ 11分で読めます。
第185回コンテストで入賞作に選んでいただいた「○○解禁」がお題の短編はこちら↓ 14分で読めます。
バラを育ててはいけません (ファンタジー)