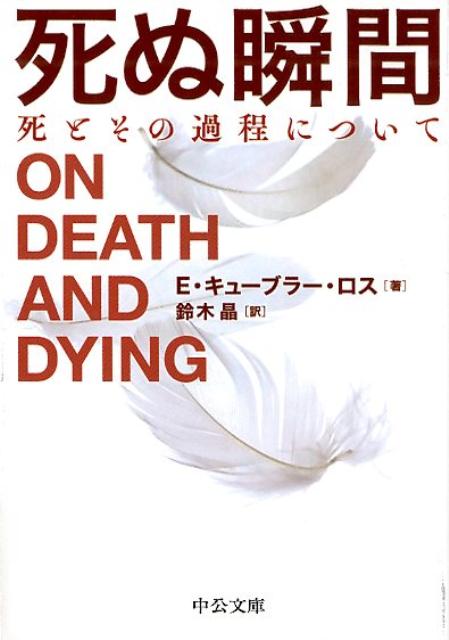プロバガンダによって
生きる事の意味や価値という事は、言わずもがなであり
逆に、タイトルにキャッチーに書いたように死への憧れや、死に向かう事
死と云うものは悪い事のように忌避されてきた昭和の時代には
祖父や祖母が死んだ時でも、明日学校だから心配しないで寝てなさいとか、
葬式はこっちでしておくから・・・と云ったように
死に立ち会う事すら許されずに、遠ざけるかのように擦りこまれてきました。
生と死は、表と裏の関係性で一体であり、
それは人が平等であることを教えてくれます。
また、樹木が倒れ、そこに新たなる芽が息吹くように、人もまた同様なのです。
生の時間をどれだけ自分にとって意味あるものとして生きていけるのか?
それは、対極にある存在に触れて見ない事には分からないものでしょう。
例えて云うならば、高い所から飛び降りて怪我をすれば
痛い事を知って、痛いだろうことをしなくなるのと同様です。
また、バイク事故を起こし、救急車で運ばれた後には
あーなるかもしれないからという予測によって、事故回避能力が高まりますし
事故が起こった場合に身を守る為のプロテクターも装備して乗ることでしょう。
それは生への強い執着心を産んだという証明でもあるかもしれません。
軽装で乗っている人は、痛い思いをまだしていないのです。
それは、つまり生への執着が生れていないという事でもあるかもしれません。
多くの人は、病気をして入院をした後にシャバ(娑婆)に出て、
いつも通っている景色を見渡した時に新鮮に見えたりして
今ココに存在する事に何故だか感動したりしませんか?
死というものが素晴らしいという事ではありませんが
しっかりと視線をそらさず、それに向き合う事で、
残された時間を有意義に生きる事が出来ると思うんです。
アルコールを飲み過ぎれば、
肝硬変になって肝臓癌になって寿命を短くしてしまう事でしょう。
だからと云って悪いと云われるものを全て禁止し
忌避さえすれば人生が豊かになるのでしょうか?
アルコールは適量を飲めば陽気にさせて、口数を多くし、
心の壁を排して心が通じ合うように会話が進みます。
日頃、溝のあるように感じる人間関係でも、意外にアルコールによって
溝が無くなり、人生が楽しくなることもあるかもしれません。
タバコも同様に、喫煙所での何気ない話によって
そこでは身分に隔たり無く会話が横行し、
バカ話から知人関係に発展していく事も考えられるでしょう。
いずれも死へと近づける社会的悪事行為は共通しています。
死へ向かう行為というのは、人を等しく見つめる効果があるように思います。
逆に生への強い執着は、金を稼ぐ為に人を騙したり
人を蹴落としてまで自分が優位に立とうとする、
醜い心(しこめ)が育まれるような気がします。
死というと、すぐに自殺というキーワードが思い起こされて、
死を喚起しているのでは?と錯覚されてしまうかもしれませんが
これは非常に重要なテーマです。
だからこそ
2000年前のキリスト教プロテスタント派は、
名立たる作曲家たちにレクイエムを作らせました。
死とは恐いものである、
だからこそ生きている時間を一生懸命に生きることが重要だと
そう伝えたかったのでしょう。
(寄付をすれば、しただけ救われるというのは、卑しい心なのか?
それとも敬虔さを表す指標だったのかは?未だ不明なところです)
秋田県のなまはげも、私には同様に思います。
恐怖を知る事によって、教えられることがあるように、
死というのも同様に、正しく恐れる必要があると思います。
かつて、キューブラーロスさんが書いた、「死ぬ瞬間」
にも書いてありましたが、
死ぬにはいくつかの過程を経る必要があると述べています。
ある一定の、時間と心の働きと経過を経なければ、
本物の平穏は訪れないのだと。
この本を読んでから、生きている事の意味を逆説的に考えてみると
如何に今と云うものが尊いものに感じるかが不思議です。
「今を生きる」
増税でこの先、我々が老後になろうとする時、年金で生活できるのか?
社会がどうなっているのか不安で仕方がありませんが、
今を見て一生懸命に生きていく積み重ねこそが、
まだ見ぬ死への彷徨という恐怖を阻止し
生への確かな一歩を踏み出せると思うのです。
それが、「死への美学」でもあるような気がしています。
ある意味では、この見方は、ユダヤ教にあるタルムードというべき
相反する視線思考とも考えられるかもしれません。
www
などとちょっと言い方を美化してみました。
本日もくだらないことにお付き合いいただきましてありがとうございました
シェーシェー