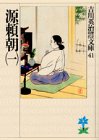伊豆富士見紀行
に託けて、頼朝だの頼家だの、北条政子だのと
あれこれ書き連ねておりますけれど、この辺りの歴史には本当に疎い。
今回このエリアに出向いた元々には韮山代官・江川太郎左衛門
への興味があったわけですが、
どうしたって源頼朝との関わり抜きではおれない場所柄でもあるものですら、
旅の友とした本が吉川英治作「源頼朝」でありました。
ご存知のように吉川作品は非常に読みやすいのものですけれど、
厚めの上下巻、結果的にはちと時間がかかってしまいましたですね。
(私本太平記 全8巻ほどではないにせよ)
それはともかくこの頼朝を主人公とする物語、
平治の乱に父・源義朝が敗れた結果、伊豆に遠流となった頼朝
が
鄙びた土地で鬱々と暮らす日常は余り歴史小説としての面白みはないわけで、
あっという間に月日の経つ十数年となります。
後に伴侶となる北条政子が平家側の伊豆目代である山木兼隆に嫁ぐと見せかけたいざこざから
打倒平氏、源氏再興を掲げて山木館を陥とすあたりは見せ場の一つながら、
続く石橋山の合戦ではものの見事に打ち破られてしまい、ほうほうの体で舟に乗り込み脱出、
安房へ逃れて再起を誓うことに。
その後、坂東武者をどんどん味方に引き入れて鎌倉に入り、
ここに幕府を打ち立てるべく、そこに腰を落ち着けて固めに入るわけですね。
合戦こそが面白いとは語弊のある言い方かもしれませんが、
戦いは動的なものであって、政権基盤の確立といったあたりは静的な部分、
どうしても賑々しい方が面白く思えるところなわけです。
確かにその後も源平の合戦は西へ逃れる平氏を追って、
一ノ谷、屋島、壇ノ浦と続きますけれど、
ここいら辺になるとどうしたってヒーローは源義経に思えてきますから、
鎌倉にどっかと腰を据えている感のある頼朝は実に地味にも受け止められようかと。
ですが、これらの戦いの様子は気になるものの、それぞれを細かに記していくと
ますます義経の存在が大きなものに見えてしまうきらいがありましょうから、
平氏追討の大詰めは戦勝報告が頼朝に届くくらいの簡単な記述に留まっています。
そして、壇ノ浦で平家を討ち果たし、
頼朝は鎌倉での位置を盤石なものにする…てなあたりで物語は終わってしまう…。
実際、1185年の壇ノ浦の戦いから14年後、1199年に頼朝は51歳で没してしまうのですね。
その14年間も決して平穏無事には行かなかったものと思いますけれど、
宿敵平家を掃討した後、幕府固めの年月はどちらかと言えば静的な世界かも。
もちろん大きなこととして奥州討伐(1186年)がありますけれど、これを書いてしまうと、
それまでのところでも大きな戦果を挙げながら追放されてしまう義経に対して、
文字通り「判官贔屓」の思いばかりを読み手に募らせることになる、
つまりはタイトル・ロールがすっかり悪者に見えてきてしまう…となりますから、
書こうにも書けないのではなかろうかと。
こう考えてみると、歴史上の一大著名人物でありながら、源頼朝という人は
史書ならばともかく、歴史小説としては書きにくい題材なんだろうなと思いましたですね。
断然、義経の方が書きやすかろうと思います。
他がやらないことをやろうと頼朝を選んだのかは分かりませんですが、
さすがに吉川英治といえども苦労したのではないでしょうか。
とはいえ韮山、修善寺と巡るに関わる上巻所収部分は、
旅の友の役割を十二分に果たしてくれたかなとは思いましたけれど。
そうそう、頼朝が描きにくい人物であるといえばですが、
(といって「描きにくい」ことそのものではないのですけれど)
昔から(例えばかつての日本史の教科書などでも)「源頼朝像」として紹介されていた肖像画は
どうやら足利直義(尊氏の弟)の像なのではないかということになってきてるようですね。
直義も尊氏共々に足利室町幕府を成立させる立役者の一人ながら、
やがて尊氏と対立して葬り去られる運命にある…となると、またしても思い出すのは頼朝と義経。
いやはや歴史にはあれこれ思うことが何とたくさんあることか…。
…というところで唐突ですが、新潟に出張と相成りまして、しばしのお暇を。
戻ってきましたら、今度こそ伊豆富士見紀行の終結に向けて
「いざ鎌倉!」でなくて、「いざ、まいらん!」と思っております。
ではでは。