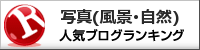夕日の色にこだわるポイント
夕焼けは逆光方向で撮る場合が多いのですが、その理由は2つあります。1つは風景を撮るとき、少し逆光気味だったり斜めや横からの光を捉えたりした方が「被写体の立体感」や「コントラスト」が出るから。もう1つは、その方向が最も空が赤く染まるからです。太陽が完全に沈み、夜の時間がまだやってきていない、いわゆる「マジックアワー」と呼ばれる美しい空が出現するのは多くの場合、太陽が沈んでいく「逆光方向」です。
撮影機材は、NikonD810、タムロンSP24-70です。
撮影の設定ポイント
1、ホワイトバランス
オートホワイトバランス(AWB)は、「自動的に白いものを白く記録する様に色温度調整を行う」機能ですので、夕暮れを撮影すると、空の赤みが物足りないことがあります。ホワイトバランス設定を曇りや日陰に設定します。
もう少し専門的にいいますと日の入り時は、オレンジ色の空が特徴的なので、ホワイトバランスをマニュアルで、ケルビン値(色温度の値)7000K~8500Kまで上げることで赤味をさらに増した写真になります。
2.露出補正
露出補正をマイナスにすると空の赤みが強くなり、建物などのシルエットはより暗くなります。カメラに露出を任せると、かなり明るい写真に仕上がってしまいます。
3.コントラスト
コントラストを強めに設定する事で明暗がはっきりし,薄い色の雲や光が浮かび上がりドラマチックな写真に変わります。
撮影モードは明るさの変化に対応できるよう絞り優先モードで撮影しf8~11絞ると太陽の輪郭がはっきりとします。
又、レンズに入ってくる光を抑える減光用フィルター「NDフィルター」もあるといいでしょう。通常はND4かND8でいいでしょう(NDの後ろの数字が大きくなる程フイルターの濃度が濃くなります)。
また、夕焼けでも太陽を直接撮るとイメージセンサーにダメージを与えることになりますので注意が必要です。
連載 「砂上の足跡」~道徳資料「浅田剛立」執筆 その1
無事3年の交流期間を終え、古巣の山香地区に帰ることとなった。赴任した向野小学校は、児童数が50人に満たない小さな学校であった。この学校には、6年間勤務することになるが、この間、小道研関係の仕事に一番追われた時期であり、充実した楽しい時期でもあった。
光文書院道徳副読本の大分県版資料を執筆することになったのは、2年目のことだった。私は5年生の資料を担当することになり、郷土の偉人を題材に「不撓不屈」「創意工夫」の価値内容から迫ることができる資料を作りたいと思った。
選んだ偉人は麻田剛立。麻田剛立は、杵築藩の儒者綾部絅斎の四男として生まれ、医学を学びながら天文学、暦学を独学し、天明6年(1786年)の日食の予報を的中させて世に知られた人物である。当時、麻田剛立に関する書籍はあまりなかったので、先哲資料館に行ったり県立図書館に行ったりして資料を探した。麻田剛立という人物を調べていくにつれて、私はどんどん麻田剛立の生き様に魅せられていった。
剛立は、幼い頃から天体に興味を抱き、医学を学ぶ傍ら、天文学、暦学を独学した。
1763年(宝暦13年)に、当時使用されていた幕府の宝暦暦に記されていなかった9月1日の日食を、独自の計算により予言して的中させ、名声を高 めた。従来一定不変と考えられていた天体運動が、常に変化する函数によるものであることを指摘したものである。 計算によって正確に日食の日を予想したのは、世界初のことであった。西洋で計算によって日食が割り出されたのが、それから150年後のことであることを考えれば、剛立の偉業の素晴らしさが一層輝いて見える。
1767年(明和4年)、34歳の時に杵築藩主の侍医となり、藩主親貞の難病治療の妙薬を作ったといわれているが、侍医の仕事が忙しくて天文の勉強が出来ないことから、何度も辞職を申し入れた。しかし受理されなかったことから、1772年(安永元年)前後に脱藩する。その後大阪に移り、先祖の出身地である麻田村の名を取り、麻田 剛立と名乗って、医師をしながらひたすら天文の研究を続けたのである。
つづく
光文書院道徳副読本の大分県版資料を執筆することになったのは、2年目のことだった。私は5年生の資料を担当することになり、郷土の偉人を題材に「不撓不屈」「創意工夫」の価値内容から迫ることができる資料を作りたいと思った。
選んだ偉人は麻田剛立。麻田剛立は、杵築藩の儒者綾部絅斎の四男として生まれ、医学を学びながら天文学、暦学を独学し、天明6年(1786年)の日食の予報を的中させて世に知られた人物である。当時、麻田剛立に関する書籍はあまりなかったので、先哲資料館に行ったり県立図書館に行ったりして資料を探した。麻田剛立という人物を調べていくにつれて、私はどんどん麻田剛立の生き様に魅せられていった。
剛立は、幼い頃から天体に興味を抱き、医学を学ぶ傍ら、天文学、暦学を独学した。
1763年(宝暦13年)に、当時使用されていた幕府の宝暦暦に記されていなかった9月1日の日食を、独自の計算により予言して的中させ、名声を高 めた。従来一定不変と考えられていた天体運動が、常に変化する函数によるものであることを指摘したものである。 計算によって正確に日食の日を予想したのは、世界初のことであった。西洋で計算によって日食が割り出されたのが、それから150年後のことであることを考えれば、剛立の偉業の素晴らしさが一層輝いて見える。
1767年(明和4年)、34歳の時に杵築藩主の侍医となり、藩主親貞の難病治療の妙薬を作ったといわれているが、侍医の仕事が忙しくて天文の勉強が出来ないことから、何度も辞職を申し入れた。しかし受理されなかったことから、1772年(安永元年)前後に脱藩する。その後大阪に移り、先祖の出身地である麻田村の名を取り、麻田 剛立と名乗って、医師をしながらひたすら天文の研究を続けたのである。
つづく
人気ブログランキングに挑戦中です。
よろしければ上のバナーを押して応援してください。