今日は福岡も雪景色であり、僕の事務所のある天神も窓から時折吹雪の様に雪が舞っているのが見える。

チャイコフスキーと言えば、「白鳥の湖」「くるみ割り人形」「眠りの森の美女」等のバレエ音楽で有名だが、生涯で7曲の交響曲を作曲している。
一つは番号の無い「マンフレッド交響曲」と言う曲で、残りは1~6番の番号が付いている。
この中で、最も良く演奏されるのが後期の4,5,6番であり、完成度も高いと言われ、1,2,3番はこれに比べると演奏される機会が少ない。
只、後期の3曲に対して、前期の3曲は、1番「冬の日の幻想」2番「小ロシア」3番「ポーランド」と呼ばれるタイトルが付いている。但し、チャイコフスキー自身が付けたのは1番の「冬の日の幻想」だけ。
この「冬の日の幻想」は業界では通称「ふゆげん」と言ってるが、前期3曲の中では最も良く演奏される曲である。
大抵、第一交響曲と言うのは、モーツアルトの様な早熟な天才以外は、比較的気合を入れて作っているもので、ブラームス等は着想から完成までに21年掛け、第一交響曲を発表したのは43歳だったから、その気合も尋常では無い。
もっとも、ブラームスの場合、ベートーヴェンを尊敬していた為、自分の交響曲はベートーヴェンを超えるほどの物を作りたいと思っていた為、尚更だ。
話が逸れたが、チャイコフスキーの一番は26歳の時、モスクワ音楽院の講師になる前の時期に書き上げたもので、その後、何度か書き直しをして34歳で改訂したものが最終稿となっている。
最初の書き直しは、11歳年上で当時の師匠のアントン・ルビンシテインから酷評されて書き直してる様だが、果たしてこの師匠はピアニストとしての才能はあった様だが、弟子の才能を見抜く能力があったのかどうかは疑問で、師匠も結構な数の曲を作曲している割には、その作品が現代に残らなかったという事からも、どちらかと言うと詰まらない方へ書き直しさせたのでは無いかと思われる。現代でも通じる話であろう。
事実、チャイコフスキー35歳の時に作ったピアノ協奏曲第1番の初演を依頼したアントンの弟のニコライ・ルビンシテインに同様に酷評を受け初演を断られた為、ドイツの著名な指揮者ハンス・フォン・ビューローに楽譜を送ったが、反対にビューローによる初演は大成功し、ヨーロッパの各都市で演奏され、その後、ニコライはチャイコフスキーに謝罪し、自らもこの曲を演奏するようになったのは有名な話で、どうもこの兄弟はたいした才能が無かったのでは無いだろうか。
只、弟とは5歳違いと年も近い事もあって、割と仲が良かった様で、「ニコライ・ルビンシテインの誕生日のためのセレナード」なんて曲も作曲していて、ニコライが亡くなった時も「ある偉大な芸術家の思い出のために」と言うピアノ3重奏曲を作曲している。
こんな感じだから、この第一交響曲も、二人からあれこれ言われたのかもしれないが、何かしら座りの悪い部分はあるものの、冬の嵐の様に木枯らし吹きすさぶロシアの大地を感じさせる1楽章や嵐が過ぎ去った後のひっそりとした雪の闇を包むような朗々とした第2楽章等、まさに冬のイメージピッタリの曲であり、全体的にはチャイコフスキーの才能を感じさせる曲だ。
有名な作曲家でも、最初の頃と最後の方の曲は割りとイメージが変わるものだが(ベートーヴェン等は顕著)、チャイコフスキーの場合は割りと最初から最後までチャイコフスキー節が一貫している気がする。
今日の様な寒い日に、暖かい珈琲でも飲みながら聴くのがお薦めである。
- オイレンブルクスコア チャイコフスキー 交響曲第1番 ト短調 ≪冬の日の幻想≫ 作品13 (オ.../全音楽譜出版社
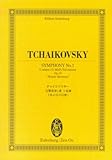
- ¥1,470
- Amazon.co.jp