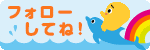【前回のお話はこちら】☆人物紹介はこちらから→★
「クゥのお父さんはね、ラヴィリティア近代戦術の草分けだったんだ」
「そうなんだ…」
ここは森の都グリダニアの隣国であり歴史ある緑豊かな小国ラヴィリティア王宮の、お膝元にある城下町国立図書館である。この物語のヒロインであるクゥクゥ・マリアージュは自分の父親がどういった勇者であったかを知る為に近々伴侶となる男性でありこの小国ラヴィリティアが故郷であるオーク・リサルベルテに、彼の蔵書であるラヴィリティアの国史を1ページ1ページ捲りながら丁寧に説明を受けているところであった。オークが続ける
「リヴァイアサン討伐叙勲の時の事を覚えている?ラヴィリティアは元々国を持たない遊牧民で自分たちの手だけで国や覇権を勝ち取ってきた戦士の国なんだ。“戦になれば負け知らず”って他の国では囁かれているけれど真実は異なっていて、引き際を明確に読んでいたから戦を長引かせて勝利してきたところが大きいんだ」
青年オークが選んでくれた百年単位で語り継がれてきたであろうラヴィリティア史の、装丁の角は形を無くし擦り切れまた厚く古めかしいその本は最近の歴史に差し掛かると途端に閉じられてしまう。その本に食い入るように見入っていたクゥが代わりに差し出され開かれたのは『ラヴィリティア剣術近代史』と名付けられた戦術書だった。オークは尚も続ける
「ラヴィリティアの近代戦術は長いラヴィリティア史の中でも異端とされていたけど、理にかなったていたし何よりも古代ラヴィリティア戦術の本質を理解した上でのものだったことがここ二十年程の研究で紐解かれたんだ。その近代戦術の開拓者が君のお父さん、エオルゼア語での発音はライラックで旧ラヴィリティア語であるトゥル語ではレイラック。だから本国ではレイラック・バン・ラヴィリティア、先々代ラヴィリティア国王の側近であり当時のラヴィリティア国王が襲名するはずだった『ラヴィリティア卿』の名を臣下の身分で持つ“ラスト・ラヴィリティア(二度とない奇跡)”だ。彼は真のラヴィリティアの勇者だよ」
「お父さんがグリダニアの人間じゃないかもって思ってはいたけどラヴィリティア人だなんて一言も言ってなかった…」
「ラヴィリティアの血脈でないことは確かなようだよ、お父さんはラヴィリティア人じゃない。そういう記述は一切存在しない、それは本当のことみたい」
「? オークはなんでそのことを知ってるの?」
「だって俺は“彼”のファンだったから」
本人の口から語られなかった自身の父親の、知られざる姿をただ呆然と聞き入るクゥに安心するよう微笑みかけるオークは彼女に言葉を重ねた
「俺たちのクラン『Become someone(ビカム・サムワン)』で使ってる戦術や配置はレイラック氏のラヴィリティア近代戦術を応用しているんだ。俺が巴術士(はじゅつし)を目指したきっかけも彼の論理的な闘い方を学ぶ為だったし、お父さんは剣士でありながら学者でもあったんだ。ヒーラーの回復士も習得し終えている、ラヴィリティアでまさしく神の様な存在だった天才だよ」
オークは歴史書よりもまだ真新しく図書館に所蔵されてばかりの近代戦術史をぱたんと閉じると懐かしむように目を細めて再びクゥに語り始めた
「彼のような理知的な人間になりたかったから子供の頃からずっと彼の歴史だけを追っていた。だから彼がどこか遠い異国からラヴィリティアに身を移して国王に寵愛を受け仕えて、貴族の称号まで与えられたことを全て知っている。それほどまでに憧れだった…本当に会いたかったな、君のお父さんに」
「オーク…」
まるで恋をするように自分の父親の軌跡を長年追い続けていたのだろう、クゥはオークのそのとても惜しむような気持ちを滲ませた横顔を静かに見守った。しばらくしてクゥは視線を降ろし閉じられた本たちを見ながらぽつり喋り始めた
「私ね、オークにお父さんの話を沢山したけど本当は心のどこかで勇者の話は嘘っぽいなって思ってたの」
「え」
「だって父親ってどこか事を大きく話すところがあるじゃない?村の人も誰もお父さんのこと知らないしお母さんもちょっとしか知らなかったし」
「そうか…」
「娘の私だから大袈裟に話しちゃってるだけかもって…でも本当だった。思ってたよりももっともっと凄い人だった」
「…これは俺の推測だけど、お父さんはお母さんにプロポーズする前に騎士を辞めたんだったね。これから求婚するお母さんに余計な気を負わせたくなかったんじゃないかな。俺がお父さんの立場なら同じ事をすると思う」
オークの言葉に弾かれてクゥは俯き加減だった顔を上げる。オークは言葉を続けた
「だからお母さんにもほとんど話をしなかった。だけどやっぱり娘の君には、クゥだけには真実を話したかったんだ。だから繰り返し言って聞かせたんだと思うよ」
「お父さん…」
何度も思い出すのは、俺は勇者だったんだぞと自慢げに繰り返し話す父親の姿。鬱陶しく思う年頃もあったけれどそれすらも愛おしい思い出にクゥは目に涙を溜めて片手でそれを拭った。オークはそんな彼女の背に手を当てて優しく撫でてやる。彼女の頭を自身の体に寄せて、肩を抱いてオークはクゥに最後にこう言った
「必ずふたりで幸せになろう、今度は俺がお父さんの話を聞かせてあげるよ」
「ありがとう、オーク」
小さなその図書館でオークとクゥは静かに身を寄せ合い陽が暮れる頃ラヴィリティアを後にした。それはラヴィリティア城で結婚の届け出と報告を済ませたあと流れ星のように消えた知られざる過去を持つ伝説の勇者の軌跡を、クゥの故郷に出向くその足で最後に寄ったラヴィリティア国城下町で彼女が初めて知った出来事であった。
オークとクゥクゥが正式にラヴィリティア国へと結婚の許しを乞う為ラヴィリティア王宮ヘ出向いた数日後、ラヴィリティア王宮内では『帝国』と呼ばれる宗主国との諍いに頭を痛めている最中であった。再び開かれたラヴィリティア貴族院会議では帝国への脅威に皆神経を尖らせ議会は混乱の極地へと追い落とされていた
「今度の支援は前回の二倍の食料支援だと…?」
「あの忌々しい国め、白々しい!!」
「もう我慢ならん!こちらが仕掛けなければそれこそ国庫が食い潰されてしまう…今こそ牽制を、ハーロック卿!」
「成らんものは成らん、今こちらが仕掛ければ帝国に大義を作らせるだけだ」
「しかし!」
貴族院の参加者概ねが最早説得の出来る状態ではなかった。ラヴィリティア第一貴族ハーロック卿は深く溜息を吐き貴族院会議聖堂じゅうに響くよう高く声を上げた
「では先んじて、ハンナ・ラヴィリティアの即位式を執り行う」
「なんと…!?」
議会は瞬く間に動揺の渦へと巻き込まれた。貴族院の関係者は次々と口を開いたがそれをハーロック卿は強く諌めた。ハーロック卿は続ける
「第一皇女の即位式は婚儀を伴う、そしてそれは即ち莫大なる金銭が動く。即位式を大々的に他国に伝え知らせて此度の支援は先送りにすると帝国に通達するのだ」
「おお!それならこちらが自然と大義名分を得られる、さして問題は起こらないかもしれぬ」
ひとりの貴族が声を上げると同時に聖堂内の空気が緩んだように見えた。ハーロック卿はその隙を見逃さず席を立ち上がり続けて叫んだ
「では時期を早め第一皇女即位式を実施する。皆の者、良いな」
議会は満場一致で結審した。ラヴィリティアの歴史が今まさにオーク達の知らぬところで静かに、しかし着々と動こうとしていた。

小鳥達がさえずる声が聞こえる。場所は変わりここはオーク達がクランを構える森の都グリダニアの北に位置する十二神大聖堂。エオルゼアの朝日がグリダニアの大地を照らし、また十二神大聖堂がその光を浴びて神々しく輝いた。大聖堂の奥中には今日ここで結婚式を挙げようとする新婦の、クゥクゥ・マリアージュの姿があった。本来なら結婚式の来客の為に使われる控室でマーメイドラインながらもトレーンが効くウェディングドレスを纏ったクゥクゥが、着付けに駆けつけた同じクランの女冒険者オクーベルと、オークの懐番のリテイナーであり仕立て屋を営むタチュランタに支度の微調整を行われていた。タチュランタはクゥの髪を整えた後、新郎のオークに声をかける為に一度控室を後にする。ドレスを整え終えたオクーベルがクゥに声をかけた
「クゥ、本当に聖堂の中で一人で動けるか?ケイも外で控えているがドレスの裾を持って貰ったらどうだ、本当の天使なんだから」
「大丈夫だよ、オクベルちゃん。心配性なんだから!それにひとりじゃないよオークが側にいるもの」
「そうか。抱きしめてやりたいけど着飾っているから今はだめだな、オークに何か言われそうだ」
「オークはそんなことで怒らないよ」
同じクランでクランを立ち上げた時から共に苦楽を共にした女同士、そこには深い絆があった。親友と呼べる期間をとっくに飛び越えてまるで姉妹のように家族のようにふたりは手を取り合った。クゥがオクーベルに心からの感謝を述べた
「オクベルちゃん、何から何まで本当にありがとう。大好きよ」
「ああ、私も大好きだ」
そう言ってクゥとオクーベルふたりが微笑み合ったそのとき控室の扉が大きく開いた。タチュランタが勢いよく扉を開き新郎オークにクゥクゥのウェディングドレスを見せつけるよう取り計らったのだった。しかしオークの第一声は意外な言葉だった
「新郎の俺と愛を誓い合う前に俺の愛しい奥さんと愛の言葉を交わすのは控えて欲しいな、オクベル」
「はいはい、わかったオーク。では私はケイ達と大聖堂の外で待ってる」
オークの新郎姿と先程の奥さんという言葉に一人感動しているクゥを横にオークはその場を後にするオクーベルに最後に声をかけた
「オクベル、いつもクゥの側に居てくれてありがとう。これからも彼女を見守っていてほしい」
「言われるまでもない、お前こそしっかりなオーク」
「ああ」
両親が新婦を引き渡すように女冒険者オクーベルと新郎オークが固く約束をして彼と新婦のクゥは控室にふたりきりとなった。未だ夢見心地になっているクゥと見つめ合いオークは最愛の彼女に一歩近づいて愛を囁いた
「さっき一番に言えなくてごめん、でもふたりきりの時のほうが良いかなと思って。とても綺麗だよ、クゥ」
「ありがとう、オーク」
「今すぐ口づけをして抱きしめたいけどそれもやっぱり最後だな、こんなに綺麗なんだからしばらくこうして見ていたい」
「うん、私も綺麗な姿をオークに見ててもらいたい」
クゥはグリダニアの朝日と同じ眩しい微笑みをオークに贈る。今日はふたりだけの結婚式。生涯永遠に覚えていたいと願うようなキスをクゥの真白な手袋の上から念入りに押し当てたオークは、朝露を纏う大地に注ぐ温かな陽をはらんだ笑顔で美しく愛しい自らの伴侶に微笑みを向けるのだったー。
(次回に続く)
↓読者登録をすれば更新されたら続きが読める!
ぽちっとクリックしてね♪
↓他の旅ブログを見る↓
☆X(※旧ツイッター)

☆インスタグラム
☆ブログランキングに参加中!↓↓