
2007年、私がマインドマップを本気で学びはじめた頃、辰巳ジャンプは部員数が女子5人、男子1人という状況でした。チーム解散の危機という事態でした。最大の原因は私の「異動」でした。前任校で異動期限の6年を過ぎ、校長とも話し合って教育委員会に具申していただき、異動期限を延長していましたが、さすがに8年目に入った時点で「もうこの学校での使命は果たしたかな」という気持ちになっていました。
何しろ本当にたくさんの仕事をさせてもらい、自分の財産となる実践を積ませていただきました。
「ホームページ」
全日本小学校ホームページ大賞で全国ベスト8入賞する。
この件で、読売新聞・TBSラジオ・江東区報・ケーブルテレビ等の取材を受ける。
「スクールキャラクター・たもちゃん」
茨城県のタニコーさんの協力を得て、スクールキャラクターを誕生させる。
「幼稚園との交流活動」「1年-6年交流活動」
カリキュラム化の基礎を作る。今も学校の目玉として活動が続いている。
「スマイルチーム活動」
特活主任としてたて割りの班活動を作り出す。
「塩浜福祉園との交流活動」
成人の障害者厚生施設である福祉園との給食交流を生み出す。
「辰巳ジャンプVC」
このブログで記事にしているチームですね。
「テレビ取材」
NHK総合・NHK教育・テレビ東京・NTV・江東ケーブルの番組に協力。
「区で初の学校公式ブログ導入」
日光の実踏先から学校の子どもたちとブログでやり取りし、遠隔授業も実践してみた。
「マインドマップ活用授業」
実は前任校でも授業で使ったことがあるのです。うまくいかなかったけど。
「北海道・峰浜小学校とのサケ飼育交流」
東北新社さんが取材してくれました。
ここに出したのは氷山の一角で、まだまだ実践はあるのですが、これだけやれば「燃え尽きた感」も若干あるのですね。「もういいでしょう。私を解放してください」と。そこで「異動」することにしたのです。
今、反省してみると、この時点で私の潜在意識には「もう辰巳ジャンプはこれ以上のチームにはできないかもしれない」という実感が深く沈んでいたように思えます。
これを打破するまで1年半かかりました。チーム練習もあまりできず、最も低迷していた時に、時間があるのでマインドマップを勉強してみたわけです。本気でマインドマップに取り組んでいくと、自分自身がグーグルのようになり、自分にとって必要な情報が自分のアンテナに次々と引っかかってくるようになりました。そのひとつが「ルー・タイス講演会」でした。
辰巳ジャンプ解散の危機を打破したきっかけは、ルー・タイス氏の話を直接聞けたことでした。「スコトーマ(盲点)」を意識すること、ビジョンを持って取り組むことの意味などを教えてもらえました。それを元にして自分の潜在意識を変える努力をした結果、チームは甦りました。
そのことを書いた2009年10月5日の日記を再掲載します。
ホールブレインバレーボール理論 「アファメーションで潜在意識に刷り込む」
辰巳ジャンプは最近の1年間で部員が急増しました。12名いる部員のうち10名はこの1年以内に入部してくれた子ども達です。そして私の中にあるイメージによると、部員はまだまだ増えていきます。
いったい何をしたのでしょうか???
実は2年半前、私は現任校に異動し、「辰巳ジャンプももう終わりかな。」と感じていました。さらに1年半前には、「もう辰巳ジャンプを解散して、バレーボール指導者から引退するべきかな・・・」ともまで思っていました。
この潜在意識がチームをボロボロにしていたのです。
昨年の11月、私は自分自身に対して、「アファメーション」という手法を試みました。辰巳ジャンプというチームの将来像(ビジョン)を明らかにし、私自身の潜在意識にある「あきらめの心」に終止符を打ったのです。
そして出てきたのが、こんなアファメーションです。
「辰巳ジャンプは必ず復活を遂げる。2009年5月、部員が20人を超え、体育館には子ども達の声が鳴り響いている。2010年1月、部員が30人を超え、各学年で1チーム作ることのできるチームである。」
大切なことは、現在形の強い言葉で肯定的な宣言をし、それを紙に書いておくことです。宣言を毎日読むことで潜在意識にイメージを定着させていきます。
さらにこのブログ内でも何回もアファメーション文を載せるようにしてきました。
辰巳ジャンプは組織体ですから、私が「辰巳ジャンプの復活」を宣言すれば、チーム全体がその方角に自動操縦されます。
「アファメーション」というのは、本当に力強く自らを高めてくれる手段です。
今回の記事で私が何気なく書いていること、「ユングの心理学」や「アドラー心理学」にも通じる面がありますので、ぜひ研究してみてくださいませ。
読んでいただきありがとうございます。
できましたら応援の1クリックをお願い致します。
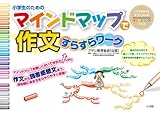 | マインドマップで作文すらすらワーク (ドラゼミ・ドラネットブックス) |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |