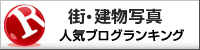前回の続きです。
今回は本丸(主郭)の西側です。
下図⑯にある「さざれ石」です。
「君が代」の歌詞にあるために、
どこの神社にもある「さざれ石」
です。
4トンの重さがあり、亀石と宮司
が命名したそうで、各地の神社に
ある「さざれ石」の中でも最大に
近い大きさです。
「さざれ石」の解説板です。
さざれ石(細石)は小石のことで、
それが合体して「巌(いわお)と
なったさざれ石」をさざれ石と言
います。
学術的には石灰岩が雨水で溶解し、
小石がコンクリート状に凝結して
固まってできたものです。
ボケてますが、このような
イベントポスターもありました。
マラソン大会が一昨日終わって
います。
⑰付近に行くと
左側の甲陽武能殿に行くと
甲陽武能殿です。
ここで能などののイベントが
出来ますね。
上図⑱の名水の方に行くと
⑱にある「姫の井戸」です。
信玄公の娘誕生のときに、
産湯に使用したことから
「姫の井戸」と言われま
す。また「茶の湯の井戸」
とも言われ、茶会の時に
使用されたようです。
解説板です。
戦国時代の本丸配置想像図です。
姫の井戸を拡大した所です。
龍の口から水が出ているようで
す。
手水舎の手水鉢に花を浮かべた
ものが花手水(はなちょうず)
と呼ばれています。
コロナ禍になってから感染拡大
防止の観点から手水舎で手を洗
えない代わりに、目で見て心を
清めてもらうのを目的に、利用
者のいない手水舎に、花を飾る
花手水を設置する神社やお寺が
増えています。
飲用出来る水ですが、
コロナ下なので柄杓を撤去しています。
姫の井戸の向かい側には
武田水琴窟がります。
江戸時代後期に水琴窟が
考案されたようで、武田
式というのは菱紋がある
からでしょう。
⑱附近にはにわとり小屋もあります。
高天原に天照大神という太陽のような
神様がいました。
彼女には乱暴者で名高い弟の須佐之男
命がいました。諫めても反省の気配も
ない弟に手を焼き、彼女は天の岩戸に
引きこもってしまったのです。
すると、たちまち国中が真っ暗闇にな
りました。
これには神様たちも困り果て、岩戸の
前に集まると歌や踊りではやし立てま
した。そして朝が来た合図にニワトリ
達にコケッコー、コケコッコーと次々
と鳴かせたのです。
外が賑やかで、時を告げるニワトリま
でも盛んに鳴き続けています。不審に
思った天照大神が重い岩戸を少し開け
て覗きました、すると力持ちの神様が
岩戸を開けたそうです。
ということで、にわとりのいる神社が
あります。
⑲から⑳方向は
⑳の方に歩くと
江戸時代に築かれた天守台
があります。
下図から戦国時代は信玄の
子供屋敷があった所ですね。
今回はここまでで、次回に続く
読者募集中、読者登録はここのリンクです。
希望で読者(フォロアー)相互登録します。
2日後午後8時半~9時頃に更新しています。
登録では「相手わかるように」に設定して
読者登録してください。
読者様のブログはたまに拝見に行き、
「いいね」やブログ村・ブログラン
キングは出来るだけ押します。
Ctrlキーを押したままで、下の
ボタンを押すと画面飛びしません。
が飛ばされません。 お手数ですが、
よろしくお願いします。
![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ
ポチお願いします。