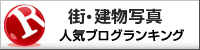今日は櫻井神社の紹介です。
大阪府堺市南区片蔵にある神社です。延喜式神名帳に記載され、
国宝に指定された割拝殿があります。
伝承によると、この地方に住居していた桜井朝臣の一族が、その
祖先である武内宿禰命を奉斎したと伝わります。推古天皇597年
に八幡宮を合祀、応神天皇、仲哀天皇、神功皇后を奉斎していま
す。上神谷八幡宮(にわだにはちまんぐう)とも言われます。
鳥居が無く、お寺のような山門があります。
合祀された八幡宮には鳥居があります。
右上に桜井神社があり、左下に池田恒興の祖先 (グーグルより引用)
池田氏発祥の地である池田郷があります。
門をくぐると
左側に社務所と手洗舎があります。
右側には絵馬堂があります。
神輿の倉庫です。
これが桜井神社の国宝拝殿です。
この拝殿は建築様式やその技法から鎌倉時代中期に建てられたと考えられる建物で、
現存する拝殿建築のなかでも最も古いものです。鎌倉時代に郷村が成立すると、そこ
には郷村の神社・お寺が祀られました、ここ上神谷郷でも古くからあったこの神社を祀
り、郷内団結の証となったと考えられます。稲の収穫後毎年10月の5日に近い日曜日
に奉納される「上神谷のこおどり」は国選択・府無形文化財となっています。
現在の拝殿は中央に通り抜けの通路を持つ割拝殿形式の建物ですが、祭礼時には、
通路の両脇の蔀戸(しとみど)という建具を降ろして、床にすることができるように工夫
されています。通路に面した柱には長方形の穴の跡があり、建設当時は通路の部分も
板敷の部屋であったようです。
正面から妻側にまわると、梁の間にはかえるの足のような形をした蟇股(かえるまた)
という部材があります。この形が簡単な板状のものであることや、梁の両端に彫刻がも
ちいられていないことなどは、鎌倉時代の建物の特徴です。内部も天井板が貼られて
いないので、妻側の構造技法と同様な梁や蟇股で建物が組み立てられていることがわ
かります。
堺市内では唯一の国宝であり、天正5年(1577年)には、織田信長の根来攻めのた
め、拝殿を残してすべて焼失しましたが再建されています。
今日は此処までです。明日は堺市立みはら歴史博物館の紹介です。
読者募集中ですので、読者登録はここのリンクです。
希望があれば、相互登録します。相互アメンバーも募集中です。
「相手わかるように」に設定して登録してください。
読者のブログ村・ブログランキングを出来るだけ押しに行きます。
Ctrlキーを押したままで、ポチしたら画面が飛ばされません。
お手数ですが、よろしく。![]()
![]() ぽちっと
ぽちっと![]()
![]() 押すだけ
押すだけ

</