今回は、ヨハン・ネポムク・フンメルの「マンドリン協奏曲 ト長調」のDTM打ち込み音源をご紹介します。
この曲は、数あるマンドリンのための楽曲の中でも最高傑作と名高く、軽やかで美しいメロディに満ち溢れています。しかし、その楽譜は長らく失われ、「幻の協奏曲」と呼ばれていました。
作曲の背景:若き天才ピアニストとマンドリンの名手
この協奏曲は、フンメルが21歳だった1799年頃、ウィーンで作曲されたと言われています。当時のフンメルは、モーツァルトの弟子としても知られ、超絶技巧を誇るピアニストとしてヨーロッパ中にその名を轟かせていました。
そんな彼がなぜマンドリンの協奏曲を? その理由は、当時のマンドリンの名手、バルトロメオ・ボルトラッツィとの出会いにありました。フンメルはボルトラッツィの卓越した演奏技術に触発され、彼の妙技を最大限に引き出すべく、この協奏曲を書き下ろしたのです。マンドリンの可憐で繊細な音色と、フンメル得意の流麗で華やかな旋律が見事に融合した作品です。
一度は失われた「幻の協奏曲」
しかし、この名曲は完成後、いつしか楽譜が失われ、100年以上にわたって演奏されることのない「幻の作品」となってしまいました。その楽譜が再び日の目を見たのは20世紀に入ってからのこと。大英博物館で発見され、ようやく現代の私たちがその響きを聴けるようになったのです。
フンメルは撥弦楽器にも詳しかった?
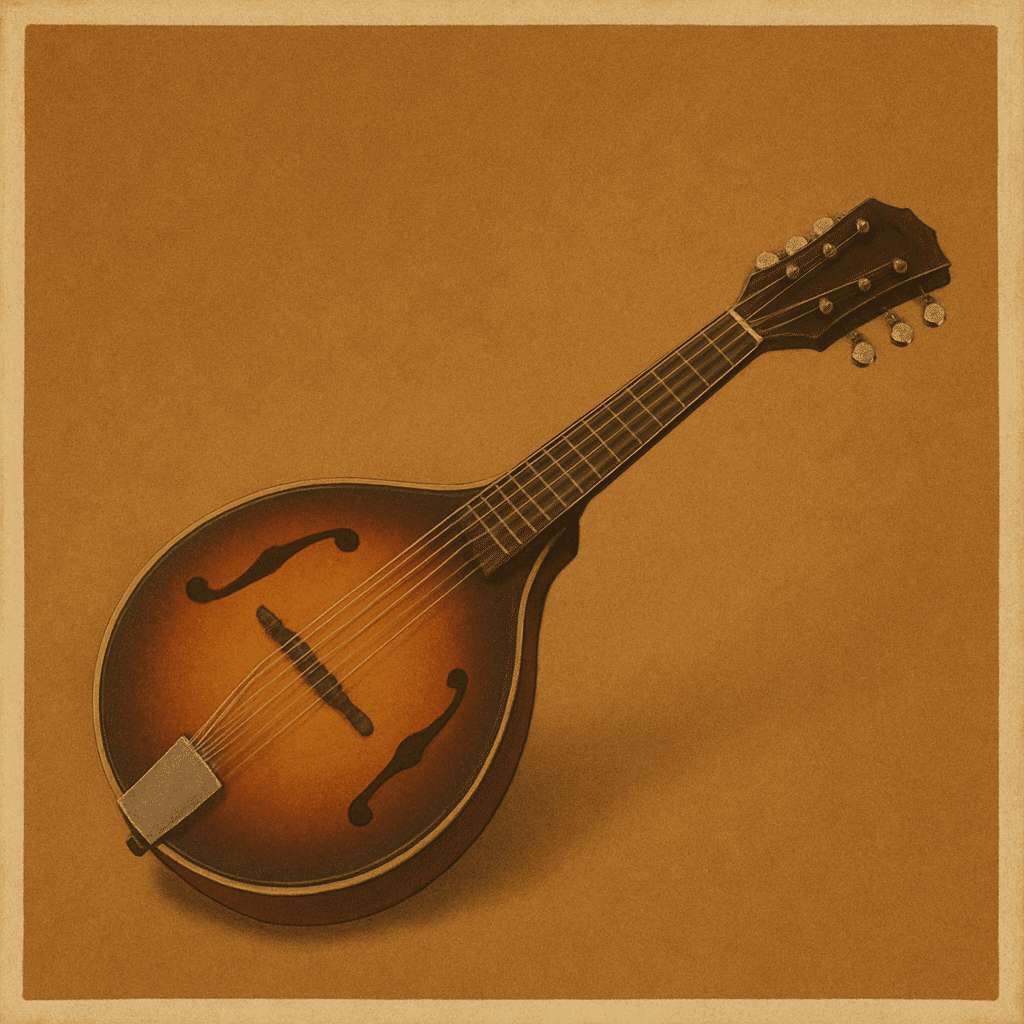
実は当時、マンドリンのための曲は、その楽器の演奏家自身が作ることがほとんどでした。フンメルの師であるモーツァルト(オペラ『ドン・ジョヴァンニ』など)や、ベートーヴェンもマンドリンを用いた小品を残していますが、協奏曲という本格的な形式で書いたのはフンメルだけです。
フンメルはピアノだけでなく、ギターやマンドリンといった撥弦楽器にも深い理解を持っており、他にもマンドリン・ソナタやギターを含む室内楽曲を残しています。その中でもこの協奏曲は、彼の作品群、ひいてはクラシック音楽全体における撥弦楽器のレパートリーとして、極めて重要な位置を占めています。
残念ながら、この曲の正確な初演記録は残っていません。しかし、名手ボルトラッツィのために書かれたという経緯から、彼自身によって初演された可能性が非常に高いと考えられています。 (参考: Repertoire and Opera Explorer, Encyclopadia Britannica)
オーケストラ編成は、独奏マンドリン、フルート 2本、ホルン 2本、弦楽合奏となっており、これは、マンドリンの繊細な音色がオーケストラに埋もれてしまわないように、というフンメルの巧みな配慮の表れです。
各楽章の聴きどころ
この協奏曲は、急-緩-急の伝統的な3楽章形式で書かれています。
-
第1楽章: Allegro moderato e grazioso (アレグロ・モデラート・エ・グラツィオーソ)
優雅なオーケストラの序奏で幕を開けます。続いて登場する独奏マンドリンは、かき鳴らすような奏法ではなく、細かな音を連続させるトレモロや、素早い音階で超絶技巧を披露します。特に、16分音符や3連符が目まぐるしく交錯する部分は、まるで宝石がキラキラと転がるような華やかさです。 -
第2楽章: Andante con variazioni (アンダンテ・コン・ヴァリアツィオーニ)
「変奏曲付きのアンダンテ」という意味の通り、マンドリンが奏でる牧歌的で美しい主題が、様々な形に姿を変えていく楽章です。技巧的な変奏の合間に、どこか哀愁を帯びた短調の舞曲風のメロディが現れる部分が非常に印象的です。 -
第3楽章: Rondo: Allegro (ロンド:アレグロ)
軽快な6/8拍子のロンド形式で、心が弾むような楽しいフィナーレです。主題が何度も繰り返し現れる中で、マンドリンが軽やかに駆け巡ります。フンメルが数年後に作曲したマンドリン・ソナタの終楽章にも通じる、陽気で祝祭的な雰囲気に満ちています。
もう一つの顔:ピアノ協奏曲 Op.73への編曲
この協奏曲には、実はもう一つの姿があります。フンメルは1816年頃、この曲を自身の最も得意とするピアノのための協奏曲(作品73)に編曲し直しているのです。
これは単なる楽器の置き換えではありません。マンドリンの技巧的なパッセージは、ピアノならではの華やかなアルペジオやオクターヴ奏法に書き換えられ、より壮大でヴィルトゥオーゾ的な作品に生まれ変わっています。マンドリン版と聴き比べてみると、同じメロディが楽器の特性に合わせてどうアレンジされているかが分かり、非常に興味深いです。
おすすめのCD
この協奏曲は多くの名演がありますが、特におすすめしたいのが、**アリソン・スティーブンス(Alison Stephens)**がマンドリンを、**ハワード・シェリー(Howard Shelley)**がロンドン・モーツァルト・プレイヤーズを指揮した2001年の録音(Chandos盤)です。マンドリンの粒立ちの良い美しい音色と、古典派音楽を得意とするシェリーの的確なサポートが見事な名盤です。
映像内の譜面について
今回お聴きいただく音源は、私自身が打ち込みで制作したものですが、動画内に表示される楽譜は、楽譜作成ソフトDorico 5の再生画面です。正確な記譜よりも、MIDIデータとしての入力と、強弱やテンポの揺れといった音楽表現を優先して制作しているため、実際の楽譜とは異なる部分があることをご了承ください。
【制作環境】
-
曲名: マンドリン協奏曲 ト長調 S.28 (Mandolin Concerto in G, S.28)
-
作曲者: J.N.フンメル (Johann Nepomuk Hummel)
-
制作: Hummel Note
-
DAW/シーケンサー: Dorico 5,
-
マスタリング: Singer Song Writer
-
使用音源: Note Performer 5
-
サムネイルと動画作成: CyberLink PowerDirector
