11月14日はフンメルの命日です。
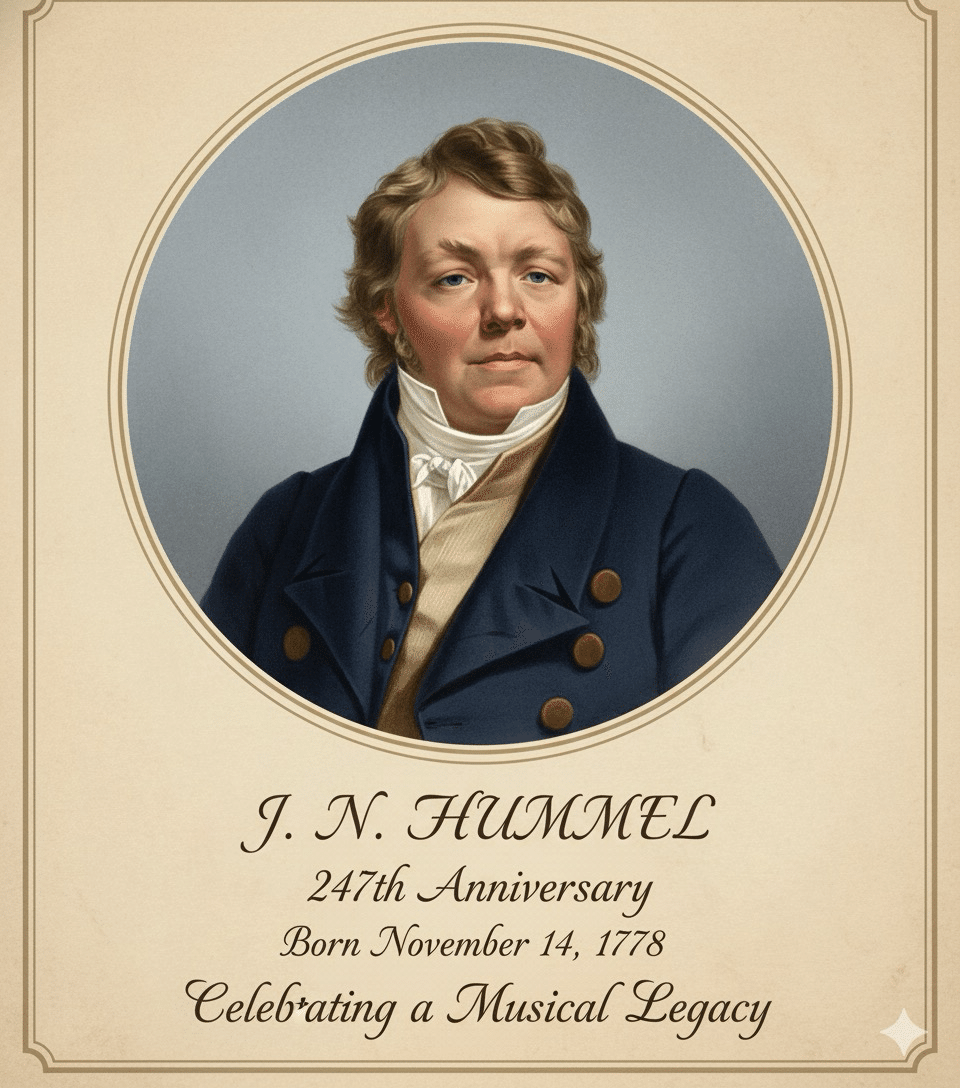
ヨハン・ネポムク・フンメル(Johann Nepomuk Hummel, 1778-1837)の弦楽四重奏曲 Op.30は、全3曲からなる作品群で一般的に1804年頃、フンメルがハイドンの後任としてエステルハージ家の宮廷楽長(Konzertmeister)を務めていた時期に作曲されたとされています。ベートーヴェンのパトロンとしても知られるロプコヴィッツ公に献呈されました。
音楽的特徴
フンメルはモーツァルトの弟子であり、ベートーヴェンとは同時代にウィーンで活躍したライバルでした。このOp.30の四重奏曲群は、ベートーヴェンがOp.18で示した革新的な(あるいは古典派の枠組みを壊そうとする)アプローチとは対照的です。
フンメルはむしろ、師であるモーツァルトやハイドンによって確立されたウィーン古典派の様式を基礎とし、その上で洗練された旋律と華麗な技巧を盛り込むアプローチをとっています。全体として、非常に流麗で、耳に心地よい響きと均整の取れた形式美を持っていますが、同時に演奏(特に第1ヴァイオリン)には高度な技術が要求されます。
この変ホ長調の四重奏曲は、古典的な4楽章形式で構成されていますが、第3楽章に大きな特徴があります。
第1楽章: Allegro con spirito 力強い2つの和音で劇的に始まります。その後、ソナタ形式に沿って展開されますが、第1主題は半音階的でしなやかな旋律を持ち、続く第2主題は非常にハイドンを彷彿とさせる明朗快活なものです。モーツァルトがハイドンに捧げた「ハイドン・セット」や、ハイドン自身の後期の四重奏曲(Op.76など)の影響が色濃く感じられる、充実した楽章です。
第2楽章: Andante 歌謡的(カンタービレ)な美しい緩徐楽章です。旋律の扱いには、モーツァルトの「不協和音」四重奏曲の緩徐楽章に見られるような、バロック音楽の対位法的な書法を思わせる緻密さがあります。
第3楽章: Allemande e alternativo この曲集の最も独創的な楽章です。フンメルは、伝統的なメヌエットやスケルツォの代わりに、バロック時代に遡るドイツの舞曲「アルマンド」を採用しました。 ここで奏されるアルマンドは、優雅な舞曲というよりも、力強く推進力のある、足を踏み鳴らすような(ある解説では「重く、力強い」と評される)非常に個性的な音楽です。中間部(Alternativo)も、アルマンドとは異なる、より軽快で速いテンポのドイツ舞曲が用いられています。
第4楽章: Finale: Presto 6/8拍子の、非常に速くエキサイティングなフィナーレです。「狩り」や「障害物競走(steeple chase)」にも例えられるほどの疾走感を持ち、聴き手を熱狂のうちに終結へと導きます。この種の急速なフィナーレは、後にシューベルトの作品で頻繁に見られるスタイルを先取りしているとも言われています。
これでOp.30の3つの弦楽四重奏の打ち込みは終わりましたので、後日改めてフンメルが残したこの唯一の弦楽四重奏集の記事を書こうと思ってます。
