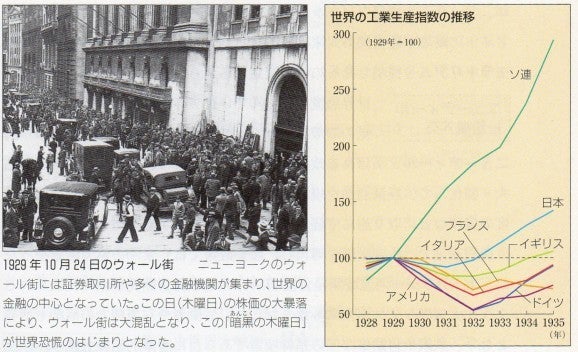1928(昭和3)年の「第9回近代オリンピック=アムステルダムオリンピック」は、
陸上・三段跳びの織田幹雄、水泳・男子200m平泳ぎで鶴田義行が、共に「金メダル」を獲得し、日本人初の、オリンピックの「金メダリスト」となった。
また、陸上の女子800mで、人見絹枝が「銀メダル」を獲得し、日本人の女子選手として初のメダリストとなった。
このように、1928(昭和3)年の「アムステルダムオリンピック」は、
日本人選手の大活躍が目立ち、日本のスポーツ界の躍進を示したが、
その頃、世界情勢は激動の時代であり、日本も「昭和」の時代が幕を開け、不穏な状況であった。
というわけで、今回は1932(昭和7)年の「第10回近代オリンピック=ロサンゼルスオリンピック」と、そこに至るまでの世界や日本の状況などを描く。
今回は、その「前編」として、1931(昭和6)年の「満州事変」前夜までを書いてみる事としたい。
それでは、ご覧頂こう。
<「国際強調」の時代①~1919(大正8)年の「ヴェルサイユ条約」⇒1920(大正9)年の「国際連盟」発足⇒1922(大正10)年「ワシントン海軍軍縮条約」締結>
オリンピックは「平和の祭典」という理念を掲げているが、
「第1次世界大戦」(1914~1918年)という、悲惨な大戦争を経験したヨーロッパ各国は、
「もう戦争は懲り懲りだ」
という気持ちが強かった。
そこで、「第1次世界大戦」終結のために締結された、1919(大正8)年の「ヴェルサイユ条約」により、「国際協調」が謳われたが、この「ヴェルサイユ体制」とは、簡単に言えば「ドイツを、二度と戦争させない国にする事」が、その大きな目的であった。
そのため、ドイツの再軍備禁止や、ドイツへの多額の賠償金の請求など、ドイツにとっては過酷な内容となってしまった。
また、「ヴェルサイユ会議」の際に、アメリカのウィルソン大統領の提唱により、
1920(大正9)年、国際協調機関として、「国際連盟」が設立されたが、
「国際連盟」には、敗戦国ドイツは参加を認められず、社会主義国家のソ連も招かれなかった。
また、言い出しっぺのアメリカも、議会の批准を得られず、不参加になるなど、初めから前途多難なスタートとなった。
一方、日本は英国・フランス・イタリアと共に「国際連盟」の常任理事国となり、「一等国」として認められた。
そして、1922(大正119年には「ワシントン海軍軍縮条約」が締結され、国際社会は「軍縮」の方向に舵を切った。
<「国際協調」の時代②~1928(昭和3)年8月27日…「パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)」調印~後の「日本国憲法」の「平和主義」の元ネタに!?>
1928(昭和3)年8月27日、「アムステルダムオリンピック」が閉幕した直後、
アメリカの国務長官、フランク・ケロッグと、フランスの外相、アスティリード・ブリアンによって提唱された、
「パリ不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)」が、アメリカ・英国・フランス・ドイツ・イタリア・日本など、当時の世界の列強15ヶ国で調印された。
その後、ソ連なども含め、最終的には63ヶ国が調印するという、大規模な「平和条約」に発展した。
「パリ不戦条約」とは、一言で言えば、
「全ての戦争行為は違法であり、国際紛争解決の手段として戦争をする事は禁止する」
という内容の物である。
これは、読んでわかる通り、後の「日本国憲法」の「平和主義」の理念の「元ネタ」となった。
勿論、この理想どおりに行くのが一番良いのであるが、「世界平和」というのは、残念ながら、各国のパワーパランスに大きく左右されてしまうというのも、また現実である。
果たして、この先、「パリ不戦条約」の理想どおりに、また「オリンピック」が掲げる通り、「世界平和」は実現されて行くのであろうか。
<1929(昭和4)年10月24日…アメリカのニューヨーク証券取引所(ウォール街)で株価が一斉に大暴落する「暗黒の木曜日」⇒やがて「世界恐慌」が起こり、世界中の経済状態が破綻~後の「第2次世界大戦」の遠因に>
1929(昭和4)年10月24日、あの「永遠の繁栄」を誇っていたアメリカで、大波乱が起こった。
この日(1929/10/24)、アメリカのニューヨーク証券取引所(ウォール街)で、突如、株価が一斉に大暴落したのである。
降って湧いたような株価の大暴落により、ウォール街は大混乱となったが、これが世界を一変させる事となる、「暗黒の木曜日」である。
当時、アメリカ経済は空前の繁栄を誇っていたが、実際には、人々が争うように、無茶な投機を繰り返し、実体経済とはかけ離れた「バブル経済」だったのである。
それが、とうとう破綻してしまったのであった。
この「暗黒の木曜日」が、所謂「世界恐慌」の引き金となった。
「世界恐慌」は、文字どおり世界中に波及し、世界中の資本主義国家の経済は、メチャクチャになってしまった。
そして、「世界恐慌」により、各国は不況のどん底に陥り、それが「第2次世界大戦」の遠因となったが、その事については後述する。
ともあれ、「暗黒の木曜日」⇒「世界恐慌」により、アメリカの「永遠の繁栄」は、呆気なく終焉し、世界は「冬の時代」に突入した。
<一方、その頃の日本は…?~浜口雄幸首相&井上準之助首相、「緊縮財政」⇒「金解禁」で、「昭和恐慌」&「世界恐慌」のダブルパンチを乗り越えようとするが…?>
では、その頃の日本は、どうだったのかといえば、
大正末期~昭和初期にかけて、東京の街には、お洒落な洋装をした「モダンガール」が闊歩し、
銀座の街でショッピングを楽しむ「銀ブラ」が流行ったりなど、一見、華やかな様相を呈していたが、
一方では、「昭和恐慌」により、食うにも困るような人達も沢山居るような時代であった。
1929(昭和4)年7月、浜口雄幸・首相&井上準之助・蔵相の浜口内閣が成立したが、
この時、「昭和恐慌」に喘いでいた日本に、前述の「世界恐慌」も発生し、日本経済も大打撃を受けた。
浜口首相と井上蔵相は、「昭和恐慌」&「世界恐慌」のダブルパンチを乗り越えるため、
「緊縮財政」を行なう一方、1930(昭和5)年1月に「金解禁」を断行した。
「金解禁」とは、金貨幣または金の輸出禁止を解除する事を言うが、
浜口内閣が金の自由輸出禁止を解除し、「金本位制度」に復帰させた政策を指す。
これは、日本経済を長期的な視野に立って、建て直すような政策であり、一時的には金が流出し、デフレが加速するような「荒療治」だったが、この時は、これが完全に裏目に出てしまい、更に1930(昭和5)年には冷害による大凶作も起きてしまい、日本経済は破綻寸前となった。
つまり、浜口内閣&井上蔵相の経済政策は、完全に大失敗であった。
この時代の日本を象徴する言葉として、
「大学は出たけれど」
という流行語が有る。
小津安二郎監督の映画『大学は出たけれど』は、せっかく大学を卒業したのに、大不況により就職先が見付からず、苦悩する青年を描いた作品であるが、当時の大卒の学生の就職率は30%という、「超氷河期」であり、街には失業者が溢れた。
1929(昭和4)~1930(昭和5)年にかけて、日本は大不況の、酷いどん底の時代であった。
だが、そんな時でも、暢気な「モダンガール」は、まだまだ街には沢山居たようである。
<1929(昭和4)~1931(昭和6)年…「早慶戦黄金時代」が到来~大不況でも、神宮球場は早慶戦の大熱戦に熱狂>
だが、こんな不況のどん底の時代にあっても、神宮球場は「別世界」であった。
1929(昭和4)~1931(昭和6)年頃の東京六大学野球は、人気絶頂を迎えていたが、
中でも、この頃は早稲田と慶応の実力が伯仲し、毎シーズンのように、早稲田と慶応が優勝を争った。
そして、早稲田と慶応が激突する「早慶戦」を見るために、神宮球場には超満員の観客で埋め尽くされ、
早慶両校の学生は勿論、ファンは「早慶戦」に熱狂的な声援を送った。
まさに「早慶戦黄金時代」が到来したのであるが、神宮球場では、「早慶戦」のチケットを求め、徹夜組が出現する程であった。
前回の記事で、1927(昭和2)年に慶応が新応援歌『若き血』を作り、早稲田に勝利したというエピソードを書いたが、
1931(昭和6)年、今度はそれに対抗した早稲田が『紺碧の空』という新応援歌を作り、早稲田が慶応に勝利した。
この『紺碧の空』を作曲したのが、当時、まだ新進気鋭だった頃の作曲家・古関裕而であり、『紺碧の空』は、古関裕而の出世作となった。
『紺碧の空』誕生については、朝ドラ『エール』でも描かれていたが、当時の古関裕而は新婚ホヤホヤであった。
『エール』では、古関裕而(古山裕一=窪田正孝)が、妻・金子(古山音=二階堂ふみ)の励ましにより、苦悩の末に『紺碧の空』を作り出す様子が描かれていたが、大変に見応えが有った。
というわけで、華やかな「早慶戦黄金時代」に、当時の学生やファン達は酔っていたのであるが(※半ば、ヤケクソだったのか?)、
前述の通り、学生達は、せっかく大学を卒業しても、就職先が見付からないという、厳しい現実が有った。
思えば、「早慶戦」というのは、そんな厳しい現実を、ひと時でも忘れられるような、「夢の空間」だったのかもしれない。
いつの時代も、野球場は、ひと時、この世の憂さを晴らせるような「異空間」であり、そこが生で野球を見る醍醐味だと言えよう。
<1930(昭和5)年秋…法政野球部が東京六大学野球で初優勝~法政大学の校歌誕生のシーズンに、法政が悲願の初優勝を達成>
もう一つ、この時期の東京六大学野球の話で、付け加えさせて頂くと、
1930(昭和5)年秋、エース・若林忠志投手を擁する法政が、悲願の初優勝を達成したという事を、特筆させて頂きたい。
名門・法政野球部の記念すべき初優勝であるが、このシーズンは法政大学の校歌(作詞:佐藤春夫、作曲:近衛秀麿)が誕生したという事も有り、法政大学の歴史上、非常に重要なシーズンとなった。
<1930(昭和5)年…「ロンドン海軍軍縮条約」と「統帥権干犯」問題とは!?~浜口雄幸首相、狙撃で重傷を受け、退陣に追い込まれる>
さて、1929(昭和4)年の「世界恐慌」の発生により、世界中が大不況に苦しむ中、
世界各国の間では「軍縮」「国際協調」の流れが堅持されており、
1930(昭和5)年に、改めて「ロンドン海軍軍縮条約」が締結される事となった。
1922(大正11)年の「ワシントン海軍軍縮条約」では、各国の主力艦の保有量が規定されたが、
補助艦の保有量については、「先送り」になっていたため、改めて「ロンドン海軍軍縮条約」で、補助艦の保有量が定められる事となっていた。
当時の浜口雄幸首相の内閣は、「協調外交」を基本とする、幣原喜重郎が外相を務めていた事もあろ、「ロンドン海軍軍縮条約」に賛成の立場であった。
だが、浜口内閣を構成する、与党の「民政党」に対し、野党の「立憲政友会」は、条約には反対の立場を表明した。
また、海軍省は条約に賛成だったが、これに猛然と反対を唱えたのが、海軍軍令部である。
つまり、当時の政府と軍部(海軍)は、条約賛成と反対に、真っ二つに分かれていた。
結局、「ロンドン海軍軍縮条約」は、1930(昭和5)年1月に、締結されてしまった。
だが、海軍軍令部は、政府に対し、こう言って猛反発した。
「海軍軍令部は反対したまま、条約したのは、統帥権干犯ではないか!?」
海軍側は、突如、「統帥権干犯」なる言葉を持ち出し、政府を攻撃したのである。
それは、つまりどういう事なのかといえば、当時の大日本帝国憲法では、軍部は政府の下でコントロールされているのではなく、
直接、天皇の「統帥権」によって管轄されているのだから、政府が軍部の反対を押し切るのは、その「統帥権」を犯している、
つまり、「政府は、天皇陛下の直接の管轄にある、軍部のやる事には、口出し出来ない筈である」というのが、軍部側の理屈であった。
要するに、当時の憲法では、軍部は政府の管轄になく、「文民統制」の体制ではなかったわけだ。
その後、1930(昭和5)年11月14日、浜口首相は東京駅でテロリストに狙撃され、
危うく一命は取り留めたものの、これが原因で退陣に追い込まれた。
前述の「統帥権干犯」問題で、軍部の突き上げを受け、心労が重なっていた上に、更に追い打ちをかけられた形である。
この後、軍部は何かと言えば「統帥権干犯」を持ち出し、
「軍部のやる事に、いちいち口を出すな」
と言わんばかりの、「暴走」を繰り返して行くのだが、後から思えば、これが「昭和史」の大きな分岐点となった。
政府が、軍部をコントロール出来なければ、軍部がどんどん暴走して行くのは、当然である(※今の「コロナ禍」で、政府が「分科会」をコントロール出来ず、「分科会」が暴走している状況と似ていると言ったら、言い過ぎだろうか)。
また、昭和天皇も、あの「張作霖爆殺事件」以来、内閣の上奏には全て裁可を与えると既に決意してしまっていた。
つまり、軍部が暴走すれば、それを止める者は誰も居なくなってしまうという体制が、出来上がった。
この時、日本は非常に危険な道へと、一歩、足を踏み入れたのである。
<「昭和」初期の「エロ・グロ・ナンセンス」と江戸川乱歩~不穏な時代に、退廃的な文化が花開く>
「昭和」初期、日本が少しずつ不穏な空気に包まれて行く頃、
日本では「エロ・グロ・ナンセンス」と称される、退廃的な文化が花開いていた。
「エロ・グロ・ナンセンス」とは、「エロ(エロティック、煽情的)、グロ(グロテスク、怪奇的)、ナンセンス(ばかばかしい)」を合わせた語であり、
昭和初期の日本文化を端的に表した言葉である。
そして、「エロ・グロ・ナンセンス」の時代を象徴していた作家が、江戸川乱歩である。
名探偵・明智小五郎を主人公とする、一連の作品は、耽美的で妖しい世界観であり、一度読んだから癖になる、奇妙な魅力が有った。
江戸川乱歩は、土蔵を改造して、そこを住処にして、真っ暗な土蔵で一日中、籠もって作品を書いているような、変わった人だったらしいが、そういう所も、乱歩の作品の、何とも言えない魅力の元になっていたのかもしれない。
というわけで、政治が乱れ、国が不穏な雰囲気になった時こそ、
文化は爛熟し、退廃的な文化が生まれるというのは、いつの世も同じである。
国の全盛期を過ぎ、国が下り坂になった時にこそ、文化は栄えるものだというが、
「エロ・グロ・ナンセンス」も、まさにそんな感じである(※この頃、「モダンガール」も、まだまだ元気だった)。
人々は、退廃的な文化で「現実逃避」し、浮世の憂さを忘れていたかったのであろうか。
<その頃、ドイツは…?~ヒトラー率いるナチスが、1930(昭和5)年9月の選挙で「107議席」を獲得し、ナチスは「第2党」に躍進~しかし、ヒトラーは銘(腹違いの姉の娘)のゲリの自殺に、大きなショックを受ける>
さてさて、日本が「ロンドン海軍軍縮条約」を巡り、「統帥権干犯」問題で大揺れになっていた頃、
ドイツでは、アドルフ・ヒトラー率いるナチスが、快進撃を見せていた。
ナチスは、それまでの常識を覆すような、大胆な選挙戦術を取っていたが、
例えば、ナチスのポスターやビラを大量にばら撒いたり、ヒトラーが飛行機を使って、ドイツ全土で精力的に演説を行なったり、
当時はまだ新しいメディアだったラジオを使って、ナチスの宣伝を行なったりと、
とにかく、ありとあらゆる手段を使い、大衆の心を掴んで行った。
その結果、1930(昭和5)年のドイツの国会選挙で、ナチスは「107議席」を獲得し、「第2党」へと大躍進した。
だが、この時、ヒトラーは大きな落とし穴に落ちてしまった。
当時、ヒトラーには腹違いの姉の娘で、ゲリという名前の姪が居たが、
ヒトラーは、ゲリの事を溺愛しており、ヒトラーは、ゲリに男が近付かないよう、終始、監視している程であった。
この事は、水木しげるの『劇画ヒットラー』でも描かれているが、
とにかく、ヒトラーはゲリに異様に執着しており、ゲリを手元から離そうとはしなかった。
ゲリは、歌手志望であり、音楽の勉強のために、ウィーンに行きたいと訴えていたが、ヒトラーは、それも許さなかった。
こうして、次第に精神的に追い詰められて行ったゲリは、1931(昭和6)年9月18日、遂に自ら命を絶った。
ゲリは、享年23歳という若さだったが、ヒトラーは愛する姪の自殺に、大きなショックを受け、一時は精神的に錯乱し、ヒトラーも自殺を考える程まで落ち込んでしまった。
ヒトラーは、長い間、精神的な打撃から立ち直る事が出来なかったが、政権獲得間近に思われたナチスも、このため、一時的に活動が停滞してしまうのである。
<その頃、ソ連は…?~「社会主義国家」のソ連は「世界恐慌」の影響も受けず、「第1次5ヵ年計画」に邁進>
では、その頃のソ連はどういう状況だったのかといえば、
ソ連は「社会主義国家」だったので、そもそも「世界恐慌」の影響も全く受けなかった。
この頃、ソ連は既にスターリンの独裁体制が確立されており、
スターリンは「社会主義国家」完成を目指し、1928(昭和3)~1932(昭和7)年に「第1次5ヵ年計画」を押し進めた。
スターリン率いるソ連は、「コルホーズ」(集団農場)、「ソフホーズ」(国営農場)を全国に作り、
農業の集団化を進め、国家主導で工業化を推進したが、その成果が出て、ソ連は飛躍的に国力を伸ばした。
だが、スターリンは、この政策に反対する勢力を徹底的に弾圧・粛清し、逆らう者は皆殺しにしていた。
また、1930年代の初めには大飢饉が発生したが、ソ連は飢餓に苦しむ農民に救いの手を差し伸べず、あくまでもノルマ達成を求め、過酷な収奪を繰り返した。そのため、夥しい数の農民がバタバタと死んで行った。
ソ連は、全く自由の無い、恐ろしい体制であり、膨大な数の人々の犠牲の上に成り立っていた。
だが、当時は、ソ連のそのような実態は、外部には一切秘密にされ、「社会主義国家・ソ連=理想の国家」と思われていたというのだから、恐ろしい。
世界中の人々が、ソ連と言う国の恐ろしい実態を知るようになるのは、まだまだ先の話である。
<日本にとって「満州」(中国東北部)とは!?>
さて、いよいよ日本と「満州」の関わりについて書く。
日本は「日露戦争」に勝利した結果、中国東北部、所謂「満州」の権益を得た。
この満州について、当時の日本は、どのような考え方を持っていたのかといえば、概ね、次の3つに大別されるという。
①ロシア(※後のソ連)が、諸権利を奪い返しに、再び南下して来る恐れが有るため、「満州」をロシアからの国防のための最大の「防衛線」=「生命線」とする必要が有る。⇒1919(大正8)年以降、「満州」防衛のため「関東軍」が駐屯。
②資源の乏しい日本の、新たな資源の供給元にするため⇒それまで、専らアメリカ・英国から資源の輸入を行なっていた日本が、「満州」で大量の鉄た石炭を得る(※しかし、石油は発見されず)。
③人口が急増した日本の、新たな「移民先」としての役割を果たす。
…という事で、いずれも、日本が欧米列強に肩を並べ、世界の一等国になって行くためには、
「満州」は、重要な位置を占めて行く事となったが、とは言っても、あくまでも「満州」は中国の一部であり、
日本は「満州」の権益を優先的に得ていたに過ぎない。
だが、この「満州」を、日本が領有すべきであるという考え方が生まれるようになった。
<天才軍人・石原莞爾の「満蒙問題私見」⇒「世界最終戦論」とは!?~「日本が満州・蒙古(モンゴル)を領有し、来るべきアメリカとの『世界最終戦』に備える」という、遠大な計画>
この頃、陸軍に石原莞爾という、天才的軍人が現れた。
石原莞爾は、陸軍士官学校では、超優等生であり、「陸軍に石原あり」と言われた程の、傑物だったという。
その石原莞爾が、1931(昭和6)年5月、「満蒙問題私見」を発表したが、その概要は、下記の通りである。
「日本は、いつかはアメリカと戦う時が来るであろう。それは持久戦になるが、対米持久戦に勝つためには、中国の4臆の民衆に経済的新生命を与え(※助けてやって)、これによって日本の商工業を振興し、なるべく速やかに、欧米列強に対し、日本の工業の独立を達成する。そのためには、満蒙(満州・蒙古(モンゴル))の領有が、不可欠である」
更に、石原莞爾は、「世界最終戦論」を発表し、次のような構想を述べている。
「第1次世界大戦後、ともかく世界に平和が戻ったが、列強は、いずれまた次の世界戦争を始める。色々な組み合わせの下に戦って行く内に、最後にソ連、アメリカ、日本が残る。最終戦を前に、日本は戦わずして、じっと国力と戦力を整えていれば、準決勝でアメリカがソ連を破り、決勝戦では日本とアメリカが戦う。これが、『世界最終戦争』となるが、それは1970年代ぐらいであろう」
いやはや、何とも遠大な計画であるが、石原莞爾がこれを発表したのが、1931(昭和6)年頃なのだから、
彼は、遥か遠い未来まで見越して、日本は戦力と国力を整え、アメリカとの最終決戦に備えよ、と言っていたのであった。
実際には、日本は決勝まで進めず、もっと前で負けてしまったが、最終的にはアメリカとソ連が戦ったのだから、
石原莞爾の予想も、あながち大ハズレとは言えまい。
というわけで、石原莞爾の遠大な構想に基づき、
「関東軍」は、いよいよ「満州」を領有するための行動を開始しようとしていた。
1931(昭和6)年、「満州事変」前夜を迎えていたが、この後の話については、また次回。
(つづく)