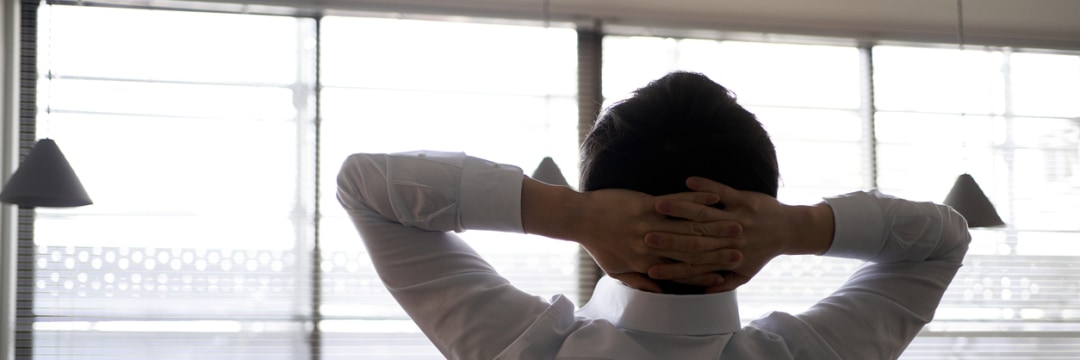こんにちは、凸凹君のママです。
4月2日は国連が定める「世界自閉症啓発デー」だったそうですね(過去形)。
そして4月2日~8日は厚生労働省が定める「発達障害啓発週間」なのだそうです。
ネットもいつにもまして発達障害関係の記事が多いような気がしたのはこれの影響かしら。


その中で気になったのがこの一連の記事。
ASD、特にアスペルガー症候群を取り上げています。
内容に特に目新しいことはないのですが(笑)、繰り返し書かれるということは、興味をひきやすい共感を得られる話題であり、そして未だ解決されていない問題ということなのだと思います。
記事の続きには問題を軽減するための一助となりそうな内容もありました。
この中で、発達障害者本人が身に付けるべきスキルとして、次の2つが挙げられています。
- 自分の特性を、第三者目線で語れるようにしておく
- ごめんなさい、ありがとうを言えるようにしておく
これは就労に限らず、本当に大事なことですね。
私も、1つ目は年齢に応じた内容で、2つ目は本当に小さいころから凸凹君に言い聞かせてきました。
前述の記事に「何度説明しても彼(障害者雇用の人、アスペ+ADHD)とは意思の疎通が図れず、それどころかこちら(指導係)が責められる」という記述があります。
状況が目に浮かぶようです(笑)
私の個人的な経験からの考えですが、ASDの場合は特に、定型の人が定型の人に伝えるのと同じ伝え方では、何度伝えても正しく伝わらないのが原因だと思います。
では指導係が悪いのかというとそうではなくて、(このケースの場合は障害者雇用枠ですし)適切な伝え方を知っている人を指導係にしなかった組織の問題ですよね。
また、発達障害の人の方にも上の2つの大事なスキルが身についていなかったという問題もあります。
発達障害者側が指導を受け入れることができる状態であることも必要不可欠だと思います。その上で、発達障害に関する知識を持っている(または経験から身についている)人を指導係にするか、少なくともサポート(通訳)として置かないと、うまくいかないのではないでしょうか。
経験のある人にはわかってもらえるのではないかと思いますが、ガチのアスペルガーの人と普通に会話しようとすると「日本語で会話しているのに日本語が通じない」という、なんとも言えない不思議な感覚に見舞われます。
なまじ同じ日本語を使っている同士だからこそ、言葉は通じる・会話は成立する(=説明すればわかる)と思ってしまうのが困りもので、これが日本語話者対外国語話者なら迷わず通訳を入れるケースでしょう。
双方から可能な限り近づくのはもちろん大事ですが、それでもだめなら中継者を介してようやく成立するキャッチボールなんだと思います。
以前書いた↑の職場では、特性のある本人が高い専門的スキルを有していたこともありますが、やはり自然に通訳やサポートをやっている人がいました。
私は日常的に、発達障害者同士の「暴投だらけのキャッチボール(できてない)」を目にする機会があります(笑)
私の身近な発達障害者にはそれを気にしない(気づかない)タイプと自分の言いたいことが伝わらないとイライラするタイプがいるので、前者同士の場合には基本的に生暖かく見守り、後者がいる場合や大事な話の場合には中継(通訳)に入るようにしています。
これを見ていると、発達障害者の就労には本人にも周囲にも大変な苦労があることは否めません。
それを少しでも軽減できたらと、凸凹君には小さいころから色々と教えてきました。
凸凹君に何かを教える・注意をするときは、きちんと理由を含めて説明するようにしています。
ASDは事実や理屈に基づいた行動をとる傾向があるので、感覚的・自動的には身につかなくても、本人が分かる説明をすれば頭では理解してくれます。
それが行動に反映されるまでには時間がかかることもありますが、少なくとも伝えていくことは無駄ではないと考えています。