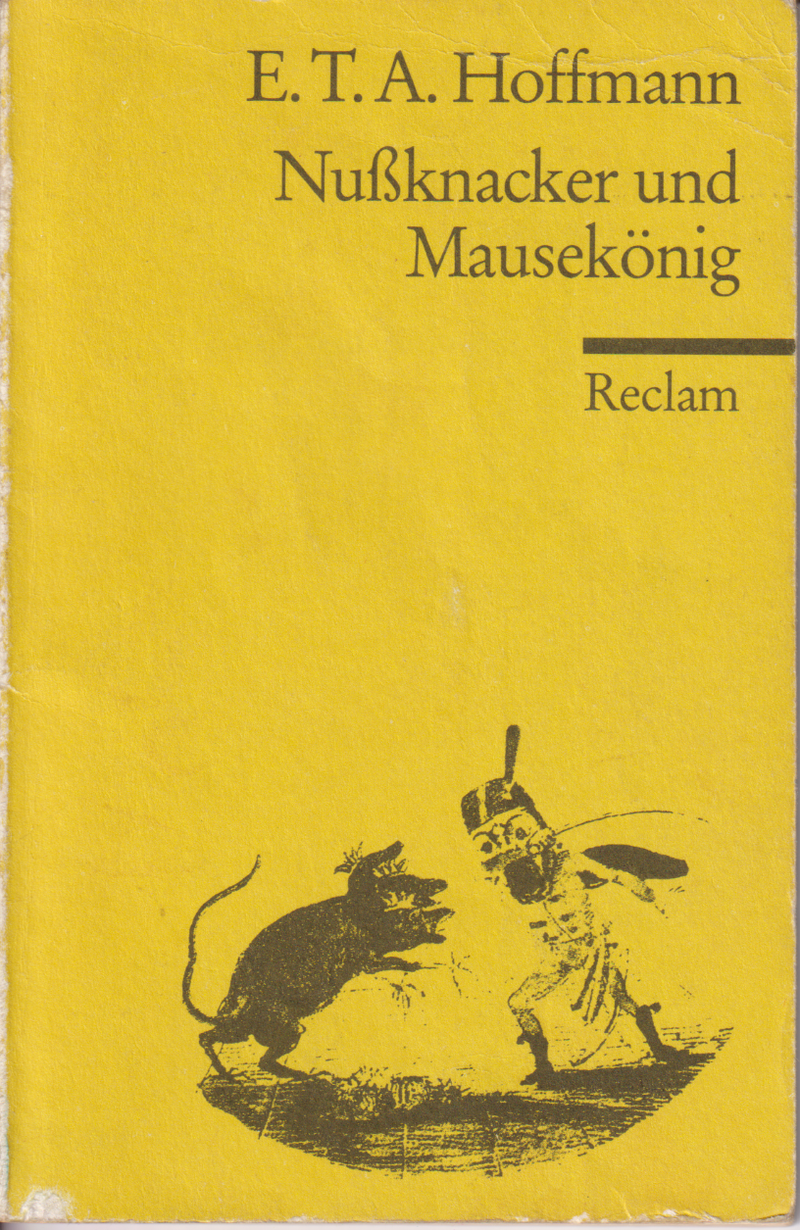ドイツや其の他のキリスト教のヨーロッパ諸国では、1年で最大の祝祭は何と言っても 12月25日のChristmas(クリスマス:
ドイツ語では Weihnachten 、フランス語では Noël)である。
一方日本では言うまでも無く、1月1日の「正月」である。
両国の各祝日には各家庭や各事業所、其の他の施設で、日本では所謂「お飾り」、そしてドイツでは
”Weihnachtsdekoration”(クリスマスの飾り)が入口や窓辺に設置される。
年末年始を通じて両方の文化を比較して、ふと思いついた事を書いて行く。
先ずは題名の日本の「お飾り」の代表格として「門松」が挙げられる。
門松の歴史を書くと、平安時代に唐の国から正月に、神が宿る新しい生命の象徴である松の枝を門に飾る風習が伝わったのが由来とと言われている。
又、当時の宮中で貴族が正月の日に外出して、松の木の枝を引き抜いて館に持ち帰って飾る所謂「小松引き」と言う遊びがあり、此れが「門松」へと進化したと推察される。
最初は松の枝を飾るだけであったが、鎌倉時代になって現在の様な竹が付け加えられた。
伝統的風習では此の門松やお飾りは神を家に招き入れる目印として新年毎に新調していた。
日本では此の様に多くの物品や生活道具が何年か経年すると、処分して新しい物を作り直したり、買い換えたりするのが一般的傾向である。
しかし今日では門松を何年も再利用する家庭も少なくないとの事である。
余も個人的には(ドイツ人的感覚で)折角職人が手で作った品物を僅か10日ないしは2週間程度の期間展示しただけで焼却するなど「勿体ない」と同時に作った職人の仕事を冒涜する様に思えるので、門松を何年も再利用する様にしている。
其の際、門松(約65cm)を我が母上方の祖父が経営していた事業所で使っていた火鉢(恐らく美濃焼)の上に乗せるので高さが約82cm程になる。
而も此の火鉢には我が家の家紋の「笹」が描かれているので大変縁起が良い。

一方ドイツでは大抵の物品や生活道具は余程状態が悪い物以外は、Reparatur(修理)、Umgestaltung(改造)Verbesserung(改良)等を施して使い続けるのである。
此れは”Weihnachtsfiguren”(クリスマスの置物)に関しても同様で、其の代表格格 ”Nußknacker”(くるみ割り人形) 、 “Kerzenhaus” od, “Lichthaus”(蠟燭の家、又は光の家)、 “Räuchermann” od, “Räuchermännchen”(タバコを吸う人)も同様に長い年月を通じて再利用している。
極端な例を挙げると20世紀の初頭や19世紀後半頃の
”Weihnachtsfigur”を所蔵している博物館や個人もいる位である。
”Nußknacker”(くるみ割り人形)の発祥は18世紀の現在のドイツSachsen州のチェコとの国境に伸びるEerzgebirge(エルツ山脈)である。
此の地方では何か特産物を生産して地元の経済を豊かにする事を余儀無くされていた。
当時、此の地方のある村に裕福だが孤独な地主が住んでいた。
彼はクリスマスにクルミをより楽しく割って食べる方法を考えた人に報酬を出すと言う御触れを出した。
何人かの候補の中でPuppenschnitzer(人形職人)の素晴らしき案が採用された。
木製(Kiefer=松、Fichte=ドイツトウヒ、Buche=ブナ)の人形に背面にレバーを付け、此れを引き上げて口を開けて、そこにクルミを挟んで割る仕掛けを作り、人形の体は此の地方の民族衣装の様に複数の鮮やかな色を塗るのである。
其の後19世紀の前半に”Nußknacker” は ”Weihnachtsfigur”(クリスマスの置物)としてドイツ全土に広まり、様々なデザイン(例:König=王様、Ritter=騎士、Soldat=兵士、Bergmann=山国の住人、Förster=森の番人、等)が考案されて行った。
余が所蔵している ”Nußknacker”(H:35cm)はOtto Mertens Kunstgewerbeの工房で制作された物で、大学時代の1991年にドイツ現地でWeihnachtenが始まる時期に入手した。
其の後、余にとって幸運の象徴である※聖騎士"St.Roland"像として、自分好みに何か所も改造を施している。
(※聖騎士"St.Roland"像はかつてHanse商業同盟に属した都市のMarktplatz(市場)に市の守り神として建てられている。 例:Bremen、 Brandenburg/H、 Gardelegen、 Perlberg、Stendal、↓等)

Heinrich Gustav: Die Rolandsäule zu Stendal
例えば、兜の上の赤いFederaufsatz(羽飾り)は手芸店で購入した物を取り付け、兜のVisier(目の防具)は薄いプラスチックの板に塗料を塗って作成した。
Lanze(騎士の槍)とSchwert(刀)はドイツの ”Weihnachtsfigur”の専門店で購入した木製部品で作成し、Schild(盾)とSchulerblatt(肩の防具)とSpange(ベルトの留め金)の上のMärkischer Adler(ブランデンブルクの赤鷲)は塗料で描き上げた。
そして背中には赤い布でマントを取り付けた。
更に上腕部と膝のLederschmuck(革製の飾り)は使い古した靴の飾りを利用して作成した。
因みにドイツのOstpreußen出身の文学作家にして作曲家であったE.T.A.Hoffmann(1776~1822)の書いた小説
"Nußknacker und Mausekönig"(くるみ割り人形とネズミの王様)は彼独特の愛らしいFantasie(幻想)が生き生きと描かれた名作である。
主人公の少女Marieの夢の中で、彼女のお気に入りのNußnackerがネズミの王様が率いる悪いネズミの集団と戦って一旦敗れてしまう。
Marieは知り合いのHandwerker(工芸品職人)のおじさんに、どうすればNußknackerが悪いネズミを退治出来るだろうかと相談すると、HandwerkerのおじさんはNußknackerの為に刀を作ってくれた。
家に帰ったMarieがNußknackerに刀を取り付けてやると、Nußknackerは見事に悪いネズミの集団を退治したのである。
更にMarieの夢の中でNußknackerはPuppenreich(人形の帝国)の王子様として現れ、御礼に彼女を自分の国に連れて行くのであった。
“Kerzenhaus”又は “Lichthaus”は名前の如く、家を模った置物の中に火の付いた蝋燭ないしは三角錐型の線香を入れる。
日本でも御馴染みの瓢箪(ひょうたん)の中身を刳り貫いて、其の中に蝋燭を立てる所謂「瓢箪ランプ」と類似している。
大抵の“Kerzenhaus”又は“Lichthaus”は素焼きの陶器製で部分的にGlasur(釉薬)や顔料で着色されている。
此の“Kerzenhaus”又は “Lichthaus”はドイツ国内に存在する様々なBaustil(建築様式)を模っているので歴史的建築を研究している者には大変興味深い物がある。
余が所有しているのは北ドイツに多く見られるFachwerkhaus(木骨家屋)とBauerhaus mit Schilfdach(茅葺屋根の農家)である。
“Räuchermann” 又は “Räuchermännchen”(タバコを吸う人)は大抵の場合木製で、其の体は上半身と下半身に分けられる。
下半身から上半身を取って、人形の腹の中に三角錐型の線香を入れる。
そして再び上半身を被せると、あたかも煙草を吸っている様に人形の口から煙が出て来るのである。
此の人形も様々な職業の人を模っているのが面白い。
余が所有しているのはKoch(料理人)である。
同様に日本文化で類似した例を挙げると、丁度「蚊やり器」と言った処であろう。
扨、以上の様に日本の「正月飾り」とドイツの ”Weihnachtsdekoration””(クリスマスの飾り)を主題にして、両国の文化を比較してみると、日本は"Renovierende Kultur(「一新」の文化)、ドイツはKonservierende Kultur(「保守」の文化)と表現する事が出来る。
両国の文化で其の他の例を挙げると、日本では家財道具が古くなったら廃棄処分して、改良した新しい物を作ったり、購入する事が主流である。
例えば住居や施設等の建造物でも大抵の場合30年ないしは50年経年すると、解体して新しい物を建てるのである。
故に日本では家財道具の「保証期限」が切れた物は、本体どころか其の部品の製造も終了するので、古い物を修理するのが容易ではない。
一方ドイツでは家財道具を安易に廃棄せず、親、祖父母ないしは其れ以前の先祖の代より手入れ、修理をしながら受け継いでいる。
同様に建造物の場合、100年以上前に建てられた物件を安易に解体したりせず、破損、老朽した部分のみ修理して、更に時代に適合した設備を追加する等して全体的に保持して行くのである。
故にドイツでは半世紀以上前から作られた物の部品でも製造したり修理する技術も残しているので、古い物を確実に保持出来るのである。
成程それぞれの文化には一長一短があるし、日本人には「日本式概念と方針」が常識として慣れているのかも知れないが、余は個人的には断然 "Deutsche Konzept u,Methode"(ドイツ式概念と方針)の方が好みに合うのである。
何故なら物事の価値を決めるのは、古いか新しいかではなく、有益か無益か、又は有意義か無意味かであると考えるからである。
即ち古より価値の有る物は守り続け、価値無き物は抹殺すれば良いのである。
「古い物」は何でも切り捨ててしまう等と言う考えは正に「愚の骨頂」であり、良き物、価値ある物はたとえ古くとも守り続け、後世の世まで残して行かねばならないのである!
日本では文化財と貴重品以外は大部分の古い物を壊して捨てるので、其の分だけ新しい物を大量に製造して販売する。
故に業者の儲けは多いが、其の反面無駄が多いし、ごみの処理に手間や費用が多くかかってしまう。
ドイツでは大抵は古い物でもReparatur(修理)、Pflege(手入れ)、Wiedergabe(再生)、Wiederverwendung(再利用)によって保持するので、新しい物を適当な量だけ製造して済ます。
故に業者の儲けは日本程ではないが、無駄が遥かに少ないし、
ごみの処理に掛かる手間や費用も遥かに少ないのである。
両国のKonzept(概念)とMethode(方針)を野球チームに喩えると、日本は得点力は高いが、失策や失点も多いチームである。
ドイツは得点力は日本程ではないが、失策や失点を最小限に抑えているチームである。
因みに大抵のプロ野球解説者は「野球の勝敗は6割以上が投手力(失点を抑える力)で決まる。」と言っている。
又、日本で複数のフィナンシャルプランナーが100人近くの「富裕層」(資産1億円以上)の人々に「資産を増やす為には、収入を増やす事と、無駄な出費を抑える事のどちらが効果的ですか?」と言う質問をした処、殆どの「富裕層」の人々が「無駄な出費を抑える事の方が大事だ。」と回答したそうである。
又、両国の政府の財政を比較しても、ドイツは1990年10月3日の"Deutsche Einheit"(国家統一)以来、旧・東ドイツを西ドイツ並みの社会水準にまで到達させる為に莫大な費用が掛かり、其れが国家の巨額な負債になっていたが、2010年までに此れを全て返済してしまっている。
其れに対し、今日の日本国政府や各地方自治体の抱える負債は天文学的な金額で、近い将来行き詰まり破綻するのではないかと危惧される程の状況である。
そして此の30年間、アメリカ経済は約2倍に発展、ヨーロッパの主要国(ドイツ、フランス、イギリス)も約1.5倍に発展しているが、他方で日本とイタリアだけが取り残された様に殆ど経済成長出来ず、税金、物価、エネルギー費のみが上昇している有様である。
詰まりこれ等の結果からも、"Deutsche Konzept u, Methode"(ドイツ式概念と方針)の方が合理的な正解であると言わざるを得ない。
新年の「縁起担ぎ」に因んで書くのだが、日本でも今だに存在が確認されていない神を信じたり、詐欺まがいの占い師の戯言を信じる、あたかもMentality(精神構造)が原始人並みの人がいる。
今日の様な「高度文明社会」に於いても尚、存在もしない「神」や、科学や医学等の学術的根拠の無い占いを信じる者がいるのには誠に呆れ返るしかない。
(大変高慢な表現になるが)この様な者共は「愚者」か「無能者」か「貧乏人」と相場は決まっている。
何故ならこう言った者共は自分に何一つ突出した「知恵」も「能力」も「財産」も無いから、自力を信じられず他力に依存するのである。
単なる「縁起担ぎ」の神頼みや、遊び半分の占い程度なら問題無いのだが、こんな他愛の無い物に毎回金銭までつぎ込む様になっては、人生観を誤っているとしか言い様がない。
一方、ドイツでは10世紀以来ずっとキリスト教一筋である。
そしてキリスト教はMonothaismus(一神教)の代表格であるし、当宗教の"Die Zehn Gebote" (十戒)の中の1つに「汝、唯一の神のみを信ずるべし」と言うのがある。
故に余程の事が無い限り、キリスト教以外の宗教に入信する事はあり得ないのである。(此の事は其の他のヨーロッパ諸国でも同様である。)
しかし、キリスト教以外には所謂 "Heroismus"(英雄崇拝)の思想は社会でも顕著に見受けられる。
其の証拠として、ドイツや其の他のヨーロッパ諸国では、日本や他のアジア諸国に比べて、英雄、天才、偉人、人傑の肖像画や彫像が大量に制作されて、美術館、博物館、城、公共施設、そして公園、市場、等に常設展示されている。
古の時代より「天才」「英雄」「偉人」「人傑」と言われた人は、自分の能力を信じて、高い目標、理想を持って、学習、努力を続ける事によって、自ら運を切り開いて大事を成し遂げたから、歴史に其の名前と業績を永遠に残せるのである!
即ち「自力」を信ずる者は、自分の人生に於いて自らが「神」(絶対的及び全能の存在)となれるのである!
凡人でも少なくとも自分の人生は自分自身で考え選択する、もしくは自分をよく知っている親しい人に相談する位の事をしなければ、「正しい人生」を歩めないのではなかろうか。
Kunstmarkt von Heinrich Gustav All rights reserved