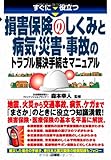・体の変更
・諸手取り呼吸法
・脱出
・坐り技呼吸法
お母さんが合気道に期待することとはなんだろうか?
礼儀作法、護身術、友達作り、色々考えられる。
どうすればそれに応えられる?
それを的確に読み取って応えることができるのならば、もっと熱心に通わせてくれるだろう。
剣5の合わせ。
打ち太刀が左右に替わりながら5の素振りの要領で打ち込んでくる。
受け太刀はまっすぐ下がって受ける。
まっすぐ下がるというのがポイント。
この動画は、受け太刀、打ち太刀の視点で撮影したもの。
実際はもっと迫力があります。
See more videos -> http://www.youtube.com/user/hirochen42/videos