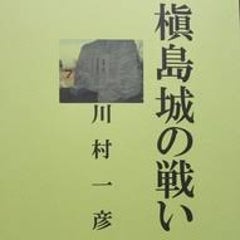伊賀転封後
天正13年(1585年)閏8月、秀吉は領国内の大規模な国替えを行い、畿内については羽柴一門・近臣で固める政策を実施した。
この国替えで大和国には秀吉の弟・羽柴秀長が入国し、代わって定次は領国を大和国から伊賀国上野に移封された。
この移封について、大坂や都に近い大和国から定次を追い出した実質上の左遷ではないかとする説がある。
この説に拠れば、石高も大和時代に較べて大幅な減封であり、筒井氏は伊賀国で苦難の時代を送ったとされる。
またこの移封の背景には、大和に根を張る寺社勢力との確執があったとされる。順慶の存命中、寺社は筒井氏に対して従順であったが、順慶が死去すると筒井家の力が弱まったと判断し、反抗的な姿勢を顕在化させたことにより、筒井氏移封および秀長の統治によりこれら勢力に対する政策を打ち出したとされる。
これとは別に、明確な理由もなく大減封は考え難い、とする説がある。
江戸時代の編纂物『増補筒井家下記』には定次は伊賀一国12万石・伊勢国の内で5万石・山城国の内に3万石の計20万石を与えられており、一方、移封前の大和44万石の内で与力を除いた筒井氏の純所領は18万石であり、伊賀国への移封は減封ではなくむしろ、2万石の加増であったとしている。また伊賀国は関東に対しての備えとしての役割を持つ街道の要衝であり、そのような重要な土地に定次を配置したことは、秀吉が定次を評価し、一定以上の信頼を寄せていたことの証左と考えることができるとする。
伊賀移封に伴い、定次は伊賀上野城を築城した。また、秀吉から羽柴姓を名乗る事を許され、従五位下伊賀守に任命された。
天正14年(1586年)、灌漑用水を巡って中坊秀祐と島左近の間で争いが起こり、定次が秀祐に有利な裁定を下した事で、憤慨した左近が筒井家を去るという事件が起こる。筒井家を去った左近は石田三成に仕えた。
松倉重政、森好高、布施慶春といった有力家臣達も前後して筒井家を去っている。その背景には、秀祐らの台頭と専断があった。定次には、彼らを完全に抑制するだけの力量はなかったとも推測される。
同年の九州征伐では、伊賀国の留守を十市新二郎に任せ、1,500の手勢を率いて出陣、豊臣秀長の部隊に所属し、日向高城攻めなどで活躍する。天正16年(1588年)、豊臣姓を下賜された。
天正18年(1590年)の小田原征伐では韮山城攻めに参加した。天正20年(1592年)からの文禄・慶長の役にも手勢3,000を率いて出陣し、肥前名護屋に詰めたが、朝鮮に渡航した形跡は残っていない。朝鮮の役の最中、顕著な武功を立てた加藤清正に称賛の使者を送った事や、名護屋で酒色に溺れ、中坊秀祐を憂慮させたことなどが『和州諸将軍伝』に記述されている。
同書の記述によると、定次は病を得、秀吉の承諾を得て途中伊賀国へ帰国したという。
13「関ヶ原以後」
慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは東軍に与した。定次は同腹の兄弟・筒井玄蕃允を城に残して会津征伐へ向かったが、その間に城を西軍方の新庄直頼、直定父子に奪われた。
玄蕃允は敵兵に恐れをなし開城して高野山へ逃げた。この出来事は徳川家康の耳に入り、定次は引き返して多羅尾口から伊賀国に入った。主君の呼びかけに兵や下人らが集まり始め、大軍になった。新庄父子は勝ち目がないことを悟り、定次の嫡男を人質に和睦し、島ヶ原で開放した(『伊乱記』)。その後、定次は関ヶ原に駆けつけた。
戦後、家康から所領を安堵され、新庄父子は改易された。
江戸時代
慶長8年(1603年)家康が征夷大将軍に任命され江戸に幕府を開くと筒井氏は伊賀一国を支配する国持大名となり、定次は伊賀守に叙任された。
慶長13年(1608年)、中坊秀祐が定次の不行状を訴え、定次は幕命により改易となり、ここに大名としての筒井氏は滅亡した(筒井騒動)。
改易の理由については、度々大坂城に赴き、豊臣秀頼や大野治房らと誼を通じていたこと、領国における悪政、酒色に耽溺したから、キリシタンによる訴訟、豊臣恩顧の大名であり伊賀国という大坂近郊の要地を支配していたことを幕府から危険視された(定次改易後の伊賀には外様ながら家康の信任厚かった藤堂高虎が入った)、など数々の理由が挙げられている。
定次は改易された後、鳥居忠政のもとに預けられることとなった。 慶長20年(1615年)3月5日、大坂冬の陣にて豊臣氏に内通したという理由により、嫡男・筒井順定と共に自害を命じられた。
享年54。切腹を賜った経緯について、『伊陽安民記』『翁物語』は、大坂冬の陣の際、城中から放たれた矢の一つに筒井家で使われていたものがあり、その矢が内応の示唆を疑わせ、自害を命じられたと記している。
しかしこの矢は筒井家が改易された際に四散したものが大坂城に紛れ込んだものと考えられている。