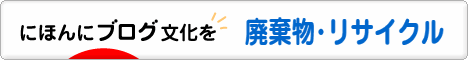環境配慮契約法(グリーン契約法)の背景や目的など【産廃処理に悩む排出元向け環境コンサルタントコラム】東新一
環境配慮契約法(グリーン契約法)の背景や目的など)
前回のコラムでは『グリーン購入法(背景や目的など)』をご紹介しました。今回は『グリーン購入法』と非常によく似た法令『環境配慮契約法』をご紹介します。『環境配慮契約法』は、別呼称では『グリーン契約法』と呼ばれている法令で、正式名称は『国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律』です。この法令は2000年グリーン購入法が制定の後、2007年に制定されました。
<環境配慮契約法(グリーン契約法)>
環境配慮契約法は、国など公的機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを示した法律です。
グリーン購入法は、国など公的機関が率先して環境物品などの製品やサービスの調達の推進を示した法律です。
グリーン購入法は環境物品等の製品・サービスの環境性能を規定し、グリーン契約法(環境配慮契約法)は契約類型ごとに総合評価落札方式/プロポーザル方式など推奨する入札・契約方式等を規定しています。この二つの法律はお互い連係(グリーン購入法で一定水準の環境性能を満たす製品・サービスを調達し、環境配慮契約法で製品・サービスを調達する上で、価格に加えて環境性能を総合的に評価する)を取り合い、合理的かつ効率的に進められています。
グリーン購入法と環境配慮契約法の比較(『性格』『趣旨』『基本方針の対象品目・契約類型』『内容など』)は次のとおりです。(出典:環境省)
環境配慮契約法(グリーン契約法)の目的は、同法第一条に『この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする』と示され、『温室効果ガス等』とは、温室効果ガスその他環境への負荷の原因となる物質と定義しています。
続いて、環境配慮契約法(グリーン契約法)の『責務』ですが、グリーン購入法では『国及び独立行政法人等』『地方公共団体』『事業者及び国民』にそれぞれ責務がありましたが、環境配慮契約法(グリーン契約法)では『事業者及び国民』の責務はありません。環境配慮契約法(グリーン契約法)の『責務』は、国や独立行政方針、そして、地方公共団体に対してのみで次のように示されています。
<国及び独立行政法人等の責務:義務>
国及び独立行政法人等の責務は、温室効果ガス等の排出削減をするため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めなければならない。
<地方公共団体の責務:努力義務>
地方公共団体及び地方独立行政法人は、温室効果ガス等の排出削減をするため、エネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、区域の自然的社会的条件に応じて、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に努めるものとする。
ここまで環境配慮契約法(グリーン契約法)の目的や性格、趣旨、基本方針の対象品目・契約類型、内容などをご紹介してきましたが、そもそも何故『環境配慮契約法(グリーン契約法)』が出来たのでしょうか?その理由として、主に以下の5点が挙げられます。
◆全球大気平均CO2濃度問題
◆世界と日本の気温と長期変化傾向問題
◆日本の大雨の発生頻度と熱帯夜
◆地球温暖化対策計画の改定及び目標
◆日本の温室効果ガス排出量の推移と目標
<全球大気平均CO2濃度問題>
・地球全体の月平均CO2濃度は年々上昇し、2015年12月に400ppmを超過、更に直近では2.0ppm/年、増加している
・世界と日本の気温はともに上昇傾向にある
・世界の平均気温は2014年から9年間間が上位9番目まで占有
・日本の平均気温は1990年以降高温になる年が頻出
<日本の大雨の発生頻度と熱帯夜>
・1時間降水量50mm以上の短時間強雨の年間発生回数は、1976年~1985年の10年平均値が約226回に対し、2012年~2021年の10年平均値が約327回と約1.45倍に増加
・1910年~2021年における日最低気温25℃以上(熱帯夜)の年間日数は大幅増加。熱帯夜は100年あたり17.8日の増加
<地球温暖化対策計画の改定及び目標>
・地球温暖化対策計画における温室効果ガス排出量/吸収量の目標:「2050年カーボンニュートラル」宣言、2030年度46%削減目標等の実現に向け、計画を改定(2021年10月22日閣議決定)
<日本の温室効果ガス排出量の推移と目標>
・2050年カーボンニュートラル
・2030年度2013年度比46%減=7.6億t
続いて、環境配慮の必要性と意義ですが、その内容は以下のとおりです。
◆2030年度の温室効果ガス総排出量を2013年度比で46%削減、さらに50%の高みに挑戦することが日本の国際約束(日本のNDC)
◆2021年10月に2050年カーボンニュートラル宣言等の実現に向け、地球温暖化対策計画、政府実行計画、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略、エネルギー基本計画等の関連計画等が改訂
◆日本の二酸化炭素排出量のうち、電力部門からの排出量は全体の約4割を占有(電気熱配分前の直接排出量)
◆電力はあらゆる場面においてエネルギーとして使用されることから、他部門の排出削減対策にも大きな影響を及ぼすもの
◆2030年度までに必要となる削減量の過半を占める電力部門における排出係数の低減が必須
となっています。
最後に環境配慮契約法(グリーン契約法)での「産業廃棄物の処理に係る契約」を説明します。まず、基本的な考え方は、以下の4点です。
1.優良認定制度への適合の評価による裾切り方式を実施
2.収集運搬から中間処理、最終処分の各処理過程における温室効果ガス等の排出削減による各環境質の保全を考慮する
3.再生利用や適正処理の実施に関する能力や実績等の評価は、優良認定制度への適合状況を考慮する
4.入札条件は、処理する産業廃棄物の種類や再生資源化の種類等の特性を踏まえ、調達者において設定する
続いて、産業廃棄物の処理に係る契約における環境配慮の必要性と意義は以下のとおりです。
◆産業廃棄物の適正処理の推進
・不法投棄は撲滅に至らず、不適正処理も多く発生
・不法投棄等の行為者、廃棄物処理事業者に対する規制強化とともに、排出事業者の責任の強化
・産業廃棄物の処理にあたっての優良産廃処理業者認定制度の活用
◆温室効果ガス等の排出削減
・廃棄物分野から排出される温室効果ガス等の削減
・廃棄物の資源としての再生利用の促進
つまり、ここでは、温室効果ガス等の排出削減と適正処理や再生利用の能力・実績等を考慮した事業者選定が必要です。
また、ここでは、環境配慮契約の観点から、以前にもご紹介しました『プラスチック廃棄物の排出抑制、再資源化等の促進につながる取組み』も必要とされそうです。
続いて、産業廃棄物の処理に係る契約における評価区分・配点例をご紹介します。それは以下の図(出典:環境省)のとおりです。
<環境配慮への取組状況>
①環境/CSR報告書②温室効果ガス等の排出削減契約・目標③従業員への研修・教育
<優良基準への適合状況>
①優良適性(遵法性)②事業の透明性③環境配慮の取組④電子マニフェスト⑤財務体質の健全性
裾切り方式では、ポイント評価し6割以上の点数事業者に入札参加資格を付与します。また、優良適性(遵法性)の評価では、適正な産業廃棄物処理の実施に係る能力や実績等を評価する観点から、特定不利益処分を過去5年間受けていないことが要件になっています。
以上、如何でしたか?今回は、環境配慮契約法(グリーン契約法)の目的や背景などをご紹介してきました。産廃処理に係る契約における評価項目・・・環境/CSR報告書、温室効果ガス等の排出削減計画と目標、従業員の研修、インターネットによる情報公開の実施、ISOやEA21、電子マニフェストは非常に興味深い評価項目です。単に〇✖ではなく、それぞれに取組みのレベルがありそうですね。
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
☆プラスチック資源循環促進法(背景や目的など)
☆グリーン購入法
☆【無料経営相談や環境・廃棄物相談:お問合せ先】